「コストをかけて新卒を採用したのに、すぐに離職してしまう・・・」
「面接時に学生の本質を見抜くことが難しく、実際の印象とかけ離れていることが多い」
といった悩みを抱えている新卒の採用担当の方はいませんか。
本記事ではそんな方に向けて、学生の本質を見抜くために有効な「コンピテンシー面接」について解説します。コンピテンシー面接の評価基準や進め方マニュアル、質問例等も掲載しているので、新卒採用の面接官を行う方は必見です!
コンピテンシー面接とは?
コンピテンシー面接とは、採用面接を受けにくる新卒学生の本質を見極め、自社にマッチするかどうかを判断する面接方法のことです。近年では、公務員試験でもコンピテンシー面接が行われるようになっています。 新卒採用の場合、社会人経験が浅い求職者が多いため、学歴や資格が判断基準になりやすいです。
会社にとってマッチ度の高い求職者を集めるようとする採用において、学歴や資格に関する情報は表面的です。 一般的に高学歴の人材が優秀である「確率」は高いと言われています。
しかし、優秀な学生が必ずしも自社の社風や理念と合うとは限りません。求職者の学歴やスキル、第一印象で判断するのではなく、それらに表れない行動特性や本質を見極めることで、入社後のミスマッチを減らすことができるでしょう。
またコンピテンシー面接は、新卒採用だけでなく、昇格審査や転職・中途の採用面接でも有効です。
※コンピテンシーとは?
ビジネス用語で「職務や役割において優秀な成果を残す従業員の行動特性」のこと。
コンピテンシー面接と従来の面接の違い
▼従来の面接とコンピテンシー面接の違い
| コンピテンシー面接 | 従来の面接 | |
| 評価の対象 | ・行動特性(その人の思考・行動パターン)
・学生の本質 |
・印象
・学歴や現在のスキル ・実績 |
| 質問の内容(例) | ・なぜその行動をしようと思ったのか(行動特性)
・モチベーションはどこにあったのか |
・取り組んだ事柄の大まかな内容
・自社を志望する理由 |
| 面接官による評価 | ・基準があるため、客観性が担保されている | ・基準が曖昧なため、面接官によって評価がバラバラ |
| 面接の流れ | ・全ての面接官がある程度同じ | ・面接官によって進め方が異なる |
コンピテンシー面接と従来の面接の違いは、「学生の評価基準」「質問の内容」にあります。
従来の面接では、学生時代に力を入れたことや自己PR、志望動機をおおまかに聞き、その受け答えの印象に合わせて、その学生の学歴を踏まえて評価が行われていました。
つまり学生が「どんな行動特性を持っているか」より「どこの大学出身で、どんな経験をしてきたのか」を重要視していたのが、従来の面接です。印象も重要視していた従来の面接は、合否の基準が曖昧で面接官によって評価がバラバラになることが少なくありませんでした。
一方コンピテンシー面接は、入社後の仕事への取り組み方や配属予定の部署社員との相性などの「学生の行動特性」を見極めます。そのため印象や、うわべの実績、能力だけに頼らない評価が可能です。つまりコンピテンシー面接は、30分〜1時間という短い面接時間で「学生の本質」を見極めるために有効な手段なのです。
コンピテンシー面接の6つのメリット
コンピテンシー面接のメリットは以下の6つです。
▼コンピテンシー面接の6つのメリット
- 入社後に活躍できる人材を多く採用できる
- 経験の少ない面接官でも適切に評価できるようになる
- 学歴や現在のスキルに囚われない採用活動ができる
- 評価基準が明確なため、面接官によるバラツキが生じにくい
- 求職者の行動特性を見抜ける
- 求職者の嘘を見抜きやすくなる
1、入社後に活躍できる人材を多く採用できる
まず第1に「入社後に活躍できる人材を多く採用できる」ことが挙げられます。
前提として、「優秀な学生 = 自社で活躍できる人材」とは限りません。
「頭のキレはいいけど、周囲とのコミュニケーションが苦手で、本来のパフォーマンスを発揮できていない」
「体育会系出身の学生だけど、想像していたよりストレス耐性が弱く、うちの部署の雰囲気に合わない」
「学歴や実績を重視しすぎた結果、性格的に合わない学生を多く採用してしまった」
という場合は、コンピテンシー面接がおすすめです。
新卒採用は、スキルや実績よりもポテンシャルが重要視されます。 だからこそ、入社後に活躍できる人材を見つけるには、会社の社風や部署との相性を確かめる必要があるでしょう。
コンピテンシー面接は行動特性を深掘りするため、学生のポテンシャル・本質をより見極めやすくなります。
2、経験の少ない面接官でも適切に評価できるようになる
第2のメリットとして「経験の少ない面接官でも適切に評価できるようになる」があげられます。コンピテンシー面接は、面接で評価するべき項目や面接の流れが明確に決まっているため、面接経験が少ない社員でも何をすべきかが分かりやすくなっています。
「面接経験が少ない社員による学生の評価が、今まで適切になされてこなかった・・・」とお悩みの場合は、コンピテンシー面接の実施がおすすめです。
3、学歴や現在のスキルに囚われない採用活動ができる
第3のメリットとして「学歴や現在のスキルに囚われない採用活動ができる」が挙げられます。従来の面接だと「学歴が少し足りていないない」という印象があると、その後の面接の評価にバイアスがかかってしまうことがありました。
冒頭でも説明しましたが、一般的に高学歴の人材が優秀である「確率」は高いと言われています。 しかし、学歴が高くないからといって優秀でないとは限りません。
優秀な学生を学歴バイアスによって、不採用としてしまうのは、会社にとって損失です。コンピテンシー面接により、学生の行動特性を見極めることに集中することで、学歴やスキルに囚われない採用活動ができるようになります。
4、評価基準が明確なため、面接官によるバラツキが生じにくい
第4のメリットとして「評価基準が明確なため、面接官によるバラツキが生じにくい」が挙げられます。
先程触れたように、コンピテンシー面接は評価基準が明確で、質問がマニュアル化されていることが多いです。そのため、面接官ごとの評価にバラツキが生じにくく、「自社の採用要件にマッチした優秀な学生」を多く採用することができます。
5、求職者の行動特性を見抜ける
第5のメリットとして、「求職者の行動特性を見抜ける」があげられます。コンピテンシー面接は「その人個人がどんな人なのか」を見極めるために有効な手段です。実績を残している候補者がいたとしても、その実績を残せたのは一緒にいたメンバーが強力だった可能性もあれば、運がよくたまたま上手くいった可能性もあります。
コンピテンシー面接は、実績といった表面上のものではなく 「その行動をした理由はなにか」 「チームで担っていた役割はなにか」 といったことを、具体的に深掘りしていきます。
そのような深掘りを続けることで、再現性が生まれ「入社後どんな場面で活躍してくれるのか」が想像しやすくなるでしょう。
6、求職者の嘘を見抜きやすくなる
求職者は面接の時、自分を少しでも良く見せようと嘘で取り繕おうとしたり、話を過剰に盛ってしまったりすることがあります。
コンピテンシー面接は、質問の回答に対しさらに掘り下げた質問をするため、求職者が嘘をついても、どこかで辻褄が合わないということが発生するのです。そのため、求職者の嘘を見抜きやすくなり、本質を見ることができます。
コンピテンシー面接の3つのデメリット
コンピテンシー面接のデメリットは以下の3つです。
▼コンピテンシー面接の3つのデメリット
- モデルとなる社員がいないと実施が難しい
- 実施するまでに手間がかかる
- ヒアリングに時間がかかる
1、モデルとなる社員がいないと実施が難しい
まず第一のデメリットとして、コンピテンシーの指標となる社員の存在が必須であることが挙げられます。コンピテンシー面接では、社内で高い評価を受ける社員の行動特性を分析し、その行動特性と一致した新卒を採用する必要があるからです。
つまり「あの人のような学生を採用したい!」というモデルが社内にいないと、コンピテンシー面接の実施は困難になります。
2、ヒアリングに時間がかかる
コンピテンシー面接は回答に対し、更に掘り下げた質問をしていくため、通常の面接よりもヒアリングに時間がかかります。面接に時間がかかれば、会社によっては負担がかかったり、面接ができる人数が通常よりも減ってしまったりすることがあるでしょう。
3、実施するまでに手間がかかる
また従来の面接に比べて実施するまでに手間がかかることも、デメリットの1つとして挙げられます。
コンピテンシー面接ではモデルとなる社員の特定から質問項目・評価の選定まで、面接の実施前に多くの準備が必要になります。場合によっては職種や部門ごとに聞き取り調査が必要になり、さらに時間がかかる可能性があるので、注意が必要です。
コンピテンシー面接に必要な準備について次の見出しで解説しています。
【面接前の準備】コンピテンシー面接の進め方
ここからはコンピテンシー面接を行う前に、準備しておくべきことを紹介します。面接前の準備として、以下の2つを行いましょう。
▼コンピテンシー面接の準備で行うべきこと
- 評価する行動特性を決める
- 面接で行う質問を決める
①評価する行動特性を決める
まずは面接で評価する行動特性について決めていきます。行動特性とは、その人の思考・行動パターンのことです。このときの行動特性は、自社で活躍できるようなものであることが望ましいです。そこで、以下の3点から面接で評価する行動特性を決めていきましょう。
▼評価する行動特性を決める3つのステップ
- 社内で活躍している社員をピックアップ
- 成績が良い社員に共通する行動特性を特定
- 面接時に重視する行動特性を決定
まずは社内で活躍している社員をピックアップします。社内で実績を上げている優秀な人材や、上司など周囲の人から評価が高い複数の人材にアンケートをとり、そこから自社で優秀な社員に共通する行動特性を特定します。
例えば優秀な人材で「積極的に意見を言う」という行動特性が共通している場合、面接で評価するべき行動特性は「積極的に意見を言う」となります。面接の中で、例えば「主体性のあるエピソードがあるか」「チーム内で進んで意見を言いプロジェクトを動かした経験があるか」という部分から判断できるでしょう。
共通する行動特性が多い場合、行動特性を優先順位をつけて分けていきましょう。自社で活躍する行動特性全てを持っている学生はなかなかいません。そのため、まずは重要度別に行動特性を決めることが大切です。
❚ コンピテンシーモデルを作成するとマッチ度を判断しやすい
行動特性について決めた後、さらにマッチ度を高めるならコンピテンシーモデルを作成することがおすすめです。コンピテンシーモデルとは、優秀な人材の行動特性を人物像としてモデル化したものです。コンピテンシーモデルを作成することで人物像のイメージがつきやすいため、自社にマッチした人材を見分けやすくなります。
コンピテンシーモデルは3つのタイプがあり、それぞれ作成方法が異なります。
▼コンピテンシーモデルの3つのタイプ
- 実在型
- 理想型
- ハイブリッド型
◎実在型モデル
実在型モデルは、社内で成果を挙げている人にヒアリングなどをして作られるモデルです。
コンピテンシー面接を採用している多くの企業は、このモデルを利用しています。
現実に即したモデルを設計することができ、成果を上げるために必要な行動特性をイメージしやすいです。
◎理想型モデル
理想型モデルは、企業が求める人物像をベースに評価項目を作成するモデルのことです。
企業の経営ビジョンや事業戦略から、理想とするモデルを想定しながら行動特性、評価項目をせっていします。
社内にモデルの大砲となる人がいない場合や、新たな人材を採用したい場合に有効です。
◎ハイブリッド型モデル
ハイブリッド型モデルは、「理想型モデル」と「実在型モデル」を組み合わせて作成するモデルのことです。
実在型モデルを作成したのち、足りない部分に理想型モデルの要素を組み込み、評価項目を調整します。
それぞれのモデルの良いとこどりをしているため、3種類のモデルの中で最も優れたモデルとも言えるでしょう。
❚ 自社にマッチした学生を採用するならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
②面接で行う質問を決める
面接で評価する行動特性を設定した後は、その行動特性を判断できる質問を決定していきます。コンピテンシー面接で聞きたい質問例について、この後の見出し「コンピテンシー面接の質問例」でご紹介します。
❚ 継続的にコンピテンシー面接を実施するためにマニュアル化する
コンピテンシー面接を効率よく行うためには、面接内容をマニュアル化することがおすすめです。 深ぼる内容をマニュアル化しておけば、面接官によって評価のバラツキがなくなり、学生の評価がしやすくなるでしょう。
例えば、以下のような例が考えられます。
- リーダーシップを聞きたい質問なのに、1人で行った内容の話をしたら×評価を付ける
- 課題解決力の話であれば、思考の深さを深ぼる
- 思考が深いかどうか不明であれば△の評価を付ける
- ○の評価を下したのであれば、その他の行動特性も深ぼる
このように、面接前に評価内容や聞くべきことをマニュアル化しておくのがおすすめです。
また、学生を評価する際は、評価シートを作っておくと評価基準が明確になり、他の面接官から見ても分かりやすくなります。評価シートのテンプレートをこの後の見出し「コンピテンシー面接で使える評価シートのテンプレートを紹介」で紹介しています。
【面接の流れ】コンピテンシー面接の進め方
ここからは、コンピテンシー面接の進め方について解説していきます。コンピテンシー面接の進め方は以下の4つです。
▼コンピテンシー面接の進め方
- 重視する行動特性が分かる質問を行う
- 答えにより適宜深掘り質問を行う
- 評価を付ける
- その他に重視する行動特性の質問に移る
1.重視する行動特性が分かる質問を行う
まずは事前に決定した「重視する行動特性」が伝わるような質問を行いましょう。
例;「課題解決力があるか見極めたい」
<質問例> ・課題・問題を解決してきた経験はありますか。
- なぜその方法を採用しようと思ったのですか。その他に方法は無かったのですか。
- もう一度同じ課題にぶつかったら、同じ方法で解決しますか。それとも別の方法を採用しますか。
2.答えにより適宜深掘り質問を行う
質問の返答を見て、適宜質問への深掘りを行いましょう。 学生の話す内容に少しでも疑問・質問があれば、遠慮なく聞くようにすることで、ミスマッチを防止できます。
3.評価を付ける
質問への返答を見て、学生に評価を付けましょう。 評価方法としては、1、2、3といった数値や、○×△などを用いると、評価方法が明確になり、他の面接官でも理解しやすくなります。
4.その他に重視する行動特性の質問に移る
重視する行動特性に関する質問が完了したら、その他に重視する行動特性に関する質問に移りましょう。 重視する行動特性が複数ある場合は、ステップ1〜4を何度も繰り返し「本当に自社にマッチしているか」を漏れなく確認するのがおすすめです。
コンピテンシー面接の質問例
コンピテンシー面接の質問例としておすすめなのが「STARワークフレームを用いた質問」です。STARワークフレームは、Google社が採用している候補者を公平に判断するために用いられるものです。
具体的には S:Situation(状況) T:課題(Task) A:行動(Action) R:結果(Result) の4つの頭文字を取ったものです。この4点にそった質問を行うことで、新卒学生の行動特性が分かりやすくなるでしょう。 具体的な質問例を下記で見ていきます。
状況(Situation)
<聞くべき内容>
- 取り組んだ内容
- チーム体制
- なぜそれに取りくもうと思ったのか(背景)
- どれくらい難易度が高かったか
- 期間はどれくらいか
<質問例>
- チーム体制を詳しく教えてください。加えてその組織内のあなたの役割はなんですか。
- あなたが行っていた内容の難易度を分かりやすく教えてください。
- なぜその事柄に挑戦しようと思ったのですか。
課題(Task)
<聞くべき内容>
- 掲げた目標 ・目標に到達するまでの課題、問題
<質問例>
- その内容の中で、あなたはどんな目標を掲げましたか。
- その目標を達成するうえで、一番の課題・問題はなんでしたか。また、なぜそれを一番の課題問題だと考えたのですか。
- 問題点をどのように発見しましたか。
行動(Action)
<聞くべき内容>
- 具体的な行動内容
- 行動を行う上で、一番大変だったこと
- 工夫した点
<質問例>
- 課題を解決し目標を達成するために、あなたは具体的にどんなことを行いましたか。
- なぜその行動を行おうと思ったのですか。意図を聞かせて下さい。
- その行動の中で「あなたならでは」の行動を教えて下さい。
- 特に苦労したこと・大変だったことを教えて下さい。
結果(Result)
<聞くべき内容>
- 最終的な結果・成果 (できるのであれば定量的に)
- その経験から学んだこと ・周囲からの評価
<質問例>
- 最終的な結果はどうなりましたか。数字で表せるのであれば、定量的に教えて下さい。
- その行動によって、あなたが周囲からもらった評価があれば教えてください
- 行動を振り返って、反省点などがあれば教えてください
コンピテンシー面接の評価方法(コンピテンシーレベル)
続いて、コンピテンシー面接の評価方法について解説していきます。自社にマッチする学生を採用するために、評価基準は非常に重要なものです。
そこで、コンピテンシー面接における評価シートのテンプレートを作成しました。 コンピテンシー面接実施時の参考にしてみてください。
▼コンピテンシー面接で使える評価シートのテンプレート
上記のテンプレートでは、「STARワークフレーム」を用いています。
また、ここからは評価方法としてコンピテンシーレベルを紹介していきます。コンピテンシー面接の評価のひとつの参考にしてみてください。
▼コンピテンシーレベル
- レベル1:受動行動
- レベル2:通常行動
- レベル3:能動・主体的行動
- レベル4:創造・課題解決行動
- レベル5:パラダイム転換行動
レベル1:受動行動
受動行動はその名の通り「人から指示を受けて行った受動的な行動」を指します。
「リーダーに指示された行動のみをした」「仕方なく行動した」といったものは、全てこの「レベル1:受動行動」に該当します。
レベル2:通常行動
通常行動は「やるべきことを必要最小限に行った行動」を指します。
作業は自分一人で行うことができますが、工夫が見られず、誰もができるようなことを普通にやっている状態は「レベル2:通常行動」に該当します。
レベル3:能動・主体的行動
能動・主体的行動は「明確に自らの意見があり、それを基に行った行動」を指します。
「言われたことだけでなく、今必要なことを自らの意思を持ってできる」状態は「レベル3:能動・主体的行動」に当てはまります。
レベル4:創造・課題解決行動
創造・課題解決行動は「主体的に行動する中で、課題を解決するための方策を自ら考え実行した行動」を指します。
「主体的に行動し、仮説検証を回していくことで、何が最適なのかを特定できる」 「課題解決のために、独創的なアイディアを出すことができる」 といった状態は「レベル4:創造・課題解決行動」にあたります。
レベル5:パラダイム転換行動
パラダイム転換行動は「常識に囚われず、誰もが思いつかないアイディアを実行し、なおかつ周囲から賛同が得られる行動」を指します。「アイディアの斬新さ」と「周囲からの評価」の2つがポイントで、この2つが満たされている状態は「レベル5:パラダイム転換行動」にあたります。
新卒の学生で、レベル5:パラダイム転換行動の状態にある学生は、決して多くありません。そのため、あまりに採用要件を厳しくしてしまうと、母集団の数が減ってしまうこともあります。
「現在のコンピテンシーレベルは低いが、入社後に成長しそうか」という観点も、新卒のコンピテンシー面接では重要です。
コンピテンシー面接での注意点
コンピテンシー面接を実施するうえでの注意点は以下の3つです。
▼コンピテンシー面接での3つの注意点
- 応募者を公平に判断するという意識を忘れず持つ
- 第一印象や現在のスキルなどに囚われすぎない
- 職種によって、質問内容や深掘り質問は変更する
コンピテンシー面接は、評価軸を定めて面接を行うことで、面接官が応募者に抱いた印象によって結果が左右されにくいというメリットがあります。
一方で、それでも第一印象や学歴、現在のスキルという情報から応募者を判断しやすいこともありえます。公平に判断すること、評価につながりやすい学歴や現在のスキルなどにとらわれないことが大切です。
また、同じ会社でも職種によって理想とするコンピテンシーモデルは異なるでしょう。そこで、職種ごとに質問内容や深掘りをする質問を変えることもよりよい人材を採用するために必要になります。
コンピテンシー面接の導入事例
コンピテンシー面接を実際に導入している企業は、どのようなコンピテンシーモデルを採用しているのかご紹介します。
【株式会社RevComm(レブコム)の導入事例】
【参考】株式会社RevComm(レブコム)「コンピテンシー面接」
過去に実績として以下7つの能力が発揮されているのか、その再現性を見ています。
<7つの能力>(コンピテンシーモデル)
①コミュニケーション能力
②ヒアリング能力
③交渉力
④課題発見力
⑤セルフマネジメント能力
⑥対応力
⑦行動力
過去の実績における発揮が、入社後の発揮に繋がるとみて採用を行っています。
コンピテンシー面接で使える本(書籍)・漫画をご紹介
次にコンピテンシー面接でおすすめの本・漫画を紹介します。 コンピテンシー面接の基本を知りたいという方は、以下の2冊がおすすめです。
コンピテンシー面接マニュアル 川上真史著 弘文」
コンピテンシー面接導入時に検討すべきこと等が、詳しく書かれています。 コンピテンシー面接の成功事例なども掲載されているなど、情報量が豊富で非常に参考になる一冊です。
まんがでわかるコンピテンシー面接 川上真史 弘文堂
コンピテンシー面接の基本が、漫画でまとまっています。 導入方法から、実践まで分かりやすく漫画にまとまっているので、採用面接官を担当して間もない方でも読みやすい一冊です。
求める人材を採用するならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
まとめ
いかがでしたか。 コンピテンシー面接は、印象だけではない「学生の本質」を見極めるために、有効な面接方法です。
「新卒がすぐに退職してしまい困っている・・・」という場合は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。




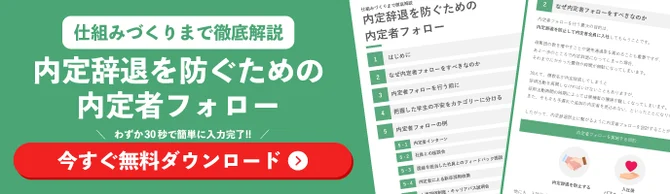
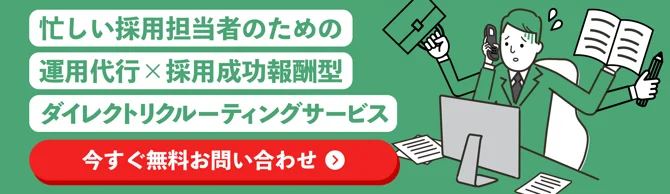
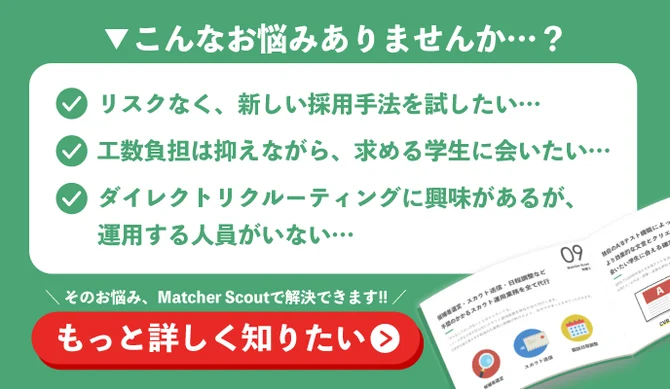




_Crop%20Image.jpg)
