企業が人材を集めるにはビジネス実務を積んできた人を採用する「中途採用」とキャリア未経験の学生を採用する「新卒採用」の2つがあります。
「求める人材は中途採用か新卒採用どちらで獲得できるのか知りたい」
このようなお悩みを抱えている採用担当者様はいらっしゃいませんか。この記事では、中途採用と新卒採用の違いや特徴について解説しています。
新卒採用と中途採用の違いとは?
企業の採用活動は、大きく「新卒採用」と「中途採用」に分けられます。
ここでは、新卒と中途採用がそれぞれどのように定義されているかを解説します。
新卒採用とは
新卒採用とは一般的に、新卒採用とは3月末に学校を卒業見込みで就職活動をする新卒の学生を一括で採用することを指します。
近年の新卒採用市場では、一定条件を満たすインターンを通じた採用が解禁されるなど、企業間における新卒採用の競争は激化傾向にあると言えるでしょう。
新卒採用では、即戦力としてのスキルよりもポテンシャル・人柄・成長意欲・企業文化との相性が重視される傾向があります。入社後は研修やOJTを通じて、時間をかけて育成していくことが前提です。
中途採用とは
中途採用とは、第二新卒・未経験者・キャリア採用の3つから構成される新卒の学生以外を採用する採用区分のことを指します。それぞれの定義について詳しく解説します。
❚ 第二新卒採用
第二新卒採用とは、新卒で入社した企業を3年未満で転職することを検討している求職者を採用することです。企業によっては卒業して間もないことから第二新卒を新卒と同じように扱っています。
第二新卒として就職活動を行っている求職者は基本的なビジネスマナーを身につけていながらも、特定企業から受けた影響が比較的小さいことから柔軟性や適合性が高い傾向にあります。
しかし、転職への抵抗が小さいことから早期退職のリスクが高いことには注意しましょう。
❚ 未経験者採用
未経験者採用とは、特定の職種または業界での職務経験がない求職者を採用することです。
さまざまな背景を有する人材を採用することで、異なる視点からの課題解決が見込まれます。しかし、未経験者の教育に周囲の負担が一時的に増加したり、大幅な変更は既存の従業員から反発されたりする可能性については注意する必要があります。
未経験採用では実務経験は問われないものの、学習意欲・適正・将来性が重視される点が特徴です。人手不足の業界や、育成体制が整っている企業で行われることが多く、キャリアチェンジの入口として活用されます。
❚ キャリア採用
キャリア採用とは、企業が求める職種について一定の知識・スキル・経験を持っており、即戦力になりうる人材を採用することです。一定の経験がある人材を採用することは教育コストを削減し、自社にないノウハウを取り込むことで競争力の向上が見込めます。
しかし、社風や価値観が合わない場合、ミスマッチが発生する可能性が高い点については注意する必要があります。
新卒・中途採用の採用割合

株式会社学情の調査によると、2025年度の採用活動における中途採用と新卒採用の割合は、「5:5」が24.2%で最多となりました。
つまり、4社に1社は中途採用と新卒採用を同じ割合で実施しているということです。新卒採用・中途採用で採用できる人材は異なるため、どちらも採用することで組織のバランスを保っていることが考えられます。
また、中途採用よりも新卒採用を中心に行っている企業は38.2%、新卒採用よりも中途採用を中心に行っている企業は36.5%でした。新卒採用を実施している割合が高い企業の方が多いですが、その差は小さいことが分かります。
【参考】株式会社学情『4社に1社がキャリア採用と新卒採用を同割合で計画。「キャリア採用の人数を増やす」3割超。30代前半までの若い世代の採用に意欲』
【比較表】新卒採用と中途採用の違いを7項目で一気に整理
新卒採用と中途採用では、採用の目的や進め方が異なります。ここでは、7つの項目から、両者の違いを解説します。
採用対象
1つ目は、採用対象の違いです。
❚ 新卒採用の採用対象
新卒採用は、その名の通り新卒の学生を対象に行います。新卒とは、その年に学校を卒業する、あるいは卒業見込みの学生を指します。
しかし、国の方針で卒業後3年までを新卒扱いとする企業も増えています。その影響により、基本的には卒業後3年以内は新卒として扱われることを理解しておくとよいでしょう。
❚ 中途採用の採用対象
中途採用は自身でキャリアを積んできた社会人を対象に行われます。そのため、ターゲットの幅が非常に広く、スキルや年収の幅も非常に広いことが特徴です。
また、新卒から3年以内の社会人を第二新卒という場合もあります。
②採用基準
2つ目は、採用基準の違いです。
❚ 新卒採用の採用基準
新卒採用では、社会人未経験の学生を採用するため、将来性を重視したポテンシャル採用を行います。
❚ 中途採用の採用基準
中途採用は実務スキルやこれまでの経験が重視されます。中途採用は即戦力を求めて行われることが非常に多いです。そのため、これまでのキャリアや実務スキル、資格職であれば資格の有無が重要視されます。
もちろん、若手の中途採用であればポテンシャルを考慮しての採用もありますが、基本的には即戦力として活躍できるかが中途採用の採用基準です。
③採用時期・スケジュール
3つ目は、採用時期・スケジュールの違いです。
❚ 新卒採用の採用時期・スケジュール
一般的に新卒採用は、学生が学校を卒業する3月に合わせて、4月入社で一括採用されることが多いです。そのため、採用活動を行う時期は入社1年前、大学3年生の3月頃がピークになります。ただ、近年では、就活の早期化に伴い、入社の2年近く前から新卒採用活動を行う企業も増えています。
◎新卒採用の採用スケジュール例
以上が新卒の採用スケジュール例です。就職活動の早期化により、大学3年生の10月から早期選考、2月から本選考を開始している企業も多いです。コンサルティング業界など、業界によってはさらに前倒しで採用活動をしている企業もあります。
❚ 中途採用の採用時期・スケジュール
中途採用は、あるポジションに欠員が出る、または新規事業立ち上げに際してその領域のプロを雇う場合がほとんどです。そのため、中途採用は不定期での採用となります。
一般的に不足しているポジションが充足すれば採用は終了しますが、求める人物像とマッチする人材を見つけるのが困難な場合、通年で中途採用を行っている企業もあります。
④採用コスト
4つ目は、採用コストの違いです。
株式会社リクルートの調査によると、2024年度の新卒採用の採用単価(1人あたりの採用コスト)は56.8万円、中途採用の採用単価は144.94万円でした。
中途採用のほうが新卒採用よりも採用コストが高い傾向にあり、中途採用は新卒採用よりも3倍近く高いことがわかります。
❚ 新卒採用の採用コスト
2024年度
年間採用費:287.0万円(上場企業は917.6万円、非上場は233.1万円)
採用単価:56.8万円
【参考】マイナビキャリアリサーチLab『マイナビ 2024年卒 企業新卒内定状況調査』
❚ 中途採用の採用コスト
2024年度
年間採用人数:3.9名
年間採用費:565.3万円
採用単価:144.94万円(調査データに記載された年間採用人数と年間採用費から算出)
【参考】マイナビキャリアリサーチLab『中途採用状況調査2025年版(2024年実績)』
また、新卒採用は一括採用でスキルを求めない採用のため、業種ごとにコストの変動は少ないですが、中途採用は求めたいスキルが業界・業種によって大きく違います。そのため、業界・業種によっては採用単価が平均より高くなる場合もあります。
採用コストを抑えて新卒採用を行いたいならMatcher Scout
「採用コストを抑えながら求める人材に会いたい」
「求める人材で母集団を形成したい」
といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービスです。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、費用面でのリスクを心配せずに、効率的な採用活動を進めることができます。ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
⑤自社文化への染まりやすさ
5つ目の違いは、自社文化への染まりやすさです。
❚ 新卒採用の自社文化への染まりやすさ
新卒で入社する学生は今まで企業に属した経験が少ないため、新卒入社した組織の文化に染まりやすいという特徴があります。組織の色に染まりやすいため、自社を引っ張っていくコアメンバーとしてキャリアプランをたて、育成することが可能です。
❚ 中途採用の自社文化への染まりやすさ
中途採用は自分の働き方や仕事に対する考えが既に確立されている場合が多いです。これまで働いてきた会社での経験があるため、入社後しばらくは自社の仕事のやり方や流れになじめない可能性もあります。
逆に、従来までの自社の仕事のやり方にとらわれず、新しい視点から仕事に取り組むことで今まで生まれなかった発想や新しい視点を手に入れるチャンスとも言えます。
企業にとって、中途採用は他社の企業文化を取り入れる貴重なチャンスです。しかし、ミスマッチが起これば結果的に中途で採用した社員が十分に力を発揮できないような環境になってしまう可能性もあります。
⑥離職率・定着率
6つ目の違いは、離職率です。新卒採用は、育成前提である分、定着すれば長期的に活躍してもらえる可能性があります。一方で、入社後のギャップが大きいと早期離職につながるリスクもあります。
中途採用は即戦力として活躍しやすい反面、条件や環境次第では転職の選択肢を持ち続ける人材も多い傾向があります。
❚ 新卒採用の離職率・定着率
厚生労働省によると、令和4年3月卒業の新卒就職者の就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者で37.9% 、新規大卒就職者で33.8% という結果でした。新卒で採用した学生の3割以上が、入社して3年以内に退職しているということです。
【参考】厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年4月卒業者)を公表します」
❚ 中途採用の離職率・定着率
中途採用の離職率は、新卒採用の1.5倍と言われており、中途採用で獲得した人材の方が、新卒の学生より離職率が高い傾向にあります。
その理由の1つに、中途採用の社員は前職を辞めて転職して現在の企業に入社した人材であることがあげられるでしょう。何回も転職をする人は、自分のキャリアのビジョンが明確に定まっている場合や、働く環境を重視している場合が多いです。
その場合、入社後に「何か違う」と違和感を覚えた場合は、再び違う企業へ転職する可能性があります。複数の企業の就業経験があるからこそ、1社しか就業経験のない新卒に比べて転職までのスピードが早いことも考えられます。
そのような事態を防ぐためには、入社する際に中途採用の求職者と自社の企業文化や意識のすり合わせが重要になってくるでしょう。
⑦給与・待遇・昇進の考え方
7つ目は、給与・待遇・昇進の考え方の違いです。
❚ 新卒採用の給与・待遇・昇進の考え方
給与や待遇について、高卒や専門卒、大卒などによって多少の変動はあるものの、新卒採用の場合は月収や年収にそこまで大きな差はなく、待遇にも差はありません。
ポテンシャル採用のため、これからの期待をこめた給与の設定となります。それほど高い金額ではないため、入社してすぐに力が発揮できなくてもそこまで大きな問題にはなりません。教育段階を経て徐々に実力をつけていき、実力に伴い給与もあがっていく仕組みです。
◎新卒採用の初任給・平均年収
厚生労働省によると、新卒の大学生の初任給の手取り平均額は25.5万円で、前年の23.7万円から1.1万円増加しました。また、新卒1年目の平均年収は297.9万円で、前年の284.7万円から13.2万円増加しています。初任給・平均年収ともに増加傾向にあることがわかります。
【参考】厚生労働省『令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況』
❚ 中途採用の給与・待遇・昇進の考え方
中途採用の場合は、スキル次第で給与の幅が大きく変化します。入社時のスキルによって給与が決まるので、どれだけ実力があるのかを見極めることが重要でしょう。
低い給与を提示しても人は集まりませんが、高い給与を提示することはミスマッチが起きたときのリスクになります。そのため、中途採用における給与設定は特に難しい問題となりがちです。
◎中途採用の平均年収
株式会社マイナビによると、転職者の11月の全国平均初年度年収は501.2万円で、前年11月の平均478.4万円から22.8万円増加しました。
この初年度年収を12で割った場合、月収はおよそ41万円と出すことができます。ほかにボーナスなどもあるため月収の値は前後しますが、中途採用の平均的な月収はおよそ35万円~41万円前後であると考えることができます。
【参考】株式会社マイナビ「2025年11月度 正社員の平均初年度年収推移レポート」
【参考】株式会社マイナビ「2024年11月度 正社員の平均初年度年収推移レポート」
新卒採用のメリット・デメリット
新卒採用にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。ここでは、それぞれについて詳しく解説します。
新卒採用のメリット
ここでは、新卒採用を行うメリットを次の4つから解説します。
▼新卒採用のメリット
- 優秀な人材を幹部候補生として囲い込める
- 企業文化や理念が浸透した人材を育成できる
- 組織の年齢バランスを保てる
- 1人あたりの採用コストが低い
①優秀な人材を幹部候補生として囲い込める
1つ目のメリットは、ポテンシャルが高い優秀な人材を確保し、自社で育成できる点です。一般的に、新卒学生の給与は一定のレンジで設定されます。そのため、個で評価される中途採用に比べて、ポテンシャルが高い優秀な人材を採用しやすいと言えます。
また、同期がいることでお互い支え合いながら切磋琢磨できるため、高いポテンシャルを生かせることが期待できます。
②企業文化や理念を継承する人材を育成できる
2つ目のメリットは、企業文化や理念を将来にわたって継承できる人材を育成しやすい点です。新卒採用では、自社が新卒者にとって初めて就職する企業となります。そのため、仕事の進め方や価値観、働く上ので「当たり前」が自社基準になりやすいです。
また、先輩や上司から丁寧に仕事を教えられるなど、育ててもらえることで、愛着を持ちやすい点も特徴です。
さらに、新卒採用は入社後の研修期間が長いため、企業文化が組織内に浸透しやすく、長期的な人材育成につながるといえます。
③組織の年齢バランスを保てる
3つ目は、組織の年齢バランスを保てることです。企業の長期経営を考えると、毎年フレッシュな人材が入社することは、大きなメリットになります。スキルが高いベテランが多い企業では、スキルの継承ができず、経営が立ち行かなくなる可能性が高いです。
また、若い世代の採用を行うことで時代のトレンドや新しい感覚を自然と取り入れることが可能です。新卒採用を毎年行うことで、社員の年齢構成バランスがとれ、企業の安定した成長が可能になります。
④1人あたりの採用コストが低い
4つ目のメリットは、採用コストが低いことです。新卒採用は同時期に多くの人材を採用するため、効率よく採用活動を行えます。
また、新卒採用では入社時期や研修期間が既に決まっているため、研修を新卒社員全員に同時に行うことができます。採用人数が1000人であっても、同時に採用活動・研修を行えるため、1人あたりのコストを大幅に下げられるでしょう
新卒採用のデメリット
ここでは、新卒採用を行うデメリットを次の3つから解説します。
▼新卒採用のデメリット
- 採用までにかかる工数が多い
- 教育・研修が必要である
- ミスマッチが起こる可能性が高い
①採用までにかかる工数が多い
新卒採用のデメリットの1つ目は、採用までにかかる工数が多いことです。新卒採用は会社説明会や就活セミナー、インターン企画や書類選考、面接、内定式、内定者研修まで含めると1年以上かかることが多いです。
また、最近は早期選考が主流になっていることも影響し、その年の採用が終わる前に翌年の採用に向け動き出さなければならないこともあります。こうした新卒採用市場の変化に伴って採用担当者の工数が多くなっています。
②教育・研修が必要である
2つ目のデメリットは、一人前に育てるために研修や教育が必要であることです。新卒の学生は経験が浅いため、ビジネスマナーなどの基礎的な研修から始まります。その後、自社のサービスや具体的な仕事フローを会得する必要があります。
このように、自社に貢献できるようには時間もコストもかかるため、初めから企業に貢献することは難しいでしょう。
③ミスマッチが起こる可能性が高い
3つ目のデメリットは、ミスマッチのリスクが高いことです。多くの新卒は、学生と社会人のギャップに戸惑うことが多いです。特に、入社前に想像していた華やかな部分と現実に悩む人も多いでしょう。
採用要件を明確に定め、透明性の高い情報公開をすることは、ミスマッチによる早期退職を防ぐ上で重要です。
中途採用のメリット・デメリット
次に中途採用のメリット・デメリットを確認していきましょう。
中途採用のメリット
ここでは、中途採用を行うメリットを次の4つから解説します。
▼中途採用のメリット
- 即戦力としての活躍が期待できる
- 基礎的な研修が必要ない
- 短期間かつ必要なタイミングで採用できる
- 新しいノウハウを組織に導入できる
①即戦力としての活躍が期待できる
1つ目のメリットは、中途採用で獲得した人材は即戦力としての活躍が期待できる点です。多くの場合、中途採用では採用要件に求めるスキルや経験を設けています。そのため、採用される人材は基本的にその企業で働くための基本スキルが備わっています。
企業の雰囲気や仕事のやり方に慣れてしまえば、すぐに戦力として活躍してもらえるでしょう。
②基礎的な研修が必要ない
2つ目のメリットは、中途採用で獲得した人材はビジネスマナーなどの基礎的な研修が必要ないことです。中途市場の人材は、前職で研修を受けていたり、実際にビジネスの現場経験があるために基礎的なビジネスマナーが備わっています。
また、同業種で働いていた人であれば業界のルールや仕事の流れについての教育も不要になるため、さらに教育コストを下げることができるでしょう。
一方、新人研修は基本的に先輩や上司が教育することになり、その間教育をしている人の手を止めてしまいます。そのため、研修の期間がほとんどいらない中途人材を採用することで、指導の負担や研修の費用などが抑えられるのです。
ただし、自社のルールや文化についての理解を促すための研修は必要になります。実際に実施することで、早く企業文化に馴染むことができ、業務効率も上がるでしょう。
③短期間かつ必要なタイミングで採用できる
3つ目のメリットは、短期間かつ必要なタイミングで採用できることです。中途採用の場合、新卒採用と同様に会社説明会を行う場合もありますが、転職エージェントなどを活用し個人面談で進めることが多いです。
実際、最初に連絡をとってから早ければ1カ月程度で内定提示まで進むこともあります。このように、中途採用は採用までにかかるプロセスが少ないため、短期間で、かつ必要なタイミングで人材を獲得できるというメリットがあります。
④新しいノウハウを組織に導入できる
4つ目のメリットは、中途採用を行うことで組織に新しい風を吹かせることができる点です。中途人材を採用することで、他社での経験やノウハウを自社に取り入れることができます。
こういった情報は企業成長や事業成長につながる新しい発想につながります。また、今まで気づけなかった自社の課題も、他社の視点を持った人材を採用することで気づくことができるかもしれません。
中途採用のデメリット
ここでは、中途採用を行うデメリットを次の3つから解説します。
▼中途採用のデメリット
- こだわりが強い場合がある
- ミスマッチが起きたときのダメージが大きい
- 若い世代が育たず、会社の長期的な成長につながらないリスクがある
①こだわりが強い場合がある
1つ目のデメリットは、中途で採用する人材は仕事のやり方にこだわりが強い可能性があることです。中途採用のメリットの1つに、「即戦力として働ける」ことがあります。これは言い換えると自身の仕事のやり方やスタンスが確立されているということです。
中にはこれまでのやり方にこだわるあまり、自社の仕事のフローを無視して自己流で仕事を進める方もいるでしょう。
中途採用で獲得した人材と既存の社員の両方に最大限活躍してもらうためには、双方の良いとこどりをした業務プロセスを確立するといった柔軟性が必要です。
②ミスマッチが起きたときのダメージが大きい
2つ目のデメリットは、ミスマッチが起きたときのダメージが大きいことです。中途採用は多くの場合、即戦力を期待して採用することが多いです。
そのため、ミスマッチが発生すると期待した成果を得る前に転職してしまい、時間や費用だけが無駄になってしまう可能性があります。
また、中途採用はスキルや経験で評価する分、給与も高くなりがちなため、経済的なダメージも大きいでしょう。
③若手が育たず、長期的な企業成長が損なわれるリスクがある
3つ目のデメリットは、若い世代が育たず、組織がマンネリ化し、企業の成長が停滞してしまう可能性があることです。中途採用は基本的に即戦力となる人材を採用するため、年齢が高くなったり、一定の年代に偏りがちです。
新しく入社してくるのが自分より年齢が高く、スキルが高いメンバーばかりになれば、若手の活躍機会が奪われ、成長実感を感じられないことで若手が不満を募らせてしまうかもしれません。
若い世代の成長機会が減ってしまうということは、今後の会社を担う人材の成長機会を減らすのと同じことです。即戦力で活躍してくれるからといって中途の社員ばかりを採用すると、会社の将来的な成長に影響を与える可能性が高いです。
「将来のコアメンバー採用」なのか、「欠員による急遽の採用」なのか、事前に目的を明確にし、採用の必要性を吟味しなければ組織のマンネリ化を招いてしまいます。
【ケース別】新卒・中途どちらの採用手法が向いている?
新卒採用と中途採用それぞれのメリット・デメリットを解説してきました。ここでは、想定されるシチュエーション別に適した採用手法を解説します。自社の状況と照らし合わせて参考にしてみてください。
▼想定ケース一覧
- 将来幹部候補となる人材が欲しい
- 専門性の高い人材を自社で育成したい
- 今すぐ即戦力として活躍してくれる人材が欲しい
- 組織に新しいノウハウ・風を吹かせたい
- 若手比率・年齢構成を整えたい

1.将来幹部候補となる人材が欲しい
⇨新卒採用が適している
今の事業を継続して行っていく予定の場合、あるいは事業拡大に備えて将来のコアメンバーを採用したい場合、若い人材の獲得が必要になります。若い人材は即戦力にはなりにくいものの、変化に柔軟に対応でき、企業を長期的に支えていく最適な存在です。
新卒採用には多くの手法が存在するため、自社にマッチした手法を比較検討して選択することが重要です。
2. 専門性の高い人材を自社で育成したい
⇨新卒採用が適している(場合に応じて中途採用も◎)
エンジニアなど、理系の一部の技術職や研究職は母数が非常に少なく、採用したいタイミングにそもそも転職市場にいない可能性もあります。
そのため、既に専門性の高い社員が在籍している場合には、新卒採用をおすすめします。実務未経験であっても、教育の中で実務に触れていき、数年後には社内の希少人材として活躍してくれるでしょう。
しかし、自社にそもそも専門性を持った人材がいない場合、採用要件を決めたり、技術や知識の高さを判断することも難しくなります。そのため、中途採用である程度スキルを持った人材を採用したい場合、その領域に強い転職エージェントを活用することもオススメです。
3. 今すぐ即戦力として活躍してくれる人材が欲しい
⇨中途採用が適している
今すぐ即戦力として活躍できる人材を採用したい場合、中途採用がオススメです。事前に期待する役割や必要な経験、スキルを設定したうえで採用に取り組むことで、効果が期待できるでしょう。
中途採用はピンポイントで必要になることが多いため、採用までのスピードが速く条件に合った人材を紹介してくれる人材紹介サービスがおすすめです。
4. 組織に新しいノウハウ・風を入れたい
⇨中途採用が適している
組織に新しい風を吹かせるためには、他社でスキルを磨いた人材や、新しいリーダーになれるような人材が必要となります。この場合、中途採用がおすすめです。
職務経歴書で過去の経験や実績を把握することはもちろん、管理職経験がある人材などには、マネジメントのノウハウについて意見交換するなどして、自社にマッチした人材か見極めることも可能です。
マネジメントに特化した管理職やスキルを磨いた人材をピンポイント採用する場合も、人材紹介サービスがおすすめです。
5. 若手比率・年齢構成を整えたい
⇨新卒採用が適している
組織の年齢層が偏っている場合や、将来的な人材不足を防ぎたい場合は、新卒採用が効果的です。特定の年代に人材が集中していると、数年後に退職や異動が重なり、業務やノウハウが一気に失われるリスクがあります。
毎年一定数の若手人材を採用・育成することで、
・業務や知識の継承がスムーズに進む
・世代間で役割分担ができ、組織運営が安定する
・将来のリーダー候補を計画的に育成できる
といった効果が期待できます。
また、新卒社員が継続的に入社することで、組織に新しい価値観や発想が自然に取り込まれやすくなり、変化に強い、持続的に成長できる組織づくりにもつながります。
❚ 新卒採用と中途採用を判断する際の視点
新卒採用と中途採用のどちらを選ぶかは、「いま何が足りていないか」だけでなく、「将来どのような組織を目指すのか」を基準に考えることが重要です。
短期的に成果を出せる即戦力を求めるのか、時間をかけて人材を育成して将来の中核人材を増やしたいのか、事業フェーズや組織の状況に応じて新卒採用と中途採用を組み合わせ、中長期視点で採用戦略を設計することが、持続的な組織成長につながります。
新卒採用・中途採用を成功させるためのポイント
新卒でも中途でも、採用をうまく進めるには事前準備が大切です。ここでは、採用を成功させるためのポイントを整理します。
▼新卒採用・中途採用を成功させるためのポイント
- 事業計画を明確にする
- 人事戦略を定める
- 採用計画を設計する
- 採用戦略を立てる
事業計画を明確にする
採用の前に、まず事業計画を確認します。「どの事業に・いつまでに・どれだけ人が必要か」が見えると、採用の方向性が定まります。
▼事業計画で整理するべきこと
- 事業目標
- 売上予測
- 人員構成
この整理ができると、採用計画が立てやすくなり、新卒/中途どちらが合うかも判断しやすくなります。
人事戦略を定める
次に、必要な人材を具体化します。 事業計画から逆算して、以下を整理しましょう。
▼人事戦略を定めるうえで考えるべきこと
- どの事業・部署の人材が必要か
- 求めるスキルや経験
- 必要な人数
配置転換で足りる場合もあります。採用が必要なら、人物像を描いたうえで、新卒と中途の比率も検討していきます。
採用計画を設計する
採用計画は、採用活動をスムーズに進めるための設計図です。人数・時期・予算・選考フローを決め、進捗を管理しやすくします。
▼採用計画で決めるべき項目
- 採用人数
- 採用時期
- 採用予算
- 選考フロー
- KPI(応募数・通過率・内定率など)
▼新卒採用の採用計画の進め方
- 年間スケジュールを前提に計画する
- 母集団形成を意識した人数設定を行う
▼中途採用の採用計画の進め方
- 必要なタイミングで柔軟に採用する
- 選考スピードを意識した設計にする
事前に計画を整えておくことで、無理のない、成功につながる採用活動を進めやすくなります。
採用計画の立て方について、以下の記事で詳しく解説していますので、そちらも合わせてご確認ください。
【参考】採用計画の立て方を5つのポイントで紹介します|テンプレート付き
❚ 採用フローの設計のポイント
採用計画において、採用フローの設計は非常に重要です。なぜなら採用フローは応募から内定までをスムーズにつなぐための流れであり、複雑すぎたり遅すぎたりすると離脱につながる可能性があるためです。
新卒採用・中途採用それぞれにおける採用フローの設計のポイントは以下の通りです。
◎新卒採用の採用フロー設計ポイント
- ポテンシャルや意欲を段階的に見極める
- 説明会や面談など、相互理解の場を設ける
- 選考期間が長くなりすぎないよう調整する
◎中途採用の採用フロー設計ポイント
- スキルや経験を早い段階で確認する
- 選考回数を最小限に抑える
- 合否判断はスピードを重視する
採用計画で定めた選考フローやKPIと連動させることで、無理のないスケジュールで採用活動を進めやすくなります。
面接で見るべきポイントを明確にする
面接では、スキルや経験だけでなく、事業や組織との相性も含めて総合的に確認することが大切です。具体的には、次のようなポイントを意識して見ていきましょう。
▼中途採用の面接で見るべきポイント
- 求めるスキル・経験を満たしているか
- 組織やチームにフィットしそうか
- 新しい環境にも対応できそうか
【Q&A】新卒採用・中途採用の違いに関するよくある疑問
新卒採用と中途採用については、立場を問わず多くの疑問が寄せられています。ここでは、特によくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説していきます。
Q.第二新卒とは?新卒・中途採用との違いは何ですか?
第二新卒とは、新卒で入社後、おおむね1〜3年以内に転職活動を行う若手人材を指します。法律上の明確な定義はありませんが、実務経験が浅い点が特徴です。
新卒採用は学生が対象であるのに対し、第二新卒は社会人経験がある点で中途採用に分類されます。一方で、ポテンシャルや成長意欲を重視されやすく、評価軸は新卒採用に近い側面もあります。
Q.新卒採用と中途採用での給料・出世に違いは出ますか?
企業や制度により異なりますが、入社時の給与やスタートポジションには違いが出ることが多いです。
新卒採用は、一律の初任給からスタートする制度が一般的です。一方、中途採用は、経験やスキルに応じて、より高い給与や役職で入社する場合もあります。
ただし、長期的な評価や昇進は入社後の成果次第であり、新卒・中途による差が固定されるわけではありません。
Q.新卒採用と中途採用における面接・採用フローの違いを教えてください
新卒採用では、説明会・エントリー・複数回面接・内定という長期的なフローが一般的です。人柄や価値観、成長意欲を見極めることが重視されます。
中途採用では、書類選考と数回の面接で完結する短期・実践重視のフローが多く、即戦力性やスキルの確認が中心となります。
Q.新卒採用・中途採用市場の最新動向を知りたいです
近年は、人材の流動化が進み、新卒一括採用に加えて中途採用を強化する企業が増加しています。特にIT分野では即戦力ニーズが高く、中途採用の比重が年々高まる傾向にあります。一方で長期的な人材育成を目的に新卒採用を継続する企業も多い状況です。
このような背景から、新卒採用と中途採用を併用する「ハイブリッド採用」が、現在の主流となりつつあります。
【参考】パーソルキャリア株式会社『doda転職求人倍率レポート(2025年7月発行版)』
新卒採用を行うならMatcher Scout
「採用活動の業務に日々追われている」「採用担当だけでは手が回らない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービスです。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、工数をかけずに効率的な採用活動を行うことができます。弊社の担当者と一緒に採用活動を成功させませんか?ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】運用負荷は一番少ない。「効率的」に「会いたい学生」に会えるツール
まとめ
いかがでしたか。新卒採用と中途採用の違いや特徴を理解することで、自社に適した採用手法を選択できます。メリット・デメリットを理解したうえで、今の自社のシチュエーションに適した採用手法はどちらなのか、あるいは両方同時に行うのか考えることが大切です。




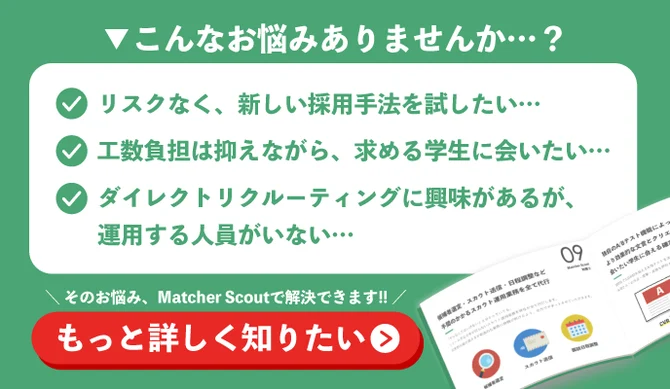

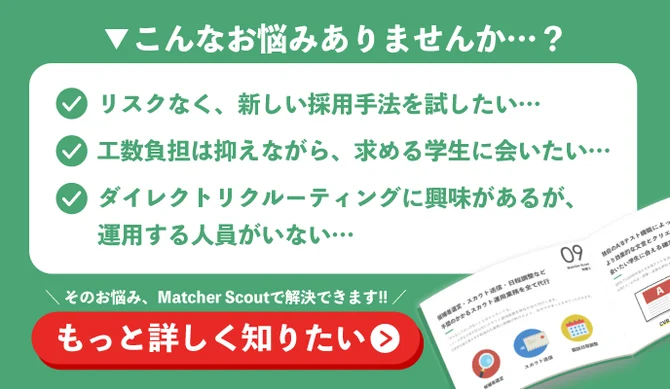



_Crop%20Image.jpg)

