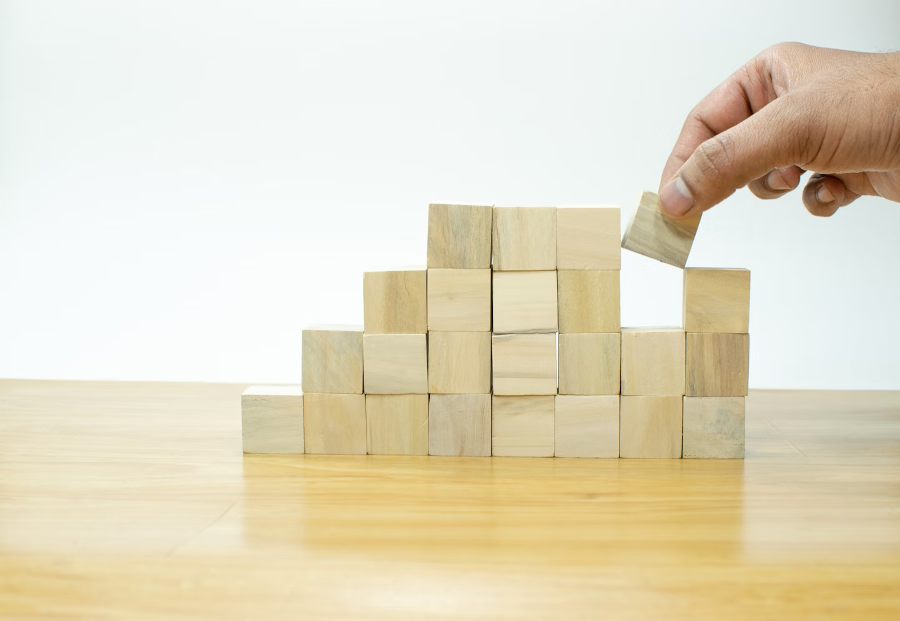近年人材活用界隈で度々話題になるHRテックですが、どのような領域で活用されているのでしょうか?
本記事では、最近の市場動向を踏まえて導入をおすすめする理由と企業を紹介します。
人事業務を効率化するHRテックとは?
HRテックとは、Human Resource(人的資源) と Technology(技術)を掛け合わせた造語で、採用管理や人員配置、事務手続きのような人事業務における様々な課題をビッグデータやAI(人工知能)、クラウドのような先進技術を用いて組織に変革をもたらすサービス・技術の総称を指します。
例えば、履歴書を基に採用候補者の特徴を分類したり、数値入力のような事務手続きの自動化もHRテックの1つです。
従来の人事システムとの違い
従来の人事システムとは、「採用情報や従業員情報のような情報の一元管理」や「手動業務の自動化」を通して業務を効率化することを目的としたシステムです。これに対してHRテックは業務の効率化の先にある、データの分析・活用を通じた組織変革を目的としています。
HRテックが解決する7つの業務
HRテックの活用は人事業務の高度化を実現できます。例えば、数値入力のような単純作業をHRテックでカバーすることで空いた時間は、人材管理や人事戦略に活用できるでしょう。
それでは、具体的にどのような業務を解決できるのでしょうか。ここでは、次の7つについて解説します。
▼HRテックが解決する7つの業務
- 採用管理
- タレントマネジメント
- エンゲージメント
- 勤怠管理
- 給与計算
- 健康管理
- 事務手続き
①採用管理
採用管理の分野では、求人情報の掲載から応募者の選定、面接調整、最終的な採用決定など一連のオペレーション業務を自動化できます。さらに、得られた選考データを次の採用業務に生かすための分析を行うことが可能です。このように過去のデータを活用することで、応募者の選定や潜在的な採用候補者へアプローチも可能になります。
②タレントマネジメント
組織の力を最大化するには従業員のスキルをひとり1人把握し、人事配置を適切に行う必要があるでしょう。しかし、従業員規模が大きくなるにつれて、この作業は煩雑になって行きます。そこで、HRテックを活用して従業員のスキルや業績、キャリアの進展を継続的に可視化して一元管理することで個々の能力を生かした配属を可能とします。
③エンゲージメント
エンゲージメントとは従業員の企業に対する愛着や思い入れを指します。職場満足度や業務へのモチベーションを測定し、従業員と企業との関係性を可視化します。従業員のエンゲージメントを分析してトラブルや離職を未然に防ぐ施策を実施できるでしょう。
このように、従業員のエンゲージメントを事前管理することで企業の安定的な成長に貢献する組織を作ることができます。
④勤怠管理
近年は、テレワークやフレックスのように勤務体系が多様化しています。そんな中、HRテックによる勤怠管理の自動化は、手作業と比べて入力ミスを減らすだけでなく、入力者の時間やエネルギーを大きく減らすことになるでしょう。
特に、ヒューマンエラーを減らすことは従業員と企業の信頼関係の維持につながるでしょう。
⑤給与計算
給与計算では従業員の給与やボーナス、控除を自動で計算するだけなく、法改正等の変更に柔軟に対応できます。さらに、クラウド型システムによってどこからでも給与計算が可能で、明細の生成や振り込みの機能も提供されています。
また、給与計算を一元管理することで人件費の計算も容易になるでしょう。
⑥健康管理
HRテックを使って従業員の健康状態を追跡調査・分析することでストレスや病気による離職、休職を予防できます。特に、一元管理されたデータを産業医と共有することで事前準備によって生じる煩雑な業務の削減が可能です。
⑦事務手続き
事務手続きの自動化ツールは文書の記入や承認、データ入力の際に発生するミスを削減できる上、一元管理されたデータベースによって情報の更新を容易に行えます。
これにより、作業時間を短縮し、業務効率の改善が狙えるでしょう。
HRテックを導入するメリット
HRテックを導入することでどのようなメリットが得られるのでしょうか。
ここでは、次の4つのメリットについて紹介していきます。
▼HRテックを導入する4つのメリット
- 人事業務の効率化・高度化
- 企業にマッチした人材の採用
- データ分析に基づいたタレントマネジメント
- 従業員の離職率低下
①人事業務の効率化・高度化
HRテックが活用される中で大きな力を発揮してくるのがこの「人事業務の削減」です。例えば、オンライン入社手続き、年末調整や契約などの単純な業務をHRテックに代行させることができます。このような人事業務の削減によって、担当者はより高度な業務に従事することができるようになります。
②企業にマッチした人材の採用
近年、AI・機械学習を用いて過去のデータを採用に活用する企業が増加しています。例えば、自社で活躍している従業員のエントリーシートをAIに学習させることで、応募者のエントリーシートから自社にマッチした人材か否かを判断させることができます。
③データ分析に基づいたタレントマネジメント
人事担当者に判断を委ねられていた組織マネジメントにも大きな影響を与えています。
大きく分けて、以下の2つが効果を生むと考えられます。
(1)評価基準の明確化
社員一人一人の働きを可視化し、データとして算出することで評価基準を明確化できます。社員を客観的に評価することで公平な組織マネジメントが可能になるでしょう。一方、平等な評価が得られる環境では、長時間勤務を行い過労状態になる社員が出る恐れもあります。
HRテックを用いて勤務状況の管理も同時に行うことで、こうしたリスクを未然に防ぎ、健全で公正な組織運営を実現できます。
(2)データ分析に基づくタレントマネジメント
社員ひとり一人が持つ特性・志向は異なります。得意不得意やモチベーションの上げ方にも差があるため、人事には見えていないスキルセットや個人の価値観なども、企業が把握しておくべき重要な要素です。
HRテックを用いることで、こうした個々のデータを集積・分析し、より効果的な人材配置や組織マネジメントが可能になります。評価基準が明確化され、自分にあった部署で働くことができれば、社員たちは自然と帰属意識が高まり、より高いモチベーションで働くことができるでしょう。
④従業員の離職率低下
多くの企業で人事の課題となっているのが離職率の高さで、主な原因に企業と学生のミスマッチと言われています。例えば、「キャリアアップができない」「やりたい仕事ができない」「思ったように成果を出せない」など入社前の理想と現実のギャップがあげられます。
このようなギャップを無くすためには、採用段階でもっとコミュニケーションをとることが重要です。HRテックによる人事業務の効率化により、学生とコミュニケーションをとる時間が確保できるとともに、組織マネジメントの質も高めていけるため、結果として離職率の低減につながります。
HRテックで使われるテクノロジーとは?
ここからは、HRテックで使われるテクノロジーにはどのようなものがあるのか紹介していきます。
①AI技術
HRテックを語る上で重要な要素となるのがこの「AI技術」の進化です。AI技術とは、人工知能・機械学習とも呼ばれ、学習したデータにもとづいた分析や解析を行うことが可能です。
ただし、今までの採用実績から学習するデータが大量にある大手企業に比べて、元のデータが少ないスタートアップ企業などではうまく効果を発揮できないこともあります。
②クラウド
「クラウド」とは、自社でサーバーを用意しなくても、インターネット環境があればどこでもシステムにアクセスできる技術です。
SaaSやクラウドシステムと呼称され、働き方改革やコロナウイルスによるリモートワークの影響を受け、多くの企業がこのクラウド型サービスを利用するようになりました。従来の金銭的・人的コストがかかるオンプレミス型とは異なり、端末や場所に関わらず利用することができることが爆発的に注目されるようになった要因だと考えられます。
③ロボティクス・プロセス・オートメーション(RPA)
RPAは、クラウド上で動くソフトウェアであり、計算や転記を自動で行うことができるものです。請求書や経費の処理、発注や受注の業務を自動化・効率化してくれます。
HRテックを導入するステップ
実際にHRテックを導入する際はどのようなステップが必要になるのでしょうか?次の4つのステップにわけて解説します。
▼HRテックを導入する4ステップ
- 導入目的に基づく運用計画の立案
- 利用サービスの選定
- トライアル運用の実施
- PDCAによる改善
①導入目的に基づく運用計画の立案
まずは、現在の人事業務における課題を洗い出し、解決すべき課題の優先度やボトルネックを特定して、なぜHRテックを導入するのか目的を明確にしましょう。
例えば「離職率が高い」という課題がある場合、根本的な原因として、採用のミスマッチや労働環境などいくつかの要因が考えられるでしょう。課題が明らかになったら、何年後にどのような状態になっていたいのかゴールを設定し、そこから逆算して運用計画を立てます。その際、現場のマネージャーやバックオフィスの管理職などにも議論に加わってもらいましょう。
②利用サービスの選定
運用計画に沿ってHRテックの選定を行いましょう。HRテックは多種多様なものが存在するため、複数のサービスを比較検討して自社の課題解決に適したものを選ぶ必要があります。
サービスを選定する際には、単に課題解決につながりそうかだけではなく、自社が導入している既存システムとの相性にも注意してください。既存システムとの連携がうまくいかないと、入力や管理が二重になってしまうなど無駄な工数が発生する可能性があります。
③トライアル運用の実施
導入するHRテックを選定したら、本格的な導入の前にトライアル運用を行いましょう。トライアル運用を行うことで、見落としていた課題が明らかになることもあります。
期間と適用範囲を定めて効果測定を行うことで、本導入時の効果をより高める策を講じたり、運用ルールなどを周知したりする際に役立てることができるでしょう。
④PDCAによる改善
正式に導入した後は、1年未満の短いスパンで効果検証と改善を繰り返してください。使いづらい点はないか、コストは削減できているか、業務は効率化できているかなど、導入効果を計測し、さらなる効率化を図りましょう。
HRテックを運用する際の注意点
ご紹介したように、HRテックを運用することによってさまざまな効果が期待できます。ここでは、HRテックを効果的に運用するために注意すべき点を以下の3点紹介します。
▼HRテックを運用する際の注意点
- 中長期的な視野を持つ
- 個人情報の取り扱いに気をつける
- あくまで業務をサポートするツールとして扱う
①中長期的な視野を持つ
HRテックは、導入してからすぐに効果が出るわけではありません。自社の情報をデータとして蓄積し、活用するには時間も労力もかかります。
HRテックを効果的に活用するには、利用者側のリテラシーも必要です。そのためHRテックを用いた課題解決は、中長期的な視野を持って取り組むようにしましょう。
②個人情報の取扱い
HRテックを活用した人材管理では、膨大な個人情報を集積し取り扱います。セキュリティ対策をしっかりと行い、社員の個人情報やプライバシー保護に注意して運用しましょう。
③あくまで業務をサポートするツールとして扱う
HRテックはあくまでも人事業務を効率化し、サポートするツールです。HRテックに過度に期待したり依存したりすることは避けましょう。
データばかりを鵜呑みにするのではなく、現場の状況や意見も鑑みながら、「人」が主体となって業務にあたるということを念頭に置いてください。
HRテックを提供する企業ランキング
ここで、HRテックの企業売り上げランキングを上位から紹介し、各社が提供しているサービスをご紹介します。
株式会社リクルート
株式会社リクルートは、主に以下のHRテックサービスを展開しています。
- 特徴:求人検索エンジンIndeedへの掲載ができる無料採用支援ツール
- 特徴:応募から入社までの選考状況をクラウド上で一元管理する無料採用管理システム
- 特徴:シフトの作成と管理がひとまとめで行えるシフト管理サービス
- 特徴:個人と組織の課題をそれぞれ見える化し、働き方改善をささえるHRサーベイ
株式会社ビズリーチ
株式会社ビズリーチは、主に以下のHRテックサービスを展開しています。
- 特徴:勤怠管理や人財活用などの各システムを展開
株式会社SmartHR
株式会社SmartHRは、主に以下のHRテックサービスを展開しています。
- 特徴:労務を全てデジタル化する労務管理サービス
パーソルプロセス&テクノロジー株式会社
パーソルプロセス&テクノロジー株式会社は、主に以下のHRテックサービスを展開しています。
- 特徴:仕事を可視化しホワイトな働き方を実現する労務管理ツール
- 特徴:クラウド型勤怠管理システム
- 特徴:タレントプールの構築を行う採用管理システム
エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン株式会社は、主に以下のHRテックサービスを展開しています。
- 特徴:新入社員の入社後フォローを支援するオンボーディングシステム
- 特徴:従業員のリスキリングを支援するe-ラーニングシステム
- 特徴:人事コンサルのサポートも受けられるタレントマネジメントシステム
- 特徴:採用プロセスを効率化する無料の採用管理サービス
株式会社マイナビ
株式会社マイナビは、主に以下のHRテックサービスを展開しています。
- 特徴:人材開発・組織開発を支援するタレントマネジメントシステム
- 特徴:アルバイト、パート向けの採用管理サービス
- 特徴:新卒採用に特化した採用管理サービス
freee株式会社
freee株式会社は、主に以下のHRテックサービスを展開しています。
- 特徴:会計・税務・給与などをクラウド上で管理できるシステム
- 特徴:労務事務を一気通貫で管理できるクラウドサービス
HRテックの導入事例
①株式会社日立製作所
株式会社日立製作所では、世の中の流れが「コトづくり」に変化しつつある中で、「モノづくり」に特化した人財が多いということが課題でした。そこでHRテックを導入し、「コトづくり」に特化した人財を採用することで、5%程しかいなかった「コトづくり」人財を15%まで上げることに成功しました。
そして更なる問題として、タレントマネジメントの点に関しても改善させていこうと考え、
「生産性の向上」「配置配属のフィット感の向上」を目指し、「AI分析」や「ピープルアナリティクス」を活用しながら、現在も新たな施策を打ち続けています。
【参考】Hitachi, Lt_人事の実践経験者が語る! HRテックを活用した日立の働き方改革の実例
②エイベックス株式会社
エイベックス株式会社では、採用管理ツールを複数使用していることでミスが起こりやすく、タイムロスを生み出してしまっているという課題を抱えていました。従業員数も膨大であるため管理業務に時間を取られてしまい、新たなチャレンジができないなど、事業の停滞といった意味でも解決しなければならない問題だったと言えるでしょう。
そこでHRテックを導入したことで、採用管理システムの導入で管理ツールが統一され、管理がシンプルになり、無駄な工数を約4割削減することに成功しました。
また、連絡漏れや単純なミスなどが減り、採用業務にかける不安というものが払拭されたため新たなチャレンジが可能となる事で更なる改革を進めることができるようになりました。
③ソフトバンク株式会社
ソフトバンク株式会社では、年間3万人の求人応募があり、採用業務に多大な人的資源を費やしていました。膨大な人数のエントリーシートの合否判定を行わなければならないため、人事担当者ごとの判定の偏りやヒューマンエラーが起きやすいという課題もありました。
結果として、早期退職や求める人材と異なる人材を採用してしまうといった事態が起こってしまっていたのです。
これを解決するために同社は「AI」によるエントリーシートの振り分けを導入しました。
多大な時間を要しヒューマンエラーも起きやすいエントリーシートの振り分けに「AI」を起用することで、振り分けにかかっていた時間を約8割削減することに成功しました。
それだけでなく、AIに過去の応募者のデータを学習させたことで、企業にマッチした学生を採用することが可能になったと言えるでしょう。
【参考】日本の人事部_AIによるエントリーシート選考が“攻めの採用”を加速させる 500時間の工数を削減した“ソフトバンク流”未来の新卒採用(前編)
④株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントでは、社員数の増加に伴い、適材適所な人財配置の円滑化を目的として「人材科学センター」を設立しました。
「人材科学センター」では従業員の志向やコンディションといった主観的なデータを集めて分析し、組織活性に役立てます。同社は、チームと個人のコンディションの差や、マネージャーと個人のコンディションの差など、従業員ごとのコンディションの差を問題として捉えています。
ただし、企業文化にのっとったHRテックの活用を基盤としており、「AI予測」や「マッチング」を用いるのではなく、あくまで情報を集めてPDCAを回していくためのツールとして活用している様子です。
【参考】HR NOTE_「主観データを収集するだけでわかった」組織と個人のマッチング|サイバーエージェント人材科学センターに聴く#1
自社にマッチした学生を採用するには
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
まとめ
HRテックが注目されている事についての解説をしてきましたがいかがでしたでしょうか。
今後間違いなく多くの企業が取り入れていきたい技術であり、採用や人事管理に大きな影響を与えてくれることでしょう。
みなさんも導入するときは使う理由を明確にし、導入することが目的ではなく、何をしたいのかを意識した活用を心がけてみてください。




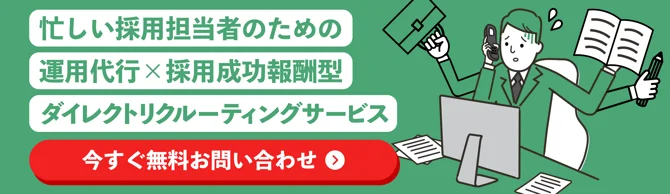
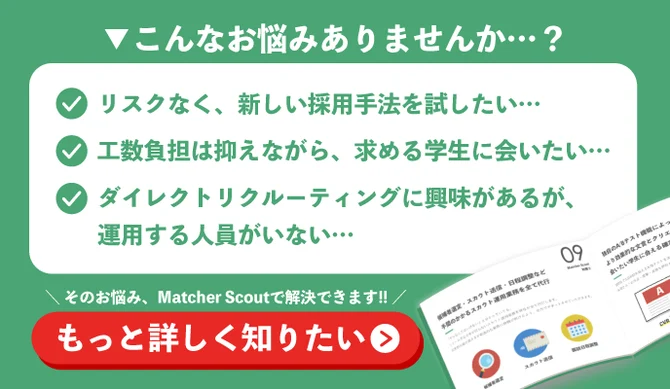
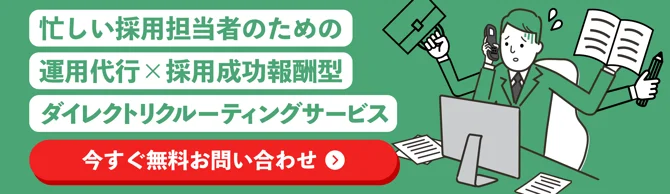




_Crop%20Image.jpg)