「面接官の間で評価軸が異なっている気がする…」
「面接でしっかり候補者を見極められているのか不安…」
面接で的確に候補者を評価するにはどうしたら良いでしょうか?本記事では、面接手法の一つである構造化面接についてご紹介します。
構造化面接は実際にGoogleの採用面接でも実践されており、注目されている手法です。本記事で構造化面接のメリットや注意点、実施する際のポイントについて確認していきましょう。
「構造化面接」とは?非構造化面接・半構造化面接との違いは?
「構造化面接」は、Googleが採用手法として導入していることで話題になりました。これがきっかけで興味をもった採用担当者様も多いのではないでしょうか。世界に大きな影響を与えている企業のGoogleが導入しているということは、それだけ効果が高い面接手法であるといえます。
ここでは構造化面接の概要とともに、非構造化面接、半構造化面接についてもご紹介します。
| 面接手法 | 質問方法 | 評価方法 |
| 構造化面接 | 全て決まった質問をする | すでに準備されている評価基準に沿って評価する(評価に一貫性がある) |
| 非構造化面接 | 事前に質問を準備せず、全て自由に質問をする | 面接官が抱いた印象から評価する(評価に一貫性がない) |
| 半構造化面接 | 最初に決まった質問をした後、面接官が自由に深掘り質問をする | 既定の評価基準と面接官の抱いた印象から評価する |
構造化面接とは
構造化面接とは、同じ職種に応募している候補者全員に対して、同じ面接手法で評価する方法のことを指します。臨床心理学で古くから使われている手法であり、事前に準備した質問や評価項目に従い、被験者の特徴を評価していきます。
エンジニアのような専門職採用では、コーディングのスキルなどから自社で活躍する素質があるかを見極めやすい一方で、総合職採用ではマインドマッチを重視した評価項目となるため、客観的なデータから候補者を見極めにくく、面接官によって評価のばらつきが出やすくなります。
そこで、質問内容や評価項目が事前に定められている構造化面接では、面接官による評価のブレが起きにくく、ミスマッチが発生しにくい仕組みとなっています。
非構造化面接とは
非構造化面接とは、質問や評価項目などを準備することなく、候補者の反応に応じて会話を展開していきながら行う面接です。その自由度の高さから、書類では見られないような候補者の意外な一面の発見や、入社への動機付けが行えます。
また、学生によって質問内容が異なるため、評価基準に一貫性がなく、面接官の判断によって合否が決まる点が特徴です。学生の本音を引き出すために面接官の技量が必要になる面接方法といえます。
半構造化面接とは
半構造化面接における候補者の分析方法は、構造化面接と非構造化面接の間に位置付けられます。半構造化面接では、構造化面接と同様に、初めの質問や評価項目を準備します。
構造化面接と異なる点は、初めに準備した質問をした後は、面接官が自由に質問をするという点です。学生の特性や本音を深掘りしやすい面接方法です。
◎自社にマッチした学生を採用するならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
【STARモデル】構造化面接の質問例
構造化面接では質問を深掘りするための質問まで用意する一方、半構造化面接では候補者の回答に合わせて面接官が自由に質問を行います。ここからは、構造化面接中にどのような質問をすればよいか、経験ベースの質問と仮説ベースの質問に分けてご紹介します。
経験(過去)ベースの質問
経験ベースの質問では、実際に今まで経験したことに対してどのように振る舞ってきたのかを聞くことで候補者の行動パターンを見ていくことを目的として行います。経験ベースの質問を行う際は、STARと呼ばれる手法を利用すると効果的です。
▼STARモデル
- Situation(状況):どのような状況だったか
- Task(課題):何が課題だったか
- Action(行動):どのような行動を取ったか
- Result(結果):どのような成果が得られたか
質問例
◎Situation(状況):どのような状況だったか
- 今まで所属した組織でのあなたの役割は何でしたか?
- どのような責任や権限を持っていましたか?
- これまでの学生生活や職務経験の中で、困難な状況に直面したことはありますか?その時の状況を教えてください。
◎Task(課題):何が課題だったか
- その組織は当時どのような目標を持っていましたか?
- その目標を達成するためには何が課題でしたか?
- 直面した問題に対して、どのような課題を解決する必要がありましたか?
◎Action(行動):どのような行動を取ったか
- どのような行動を取りましたか?
- どのように周りを巻き込みましたか?
◎Result(結果):どのような成果が得られたか
- その結果どのような変化が見られましたか?
- 今振り返って、自身の行動をどのように評価しますか?
- その行動の結果、どのような成果や学びが得られましたか?
仮説(未来)ベースの質問
仮設ベースの質問では、採用しようとしている職種に関連した業務内での出来事を仮定し、その状況への対応を聞き出し、候補者の思考パターンを見ていきます。「もし〜だった場合、どのように行動しますか?」といった起点の質問を行い、その回答から「なぜ」その行動を取ろうと考えたのかについて掘り下げていきましょう。
質問例
- 編み物講座を行うサブスクリプションサービスの売れ行きが停滞している場合、PRチームの責任者としてどのような対応を取りますか?
- もし、チーム内でメンバー間の連携がうまくいっていない状況に置かれた場合、どのように立て直しますか?
【深掘り質問の例】
「なぜその対策を取ろうと考えましたか?」
「その対策の利点と懸念点は何ですか?」
「チームのメンバーにはどのような役割を与えますか?」
「ほかに施策案はありますか?」
【面接ですぐに使える】構造化面接の質問例
ここからは、先ほど紹介したSTARモデルを活用して、面接ですぐに使えるより具体的な質問例について紹介していきます。
▼面接ですぐに使える構造化面接の質問例
- 面接で定番の質問例
- コミュニケーション能力を見極める質問例
- 論理的思考力を見極める質問例
- 真面目さを見極める質問例
- 素直さを見極める質問例
面接で定番の質問例
面接で定番の質問例は以下の通りです。
- 自己紹介をお願いします。
- 自己PRをお願いします。
- ご自身の強みと弱みを教えてください。
- 就活の軸を教えてください。
- 学生時代に最も力を入れたことはなんですか。
- これまでの挫折経験を教えてください。
- 5年後、10年後のキャリアプランを教えてください。
リーダーシップを見極める質問例
リーダーシップを見極める質問例は以下の通りです。
◎経験(過去)ベースの質問例
- チームをまとめて何かを成し遂げた経験はありますか?その時、どのような工夫をしましたか?
- リーダーとしてどのような行動をとりましたか?
◎仮説(未来)ベースの質問例
- 入社後にプロジェクトのリーダーを任された場合、何を意識してどのように行動しますか?
- チーム内で課題が生じた場合、リーダーとしてどのように解決しますか?
コミュニケーション能力を見極める質問例
コミュニケーション能力を見極める質問例は以下の通りです。
◎経験(過去)ベースの質問例
- チームで何かを達成した経験はありますか?
- 円滑なコミュニケーションを図るために何か意識して実践したことはありますか?
◎仮説(未来)ベースの質問例
- 初対面の関係者と協働する場合、どのように信頼関係を築きますか?
- 自分の意見を伝えるべき状況で、相手が年上や上司だった場合、どのように伝えますか?
論理的思考力を見極める質問例
論理的思考力を見極める質問例は以下の通りです。
◎経験(過去)ベースの質問例
- 問題が生じたとき、どのような流れで課題解決を行いましたか?
- 数値やデータを活用して提案・意思決定した経験はありますか?どのように分析を進めましたか?
◎仮説(未来)ベースの質問例
- 複雑な課題に直面し、原因が特定できない状況だった場合、どのように分析し、対応しますか?
- 複数の選択肢があり関係者の意見も分かれていた場合、どのように論理的に判断を下しますか
真面目さを見極める質問例
真面目さを見極める質問例は以下の通りです。
◎経験(過去)ベースの質問例
- 長い期間をかけて一つのものに取り組んだ経験はありますか?モチベーションはどのように保ちましたか?
- これまで目標をもって何かに取り組んだ経験はありますか?
◎仮説(未来)ベースの質問例
- もし成果がすぐに見えにくい仕事を任されたら、どのように向き合いますか?
- 地味で単調な作業を長期間任された場合、どのように取り組みますか?
素直さを見極める質問例
素直さを見極める質問例は以下の通りです。
◎経験(過去)ベースの質問例
- 課題に直面したとき、周囲の人に意見を求めて成功した経験はありますか?
- 過去の失敗を活かして成功した経験はありますか?
◎仮説(未来)ベースの質問例
- 上司から仕事でアドバイスを受けた場合、その後の仕事をどのように進めますか?
- もし上司から厳しい指摘を受けた場合、どのように対応しますか?
構造化面接が重要視されている3つの理由
構造化面接が重要視されている理由として、以下の3つがあげられます。
▼構造化面接が重視されている理由
- ミスマッチを防ぐため
- 人手不足により生産性の向上が必要であるため
- 公正な面接を実施するため
1.ミスマッチを防ぐため
構造化面接では、自社で活躍できる人材を他の手法よりも的確に見極めることができると言われています。
終身雇用制度が一般的ではなくなった現在、企業とのミスマッチが発生したときに労働者にとって転職がしやすい環境になりつつあります。離職が発生すると、企業にとって労働力が不足することはもちろん、その人材の採用コストが無駄になってしまいます。
そこで、ミスマッチによる離職を防ぐために効果的な方法が構造化面接です。実際にGoogleの社内調査で、構造化面接によって採用された人材の方が、そうではない人材よりも職務パフォーマンスの予見性が高かったという結果が出ています。
自社で活躍する人材かどうかを面接時に見極めることで、候補者と企業の双方が満足する採用を行える可能性が高まります。
【参考】Google re: Work『構造化面接を実施する』
2.人手不足により生産性の向上が必要であるため
2つ目の理由として、近年の労働市場の人手不足があげられます。リクルートワークス研究所によると、日本における労働需要と供給について、2040年に1100万人の供給不足、つまり1100万人もの人手不足が発生すると予測しています。そして、この人手不足は加速度的に増加していくそうです。
今後の加速度的な人手不足の影響によって、現状のままでは業務がさばききれなくなってしまうでしょう。
そこで、個々人に対してさらなる業務の生産性の向上が求められており、そのために企業の業務や文化に適した人材を採用すること、求職者の適材適所を見極めることが重要になるでしょう。
これを見極める手法として構造化面接の導入が進められています。半構造化面接、非構造化面接だと、面接官の印象や基準によって採用・不採用が決められるため適切な人材を取り込めない可能性があります。
3.公正な面接を実施するため
構造化面接ではあらかじめ聞く質問が決まっているため、男女や出身地など、個人による質問の違いが生じることがありません。そのため、応募者全員に公正な面接を実施することができます。
構造化面接を取り入れる3つのメリット
なぜGoogleのような大企業は構造化面接を取り入れているのでしょうか?ここでは、構造化面接を取り入れることで得られる3つのメリットについてご紹介します。
▼構造化面接を取り入れる3つのメリット
- 評価の公平性が保たれる
- 面接の効率化に繋がる
- 受験者満足度の高い面接が行える
1、評価の公平性が保たれる
「確証バイアス」というものを聞いたことはありますか?これは自分の持つ先入観や、第一印象を正しいと肯定するために都合の良い情報を無意識の内に集めようとする心理現象のことを指します。
面接官が初対面の相手に対して抱いた印象を裏付けるような証拠探しに質問が発展してしまい、候補者を正しく評価できない場合があります。構造化面接では全ての候補者に対して同様の質問を行い、評価を行うため、このような確証バイアスがかからないように改善可能です。
そのため、面接官間での評価のブレが減少し、公平に候補者を評価することができます。
2、面接の効率化に繋がる
構造化面接では、事前に質問や評価項目を丁寧に作成しています。面接ではそれらの資料を利用して行うため、必要な部分のみを残した効率的な面接が行えるようになります。実際にGoogleでは構造化面接を取り入れることによって、1回の面接で平均40分の短縮に繋がりました。
【参考】Google re: Work『構造化面接を実施する』
3、受験者満足度の高い面接が行える
構造化面接を実施し、完全にマニュアル化することで、面接官個人が質問を考える必要がなく、すべて企業が決めたことを質問することになります。その結果、質問を考える際に生じる面接官個人の価値観に沿った質問がなくなるため、価値観の違いによる応募者の不快感を防ぐことができます。
実際、面接で「この企業には入社したくないと思った」理由で一番多いのは「面接官の不快な態度・対応」で63%にも及びました。
構造化面接を行うことで応募者が不快に感じる機会が下がるため、企業自体の印象が下がるリスクを回避することができます。また、構造化面接を受験した候補者は、そうではない候補者と比べて、面接への満足度が高いという結果が出ています。
せっかく自社に興味を持ってくれた候補者には、面接に対して満足した状態で結果を受け取ってもらいたいですよね。実際に、Googleで行われた構造化面接を受けて不採用となった候補者は、構造化面接を受けずに不採用となった候補者よりも35%満足度が高かったという結果が出ています。
【参考】Google re: Work『構造化面接を実施する』
構造化面接を取り入れる4つのデメリット
様々なメリットがある構造化面接ですが、自社に取り入れる前に知っておきたい懸念点もあります。
▼構造化面接を取り入れる4つの懸念点
- 候補者の特性や人間性を見抜きにくい
- 質問の作成・見直しに労力がかかる
- 面接官に質問/評価方法を理解してもらうことが必要
- 機械的・冷たいという印象を与える可能性がある
1、候補者の特性や人間性を見抜きにくい
画一化された質問と評価を行う構造化面接では、用意した枠の範疇でしか候補者の情報を集めることができません。そのため非構造化面接よりも自由度が低く、候補者の特性や人間性が見えにくいです。
質問者と回答者という関係性が明確になりやすいため、面接中のカジュアルな会話によって候補者の自社への志望度を高めることは難しいでしょう。構造化面接は候補者の特性や能力を見極める手法のひとつであるため、候補者の内面の部分まで十分に知ることはできないことがあります。
候補者の内面を知って企業とのマッチ度を図りたい場合は、以下のような手法もあわせて取り入れると良いでしょう。
- カジュアル面談の実施
- 適性検査など、候補者の性格を把握できるツールの利用
- 選考にグループディスカッションを取り入れる
2、質問の作成・見直しに労力がかかる
構造化面接では全ての候補者に対して同じ質問と評価を行います。作成した質問や評価項目が上手く機能していないと、採用全体の計画が崩れてしまう可能性も。
自社の選考にとって最適となる質問や評価項目を作成できるように、構造化面接を経て入社した社員のパフォーマンスも確認しながら改善を行うことが必要です。
また現代はSNSで面接の質問が知れ渡る可能性があります。構造化面接の公平性を保つためにも、一定の期間で質問を変更するなどの対策を取らなければなりません。
3、面接官に質問/評価方法を理解してもらうことが必要
構造化面接を効果的に行うには、面接官と質問内容や評価方法について認識の擦り合わせをしっかりと行う必要があります。「どのような質問をどの順番で出していくのか」「なぜその質問をしているのか」「回答をどう評価すれば良いのか」などを面接官に丁寧に説明しましょう。
面接中に感じた課題点や疑問などのFBを面接官からもらい、改善に繋げる作業を行うとよりよい構造化面接が行えるようになります。
4、機械的・冷たいという印象を与える可能性がある
構造化面接は質問事項や手順がマニュアル化されているため、候補者に対して機械的な印象を与える可能性があります。「威圧的だ」「圧迫されている」と感じる候補者もいるかもしれません。
そのため、ただ質問内容をマニュアル化するだけでなく、候補者が話しやすい雰囲気をつくることが重要になります。
対策として、候補者に話しやすくする空気感をつくるためにはアイスブレイクで空気を和らげることがおすすめです。アイスブレイクで和やかな雰囲気をつくることで、候補者の飾らない姿や本音を引き出すことができるかもしれません。
どんな会社が導入すべき?構造化面接で解決できること
面接や採用の過程において以下のような課題を感じている企業には、構造化面接の導入をおすすめします。
▼構造化面接を導入するべき企業の特徴
- 面接後の評価で意見が割れることが多い
- 採用目標達成のために基準に満たない人物も採用している
- 面接時間が長くなりがち
- 早期離職者が多い
このような課題は、候補者の評価基準が不明瞭であること、採用目標に沿った質問を面接官が行えていないという2つの理由が背景にあると考えられます。
前述した確証バイアスや、目立つ特徴に意識を持っていかれて総合的な評価できなくなるハロー効果などがあるため、的確に候補者の評価を行うことはなかなか難しいです。ミスマッチを未然に防ぎ、効率的な採用を行うために、構造化面接は役立ちます。
構造化面接を成功させる5ステップ
ここでは構造化面接を実施するための手順を5つのステップで解説していきます。
① コンピテンシーの調査
コンピテンシーとは、活躍している人材が共通して持つ行動特性のことを指します。パフォーマンスの高い社員が「何を意識しながら業務に当たっているのか」「どのような思考でどんな行動をしているのか」など、思考や行動を分析してコンピテンシーを調査します。
具体的な「行動」「知識」「スキル」などではなく、その奥にある見えない「思考」「性格」「価値観」などを見ていくことがコンピテンシーを決定する際に重要です。例えば「リーダー経験がある」「アルバイト先で業務の仕組みを改善した」などはコンピテンシーではありません。
先ほどの例のコンピテンシーは、以下のように導くことができます。
リーダーシップ経験がある→指示・統率力
アルバイト先で業務の仕組みを改善した→情報整理力
また職種や役職などによって活躍のための条件が異なるため、自社が採用する人材に用意している役割のコンピテンシーを設定しましょう。
② 採用要件の設定
採用要件では、自社が採用したい人材の特徴を羅列していきます。役員や各部署に求めている人材の要件をヒアリングしながら、求める人物像を定めていきましょう。
経験、能力、価値観などある程度求めるものが定まったら、各項目を「必須条件」「歓迎条件」「NG条件」に分類していきます。例えば、Googleでは、以下の4つの要件を採用要件として設定しています
▼Googleが設定する採用要件
- 一般的な認知能力
- リーダーシップ
- Googleらしさ
- 職務に関連した知識
【参考】Google re: Work『構造化面接を実施する』
採用要件を設定する際はコンピテンシーの調査結果も反映し、活躍できる人材を効果的に採用できるように意識しましょう。
③ 面接で起点となる質問の作成
面接での質問は、「導入」と「フォローアップ」の2つの種類に分けられます。まずは導入部分にあたる、起点となる質問を作成しましょう。
起点となる質問は、採用要件にある各項目にあたり一つずつ作成していきます。例えば「主体性」という項目が採用要件にある場合は、以下のような質問が考えられます。
- ある組織で、全体のために自発的に行動した経験はありますか。
- 目標達成のために、どのように計画を立てて実行に移しましたか。
- これまで挫折した経験はありますか。その時、そのように対処しましたか。
起点となる質問は、採用要件に候補者が該当しているのか見極めるための軸となる部分です。
しっかりと各項目に対応した質問を作成できるように、「なぜこの質問を行うのか」という意図を常に意識することを心がけましょう。「【面接ですぐに使える】構造化面接の質問例」の見出しでスキル別に質問例を紹介しているため、そちらも参考にしてみてください。
④ 話を掘り下げる質問の作成
起点となる質問に対する回答が候補者から返ってきたら、その回答を掘り下げるためのフォローアップクエスチョンを行います。先ほどの「主体性」に関する導入質問で「サークルの新入部員数の低迷に危機感を感じていたため、SNS運用やイベント企画を行った経験がある」という回答があったと想定します。
この場合、「なぜ新入部員数が少なくなることを懸念したのですか?」「なぜSNS運用やイベント企画という手法を取ったのですか?」「どのような結果が得られましたか?」などの質問で掘り下げることが可能です。
話を掘り下げる質問を作成する場合、その質問によって評価したい項目についての情報が得られるかどうかが大切です。評価をより正確に行えるように、候補者の思考プロセスをより理解できるような質問を心がけましょう。
⑤ 評価基準の設定
評価基準がなければ一貫性や公平性をもって選考を行うことが難しいです。作成した採用要件や質問を元に、それぞれの項目をどのように評価していくのかについて決めていきます。
評価基準を設定する際は、「どの質問でどの項目を評価するのか」「どのような回答がどの判定に当たるのか」などを明文化していきます。例えば「主体性」の項目での質問に対し、「自身で課題発見・解決を行い、仕組み化を行った」ことが候補者の回答から読み取れたら評価は「◎」というように設定しましょう。
質問に対する候補者の実際の回答は、担当面接官がメモをして、回答と評価の実例としてナレッジを溜めていくと効果的です。
効果的な構造化面接を行うための5つの注意点
効果的な構造化面接を行うには、以下のポイントに気をつけましょう。
1、想定質問を避ける
想定質問とは、候補者が事前に回答を用意できるであろう就職活動における典型的な質問のことを指します。志望動機や学生時代に力を入れたこと、挫折した経験などに対する回答は事前準備ができるため、候補者が「企業に見せたい面」ばかりが目立つ可能性があります。
このような質問からは、実質的な候補者の思考プロセスや行動パターンなどを判断することが難しいです。質問を作成する際は、候補者が予め用意できないような質問になるよう意識しましょう。
2、誘導質問を避ける
誘導質問とは、企業側が候補者に求める回答が質問から読み取れてしまうものを指します。「弊社が第一志望ですか?」「転勤は可能ですか?」「〇〇への配属でも成果を出す自信はありますか?」などの質問は、候補者の特性を把握するための構造化面接には向いていないです。
あくまでも候補者の本音が聞けるような質問をするように心がけましょう。
3、難問奇問を避ける
「地球の直径は地下鉄の切符何枚分でしょうか?」
「自分だけ逆立ちでしか歩けなくなったら、どのように対処しますか?」
就職活動の面接では、しばしばこのような難問や奇問が出題されます。想定外の質問を行うことで、候補者の対応力や発想力を試すことが目的となっています。
一方で、Googleが行った調査によると、このような難問奇問で見られる能力が入社後のパフォーマンスにあまり影響がないことが分かりました。構造化面接では難問奇問を避け、実際の業務に関連性の高い質問を行いましょう。
【参考】Google re: Work『構造化面接を実施する』
4、構造化面接だけに頼らない
構造化面接という候補者の能力を客観的に公平に評価する手法のうちのひとつです。適性検査やグループワークなど、他の方法も組み合わせながら選考を行うことで、より多面的に候補者を見極められます。
また、面接では候補者を見極め評価するだけではなく、候補者が自社へ入りたいと思えるように志望度をあげることも重要です。前述した構造化面接のメリットや懸念点を理解した上で、強みは活かし、弱みは他の手法でカバーするなどの対応を取ることで効果的に採用活動を進めましょう。
5 、質問内容や評価基準を定期的に振り返り、改善する
構造化面接では、全ての面接において一律の質問内容と評価基準を使用して進めていきます。そのため採用要件を的確に見極められる質問が設定できていない場合や、回答に対する評価基準が曖昧になっていると、採用全体に大きな影響を及ぼします。
もちろん最初から完璧な質問や評価基準を設定することは難しいです。実際に行った面接の内容をナレッジとして溜めていきながら、質問内容が適切か、評価基準は分かりやすいか、または構造化面接を実施するタイミングは最適かなどを確かめましょう。
構造化面接を日本で導入している企業事例
構造化面接についていざ導入しようと思っても、事例がないとどのように実践すればよいかイメージがつきにくいかと思います。そこで、今回は実際に構造化面接を導入している日本企業をご紹介します。
株式会社ヌーラボ
ヌーラボでは、事前に面接の質問項目リストが作成されており、面接の際は個別にメモができるようにGoogleドキュメントをコピーして利用しているそうです。それによって、質問の漏れがなくなること、ほかの候補者と比較しながら判断が可能になったというメリットがあったそうです。
また、ヌーラボでは面接30分前に会議室に集合し、候補者の方のレジュメを見ながら、質問リストについて事前ミーティングを実施しています。それによって候補者の予習になるだけでなく、面接中に深掘りするポイントを共有することにもつながっているそうです。
【参考】wantedly「構造化面接について考えてみる #ヌーラボ人事労務アドベント]
構造化面接について学びたい方に!おすすめの書籍
構造化面接について具体的に学びたいというかたは、書籍で学ぶことがおすすめです。今回は、Googleの人事のトップがGoogleの採用・育成・評価について語った本をご紹介します。
『ワーク・ルールズ ! 』 著:ラズロ・ボック
Googleは世界に多大な影響を与える企業で、米国の雑誌『フォーブス』が選ぶ「働きがいのある企業ランキング」で何度も一位を獲得しています。社員から高評価な企業だけでなく、転職者や就活生にも大きな人気があり、Googleに採用される確率は0.2%といわれているほどです。
この本は、そんなGoogleの採用、育成、人事について細かく言及されています。
- どのように人材を選び、社員の評価をしてるのか?
- Googleはなぜそこまで働きがいがあり、ハイパフォーマンスを出せているのか?
このような疑問を解決し、世界を代表する企業の採用・育成・評価について深く学べる一冊になっています。
・著者について
著者のラズロ・ボック氏はグーグル人事担当上級副社長で、2006年にグーグルに入社しました。
従業員が6000人から6万人に増えていく過程でグーグルの人事システムを設計し、現在のGoogleにまで進化をするきっかけを作った方です。Googleは「最高の職場」としてランキングにのることも多く、それを整備したのがこの著者です。
【参考】ワーク・ルールズ! ―君の生き方とリーダーシップを変える 著:ラズロ・ボック
採用活動の工数を少なくして面接活動をするならMatcher Scoutがおすすめ
「採用活動の工数が多く、面接に十分な労力を割けない」「採用担当だけでは手が回らない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービスです。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、工数をかけずに効率的な採用活動を行うことができます。弊社の担当者と一緒に採用活動を成功させませんか?
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】運用負荷は一番少ない。「効率的」に「会いたい学生」に会えるツール
おわりに
いかがでしたか。
自社が必要な人材を効率的に見極める手法のひとつである構造化面接についてご紹介しました。自社に合った選考手法を選びながら、候補者の適性を的確に判断し、採用全体の改善に繋げましょう。




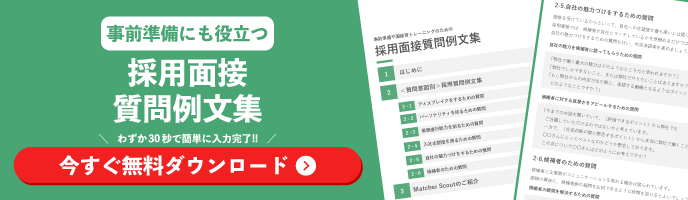
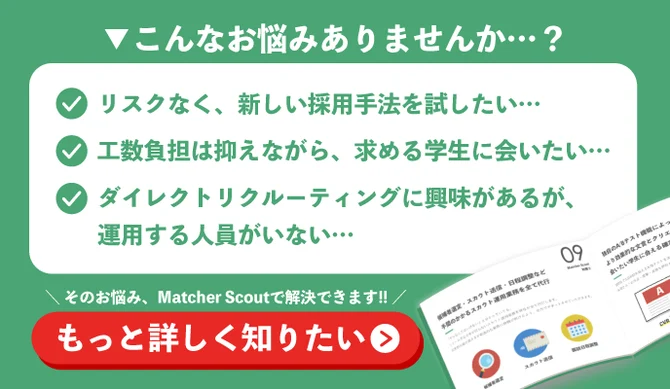
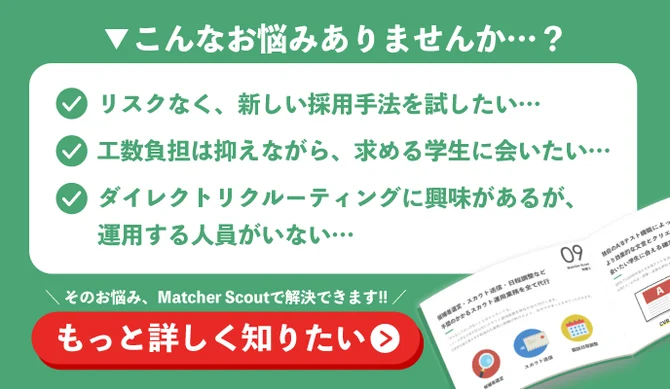




_Crop%20Image.jpg)
