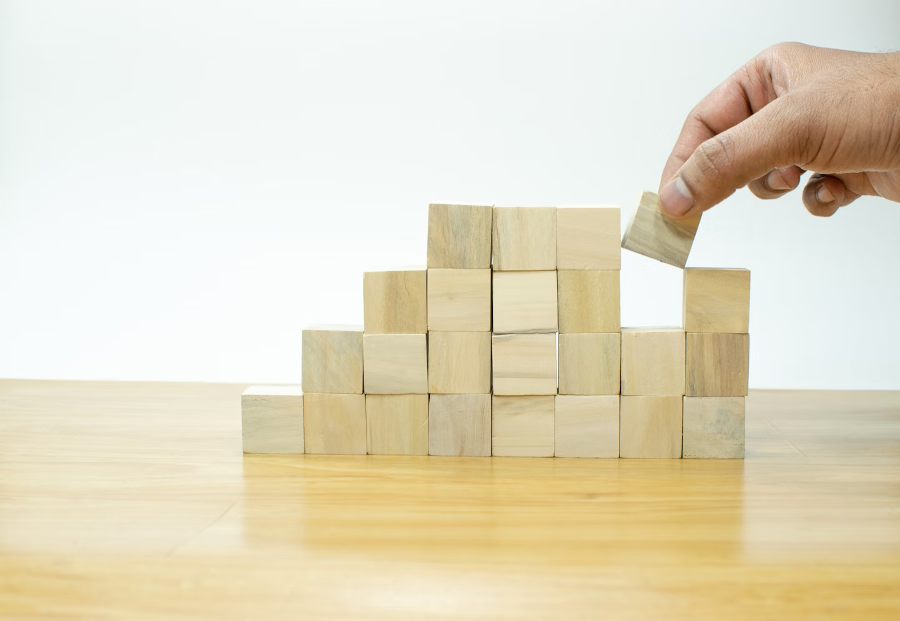近年、売り手市場が続いている中、新卒採用における母集団形成が年々難しくなっているのが現状です。自社が求める人材を確保するためには、採用市場を拡大していくことが必要になってきます。
そうした中、注目を集めているのが、「地方学生にアプローチすること」です。
本記事では、
- 地方学生の就職活動の実態
- 地方学生を採用するメリットとデメリット
- 地方学生の採用に向けた企業の取り組みやサービス
について説明していきます。
地方学生の特徴
地方学生の学生の特徴は、主に以下の2つがあげられます。
▼地方学生の特徴
- 地方への配属のハードルが低い
- 運転免許の取得率が高い
地方学生は大学進学等のタイミングで都心部に引っ越さなかった学生や大学進学のために都心部から地方に引っ越した学生のため、地方に住むことのハードルが低いことが多いです。そのため、地方に配属になった場合、都心部の学生と比較して抵抗が低いでしょう。
また、都心部と比較して公共交通機関が少ない地方の移動手段として、自動車の運転免許を取得している学生が多いです。入社後に営業職など運転免許が必要となる職種への配属もしやすいことが考えられます。
地方学生の採用が注目される背景
では、なぜ地方学生の採用が注目されているのでしょうか。その背景には、少子高齢化によって新卒採用の売り手市場が進んでいることがあげられます。
リクルートワークス研究所の調査によると、2026年3月卒における大卒求人倍率は1.66倍であり、2023年からほぼ横ばいの状態です。これは、企業の求人が求職者数よりも多いことを示しています。
加えて、従業員規模別でみると、従業員300人未満の企業では、学生1人の求職者に対して、企業の求人が約9個ある状態です。採用市場の競争は少子高齢化により激しくなり、特に中小企業の人材確保が難しくなるでしょう。
【参考】リクルートワークス研究所『第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)』
こうした人材競争が進む中で母集団形成を行う際には多くの学生にアプローチを行う必要があります。その一つとして、地方学生が注目を集めているのです。
◎自社にマッチした地方学生を採用するならMatcher Scout
「自社にマッチする優秀な人材となかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
地方学生の新卒採用における就職活動実態
地方の大学に通う大学生の就職活動は、主要都市の学生と比較し、どのような特徴があるのでしょうか? 以下で詳しく見ていきます。
▼地方学生の就職活動実態
- 就活活動にかかるコストが大きい
- 情報格差がある
- プレエントリー社数が少ない
- 秋以降も就職活動を続けている学生が多い
就職活動にかかるコストが大きい
都心部の学生の就職活動と、地方学生の就職活動では、必要となるコストが大きく異なります。ここでは、就職活動全体にかかった平均金額と交通費の地域別平均金額の2つのデータから解説していきます。
❚ 就活にかかる平均金額は都心部と地方で最大4万円の差に
就職みらい研究所の調査によると、2025年卒の学生の就職活動全体にかかった平均金額は、全体で84,434円でした。地域別の平均金額を見ると、関東が78,455円でもっとも安く、北海道・東北が111,717円で最も高いという結果になりました。
以下の表は、企業が多く集まっている関東を基準として、全国、地域別の2025年卒の学生が就職活動全体にかかった平均金額の差をまとめたものです。
▼就職活動全体にかかった平均金額
| 2025年卒(円) | 関東との差額(円) | ||
| 全国 | 84,434 | +5,979 | |
| 地域別 | 北海道・東北 | 111,717 | +33,262 |
| 関東 | 78,455 | - | |
| 中部 | 87,916 | +9,461 | |
| 近畿 | 86,073 | +7,618 | |
| 中国・四国 | 80,692 | +2,237 | |
| 九州 | 79,222 | +767 |
【参考】就職みらい研究所『【2025年卒 就職活動TOPIC】 就職活動全体の費用は微増。コロナ禍前と比べると約3割減』
この表より、九州を除いて考えると都市部から遠いほど平均金額が高くなりやすい傾向にあることが読み取れます。また、最も金額の差が大きい関東と北海道・東北では33,262円の差であり、都市部と地方では最大約3.3万円もの差があることが分かります。
❚ 都市部と地方の交通費の差は最大15,000円以上に
また、以下の表は地域ごとの就職活動にかかった交通費の内訳です。2025年卒では、関東が最も安く18,629円、北海道・東北が最も高く32,932円となり、都市部と地方の交通費の差は最大14,000円であるのが現状です。
▼就職活動にかかった交通費の地域別平均金額
| 2025年卒(円) | 関東との差額(円) | ||
| 全国 | 24,510 | +5,881 | |
| 地域別 | 北海道・東北 | 32,932 | +14,303 |
| 関東 | 18,629 | - | |
| 中部 | 25,319 | +6,690 | |
| 近畿 | 30,263 | +11,634 | |
| 中国・四国 | 31,703 | +13,074 | |
| 九州 | 26,666 | +8,037 |
【参考】就職みらい研究所『【2025年卒 就職活動TOPIC】 就職活動全体の費用は微増。コロナ禍前と比べると約3割減』
また、金銭だけでなく移動に伴うロスも生まれます。慣れない土地での就職活動という精神的負担も多くかかり、都心部の大学生よりも「とりあえずいろいろな企業説明会に行ってみよう」というフットワークの軽さを持ちにくいです。
そのため、地方学生は都心部の学生と比較して企業との接触機会が減ってしまう傾向があります。
情報格差がある
ネットワークの発達により昔と比較すると情報格差は縮まっているものの、実際に会社に出向くことで知ることのできる情報などに対して地方学生は手が届きにくいことが現状です。志望する会社に在籍する大学のOB・OGが少ない場合もあり、企業選考に際したノウハウを得られる確率が低くなります。
情報格差の影響により、地方学生は都内学生と比較し得られる選択肢が少なくなる傾向にあります。
プレエントリー社数が少ない
地方学生は時間や費用の制約があるため、多くの選択肢を持てず、志望業界を絞ってから応募する傾向があります。
公益社団法人全国求人情報協会の調査によると、2025年卒の大学生の平均プレエントリー数は14.8社でした。地域別にプレエントリー数をまとめたのが以下の表です。
▼2025年卒学生の地域別プレエントリー数
| プレエントリー数(前年との増減) | |
| 全国平均 | 14.8社(-2.0) |
| 北海道・東北 | 9.3社(-2.1) |
| 関東 | 18.0社(-0.9) |
| 中部 | 12.5社(-2.1) |
| 近畿 | 14.5社(-3.4) |
| 中国・四国 | 9.4社(-7.3) |
| 九州 | 14.2社(-0.3) |
以上の表より、関東は平均より3社多い18.0社で最も多く、北海道・東北が平均より5社少ない9.3社で最も少ない数値となりました。
以上の結果より、地方の学生は企業選びに慎重で、かつ企業接触が少ないことが分かります。そのため、企業は地方の優秀な学生との出会いが少なくなり、一方で地方学生は選択肢が限られてしまい就職活動に納得できない、という悪循環が起こっているのです。
【参考】公益社団法人全国求人情報協会『2025年卒学生の就職活動の実態に関する調査』
秋以降も就職活動を続けている学生が多い
厚生労働省の調査によると、2025年10月時点の2026年卒の大学生の就職内定率は73.4%でした。地域別に見ると、関東が最も高く81.1%、北海道・東北が最も低く58.3%となり、関東と北海道・東北で20%以上差があります。
▼地域別の就職内定状況
| 就職内定率(2025年10月) | 就職内定率(2024年10月) | |
| 全国平均 | 73.4% | 72.9% |
| 北海道・東北 | 58.3% | 61.1% |
| 関東 | 81.1% | 83.6% |
| 中部 | 75.7% | 71.9% |
| 近畿 | 71.7% | 68.9% |
| 中国・四国 | 75.0% | 65.8% |
| 九州 | 63.2% | 64.9% |
【参考】厚生労働省『令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況』
一方、厚生労働省の2025年2月1日時点の調査によると、大学生の就職内定率は92.6%で、地域別に最も高い関東は95.9%、最も低い中国・四国は88.0%と約7%の差でした。
また、2024年10月における就職内定率が最も高い地域である関東と、最も低い地域である北海道・北陸の就職内定率の差は約20%です。このことから、入社1ヶ月前の2025年2月に近づくにつれて就職内定率の地域差が小さくなることがわかります。
【参考】厚生労働省『令和7年3月大学卒業等予定者の就職内定状況(2月1日現在)を公表します』
10月から2月の間に地方学生は就職内定率を高めているということから、都市部の学生と比較して地方学生は秋以降も就職活動を続けている学生が多いということが分かります。
そのため、夏までの採用活動でうまくいかなかったと感じた採用担当者様は秋以降に地方学生に対してアプローチすることも母集団形成につながるでしょう。
地方学生採用に力を入れるメリット
地方学生の採用に力を入れるメリットは以下の6つです。
▼地方学生の採用に力を入れるメリット
- 全国の幅広い層の学生と接点を持てる
- 主要都市と比較し競争率が低い
- 優秀な学生を採用できる
- 地方配属への抵抗が少ない
- 採用ブランディングを強化できる
- リファラル採用で今後の採用成功につながる
①全国の幅広い層の学生と接点を持てる
アプローチ対象を拡大することで、求める人物像に近い学生と出会える可能性が高まります。地方学生は、時間や費用の制約があるため、かなり絞り込んだ状態で都内にある企業の説明会に参加したり、選考を受けたりする場合が多いです。
そのため、都内で地方学生と出会うには、学生の志望度をかなり高める必要があり、人数も限られてしまいます。そこで、自社が地方に赴く、もしくはオンラインで会いやすい機会を設けることで、地方ならではの経験を積んだ学生や、特殊な学部で勉強している学生など、今まで出会えなかった学生との接点を持てます。
②主要都市と比較し競争率が低い
都内の学生と比べて、地方学生の採用競争率は低いです。前述の通り、地方学生のプレエントリー社数は、都市部の学生の3分の2程度となっています。
また、説明会や選考のオンライン化が進み、従来よりは地方学生の選考参加が簡単になっている一方で、地方学生採用に力を入れている企業はまだ少ないのが現状です。都内の学生と比べて地方学生の採用競争率が低いため、数ある企業の中から自社の魅力を十分に伝えることが難しいと感じている場合は、地方での採用活動を視野に入れましょう。
③優秀な学生を採用できる
地方学生を採用することで、優秀な学生を採用できる可能性が高まります。その理由として、地方学生を採用することによって母集団を拡大できるため、優秀な人材に出会う確率も自然と上がるからです。
地元学生の中には、国公立大学に通う学生もいます。そういった人たちを対象に地方学生を採用していくことで、自社に優秀な人材を確保することができるでしょう。
④地方配属への抵抗が少ない
地方学生は地方に住んでいるため、地方配属への抵抗が少ないです。
就職みらい研究所の2024年卒を対象とした調査によると、働きたいと思う組織を選ぶ際に重視することとして、「希望の勤務地に就ける可能性が高い」と回答した人が61.2%でした。これは2017年卒と比較すると、約15.8%も伸びています。
このことから、学生がある程度勤務地を重要視していることがわかります。これは地方学生も同様に勤務地を重視している可能性が高いです。
都市部の学生は、地方配属による都市部と地方での生活のギャップから、内定辞退や早期離職が起きてしまうこともあるでしょう。しかし、地方学生は地方配属に対して、そこまで抵抗がないため、そういったリスクを減らすことが可能です。
【参考】就職みらい研究所『就職みらい研究所 REPORT 特定の地域で働きたい学生が増えているのはなぜか?』
⑤採用ブランディングを強化できる
採用活動のために現地に足を運んで採用活動を行うことは、自社の認知度向上につながります。また、現地での説明会やイベントを開催し、地方学生に良いイメージを与えることができれば、選考に応募する人が増えるかもしれません。
株式会社PR Tableの調査では、大企業の57.5%が採用ブランディングに取り組んでいることに対して、中堅企業は38.4%でした。このことから、大企業と中堅企業の間に採用ブランディングの実施状況に差が生じていることがわかります。
企業の認知度を向上させたいと考えている採用担当者の方は、採用ブランディングを強化する一つの手段として、地方学生の採用を行うことも検討してみてください。
【参考】株式会社PR Table『【採用ブランディングにおける取り組み実態調査】大企業の57.5%が採用ブランディングに取り組んでいるの対し、中堅企業は38.4%と少数派』
⑥リファラル採用で今後の採用成功につながる
地方学生は大学のOB・OGの数が少なく、就活に関する情報を得られないことが多いです。そのため、都市部の学生よりもコミュニティが狭いといった特徴を持っています。
リファラル採用は社内の人脈を駆使して自社の求める人材を採用する採用手法です。仮に地元学生を採用することができれば、その人脈を使って、さらに多くの地方学生を取り込めるでしょう。
地方学生採用に力を入れるデメリット
地方学生の採用を行う前に、リスクと対策を考えておく必要があります。
地方学生の採用に力を入れるデメリットは以下の2つです。以下の懸念点をどのようにしてクリアするのかが重要になります。
▼地方学生の採用に力を入れるデメリット
- 時間・金銭面でコストがかかる
- 地元志向の学生も多い
時間・金銭面でコストがかかる
地方学生が都市部に来るためにかかる交通費や宿泊費などを、自社が負担するかたちになることが多いです。採用担当者が少ない企業や、他の業務を兼任している担当者の多い企業の場合は、できるだけ採用にかかる工数を抑えたいところです。
地方学生の採用を行うことで、自社が抱える課題をクリアできるのか、地方学生の採用にかかるコストは問題ないかなど、採用計画全体を見直した上で判断しましょう。
地元志向の学生も多い
地方学生すべてが都市部で働くことを求めているわけではありません。
株式会社マイナビの調べによると、地元で就職を希望する26年卒の学生は52.6%でした。地元で就職したいと考えている学生に自社を知ってもらい、志望度を高めてもらうために何ができるかを検討する必要があります。
地方学生の採用を強化することで、もちろん今まで出会えなかった学生層と出会える可能性は高くなりますが、必ずしも自社の求める人材の採用に繋がるかどうかは分かりません。地方採用に本格的に力を入れる前に、「どのような学生がいるのか」、「自社にフィットする人材はどのような場所にいる傾向があるのか」などを調べてみましょう。
もし今までに採用した新卒社員の中で、同じ地方の出身が多いなどの傾向が見られる場合は地域を絞って重点的に採用活動を行っても良いでしょう。
【参考】株式会社マイナビ『2026年卒大学生Uターン・地元就職に関する調査』
地方学生の採用を強化するべき企業の特徴5選
ここまでは地方学生の特徴や地方学生の採用を強化するメリット・デメリットを解説しました。ここからは地方学生の採用に力を入れた方が良い企業の特徴について解説します。
地方学生の採用を強化するべき企業は以下の5つです。
▼地方学生の採用を強化するべき企業の特徴
- 母集団形成に悩んでいる企業
- 中小企業
- 新卒の定着率で悩んでいる企業
- 地方への展開を検討している企業
- 様々な視点・価値観を持った学生を採用したい企業
①母集団形成に悩んでいる企業
1つ目は母集団形成に悩んでいる企業です。特に「エントリー数が少ない」「エントリーがあっても採用に繋がらない」と悩んでいる企業は、地方学生の採用を検討してみると良いでしょう。
地方学生の採用を強化することで、既存の母集団を拡大し、自社にマッチした人材を集めやすくなります。
◎母集団形成を成功させるならMatcher Scout
「母集団形成を成功させたい」と考える採用担当者の方におすすめしたいのがMatcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、より多くの優秀な人材にアプローチでき、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
②中小企業
2つ目は中小企業です。
2026年卒を対象とした株式会社マイナビの調査によると、「大手志向」の学生が多い地域は「関東地方(56.9%)」や「関西地方(54.9%)」といった都市部に集中していました。一方で「大手志向」の学生が少ない地域は「四国地方(43.3%)」や「中国地方(44.0%)」といった地方出身の学生でした。
このことから、地方学生は都市部の学生と比べて中小企業をみている割合が高いことがわかります。地方学生に対して、適切な採用手法をとることができれば、母集団の形成や拡大を行うことができるでしょう。
【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査』
③新卒の定着率で悩んでいる企業
3つ目は新卒の定着率で悩んでいる企業です。
前述した通り、地方学生は都市部の学生と比べてプレエントリー社数が少ないです。しかし、そのぶん会社をじっくりと見定める傾向があるともいえます。これにより、入社後のミスマッチが低いため、会社に定着しやすい人材となりやすいのです。
そのうえ早期離職を防ぐという観点からも地方学生の採用は良い手段であるといえるでしょう。
④地方への展開を検討している企業
4つ目は地方への展開を検討している企業です。
地方への展開をするにあたり、地方配属となる人材が必要です。その際に都市部の学生を地方配属に任命することで、勤務地に対する不満が発生し、離職につながってしまうかもしれません。
地方学生は地方配属への抵抗が少ないため、地方に事業を拡大していきたい企業は地方学生の採用を検討してみると良いでしょう。
⑤様々な視点・価値観を持った学生を採用したい企業
5つ目は様々な視点・価値観を持った学生を採用したい企業です。地方学生は、その土地独自の風土や文化、コミュニティの中で育まれた独自の価値観を持っていることが多いです。
こうした学生を採用することで、社内に新たな視点や刺激をもたらします。また、地方特有の知識や経験をビジネスに活かすことで、これまでになかった市場の開拓や、新たなビジネスチャンスの創出も期待できます。
地方学生の採用におすすめの採用手法8選
 具体的に地方学生を採用していくには、どのようにすれば良いのでしょうか? 地方学生採用を行う際に活用できる主な手法と便利な媒体をご紹介します。
具体的に地方学生を採用していくには、どのようにすれば良いのでしょうか? 地方学生採用を行う際に活用できる主な手法と便利な媒体をご紹介します。
地方学生採用で活用したい採用手法は以下の8点です。ぜひ参考にしてみてください。
▼地方学生採用で活用したい採用手法
- ダイレクトリクルーティング
- 地方大学での学内セミナー
- 現地選考会
- 1日完結型選考
- オンライン選考・オンライン説明会
- オンラインの1day仕事体験の実施
- 地方学生特化型サービス
- リファラル採用
① ダイレクトリクルーティング
「ダイレクトリクルーティング」とは、企業が学生に直接アプローチする採用手法です。学生の住んでいる「地域」「都道府県」といった所在地を指定して、学生に声をかけることができます。
また、所在地に加えて、「学歴」「経験」「スキル」「価値観」などの採用要件を満たす学生に絞れば、自社にフィットした学生に効率よく会うことができるでしょう。ただし、地方の優秀な学生はたくさんのスカウトを受け取っています。そのため、スカウトを送るときは、タイトルや内容で自社の魅力をしっかり伝えることが必要です。
ダイレクトリクルーティングについてさらに知りたいという方は、以下の記事から自社に合ったサービスを見つけてみてください。
【参考】【厳選】新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス20選を比較
② 地方大学での学内セミナー
学内セミナーは、ナビ媒体掲載などの主な母集団形成の手法のなかでも比較的費用がかからないという特徴があります。そのため、地方に行くための移動費がかかっても、大きな損失にはなりません。しかし、地方大学の知名度により、参加する企業数も異なります。
有名な地方大学では優秀な学生の多さを見込んで多くの企業が学内セミナーを開催し、競争率も高くなるため、自社の求める人材を確保できない可能性があります。地方大学で学内セミナーを行う時は、自社の魅力をより上手にアピールできる環境選びが大切です。
③ 現地選考会
オンラインでの面接に何らかの懸念がある場合や、実際に学生と対面して選考を行いたい場合などは、現地選考会を行いましょう。地方学生の慣れた土地で対話することにより、緊張することもなく、より学生のリアルな部分に触れられる可能性があります。
しかし、実際に現地で選考会を開催したとしても、参加してくれる学生が少なければ求める人材と出会える可能性も低くなってしまいます。選考会をする前に、学内セミナーなどで地方の学生と接触し、自社の需要を確認しましょう。
④ 1日完結型選考
移動コストを考え、1日で応募から内定まで済ませる大胆な選考方法です。懸念点として、選考のクオリティを担保するためには面接の技術が高くなければ難しいこと、慎重な判断がしにくいことが挙げられます。
1日完結型選考を行う場合は、明確な採用要件を設定し、面接官との擦り合わせも綿密に行いましょう。
⑤オンライン選考・オンライン説明会
実際に現地へ赴かなくても、Web通話サービスなどを利用して、オンラインで選考や説明会を行うことが可能です。オンラインで会話をする面接方式の他にも、事前に学生が録画した動画を元に選考をする「録画選考」があります。
移動工数がかからない点、日程が調整しやすい点がメリットです。一方で、対面でないと伝わりきらないこともあるかもしれません。最終面接だけは本社に来てもらうなど、選考段階によってオンラインと対面を使い分けをしましょう。
⑥ オンラインの1day仕事体験の実施
オンライン開催の1day仕事体験は、本社に行く必要がないため地方学生も参加しやすいです。特に夏インターンシップなど学生と企業の最初の接点となる場合は、オンライン開催にすることで、都心部の学生に限定せず全国各地の多くの学生と出会えるでしょう。
⑦ 地方学生特化型サービス
地方学生に特化した人材紹介やナビ媒体など、地方学生と接触しやすいサービスがあります。地方学生に特化しているため、「せっかく現地に行ったのに求める人材と出会えなかった」という状況を回避できます。
地方で開催する説明会や選考会への集客など、母集団形成のために活用していきましょう。ただし、サービスの利用費がかかるため、自社に必要かどうかの判断は必要です。また、求める地方学生がどのくらいいるのかについてはサービス提供業者に確認しましょう。
地方学生特化型サービスの例は以下の2つがあげられます。
(1)ジョーカツ|大学や400以上の学生団体とのネットワークあり
- SNSや地方メディアを活用して、上京を希望する就活生にアプローチ
- 地方学生が宿泊できる完全無料の就活シェアハウスや、交通費一律15,000円の支給
- 参加学生に専任のキャリアアドバイザーがいるため、ミスマッチを減らすことが可能
おすすめの企業:地方大学や学生団体で出会える就活生の母数を増やしたい
【参考】ジョーカツ 公式HP
(2)ちほりけ|地方の理系学生の採用につよい
- 機電情報系を中心に、理系学生が多い
- 地方の理系学生に対して就活にかかる交通費や宿泊費を負担
おすすめの企業:機電情報系などピンポイントなターゲットに絞った理系学生を採用したい
【参考】ちほりけ 公式HP
⑧リファラル採用
自社の社員や内定者に地方大学在住の方がいた場合、リファラル採用を実施することで地方学生を取り込むことが期待できます。
リファラル採用を使うメリットとしては、紹介された社員の定着率が高いことがあげられます。これにより、入社後のミスマッチを減らすことができるため、母集団形成で失敗するリスクを下げることができるでしょう。
【5ポイント】地方学生の採用を成功させるには?
地方学生の採用を成功させるためのポイントを5つにまとめました。
▼地方学生の採用を成功させるポイント5選
- 選考短縮
- SNS・スカウトメールの活用
- オンライン企業説明会・Web面接の導入
- 選考参加にともなう交通費や宿泊費を企業側が負担する
- 内定後の丁寧なフォロー
①選考短縮
選考を短縮することで、地方学生の就職活動のネックである金銭的・時間的負担を軽減することができます。具体的には、現地選考会や1日完結型選考、またインターン優遇の強化などです。選考方法を工夫することで地方学生の選考参加のハードルを下げることができます。
②SNS・スカウトメールの活用
SNSで自社の魅力をアピールすることで、企業の認知度を高められ、地方学生を含めるより多くの学生からの応募が期待できます。株式会社マイナビの調査によると、26卒の学生のうち「就活準備でSNSを使用している」と回答した人の割合は全体の約7割でした。
選考情報に加えて、社内の雰囲気など企業のリアルを知りたい学生が多いです。就活生の情報ニーズは時系列で変化していくため、就活生のフェーズに合わせてSNSで発信する内容を変えることで志望度や入社意欲を高めることができるでしょう。
また、スカウトメールを活用し、優秀な人材に対してアプローチしていくことも必要です。
その際、ただスカウトメールを送るだけでなく、「学生のどんなところが魅力的で自社に合うと思ったのか」という理由をつけると、学生の応募意欲が向上するでしょう。
【参考】株式会社マイナビ『SNS就活最前線!SNSを活用する学生の事情(第1章)』
③オンライン企業説明会・Web面接の導入
冒頭で説明した通り、金銭的・時間的な負担が地方学生の応募ハードルをあげています。そこで、オンラインでの企業説明会やWeb面接を導入して、地方の学生にも気軽に参加してもらえる環境を整えましょう。
④交通費や宿泊費を企業側が負担する
地方の就活生にとって、都内で選考を受けるためにかかる交通費や宿泊費などの負担はかなり大きいものです。そこで、それらにかかる費用を一部支給する企業も出てきています。
株式会社マイナビの調査によると、応募した企業から内々定をもらう前に交通費や宿泊費を支給されたことがある学生は約65%でした。支給されたタイミングとしては、最終面接やインターンシップなどの時に支給されることがほとんどで、支給金額合計の平均は約43,000円でした。
また、上記のグラフを参照すると、支給金額は学生の在住地区によって差があることが分かります。特に北海道や甲信越といった地域からの学生に対しては多くの交通費が支払われていることがわかります。
このような工夫により、遠方から来る学生の負担を減らし応募の母集団を増やしたり、途中選考の辞退率を下げたりすることにつながるでしょう。
【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2026年卒 大学生 キャリア意向調査6月<就職活動・進路決定>』
⑤内定後の丁寧なフォロー
地方学生は、就職だけでなく東京への移住に対する心配もあります。さらに、故郷を離れることに家族が反対することも多いです。そこで、地方学生に対する内定後のサポートは丁寧に行いましょう。
サポート方法としては、地方出身の社員との対話・交流や、内定者の家族にパンフレット・社内報を送ることが特におすすめです。学生が抱える懸念を解消して内定辞退を防ぎましょう。
【事例】地方学生の採用を強化している企業
実際に地方学生の採用を実施した企業を紹介します。
①株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントでは、各コースにおける地方学生の採用を強化しています。実際に地方学生の採用活動を積極的に行った結果、2024年度に採用した新卒社員のうち、約4割が首都圏以外の大学出身となっています。
地方学生の採用活動で行ったこととしては、「オンライン動画での会社説明会」「幅広い地域で年間40回以上にわたる出張セミナー・面談」「現地選考会」を実施しています。
【参考】株式会社サイバーエージェント『雇用機会の創出と地方創生 | 株式会社サイバーエージェント』
②株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
株式会社USEN-NEXT HOLDINGSでは、全国各地から多様な人材を採用するために「超!全力採用」という新たな採用システムを導入しています。主な取り組みとしては以下の通りです。
❚ Web説明会・グループ企業が全て参加する合同企業説明会の実施
この企業説明会を開催することにより、地方学生でも説明会に参加しやすい場を作っています。
❚ カスタマイズ面接
一部の選考において、「面接官・面接場所」を自由に選択できる面接を用意しています。
【参考】株式会社USEN-NEXT HORDINGS『新卒採用に革新、動画投稿エントリーやLIVEビデオインタビューを導入「超!全力採用」で多忙な学生や地方在住の学生を応援|ニュースリリース』
【参考】株式会社USEN-NEXT HOLDINGS『選考情報 | 新卒採用 | U-NEXT HOLDINGS 採用サイト』
優秀な地方学生にアプローチしたいならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
まとめ
いかがでしたか。地方までアプローチ対象を拡大すれば、自社にマッチした人材を採用できる確率が高くなります。
地方にもポテンシャルのある学生はたくさん存在するはずです。地方学生の採用に力を入れることで、学生の情報格差や負担するコストの多さなどによる機会損失をなくしながら、自社の求める人材を見つけることができます。自社にとって納得の行く採用活動を進めていきましょう。
ぜひ今回紹介した手法や事例を参考にして、地方学生の採用を検討してみてください。




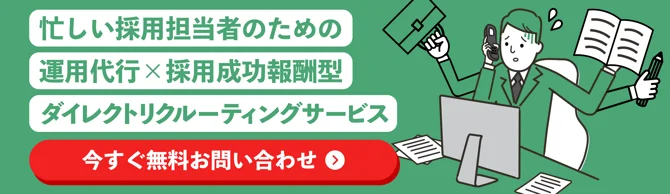
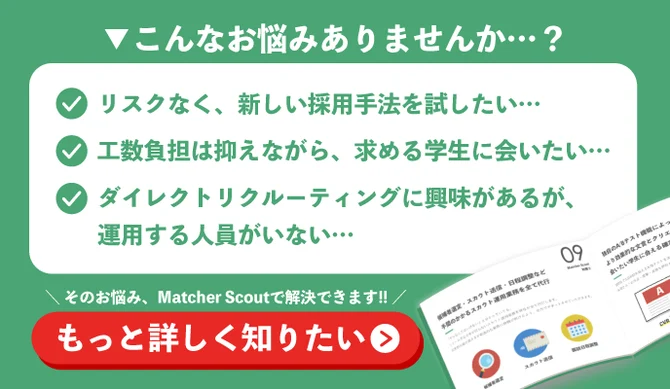





_Crop%20Image.jpg)