年々早期化する新卒の採用スケジュールですが、採用に成功する企業はどのようなスケジュールで動いているのでしょうか。本記事では、新卒採用の基本的なスケジュールや、時期によって企業が準備するべきことについてご紹介します。
27卒の新卒採用スケジュール
新卒採用のスケジュールを作成するにあたって、まずは就活ルールに則った新卒採用スケジュールを紹介します。
就活ルール基づく新卒採用スケジュール
就活ルールとは、近年の新卒採用で見られる就職活動の早期化・長期化に伴う学業への影響や安心して就職活動に取り組める環境構築に向けて政府が主導して行う企業等に対する要請のことを指します。この就活ルールは2021卒から踏襲されており、次の図のようなスケジュールを要請しています。
ただし、この就活ルールには強制力も罰則もないため、守らない企業も多く、形骸化している側面もあります。
しかし、それでも「広報」、「選考」、「内定」をルールに則って解禁している企業も多く、このルールの重要性に変わりはないでしょう。
【参考】内閣官房『2026(令和8)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について』
学生の就活動向
繰り返しになりますが、「就活ルール」は形骸化している側面があります。それでは、実際に学生はどのようなスケジュールで就職活動を行っているのでしょうか。
■インターンシップの参加状況
株式会社リクルートの調査によると、26卒の学生がインターンシップ等のキャリア形成支援プログラムに初めて参加した時期は以下のようになりました。
▼インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムに初めて参加した時期
1位 8月(30.9%)
2位 7月(15.8%)
3位 6月(10.4%)
ここから、多くの学生が、採用広報活動解禁日よりもかなり前からインターンシップなどに参加していることがわかります。
【参考】株式会社リクルート『【2026年卒 就職活動TOPIC】インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムへの参加状況(3月時点)』
■内定取得率
「就活ルール」では、大学4年(修士2年)の6月1日から採用選考活動が解禁されるとしていますが、実際に学生はどの時期に内定を獲得しているのでしょうか。
株式会社リクルートが行った調査によると、26卒学生の6月1日時点での内定取得率は82.4%でした。ここから、採用選考活動解禁日を迎える前に内定を取得している学生が多いことがわかります。
【参考】株式会社リクルート『就職プロセス調査(2026年卒)「2025年6月1日時点 内定状況」』
新卒採用スケジュールの移り変わり
それでは、新卒採用のスケジュールはこれまでどのように移り変わってきたのでしょうか。これまでの変更点についてご紹介します。
①2017卒における変更点
2017卒以前は、経団連が定めた就活ルールに基づいて新卒採用が行われており、広報活動の解禁日は3月1日以降、選考解禁日は8月1日であると決められていました。しかし、2017卒以降の採用活動において、面接などの選考解禁日を6月1日に変更しました。
この背景には、外資系などの企業を中心にルールに従わない企業が相次いだほか、学生の就活期間が伸びてしまったことが挙げられます。
②2021卒における変更点
2021年卒以降は、経団連ではなく政府が主導となって就活ルールを運用していく形に変更されました。
この背景には、経団連に加入していない外資系の企業を中心に、就活ルールを守らない企業が多く、就活ルールが形骸化してしまっていたことが挙げられます。
③2025卒における変更点
2025卒においては、新卒採用スケジュールには変更はありませんでしたが、インターンシップで獲得した学生の情報を採用活動で活用できるようになりました。
これにより、インターンシップ経由での早期選考が可能になったため、就活の早期化がさらに加速するようになりました。
27卒|新卒採用で時期ごとに企業がするべきこと
「新卒採用において、いつ、何をすれば良いかわからない」とお悩みの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。本章では、企業が時期ごとにするべきことについてご紹介します。
①2025年3月~8月
2025年3月から8月に企業がするべきことは主に以下の3つです。
▼2025年3月から8月に企業がするべきこと
- 前年度の採用の振り返り
- 夏インターンシップの母集団形成、開催
- 秋・冬インターンシップの準備
まず初めに、前年度の採用活動を振り返り、どこに課題があったのか、今年度はどのような人材を何人採用したいのかなどを明確にすることが大切です。
加えて、今年度のインターンシップの企画や母集団形成をする必要があるでしょう。優秀な人材程早くから就職活動を開始しています。そのため、インターンシップを開催し、早期から優秀な人材に接触しておくことが重要です。
■インターンシップの母集団形成ならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「インターンシップの母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
②2025年9月~11月
2025年9月から11月に企業がするべきことは以下の3つです。
▼2025年9月から11月に企業がするべきこと
- 秋・冬インターンシップの母集団形成、開催
- 夏のインターンシップで出会った学生をつなぎとめるイベントの開催
- 採用手法の検討・決定
夏のインターンシップを終えた後は、夏のインターンシップに参加した学生のつなぎ止めと、参加できなかった学生のための秋・冬インターンシップを開催する必要があります。
夏のインターンシップに参加した学生に自社に興味を持ち続け、本選考に参加してもらうためには、座談会などのイベントを開催すると良いでしょう。
また、夏のインターンシップに参加できなかった学生に向けた秋・冬のインターンシップを開催する際は、学生が学業と両立して参加できる時間や日時を選定する必要があります。そのため、短い時間で開催することができるオープン・カンパニーを検討することがオススメです。
さらに、インターンシップの開催に加えて、3月以降始める本選考に備えて採用手法の検討も進める必要があるでしょう。
③2025年12月~2026年2月
2025年12月から2026年2月に企業がするべきことは以下の5つです。
▼2025年12月から2026年2月に企業がするべきこと
- インターンシップ経由の早期選考
- 採用スケジュールの告知
- 採用手法の確定
- 面接官・会場の確保
- 広報原稿の用意
12月から2月には、選考に向けた最終調整を行います。採用スケジュールを確定し、あらかじめ告知しておくと良いでしょう。
また、新卒採用においては人事以外の現場社員や役員に面接官を担当してもらう場合も多いです。あらかじめ、面接官の日程を抑えておくようにしましょう。
④2026年3月~5月(採用広報解禁以降)
2026年3月から5月に企業がするべきことは以下の2つです。
▼2026年3月から5月に企業がするべきこと
- 説明会・合同説明会の開催、参加
- 学生への連絡
3月になり、採用広報が解禁されると、いよいよ採用に向けた説明会を開催します。これまでインターンシップに参加した学生に採用活動が始まった旨を連絡するようにしましょう。
また、採用選考解禁以前であってもエントリーシートや適性テストを学生に実施してもらうことができます。スムーズに採用選考に入れるよう、事前に学生にエントリーシートの記入や適性検査の受験を依頼しておくと良いでしょう。
⑤2026年6月~9月(採用選考解禁以降)
2026年6月から9月に企業がするべきことは以下の4つです。
▼2026年6月から9月に企業がするべきこと
- 選考
- 学生への連絡
- 選考中のフォロー
- 内定者フォロー
いよいよ6月になると本格的に採用選考が始まります。そのため、企業は選考や、それに伴う合否の連絡をする必要があるでしょう。また、選考中の学生をフォローするためのフォロー面談を実施する場合もあります。
加えて、内定を出した学生に対しては、内定辞退されないように内定者懇親会や社員面談などの内定者フォローを実施する必要があるでしょう。
⑥2026年10月~4月(内定期間)
2026年10月から4月に企業がするべきことは以下の4つです。
▼2026年10月から4月に企業がするべきこと
- 内定式の準備・開催
- 内定者フォロー
- 入社前研修・資格勉強の要請
- 選考
10月になると、多くの企業が内定式を実施し、それに伴って採用活動を終了する場合が多いでしょう。しかし、学生の多くは入社にあたって「本当にこの会社で良いのだろうか」「入社後ついていけるのだろうか」と不安な気持ちを抱えています。入社前に学生の不安な気持ちを和らげるよう、引き続き内定者フォローを実施しましょう。
一方で、入社式前後に内定辞退が出てしまった場合など、採用予定人数に達成していない場合は引き続き採用活動を行う必要があります。この時期であっても、内定式を通してミスマッチを感じ就活をやり直そうとしている学生や、公務員志望から民間志望に切り替えた学生など、一定数就職活動を続けている学生も存在します。採用予定人数の達成に向けた採用活動を実施しましょう。
【企業タイプ別】新卒採用スケジュール
ここまで、就活ルールに基づいた新卒採用スケジュールについて解説しました。しかし、企業ごとに新卒採用スケジュールは異なるでしょう。本章では、企業タイプ別の新卒採用スケジュールについてご紹介します。
▼【企業タイプ別】新卒の採用スケジュール
- 安定した採用活動を行う企業向け
- 積極的に早期選考を行う企業向け
- 内定辞退を見込んだ採用活動を行う企業向け
- 超早期の採用プロセスを持つ企業向け
【ケース①】安定した採用活動を行う企業向け
新卒の学生による応募が毎年一定数確保でき、採用スケジュールが固定されている企業向けの採用スケジュールは以下の通りです。
このような企業は就活ルールに則って、広報、選考、内定出しを行います。本選考を始めるのは6月以降となりますが、夏や冬の時期にインターンシップを開催することで本選考の母集団形成を図るのも良いでしょう。
【ケース②】柔軟に採用を行う企業向け
インターンを通じた早期選考では優秀な学生を確保し、本選考では組織のバランスを考慮した採用を目的とした企業向けの採用スケジュールは次の通りです。
概ね就活ルールに即した採用スケジュールですが、他企業に流出することを防ぐために3月より前の早い時期に内定を出すことも必要になります。
【ケース③】一定数の内定辞退を見込んだ採用を行う企業向け
内定辞退による採用人数が未達成になることを見込んで採用を行う企業向けの採用スケジュールは以下の通りです。
このような企業は他の企業よりも「早く、短く」選考を行うことで、学生の母集団を確保しつつ、選考の途中辞退を防ぐことができます。
ただし、このような採用スケジュールの場合、学生が他企業に流出するにつれて、内定辞退者数も多くなる傾向にあります。
そこで、採用計画人数を達成するために、7~10月に第2次採用を行うと良いでしょう。この時期に就活をする学生は「留学等で就職活動が遅れた」や「公務員志望だったが、民間企業志望に変わった」などが多く、これらの層を採用ターゲットにすることができます。
【ケース④】超早期の採用プロセスを持つ企業向け
外資系企業やマスコミ、ベンチャー企業のように、超早期に採用を行う企業の採用スケジュールは以下の通りです。
一部の企業は「3月より前に新卒の採用活動が終了している」というケースもあり、採用活動を行うタイミングが早いです。このような企業は内定者がインターンシップに参加した学生の大部分を占め、優秀な学生を早期に確保できます。
ただし、就職活動を終了してから入社するまでに時間があるので、社会人になることに対する不安が大きいため定期的に懇親会等で内定者に対してフォローする必要があります。
新卒採用のスケジュールを立てる前にするべき準備
近年の学生側・企業側の大まかな就活スケジュールを理解したら、採用スケジュールを立てましょう。ここでは、採用スケジュールを立てる前にやっておくべき準備を紹介します。
▼新卒採用を成功に導くスケジュールを立てる前にすべき準備
- 採用の目標人数・採用目的を明確にする
- 採用したい人物像を明確にする
- 前年度の採用活動を数値化し、課題をみつける
- 競合他社の採用状況を確認しておく
- 採用の戦略を立てよう
- 年間の大まかなスケジュールを作成
① 採用の目標人数・採用目的を明確にする
最終的な目標が決まっていないと、就職活動のスケジュールも上手く立てられません。「採用の目標人数と新卒採用の目的」を明確にしておきましょう。
具体的には「その部署で何名の新卒を受け入れるのか」「新卒採用を通じて、会社にどの様なインパクトを与えるのか」といった点を明確にしておくのがおすすめです。これらの点は、採用スケジュールを立て終わった後でも、定期的に社内で共有しておくようにしましょう。
② 採用したい人物像を明確にする
また「採用したい学生像を明確にしておく」ことも重要です。具体的には「学歴・過去の経験・スキル、保有資格・人柄」などで基準を設けるのが分かりやすいでしょう。
学生像を明確にしておくと、効率よく学生にアプローチできるので、採用活動の負担も減らすことができます。採用する学生像を決める際は、採用活動を行う人だけでなく、他部署を含めた社内全体で決めることが望ましいです。
③ 前年度の採用活動を数値化し、課題をみつける
さらに「前年度の自社の採用活動を数値化し、課題を明確にしておく」ことも重要です。
一口に採用に課題があるといっても、「母集団形成に課題があるのか」それとも「内定辞退率に問題があるのか」など、課題の箇所によって取るべき対策は異なります。まずは自社の昨年の採用実績を数値化し「採用活動のどこに問題があったのか」を明確にしておくようにしましょう。
④ 競合他社の採用状況を確認しておく
意外に思われる方も多いと思いますが「競合他社の採用状況」も確認しておくことが重要です。
学生は業界を絞って採用活動を行っていることが多く、競合の会社から先に内定が出てしまうと、選考を辞退されてしまう可能性が高まります。逆に、競合他社が採用活動を行っていない時期に学生へアプローチができれば、自社に興味を持った学生がより多く集められるようになるでしょう。
そのため「競合他社がどんなスケジュール感で就職活動を行っているのか」は知っておくべきだといえます。
⑤ 採用の戦略を立てよう
次に、採用の戦略を立てましょう。採用の戦略を立てる際は、以下のポイントに注意するのがおすすめです。
▼採用戦略策定で意識するポイント
- 社風や事業の独自性、福利厚生など自社の強みとなる点を見つける
- 学生が集まりやすい日程で、説明会やインターンシップを行う(土日や夏季・冬季の長期休みなど)
- 採用工程で効率化できる箇所はないか確認する
新卒の採用を担当する場合は「学生から自社がどの様に見えているか」を常に意識しておくことが重要です。自社の魅力を積極的にアピールし、学生に「あの会社に入りたい!」と思ってもらえるような就職活動を行いましょう。戦略がしっかりと立てられれば、採用の工程を効率化させることもできます。
⑥年間の大まかなスケジュールを作成
採用の戦略を立て終わったら、年間の大まかなスケジュールを立てましょう。新卒採用のスケジュールを立てる際は、以下の順序で行うのがおすすめです。
▼年間スケジュールの作成方法
- 広報活動・選考活動・内定出しの開始時期を決める
- 上記の時期から逆算して、会社説明会やインターンシップの日程を決める
- 会社説明会やインターンシップに参加する学生を集めるために必要な、求人媒体やサービスを選定する
- 「いつまでに何人の学生を集めるのか」「何回インターンシップといったイベントを開催するのか」等を目標から逆算して詳細に決める
採用のスケジュールを立てる際に重要なのは「最終目標から逆算して戦略を立てること」です。まずはメインとなる「広報活動・選考活動・内定出しの開始時期」を決め、その後に細かい日程を決めていくようにしましょう。
採用活動はインターンシップから面接まで、非常に多くの準備が必要です。施策を実行する時期を逃さないようにするためにも、年間のスケジュール作成は非常に重要といえます。
新卒採用を成功させるためのポイント
ここまで、新卒採用スケジュールや、スケジュールを考える際のポイントについてご紹介しました。ここでは、スケジュールを考えた上で、新卒採用を成功させるためのポイントをご紹介します。
▼新卒採用を成功させるためのポイント
- ダイレクトリクルーティングを用いる
- インターンシップを通して早期から学生と接点を持つ
- 選考におけるスピード感を意識する
①ダイレクトリクルーティングを用いる
ダイレクトリクルーティングサービスを使用することもオススメです。
「早期から採用活動を開始したいのに、なかなか母集団形成ができない...」「就活の長期化によって内定辞退が出てしまったから、代わりに優秀な人材を採用したい」と、お悩みの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
ダイレクトリクルーティングサービスとは、企業側から欲しい人材に直接アプローチすることができる採用手法です。売り手市場の現在、学生からのエントリーを待つだけではなく、企業側から直接学生にアプローチすることで、優秀な人材を採用することができるでしょう。
■母集団形成にお悩みならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
②インターンシップを通して早期から学生と接点を持つ
インターンシップを通して早い段階から学生と接点を持つことも重要でしょう。
株式会社i-plugが行った調査によると、26卒の学生のうち「夏期インターンシップに参加した企業の中で、本選考に進もうと思った企業はあるか?」という質問に対して、9割以上の学生が「ある」と回答しています。
ここから、なるべく早い段階からインターンシップや説明会などを通して学生と接点を増やすことで、母集団形成に役立てることができるでしょう。
【参考】株式会社i-plug『「インターンシップ」に関する調査』
③選考におけるスピード感を意識する
選考におけるスピード感を意識することも重要です。学生の中には、「第一志望の企業ではなかったとしても、一番早く内定をもらえた企業に決定する」と考えている人も少なからず存在します。
優秀な人材を確実に採用するために、採用スケジュールをたてる際には、採用時期だけではなく、選考間のスピード感も意識する必要があるでしょう。
まとめ
いかがでしたか。 現在は多くの学生が3年生から就職活動をはじめています。
新卒採用が早期化している中においては、採用スケジュールをしっかりと立てることが重要です。時期ごとにやるべきことを明確にし、新卒採用活動を成功させましょう。




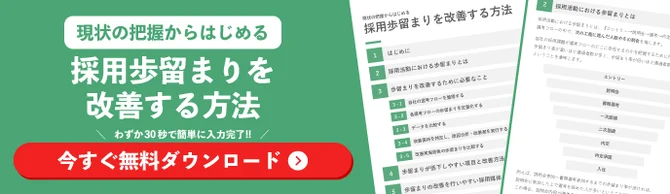






_Crop%20Image.jpg)
