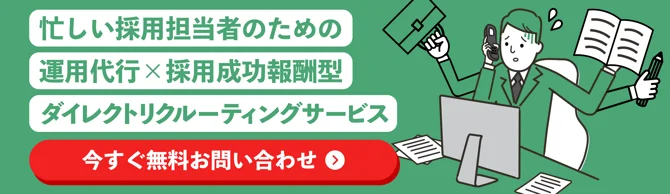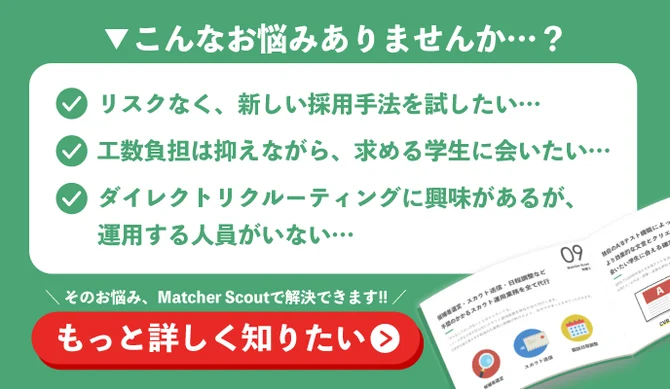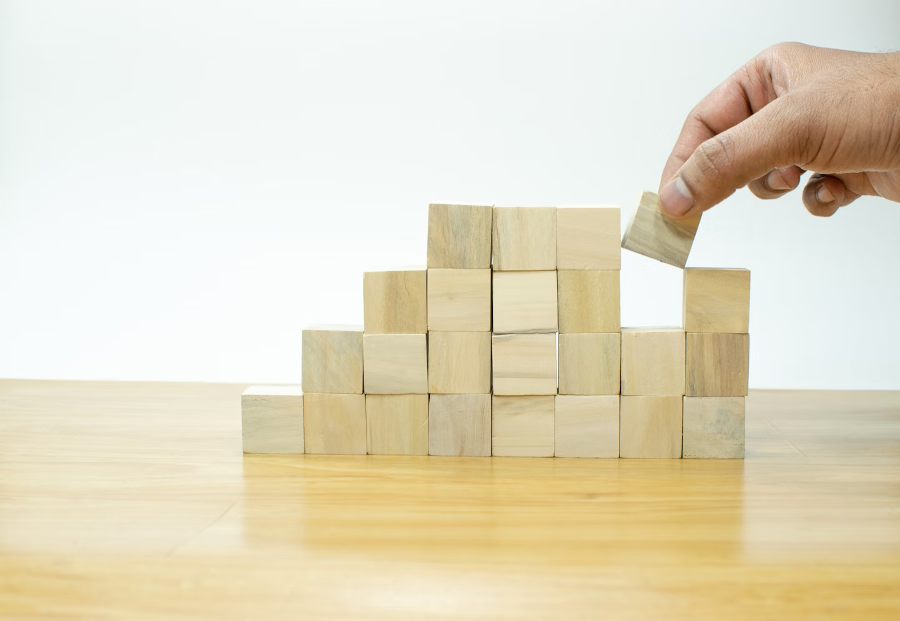採用難の現在、自社で魅力を発信できる採用広報は母集団形成の手法の1つとして注目を集めています。
しかし、「採用広報とは具体的に何か」「何をどのように発信したらよいのか分からない」といったお悩みを抱えている採用担当者様も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では採用広報の進め方やトレンドの手法を成功事例とともに解説していきます。新たに採用広報に取り組みたい方、自社の採用広報を見直したい方に必見の内容です!
採用広報とは
採用広報とは、自社にマッチした人材を獲得するために、企業の情報を広く発信することです。外からはわかりにくい企業の情報を社外へ発信していくことを通じて、採用候補者と自社との繋がりを創出することを目的としています。
具体的には、SNS・自社ブログ・採用サイトなどの手段を活用し、会社や社員の情報を発信していくことで自社の魅力を伝え、応募者の増加や、入社後のミスマッチ低減を狙います。
採用広報が注目されている背景
採用広報が注目されている背景として、以下の3つがあげられます。
▼採用広報が注目されている背景
- 労働人口減少により人材獲得が困難に
- 幅広い媒体で学生との初期接触が可能に
- 透明性のある情報が求められている
労働人口減少により人材獲得が困難に
少子高齢化の進行に伴い労働人口の減少が進行している結果、どの業界も人手不足に陥り、採用時における人材競争の激化が起こっている状態です。
リクルートワークス研究所が実施した調査によると、26卒における大卒求人倍率は1.66倍でした。
激しい競争を勝ち抜き、自社の求める人材を確保するためには、従来と同じように「ただ求人を出し、応募者の中から選ぶ」だけでは事足りません。自社の魅力を積極的に発信し、他社との差別化を図る必要があるのです。
【参考】株式会社インディードリクルートパートナーズ『株式会社インディードリクルートパートナーズ』
幅広い媒体で学生との初期接触が可能に
株式会社キャリタスが実施した調査によると、26卒の学生が新たに企業を探す手段は以下のようになりました。
▼26卒の学生が新たに企業を探す手段
- 就活情報サイト(87.4%)
- 大学の求人票(18.9%)
- 新卒紹介サービス(17%)
- 合同企業説明会※対面(15%)
- 合同企業説明会※オンライン(14.1%)
- 逆求人サービス(13.6%)
最も多かった回答は、「就活情報サイト」で87.4%でした。一方で、3位に新卒紹介サービス、6位に逆求人サービスがランクインするなど、企業の側から学生にアプローチする採用手法もランクインしていることがわかるでしょう。
【参考】株式会社キャリタス『6 月 1 日時点の就職活動調査』
▮初めてのダイレクトリクルーティングならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「採用担当だけでは手が回らない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
透明性のある情報が求められている
SNSの普及や口コミサイトの普及によって、求職者は実際の仕事内容や社風についてリアルが見えやすくなりました。実際の口コミと企業の発信している情報で差異が生じると、信頼の低下につながる恐れもあり、企業はますますオープンな情報発信が求められています。
そこで、企業が自ら発信する採用広報が注目を集めています。企業が自らの言葉で現場社員の声や働く環境、価値観を発信することで、「自分に合う会社かどうか」を判断するための材料を提供するのです。
入社後のミスマッチを防ぐためにも、採用広報で透明性のある情報を伝えることが注目されています。
戦略的な採用広報を行う目的・メリット
それでは、実際に採用広報を行うことで、企業側にはどんなメリットがあるのでしょうか。大きく分けて以下3つが挙げられます。
▼採用広報を行う目的・メリット
- 認知拡大・応募数増加
- 入社後のミスマッチ防止
- 採用コストの低減
認知拡大・応募数増加
採用広報を行うことで、自社の存在を幅広い層に認知させることができます。もともと自社に興味がある学生以外の潜在層にもアプローチを広げることができるため、より多くの学生から応募してもらえる可能性が高まります。
入社後のミスマッチ防止
採用広報活動を通じて、自社のリアルな姿を発信することで、企業の求める人材に対して自社のありのままの姿を理解してもらうことに繋がります。企業理解が深められることで、マッチ度の高い人材を集めることができます。
結果として離職率の低下、入社後のミスマッチ防止を図ることが可能になるのです。
採用コストの低減
採用広報を実施して自社の採用力を強化できれば、採用コストの低減が見込めます。応募者数増加によって、母集団獲得を円滑に進めることで広告やエージェントなどの利用を減らし、結果として採用コストを低下させることが可能になるのです。
また、入社後のミスマッチを減らし、退職者の低下に繋げることで、補填コストなど退職者にかかる採用コストを削減できます。
採用広報を成功させ、自社の採用力強化に繋げることができれば、企業側には大きなメリットになるといえるでしょう。
採用広報のおすすめ手法7選
現在トレンドの採用広報の手法は以下の5つです。それぞれの項目で具体的な媒体と特徴についても解説していますので、参考にしてみてください。
| 種類 | おすすめの企業 | メリット | デメリット |
| 採用サイト | 求職者の自社への志望度向上を図りたい | 自社の魅力を伝えることができ、ミスマッチが減る | 継続してコンテンツを生み出す必要がある |
| 採用オウンドメディア | 求める人材とのマッチ度を上げたい | 情報をしっかり届けられ、望む人材を集められる | サイト運営のためのノウハウが必要 |
| SNS | 認知度を上げたい | 拡散性があり、若年層にアプローチできる | SNS運用のノウハウが必要 |
| 採用広報動画 | 入社後のミスマッチを減らしたい | 実際に働く姿を候補者にイメージさせることができる | 作成した動画を見てもらうための戦略が必要 |
| 採用イベント | 自社に対して熱量のある学生と出会いたい | 企業の魅力や社風を熱量を持って伝えることができる | 対面で実施する場合は会場費や人件費などのコストがかかる |
| 口コミサイト | 入社後のミスマッチを減らしたい | 自社についてのリアルな内情を知ることができる | ネガティブな口コミによって求職者からの印象が下がる場合がある |
| 採用ピッチ資料 | 業務や社風を候補者に伝えたい | 情報量が多く、自社への理解度を上げられる | 作成するためにある程度の時間とリソースが必要 |
採用サイト
採用サイトは、企業ホームページとは別に、採用に関する情報を発信することが目的のサイトです。
掲載する情報として、求人票や会社概要など、具体的かつ正確な情報が中心となります。コンテンツを頻繁に更新しない点が特徴です。
■採用サイトのメリット
採用サイトのメリットとして、ターゲットとなるのが自社の求人に興味を持つ学生であるため、ターゲット層に直接的にアプローチできる点です。
■採用サイトのデメリット
一方デメリットとして、継続的にコンテンツを更新する必要がないため、継続的な母集団形成には向いていない点です。採用サイトのほかに、次にご紹介する採用オウンドメディアなど別の広報媒体を利用すると良いでしょう。
採用オウンドメディア
採用オウンドメディアは、自社で採用サイトを立ち上げ、ターゲットとなる求職者に訴求する手法です。
掲載する情報として、企業のあり方や仕事の考え方、社員インタビューなど、企業の雰囲気を伝える情報が中心になります。コンテンツを頻繁に更新する必要がある点が採用オウンドメディアの特徴です。
採用サイトとの大きな違いとして、ターゲットの違いが挙げられます。採用サイトが自社に興味を持っている求職者がメインターゲットであるのに対して、採用オウンドメディアは就職や転職を考えている層全体がターゲットです。
■採用オウンドメディアのメリット
メリットとしては、情報をしっかり届けられ望む人材を集められる点です。フォーマットや文字数に制限がなく、企業の裁量で自由に情報を発信することができるため、他社との差別化を図り、自社カラーを発信することができます。
求人媒体では、自社が求める人材に当てはまらない応募者を集めてしまうことがありますが、オウンドメディアでは企業理解を深めることができるため、マッチ度の高い人材の獲得につなげることができます。
■採用オウンドメディアのデメリット
デメリットとしては、自社でメディアを持っていない場合、一からサイトを構築する必要があるため、サイト運営についてのノウハウが必要になる点が挙げられます。
採用オウンドメディアを検討しているもののサイト構築の工数を省きたいという方は、noteやWantedlyなどの外部のツールを用いてもよいでしょう。
採用SNS
コストが抑えられ、気軽に利用できるという点から人気が高い手法がSNSです。
■採用SNSのメリット
SNSで採用広報を行うメリットとしては、拡散性があり若年層にアプローチできることが挙げられます。Instagram、X(旧Twitter)など、若年層が多く利用するメディアを利用し、情報を拡散させることができれば、広告費用をかけることなく認知度向上を図ることができます。
多くの人が日常的に利用しているツールであるため、採用ターゲットと距離が近いという点も魅力的です。
■採用SNSのデメリット
デメリットとしては、SNS運用のノウハウが必要だという点が挙げられます。フォロワー数やインプレッション数を伸ばすためにはどのような戦略が必要か、考えながら運用を続けなければなりません。
自社で行う場合には、SNS運用専門のチームを組んだり、場合によっては他社に運用代行を依頼したりするなど、自社の状況に合わせた取り組みが必要です。
採用広報動画
採用ターゲットに伝えたい情報を集約した動画をInstagramやTilTok、採用ホームページに掲載する手法も、人気が高いです。
■採用広報動画のメリット
採用広報動画のメリットとしては、実際に働く姿を候補者にイメージさせることができることです。文章では伝えきれない企業の情報を、ビジュアル面に訴求できる点が魅力的で、テレビCMのような広告効果が望めます。
応募者に対し、入社後に自社で働くイメージを持たせることができるため、ミスマッチ低減も期待できます。
■採用広報動画のデメリット
デメリットとしては、「作成した動画を見てもらうための戦略が必要である」という点です。動画を作ったらそれで終わりではなく、視聴者数を伸ばすためにはどうすれば良いか考える必要があります。
採用広報動画としてよく用いられるのはYouTubeです。YouTubeは会社や社員の雰囲気を映像で伝えることができるため、写真や文章よりも正確に伝わりやすいことがあげられます。また、Instagramのリール動画やXの動画投稿機能よりも長尺の動画を投稿することができるため、より詳細に情報を伝えることが可能です。
採用イベント
採用イベントとは、自社で行う企業説明会やインターンシップ、座談会などのイベントのことです。
■採用イベントのメリット
採用イベントを行うメリットとしては、自社の志望度が高い学生と接触できることが挙げられます。採用イベントは何らかの手段で自社に興味を持った学生が、更に自社のことを知るために応募します。
対面で実施したり、長い時間をかけて行われたりすることも多いため、自社への志望度が高い学生が集まると言えるでしょう。
■採用イベントのデメリット
デメリットとしては、採用コストがかかる点です。対面で行う場合は、会場費や人件費、社員や学生の交通費などのコストがかかってしまいます。
コストを抑えようとオンラインで開催した場合は、学生とのコミュニケーションが難しく、せっかくイベントを行っても効果が半減してしまうおそれがあることがデメリットだと言えます。
口コミサイト
口コミサイトとは、社員が自社に対する口コミを登録できるサイトのことです。
■口コミサイトのメリット
口コミサイトを活用するメリットとしては、自社の良い面・悪い面を含めたリアルな内情を知ることができるため、入社後のミスマッチを減らすことができる点が挙げられます。
■口コミサイトのデメリット
デメリットとしては、自社のネガティブな情報がそのまま伝わってしまうため、求職者からの印象が下がってしまうおそれがあることです。
また、嘘の情報が入り混じる可能性もあるため、定期的に確認して必要に応じて削除依頼を行う必要もあるでしょう。
採用ピッチ資料
採用ピッチ資料とは、「採用ターゲットに向けた会社説明資料」を指します。ただ会社の概要を説明するだけの資料とは違い、資料を見た応募者に自社を魅力的だと思ってもらうことに重点を置いています。
■採用ピッチ資料のメリット
メリットとしては、情報量が多く、自社への理解度を上げられることです。事業内容や社風、社員の様子といった細部の情報まで候補者に伝えられるため、企業理解を深められます。会社の内部が見えにくい点に悩みを抱えている企業におすすめです。
■採用ピッチ資料のデメリット
デメリットとして、作成するためにある程度の時間とリソースが必要になる点が挙げられます。ページ数としては30〜50ページあり、作成には2か月程かかります。資料作成のためにある程度人員を割く必要があるため、その点を踏まえた検討が必要です。
戦略的な採用広報の設計方法
では、実際の採用広報はどのような流れで行われるのでしょうか。
基本的には以下の6つのフェーズがあります。
▼採用広報を行う流れ
- 採用広報の目的を決める
- ターゲット像を具体化する
- 自社の魅力を整理する
- コンテンツを企画する
- 発信する媒体を選定する
- 評価軸(KPI)を設定する
1.採用広報の目的を決める
初めに、採用広報を行う目的を明確にする必要があります。企業が抱えている採用問題に応じて、選定すべき広報の手法が異なるため、効果的な採用活動を進める上で不可欠の作業です。
例えば、以下のような課題を抱えている場合、採用広報を行うことによって課題解決につながるでしょう。具体的にどのような採用広報を行えばよいか、この後の「4.コンテンツを企画する」で紹介します。
▼採用広報で解決できる新卒採用課題
- 母集団形成がうまくいかない
- エントリー数が少ない
- 自社説明会の集客が伸びない
- 自社の魅力が伝わっていない
- 内定辞退が多い
- 特定の層にアプローチできない(理系学生、地方学生など)
まず初めに採用広報を行うことで解決したい課題を明確にすることで、採用広報をより効果的なものにすることができるでしょう。
2.ターゲット像を具体化する
次に、採用したいターゲット像を具体化します。ターゲットによって発信すべきメッセージの内容や使用する媒体が異なるため、詳細かつ具体的な人物像を設定することが大切です。
できれば「〇〇大学の□□学部で、体育会系に所属している経営に興味がある学生」など、詳細まで決定することが望ましいです。ターゲットをある程度絞ることで、応募時や入社時のミスマッチを低減し、自社が求める人材の確保に繋げることができます。
ここでターゲット像を曖昧に設定してしまうと、採用広報で発信していくメッセージに一貫性が無くなってしまいます。今後の方針を定めるためにも欠くことのできないステップです。
3.自社の魅力を整理する
次に、自社の強みを明確にします。自社の強みは採用広報の軸であるため、ここを理解しておかなければ採用広報を上手く進めることができません。
「社員の仲が良い」「福利構成が充実している」など、採用ターゲットにアピールできる魅力を洗い出します。そこで洗い出した自社の強みを言語化し、発信していくことで自社のファンを形成することが目標です。魅力を整理する方法の一つとして、採用の4Pと3C分析を併用する方法があります。
4P分析と3C分析を行う際のワークシートはこちらからダウンロードできます。ぜひ使用してみてください。
◎”採用の4P”で自社の魅力を洗い出す
”採用の4P”とは、「人が組織に共感する4つの要素(4P)」に沿って自社の魅力を洗い出すための採用戦略のフレームワークです。
※マーケティング用語でよく使われる4P(Product,Price,Place,Promotion)とは別物です。

【参考】『HeaR「3C4P分析|採用活動や広報で使える人事戦略のフレームワークを公開」』
Philosophy(企業理念)・People(人・文化)・Profession(事業・業務内容)・Privilege(働き方・待遇)といった、企業の魅力を表す4つの指標の頭文字を取って4Pです。各指標の要素ごとに自社の魅力を洗い出し、求職者に訴求できる強みを見つけていきましょう!
採用の4Pを使って魅力を洗い出した後は、採用の3Cを使って自社特有の魅力を見つけていきます。
◎”採用の3C”で自社特有の魅力を探す
”採用の3C”とは、自社(Company)・競合他社(Competitor)・採用候補者(Candidate)の頭文字を取ったもので、自社・採用競合・候補者について認識を深めるために使用するフレームワークです。
※マーケティング用語としてよく使われる3C分析(Company,Competitor,Customer)のCustomer(市場・顧客)を、Candidate(採用候補者)に置き換えたものです。
▼それぞれの項目で考えるべきこと
自社(Company)
- 事業内容/ビジネスモデルは何か
- 仕事のやりがいは何か
- 採用における強み/弱みは何か
競合他社(Competitor)
- ミッション/ビジョンは何か
- 採用活動の方法は何か
- 自社にはない魅力は何か
候補者(Candidate)
- 候補者が企業選びで重視することは何か
- 活躍する社員の特徴は何か
上記の観点から競合他社と採用候補者について理解を深めたら、4P分析で洗い出した自社の魅力と3C分析を組み合わせて、他社にはない自社特有の魅力を探していきます。

自社・競合他社・候補者の3者を比較することで、候補者が求めているものの中で競合他社が提供できないもの(POD)は何かを明らかにするのです。
以上の作業で洗い出した強みを軸に、採用広報を進めていきます。
4.コンテンツを企画する
次に、設定したターゲットに対してどんなコンテンツを届けるかを決めていきます。1で明確にした採用課題を踏まえ、「ターゲットにどんな印象を与えたいか」ということを意識して、適切なコンテンツを選定する必要があります。
例えば、新卒採用課題を解決するために考えられる具体的なコンテンツ企画は表のようになります。
| 課題 | 課題解決につながるコンテンツ企画例・運用例 |
| 母集団形成がうまくいかない
(-エントリー数が少ない |
・SNS媒体を利用し、業務内容や社員インタビューなどを発信する |
| 内定辞退が多い | ・内定者向けにSNSやnoteで社員インタビューや社内イベントの情報発信 |
| 特定の層にアプローチできない(理系学生、地方学生など) | ・ターゲット別に媒体を使い分ける(Xで採用全体の情報発信を行い、noteで理系学生向けにプログラミング職の業務について発信するなど) |
5.発信する媒体を選定する
コンテンツを決めたら、次はコンテンツを発信していくための媒体を決定します。採用広報の手法としては、求人サイトやSNSなど、複数の媒体があるものの、各々で特徴が異なります。
採用広報の手法を選ぶ際は、自社の採用ターゲットや採用目的に合わせて選択することが重要です。
では、採用広報において使われる媒体には何があるのでしょうか。”トリプルメディア”を用いて以下に説明します。

トリプルメディアとは、企業がユーザーと接点を作る際に活用するメディアを「ペイドメディア」・「アーンドメディア」・「オウンドメディア」の3つに分類したフレームワークのことです。
3つのメディアにはそれぞれ特性があり、自社の採用計画に合ったメディアを選定する必要があります。
▼トリプルメディアとは
- ペイドメディア:テレビ・Web媒体といったメディアを指し、CM枠・広告枠を購入して情報を発信するタイプ。 新規アプローチや認知獲得を目的としている。
- アーンドメディア:SNSや口コミサイトといった、個々のユーザーが情報の起点となって交流ができるメディアを指す。既に興味を持っている候補者との信頼度を強化する狙いがある。
- オウンドメディア:採用企業が自社で所有するメディアのことで、採用サイトや自社ブログを指す。豊富なコンテンツを制限なく発信でき、長期的な採用を見据えた潜在層の獲得を狙いとする。
応募数を増加させたいのであれば説明会などのペイドメディアを活用するのが良いでしょうし、ミスマッチを防ぎたいのであれば採用サイトなどのオウンドメディアを活用するのが良いでしょう。
自社の採用課題に合わせ、最適な媒体を選択する必要があります。
6.評価軸(KPI)を設定する
最後に、採用広報の成果を測定するため、KPIを設定します。KPIとは、重要業績指標(Key Performance Indicator)と呼ばれるマーケティング用語であり、最終目標を達成するために実施されている施策の達成状況を測定する指標となります。
具体的なKPIの設定方法については次の章で詳しく解説します。
採用広報における評価軸(KPI)とは
KPIとは、重要業績指標(Key Performance Indicator)と呼ばれるマーケティング用語です。本章では、採用広報においてKPIを設定するべき理由と、具体的にどのようなKPIを設定すれば良いのかについて解説します。
採用広報でKPIを設定するべき理由
採用広報でKPIを設定するべき理由は以下の2点です。
▼採用広報でKPIを設定するべき理由
- 課題を明確にできる
- 効率よく採用広報を運用できる
①課題を明確にできる
KPIを設定し、定量的に採用広報の取り組みを管理することで、採用広報における課題を明確にすることができます。
KPIで設定した数値と実際の数値が乖離していた場合、その項目が課題であると判断することができるでしょう。
②効率よく採用広報を運用できる
KPIを設定し、課題を把握することで、効率的かつ戦略的な採用広報を運用することができます。
KPIを設定せず、やみくもに採用広報を運用していては、具体的な課題解決のための施策を打ち出すことができません。KPIを設定することで必要な対策を必要な頻度で行うことができ、効率よく採用広報を運用できます。
採用広報で設定するべきKPI
具体的に設定するべきKPIは以下の通りです。
長期目標(採用活動全体の評価指標)
- 応募者数(認知度は向上しているか)
- 選考通過率(自社のターゲットを獲得できているか)
- 内定承諾率(志望度は向上できているか)
- 入社後の定着率(ミスマッチ防止できているか)
短期目標(メディアとしての評価指標)
- Webページやコンテンツへの流入数(PV数)
- 採用広報動画の視聴数
- SNSのインプレッション数
- SNSのエンゲージメント数
長期目標に加えて短期目標も設定することで、定期的に成果度合いを確認し、改善につなげて採用広報の精度を上げていきましょう。KPIを導入することで、最終目標をより達成しやすくなります。
採用広報を成功させるポイント
それでは、採用広報を成功させるためにはどのような点に注意すべきでしょうか。
以下3つのポイントがあります。
▼採用広報を成功させるポイント
- 採用広告で発信するべきポイントを理解する
- 採用課題を解決できるコンテンツを選ぶ
- 採用ターゲットに向けた広報を意識する
- 現場の社員と協働する
採用広告で発信するべきポイントを理解する
採用広告を作成・運用するためには学生はどのような情報を求めているのかを理解した上でコンテンツを選定する必要があります。
株式会社キャリタスが実施した調査によると、エントリーや本選考に応募するかどうか判断する時に採用ホームページで回覧したコンテンツは以下のようになりました。
▼エントリーや本選考への参加の有無を判断する時に回覧したコンテンツ
- 事業内容・実績(66.7%)
- 待遇・福利厚生・ワークライフバランス(66.6%)
- 会社概要(48.4%)
- 企業理念・トップメッセージ(47.8%)
- 採用コンセプト・求める人物像(43%)
ここから、事業内容や実績・会社概要などはもちろんですが、待遇や福利厚生などを知りたいと考える学生が多いことがわかります。
採用広告で発信するべきポイントをしっかり理解したうえで、コンテンツ作成を行いましょう。
【参考】株式会社キャリタス『2025年卒 採用ホームページに関する調査』
採用課題を解決できるコンテンツを選ぶ
採用広報を成功させるためには、自社の採用課題を踏まえて、最適なコンテンツを選定することが重要です。
認知度自体を向上させたい場合は、まずはどんな企業なのか知ってもらう必要があるため、事業内容を中心にアピールする必要があるでしょうし、入社後の定着率を上げたい場合は、社員インタビューといったより踏み込んだ内容を発信していくのが効果的でしょう。
ただ闇雲にコンテンツを企画するだけでは、自社の採用課題解決から遠ざかってしまうため、最適なコンテンツを発信することが大切です。
採用ターゲットに向けた広報を意識する
採用広報において注意が必要なのは、自社が求める人材に向けて、一貫性のある内容を発信できているかということです。採用ターゲットを明確にせず、不特定多数の人々に対して情報を発信してしまうと、自社にマッチした人材を採用できません。
自社が求める人材を訴求するために必要な内容は何かを常に考え、魅力的な情報を発信していく姿勢が必要です。
現場の社員と協働する
企業のリアルな姿を、最大限魅力的に発信していくためには、現場の社員を積極的に巻き込むことが効果的です。採用担当者だけでコンテンツを企画してしまうと、リアリティに乏しく、表面的な内容になってしまう可能性があります。
さまざまな部署や年代の社員から話を聴いたり、記事作成を依頼したりすることで、よりリアルな視点から企業の魅力を伝えることができるのです。
採用広報の成功事例7選
採用広報で成果を出している企業事例を7選紹介します。
▼採用広報の成功事例7選
- freee株式会社
- 株式会社メルカリ
- 株式会社ベルク
- サイバーエージェント
- 三井住友カード株式会社
- レバレジーズ株式会社
- 株式会社YOUTRUST
1.freee株式会社|採用サイトでのインタビュー記事の発信
シェアNo.1のクラウド会計ソフトを運営するfreee社では、特に採用サイトでの記事発信に力を入れており、高い認知度を誇っています。
社員インタビューや職種紹介といったコンテンツが豊富に用意されており、事業に込めるビジョンを実現するため、社員がどういった活動をしているのかを非常に理解しやすい内容となっています。
具体的には、
- 何を求めて入社したのか
- 入社直後の印象
- この会社に入ることでどのような変化が得られたのか
- これからどうなりたいのか
という点について、新卒〜中途採用の社員からのインタビュー記事が載せられています。採用サイトで社員インタビューを導入したいと考えている方は是非参考にしてみてください!
【参考】freee株式会社『採用サイト』
2.株式会社メルカリ|オウンドメディアでのインタビュー記事の発信
フリマアプリ「メルカリ」を運営している株式会社メルカリは、”メルカン”というオウンドメディアを運営しており、社員インタビュー記事の発信に力を入れています。
メルペイ事業や、メルカリ10周年プロジェクトの舞台裏紹介など、プロジェクト毎に社員インタビューを行い、社員が各事業に懸ける想いにフォーカスした内容となっています。お客様へどんな価値を届けたいか、メルカリらしさはどんな点にあるかなど、社員目線でメルカリ独自の魅力がよく伝わるオウンドメディアです。
また、「Go Bold(大胆にやろう)」「All for One(全ては成功のために)」「Be a Pro(プロフェッショナルであれ)」といった3つのバリューを採用ページ全面に押し出し、メルカリが大切にしているミッションとは何かを効果的に伝えています。
採用ターゲットにとって魅力的な情報とは何かを的確に捉えたコンテンツを発信することで、潜在層のファン化に成功しています。
【参考】株式会社メルカリ『採用情報』
3.株式会社ベルク|YouTubeでの社員の再現ドラマ
株式会社ベルクは、埼玉県に本社を置くスーパーマーケットチェーンであり、採用動画の発信に力を入れることで応募者増加に成功しています。youtubeの公式アカウントにて、新卒活動中の女性を主人公にした再現ドラマを発信し、ベルクの魅力を効果的にアピールしました。
結果として、150万回以上の再生回数を獲得し、採用サイトへのアクセス数が200%に増加しました。
採用サイトにおいても、社員インタビューやnoteでのブログ発信など、豊富なコンテンツによって自社の魅力を発信しています。
【参考】株式会社ベルク『採用サイト』
【参考】株式会社ベルク「採用動画」
4.株式会社サイバーエージェント|SNSで採用情報を発信
「ABEMA TV」や「Ameba ブログ」といったメディア事業を運営するサイバーエージェントは、SNSを使った採用広報に力を入れています。
X(旧Twitter)上にて新卒採用向けのアカウントを運営し、募集情報だけでなく、企業理解に役立つコンテンツも含めた発信をしています。
【出典】サイバーエージェント「公式サイバーエージェント新卒採用」
5.三井住友カード株式会社|Instagramで就活に役立つ情報を発信
クレジットカード事業を行う三井住友カード株式会社では、Instagram上での情報発信に力を入れています。
社員インタビューなどの社風理解に繋がる情報にとどまらず、内定者アドバイスなどの就活全般に役立つ知識を発信することで、潜在層へのアプローチを図っています。
6.レバレジーズ株式会社|起業ストーリーを漫画で紹介
人材紹介事業をはじめとして幅広い事業を展開するレバレジーズ株式会社は、岩槻知秀代表取締役社長の起業ストーリーを漫画化した「若槻代表物語」の配信や、YouTubeではYouTuberを起用した広報を行っています。
「若槻代表物語」ではレバレジーズの理念や社風が生まれた背景について知ることができ、会社への理解を深めることができます。この漫画を読んで代表の考えに共感した応募者が応募することで、ミスマッチを減らすことにつながると考えられます。
【参考】JobManga『若槻代表物語 レバレジーズ株式会社』
7.株式会社フィードフォース|公式noteで社風、事業など発信
株式会社フィードフォースでは、公式noteで事業内容や社員、社風や制度など、会社についての情報を幅広く発信しています。特に社内の評価制度の変更についての記事では、その経緯が丁寧にまとめられており、会社の情報の透明性を感じられる記事となっています。
【参考】株式会社フィードフォース『フィードフォースのnote』
人事のプロが推薦!採用広報が学べる書籍3選
ここまでで、採用広報のやり方~成功事例までご紹介してきましたが、最後に採用広報について更に知識を深められる書籍をご紹介します。
▼採用広報が学べる書籍3選
- 『【小さな会社】逆襲の広報PR術』
- 『現場の広報担当2500人から生で聞いた広報のお悩み相談室』
- 『サイバーエージェント 広報の仕事術 成長を掛け算にする』
『【小さな会社】逆襲の広報PR術』
「広報になったけど、そもそも何をやれば良いか分からない」といった、広報初心者の方におすすめの一冊です。
「広報の目的とは何か」「広告と広報を行う目的は何か」といった、広報を行う上で重要となる基礎的な内容が網羅的に記載されています。
広報担当としては外せない一冊です。
『現場の広報担当2500人から生で聞いた広報のお悩み相談室』
「メディア向けにどんな資料を作ればよいか」といった、広報担当者が必ず悩むであろうことへの回答が一通りおさえられている一冊。
ベテラン広報の方にとっては当たり前の内容までかみ砕いて説明されているので、広報初心者の方には大変役立つ内容となっています。
【参考】amazon『「現場の広報担当」2500人からナマで聞いた広報のお悩み相談室』
『サイバーエージェント 広報の仕事術 成長を掛け算にする』
サイバーエージェントにおいて広報責任者を務めている方が執筆された本で、担当者目線だけではなく、会社の経営目線から広報が学べる一冊となっています。
著者は、広報担当として、知名度ゼロだったサイバーエージェントが最先端のIT企業に成長するまでの過程を経験しています。
その中で培った「攻めの広報術」がわかりやすく記載されており、ベンチャーから大企業の広報担当者まで、会社を持続的に成長させていくための広報戦術を学ぶことができます。
【参考】amazon『サイバーエージェント 広報の仕事術 成長をかけ算にする』
工数をかけずに自社にマッチした人材を採用するならMatcher Scout
「工数をかけずに自社にマッチした人材を採用したい」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
おわりに
いかかでしたか?
本記事では、採用広報のやり方から成功事例、学びを深める際におすすめの書籍までを紹介してきました。
自社の採用課題を解決し、自社が求める人材を獲得していくには採用広報を効果的に活用する必要があります。
本記事の内容を基に、自社の魅力を積極的に発信していきましょう!