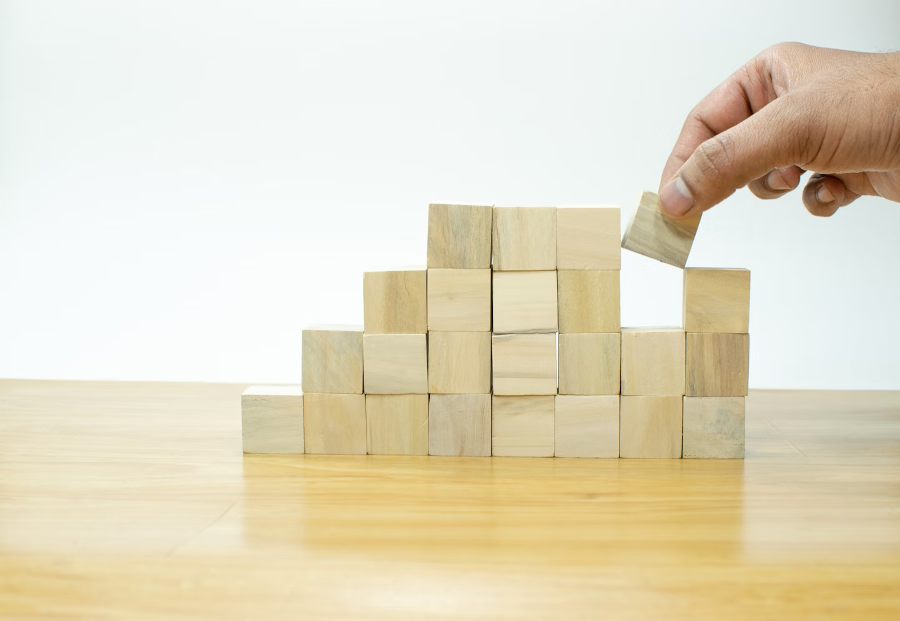これまで新卒採用はポテンシャル採用が一般的でしたが、
「新卒も中途も関係なく、すぐに成果を残せる人を採用したい」
「特定のスキルを持った新卒のみを採用したい」
といった、新卒に即戦力を求める企業が増加しています。
では新卒で即戦力を採用するにはどうしたらよいのでしょうか。また、新卒で即戦力を求めていいケースとはどんなケースなのでしょうか。
本記事では
- 新卒で即戦力を求めるのはおかしいことなのか
- 新卒で即戦力採用を実施する方法
- ポテンシャル採用の学生を即戦力人材に育成する方法
などを、新卒のダイレクトリクルーティングサービスMatcherScoutを運営する弊社の立場から紹介します。さらに、
「新卒で即戦力採用を行いたいけど、どんな学生を採用したらよいのか、求める学生像を決めるのが難しい・・・」
とお悩みの方に向けて、弊社は採用する学生像の作成に役立つ「採用ペルソナ設計シート」を作成しました。
無料なので、お気軽にダウンロードしてください!
採用における「即戦力」の定義とは
まず本記事テーマの「即戦力」という言葉を定義しましょう。
即戦力とは、「入社後すぐに組織に貢献できる経験豊富な人材」を指します。即戦力採用とは、以上で述べた人材をターゲットにした採用手法です。
また、即戦力採用と反対の意味を持つ言葉で「ポテンシャル採用」という言葉があります。ここでは、ポテンシャル採用との対比において、即戦力採用を詳しく定義していきます。
即戦力採用とポテンシャル採用を「活躍を求めるまでの期間」と「重視するスキル」の2つに分けて考えると、以下のようにまとめられます。

活躍を求めるまでの期間
従来までは、即戦力採用=中途採用、ポテンシャル採用=新卒採用とされてきました。
中途採用においては、入社後すぐに活躍できる人材の獲得を目的にしているのに対し、新卒採用においては、入社してから数年後の活躍に期待して採用活動が行われてきたという違いがあります。
新卒にも即戦力化を求める近年の動きを見ると、新卒に対しても入社後すぐに活躍できる人材が求められてきていると言えます。
新卒採用で即戦力となる人材の特徴
新卒採用において、一般的に「即戦力」になる人材の特徴は、以下の通りです。
▼即戦力になる人材の特徴
- 専門的な知識・スキルを持っている
- コミュニケーション能力が高い
- 明確なキャリアプランがある
■専門的な知識・スキルを持っている
専門的な知識やスキルを持っていることが即戦力となる人材の特徴です。従来「即戦力採用=中途採用」とされてきたのは、即戦力採用とは、実践的なスキルを持ちすぐに実務で活躍できる人材が「即戦力人材」と定義づけられてきたからでしょう。
新卒採用の場合、学生は社会人経験がないため知識を持っていても実際に業務に活用できるかとは限りません。しかし、知識やスキルを持っている学生は他の学生より即戦力人材として業務を遂行しやすいことは確かです。
また、近年では長期インターンに参加し、実務的にスキルを身につけている学生も一定数います。そのような学生は新卒で即戦力として働ける可能性が高いため、具体的にどのような知識やスキルを持っているのか、選考の段階で確認することが必要です。
■コミュニケーション能力が高い
コミュニケーション能力が高いと、業務のなかで不明点が発生した場合、すぐに上司や同僚に相談することが可能です。そのため、いち早く部署に馴染み、他の社員と協力しながら仕事に取り組むことができます。
仮にスキルの高い即戦力人材だったとしても、周囲とのコミュニケーションが取れないと円滑に業務を進めることが困難になってしまいます。コミュニケーション能力の高さは即戦力人材を求めるうえで柱となる重要な特徴ともいえるでしょう。
■明確なキャリアビジョンがある
明確なキャリアビジョンがある人材も、即戦力となる特徴のひとつです。
例えば「3年後までに部署成績1位を取る」「5年後以内にプロジェクトリーダーになる」など明確な目標がある場合、その目標を叶えるためにどう行動すればよいのか考えて業務を進めます。
専門的なスキルを持っていなかったとしても業務に必要な知識やスキルを吸収することで、即戦力となるでしょう。
新卒採用で即戦力を求めるのは求めすぎ?即戦力が求められる背景とは
新卒採用において即戦力が求められている背景には、人手不足が挙げられます。
今までの採用の現場では、即戦力と言えば中途採用。新卒に即戦力を求めることは「おかしい」「求めすぎ」「ありえない」という認識もありました。
新卒は実務経験がなくても様々な企業に就職でき、その強みを表現する「新卒カード」という言葉も存在します。しかし、現在はどの業界でも人手不足であり、ビジネスモデルの変化も激しいため、新卒でも早期戦力になることが求められています。
株式会社帝国データバンクが実施した調査によると、正社員・非正社員共に、従業員の過不足状況について「不足している」と回答した割合が上昇傾向にあり、正社員に至っては51.4%にも上っています。
人手不足の企業では、社員は自分の業務で忙しいため、人材教育に割くリソースが不足しているという課題があります。その結果として、育成コスト低減が見込める即戦力人材の確保が求められるようになったといえるでしょう。
このような時代の変化を受けて、学生の中でも「もはや新卒カードは通用しない」と考える人は増えつつあります。上記のような現状を踏まえると、一概に新卒採用において即戦力人材を求めることがおかしいとは言えないでしょう。
【参考】帝国データバンク『人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)』
ただし、実務経験のない学生が大半なので、全員を即戦力で採用するというのは難しいです。また、仕事は実務経験や専門スキルだけで成り立つものではなく、主体性・コミュニケーション能力といったソフトスキルを持っているかどうかも重要になります。
例え実務経験があったとしても、入社後周囲と協働するコミュニケーション能力がなければパフォーマンスを発揮することができません。自社が求める人材要件を整理した上で、新卒に求める能力を検討していくのが良いでしょう。
新卒の即戦力採用に適した3つのケース
新卒全員を即戦力で採用するのは難しいですが、即戦力採用の方がよい、というケースは存在します。では、新卒で即戦力採用を導入すべき場合はどのようなケースでしょうか?
ここでは「新卒で即戦力採用を行った方が良いケース」を3つ紹介していきます。
▼新卒の即戦力採用に適した3つのケース
- 専門性の高い知識が必要な職種での採用
- ベンチャー・スタートアップ企業が採用を行う場合
- すでに中途・新卒の区別なく採用を行っている場合
1つずつ詳しく見ていきましょう。
①専門性の高い知識が必要な職種での採用
エンジニアや弁護士といった士業など高い専門性が必要な職種においては、即戦力採用がおすすめです。
学生時代から、専門性の高い内容に取り組んできた新卒は、社会人と変わらないスキル・知識を持っている可能性があります。そのため、中途と同じように、持っている資格や知識に重点をおいて採用するのもよいでしょう。
特に、近年専門性の高い職種として、即戦力採用が進んでいるのがITエンジニアです。
DX化の進展が国内外で求められている昨今、IT・デジタル領域を筆頭に専門性のある人財の獲得競争が激化しています。
このような背景から、エンジニアに対して新卒でも即戦力を求める動きが出てきています。
例えば、世界有数の電機メーカーである日立製鉄所は、2022年度の新卒採用のうち9割を「ジョブ型雇用」で採用すると公言しており、技術系の500名をジョブ型採用するとしています。
【参考】株式会社日立製作所『日立が進める「ジョブ型」とは? わかりやすく解説』
「エンジニアはたくさん募集したいから、即戦力に絞ると応募できる学生が減ってしまう」
という場合は、採用枠を「即戦力枠」と「未経験者歓迎枠」に分けることをおすすめします。アプローチできる人材の幅は狭くなりますが、専門性の高い人材を採用したい場合は、即戦力採用がよいでしょう。
■専門性の高い学生にピンポイントでアプローチしたい方へ
「専門性の高い学生にピンポイントでアプローチしたいが、なかなか学生を見つけられない・・・」とお悩みの担当者様はいらっしゃいませんか?そんな方におすすめなのが、新卒向けダイレクトリクルーティングサービス「Matcher Scout」です。
Matcher Scoutでは、学歴や専攻・使用できるプログラミング言語などで条件を絞って学生にスカウトメールを送信することができます。そのため専門性の高い学生にピンポイントでアプローチが可能です。
OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信し、スカウトメールの送信など運用にかかる一切の業務を代行します。
ご興味を持っていただけましたら、ぜひ以下の資料をダウンロードください。
②社員数が少ない企業が採用を行う場合
社員数が少ないベンチャー、スタートアップ企業も、新卒の即戦力採用がおすすめです。
というのも、ベンチャー企業は人手が足りない傾向にあり、その影響で人事制度や教育体制の構築ができていない可能性があるためです。
人手が足りている企業であれば「1年目は学びの期間として、ゆっくり研修を受けてほしい」というスタンスで新卒に向き合うことができます。しかし、人手の足りない企業では新卒でもすぐに活躍してもらう必要があるかもしれません。
また、社員数が少ない時期に入社する新卒は、将来「会社のコアメンバー」になる可能性が高くなります。将来的に重要な役割を任せる人を採用するためには、新卒で即戦力採用を行うのがよいでしょう。
「将来会社の幹部候補になってほしい!」というよりも「とにかく短期的に売上を伸ばせる人材を採用したい!」という場合は、経験のある中途を採用するのがよいです。
③すでに中途・新卒の区別なく採用を行っている場合
一部の外資系企業や、日系企業がすでに行っているように「中途・新卒の区別なく採用を行っている場合」は、新卒で即戦力を求めるのがよいでしょう。というのも、中途採用と新卒採用を区別なく採用している以上、求める能力は同じ、もしくは近いものになるためです。
近年は、新卒採用において、従来通りの「一括採用」だけではなく、「通年採用」を導入する企業が増加しています。「通年採用」とは、企業が採用の時期を定めずに、年間を通じて行う採用活動のことを指します。近年は、留学生などを含めて優秀で幅広い人材を確保するためや、人手不足解消の一手として導入する企業が多いようです。
実際に、経団連が2024年に実施した調査によると、新卒採用において通年採用を実施している企業は全体の約3割でした。また、2022年に行った調査によると、今後5年で実施予定であると回答した企業は55%に上っています。
【参考】経団連『2024年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果』
また、リクルートやソフトバンクといった企業では、積極的に通年採用が実施されており、「30歳未満の未経験者であれば、学生・社会人区別なく、皆同じ窓口から採用する」という手法を導入しているようです。
【参考】リクルート「募集要項」
【参考】SoftBank「募集要項」
ただし、出会える人材の幅が広がるというメリットがある反面、採用への工数・費用が増えたり、一括採用との両立が困難だったりと、デメリットも存在します。
また、日本では、新卒採用においては未経験者が中心で、実務経験のある学生は非常に少数であるのが現状です。「数十名〜数百名を即戦力で採用する」というのは、現実的に難しいでしょう。
即戦力を求めて通年採用の導入を考える場合には、自社の採用課題を踏まえた上で、慎重に判断していきましょう。
中途と比較!即戦力の新卒を採用するメリット
新卒採用で数十名~数百名の学生を即戦力採用するのは現実的ではありません。しかし、新卒採用で即戦力の獲得を目指すことによって、中途採用の即戦力人材とは異なったメリットも存在します。
以下は、新卒・中途採用で即戦力人材を採用するメリット・デメリットを表でまとめたものです。

中途採用と比較した、即戦力の新卒を採用するメリットについて詳しくみていきましょう。

企業文化を体現していきやすい
企業文化を価値観として持つことは、社員が一丸となって業務に取り組むことに繋がるため非常に重要です。新卒で入社する社員は社会経験が少ないため、自社のカルチャーが浸透しやすいです。
一方、中途社員は前職の企業の社風や自分なりの価値観が形成されていることがあるため、企業の色に染まることは少ないでしょう。自分なりの仕事のスタイルが確立されている場合もあり、業務内容に支障が出る可能性も考えられます。そのため、中途社員よりも企業文化を体現しやすい新卒を雇うことでスムーズに業務を進めることが可能です。
特に現在は人材不足による少数精鋭で、変化の激しい世界に立ち向かわなければなりません。企業文化の体現は重視すべきでしょう。
同時期に研修ができるため効率がいい
新卒生は中途と違い一括採用するため、研修等の教育を一括で行うことができます。研修のスケジュール調整や運営準備、会場の確保など、研修にかかる手間は膨大ですよね。新卒生を全員集めて研修を行い、研修にかかるコストを抑えて効率化することが可能です。
また、全く同じ研修を同時期に行いベースラインを揃えることで、その後の新入社員の成長度を簡単に測ることもできます。社内評価がつけやすくなることもメリットといえます。
横のつながりができる
新卒社員は、同じ年に採用された同期と研修期間などを共に過ごすため、横のつながりが強くなりやすいです。横のつながりがあることで、無意識に比較してライバルのような関係性を保つため、仕事へのモチベーションが上がりやすいでしょう。
また、プライベートを含む人間関係が構築されやすいため、退職しにくくなります。
一方、中途社員の場合、前職から転職しているため企業の知り合いが少ない状態からのスタートです。そのため、同期との繋がりが強いことも中途ではなく新卒採用をするメリットです。
組織を活性化させられる
新卒採用をするたびにマニュアルや企業文化を見直すことになるため、組織が活性化されて持続可能性の高い企業へと成長することができます。また、2年目になった社員は先輩として自立を強く意識し、モチベーションを保つ要因になります。
新入社員に初歩的な質問をされることで、改めて業務を理解できることもありますよね。先の分からない時代だからこそ、若い意見を直接吸収できることは大きなメリットです。
中途と比較!即戦力の新卒を採用するデメリット
それでは、中途採用と比較して、即戦力の新卒を採用するデメリットはどこにあるのでしょうか。以下で詳しくご紹介します。

中途採用よりもミスマッチが起きやすい
中途入社の場合は、前職でどんな業務に取り組んでいたか明確なため、能力を測りやすいです。そのため自社の求める人材であるか判断しやすい傾向にあります。
また、社会人経験があるため面接官との共通言語が多く、お互い業務への認識がずれにくいのが特徴です。
一方で、即戦力採用といっても新卒の学生はポテンシャルを含めて採用を行うことが多いため、適性能力を測りにくいです。
また、社会人経験があったとしても、長期インターンシップ等の経験に留まってしまいます。そのため入社前の業務理解が不十分になり、入社後、お互いに期待していた効果が得られない可能性があります。
ミスマッチを防ぐために、新卒採用マニュアルを作成して基準を明確化することや、学生が入社後の業務をしっかり想像できるような取り組みをすることが必要です。
教育に時間がかかりやすい
いくら即戦力の新卒といっても、中途と比べれば社会人経験の差があります。
知識は豊富でも、OJTやビジネスマナーの教育などは中途よりも手厚く行う必要があります。即戦力の人材だからといって初めから上手くいくわけではありません。あくまで新卒社員であることを念頭に育てる必要があるでしょう。
新卒即戦力の採用手順①:会社に必要な即戦力とは何かを定義する
ここからは新卒採用で即戦力人材を採用するための手順を解説します。
1つ目のポイントは、会社に必要な能力やスキルを洗い出し、自社が求める即戦力人材はどんな人材かを定義することです。採用活動を開始する前に、まずは新卒がどのような能力を持っていれば入社してすぐに活躍できるのか考えましょう。
即戦力になる人物像は会社によって異なるものです。採用の目的をはっきりさせ、どのような学生を求めているのか定義付けしましょう。
以下では、新卒の即戦力人材に求める能力の例を紹介していますので、自社に必要な能力とは何か考える際にお役立てください。
▼新卒の即戦力人材に求める能力の例
- 専門性が高いスキル・資格を持っている
- ビジネスマナーができている
- 外国語のスキルが高い
専門性が高いスキル・資格を持っている
職種を決めて募集するジョブ型雇用で採用する場合におすすめです。
ITやデータ分析など理系分野の学生や、デザインなどクリエイティブに関する知識がある学生を採用することが多いです。大学や専門学校での専攻内容が一致している学生や、専攻が一致していなくてもインターンや独学で学んでいるケースもあります。
また、総合職採用と並行してフローを別に選考する企業もあります。スキル採用やスペシャリスト採用と記載していることが多いです。
ビジネスマナーができている
ビジネスマナーの研修に時間を割かずに実戦に取り組んでもらいたい場合、ビジネスマナーを採用要件として見極めることがあります。
近年、長期インターンに取り組む学生が増えています。報連相など社会人としてのコミュニケーションや、電話対応などを既に習得していることが多く、会社にとって即戦力になれるでしょう。
外国語のスキルが高い
入社後、グローバルな活躍をして欲しい場合におすすめです。
ただし、ネイティブレベルを求めるのか、読み書きができてほしいのかなどレベル感をはっきりさせる必要があります。新卒採用担当者間で認識を共有させましょう。
新卒即戦力の採用手順②:求める項目の優先度を決める

「新卒即戦力の採用手順①:会社に必要な即戦力とは何かを定義する」で即戦力の定義付けが重要だと解説しました。
しかし、ITの実務経験があって英語も堪能で発言力もあって…という学生は限られてしまいます。即戦力を求めすぎると母集団の形成に失敗し、採用活動が滞ってしまいます。
例えば、長期インターンや短期留学の経験がある学生は近年増加していますが、まだまだ少数派であることも事実です。以上の図のように、単に高いポテンシャルを持つ学生に比べると、長期インターンなどの経験を持つ学生を採用する難易度は高いといえます。
そのため、求める項目の優先度を決めることで、学生の幅を広げつつ求める人材を採用するとよいでしょう。妥協するのではなく、良い人材獲得のために優先度を決めましょう。
新卒即戦力の採用手順③:選考方法を定める

採用手法のトレンドは年々移り変わり、多様化しています。
ここでは新卒採用が初めての方でも取り入れやすい、基礎的な選定方法を紹介します。
面接・適性テスト・ES・GDで確認する項目を決める
「新卒即戦力の採用手順①②」で決定した内容を、選考においてどのように審査するのかを具体的に決めましょう。選考基準が抽象的だと選考担当者間で認識にずれが生じてしまい、求める人材を獲得できない可能性があります。
ビジネスマナーを求めるなら、アルバイトや長期インターンシップ経験を重視するのがおすすめです。第2新卒生であればほぼ確実にこの点はクリアできるでしょう。第2新卒とは、一般的には新卒入社した会社を3年未満で退職した求職者のことを指します。
ただし法的な定義はないため、企業によって第2新卒の扱いは異なります。第2新卒はビジネスマナーを有していながら、まだ他の企業の色に染まっていないため、自社の価値観やカルチャーを体現してくれる即戦力になり得ます。
スキル採用であれば、持っている資格の難易度や実務経験の有無、または学部生か院生かなどを項目として設定します。語学力では、TOEICの点数や留学等の経験など何を重要視するかが大切です。
特にポテンシャル採用は、学生の性格など親しくないと分かりえないような部分が重要になるため注意が必要です。「ガクチカ」などについて、深い質問をすることで本当にその学生にポテンシャルがあるのか探りましょう。
長期インターンシップから雇う
長期インターン生から採用する最大のメリットは、勤務態度や能力を確実に知った状態で採用できることです。自社のカルチャーや基本的な業務、ビジネスマナーをある程度身に着けているので、採用後は即戦力として活躍してくれるでしょう。
学生側も、会社のことをじっくり知ったうえで入社するためミスマッチが生じにくいメリットもあります。ただし、インターン生を雇う・育成する工数はかかる点に留意してください。
新卒即戦力の採用手順④:採用ツールを活用する
採用したい即戦力の定義、定義した項目の優先順位付け、選考中の見極め方を定め終えたら採用ツールを選定していきます。即戦力人材を採用するためには採用手法の選定も重要です。
即戦力となりうる新卒学生は人数が少ないうえに、様々な企業が採用したいと考えます。
そのため応募を待つのではなく、自らアプローチできる採用手法で母集団形成を行いましょう。ここでは企業自ら学生にアプローチできる手法をご紹介します。詳しい採用手法ごとの特徴分析はこちらからダウンロードできますので、ぜひ参考にしてみてください。
①ダイレクトリクルーティング
近年、即戦力人材を確保するためにダイレクトリクルーティングを導入する企業が増えています。ダイレクトリクルーティングとは企業が直接学生にアプローチをかける手法です。
学生のデータベースの中から、欲しい人材を選定してスカウトメールなどを送るため、求める人材にピンポイントで直接アプローチすることが可能です。
一般的な採用手法では、学生の経験・スキル等は選考を通じて知ることしかできません。
しかしダイレクトリクルーティングであれば、初めから求める能力を持つ学生のみを選考に案内するため、確認事項が多く工数がかさみやすい即戦力採用では非常に有効です。
学生を選定しスカウトを送る工数はかかりますが、最近ではこれらの業務を代行してくれるサービスもあります。このようなサービスを活用すれば、新卒採用担当者の業務負担を限りなく少なくし、なおかつ求める即戦力人材をスカウトすることが可能です。
■即戦力となる優秀な学生と出会える!Matcher Scoutとは
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
②求人情報サイト
求人情報サイトとは、マイナビ・リクナビなど、企業が求人情報を載せるプラットフォームです。
就活生は全員と言っていいほど大手求人情報サイトに登録するため、母数が非常に多い媒体です。人数が多い分様々な学生がいるため、募集事項に必要な経験等をしっかりと明記する必要があります。
③人材紹介
人材紹介とは、エージェントが企業の求める人材をヒアリングし、適合する求職者を紹介するサービスです。中途採用ツールとして活用されてきた人材紹介ですが、近年では新卒採用の場面でも広がりを見せています。エージェントは担当新卒生の希望や能力をしっかり把握しているので、即戦力になれる人材を見極め紹介してくれるでしょう。
④リファラル採用
リファラル採用とは、社員に優秀な知り合いを紹介してもらう採用手法です。社員からの紹介という点では縁故採用・コネ採用と同じです。
しかしリファラル採用では社員との関係性のみでは採用せず、通常と同じレベルの選考を行うことが特徴です。人材紹介やダイレクトリクルーティングは求める人材にアプローチできる点が長所ですが、優秀な人材には多くの声がかかるため埋もれてしまう可能性があります。
リファラル採用の場合は、求人媒体に登録しておらず、競争率は低いのに優秀な即戦力人材を獲得できる可能性が高いです。
また、社員と学生が知り合いであれば、会社の雰囲気や働き方を伝えやすいです。そのため会社に好印象を抱きやすく、ミスマッチも起こりにくい利点があります。
【参考】リファラル採用とは?報酬相場や、新卒で行うメリット・デメリット
新卒を短期間で即戦力人材に育成する方法
ここまでは、即戦力の新卒を採用する手法について紹介してきました。ここでは、入社後の新卒を即戦力化するコツについて紹介していきます。新卒を短期間で即戦力人材に育成する方法は以下の4つです。
▼新卒を短期間で即戦力人材に育成する方法
- 人材育成計画で即戦力化を図る
- メンター・管理職の意識改革をはかる
- 内定者インターンを実施する
- 研修プログラムを見直す
①人材育成計画で即戦力化を図る
1つ目のポイントは、新入社員の即戦力化を目指して育成計画の策定を行うことです。半年から1年という時間軸を設定し、新卒を育成していくイメージを持つと良いです。育成計画は、新卒がいち早く一人前として活躍するための道標と言えます。
この道標をずさんに設定してしまうと、教育担当者の負担増加や新卒の成長阻害に繋がってしまいます。育成計画に注力することで、以下3つのメリットを期待できます。
▼人材育成計画に注力する3つのメリット
- 組織の目標達成に貢献する人材を育成できる
- 計画を共有することで、新卒の成長を後押しして即戦力を育成できる
- 計画の改善により、育成環境を向上させられる
自社が目指す目標を実現するにはどのような人材を育成すべきか考えて育成計画を練り、会社の方向性と育成方針を合致させることで、将来的に組織で活躍する人材を育成することができます。
また、策定した計画を社員全体に共有することで、社員一丸となって新卒の成長を後押しするムードを醸成することに繋がります。1年ごとに育成計画を振り返り、次年度の改善に活かすことで、新卒の育成環境を継続的に向上させることも可能になるでしょう。
②メンター・管理職の意識改革をはかる
新入社員がいち早く即戦力として活躍するためには、メンターや管理職の面々といった、新卒の指導に当たる側の力が不可欠です。新人の成長環境を整えるためには、育成側が新入社員の傾向を理解し、それに合わせて指導を行う必要があります。
以下の調査結果をご覧ください。リクルートマネジメントソリューションズが実施した「新入社員意識調査2024」の一部で、新入社員が求める職場環境の変遷について示しています。

※「昨年との比較」「5年間の比較」「10年間の比較」のポイント数は四捨五入して表示。※「調査開始以来」とは、最初に調査を開始した2010年以来。
【参考】株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「『新入社員意識調査2024』の分析結果を発表」
「お互いに助けあう」「遠慮をせずに意見を言い合える」が上位となりました。「お互いに助けあう」は調査開始以来(2010年以降)継続して1位を保っていますが、「遠慮をせずに意見を言い合える」は今回の調査で過去最高となる45.1%となりました。
それに対して、「アットホーム」といった選択肢は例年選択率が下降し、今回の調査では過去最低となる36.4%でした。以上の結果を踏まえると、現在の若手社員は、自分から企業のカラーに合わせる環境というよりは、「個性」が守られた中で、周囲と協働できる職場環境を求めていることが言えます。
また、同調査によると、”上司に期待すること”という調査項目においては、「相手の意見や考え方に耳を傾けること」(50.3%)がトップで、新入社員は、上司に対して、厳しい指導よりも、「個性」を尊重するコミュニケーションを求める傾向にあることがわかります。
【参考】株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「『新入社員意識調査2024』の分析結果を発表」
新入社員の傾向をキャッチアップし、それに合わせた育成方針を打ち立てていくことが重要です。
③内定者インターンを実施する
内定者インターンとは、新卒採用で内定を出した学生に対して行う内定者限定のインターンのことです。内定後から就職前に実施するもので、実際に働くことで学生に業務理解を促す役割があります。
内定者インターンを実施することによるメリットは以下の3つです。
▼内定者インターンを実施するメリット
- ミスマッチを防ぐことが可能
- 学生の適性を見抜くことができ、適性に沿った部署配置が検討できる
- 学生に基本的な業務を教えることで、即戦力の人材に
この内定者インターンの期間で基本的な業務やスキルを教えることができれば、新卒入社後すぐに即戦力としての活躍が期待できます。
例えば、株式会社じげんの内定者インターンでは、経営推進部として新卒採用に携わる経験などができるそうです。実践的な業務を通して理解を深められ、さらに成長意欲を高められたそうです。
【参考】株式会社じげん「≪じげんの内定者インターンVol.4≫タフな環境に身を置き、自分を鍛え上げる」
このように、内定者インターンを効果的に実施することで入社前から内定者の入社意欲・業務意欲を高めることが可能になります。
④研修プログラムを見直す
入社後の新人研修は今後の新入社員の成長に直結するもの。研修を見直し、適切な内容を実施することで新入社員の即戦力化も可能です。研修を見直すためには、研修プログラムで成果を出しているチームやメンターにヒアリングを行い、自社で求める人材に近づけるような研修内容に改善する必要があります。
■新人研修で教えるべきこと
入社後の新人研修では、ビジネスパーソンとして必要なスキル・マインドの取得を促すような教育を行いましょう。ビジネスパーソンとして必要なスキルは、具体的に以下の3つがあります。
▼ビジネスパーソンとして必要なスキル
- 報連相(報告・連絡・相談)
- PDCAサイクル
- タイムマネジメント
この3つは働くうえで欠かせないスキルです。入社直後の段階で身に付けてもらうことで、スムーズに業務を進めることが可能です。また、マインド面で新入社員に身に付けてほしいことは以下の3つです。
▼マインド面で新入社員に身に着けてほしいスキル
- 主体性
- 気遣い
- プロ意識
仕事は複数人が関わって進めることが多いため、主体性がないと良い方向に仕事を進められなかったり、気遣いが足りないと関係がギクシャクして円滑に進められなかったりする可能性もあります。新入社員だとしても1人の社会人として扱うこと、プロ意識をもって取り組んでほしいことを伝えることが大切です。
まとめ
新卒採用で即戦力を求めるのはありえないという時代は終わりつつあるようです。しかしその反面、しっかりと採用手順を考えないと対象学生の母数が少なくなって、会社の為になる採用ができず失敗してしまいます。
会社のビジョンを念頭に置いて、自社における”即戦力”の定義付けを行い、採用活動を進めましょう。
その際には、本記事を新卒採用におけるやることリストのように活用していただければ幸いです。




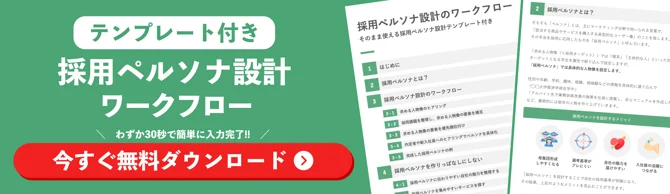
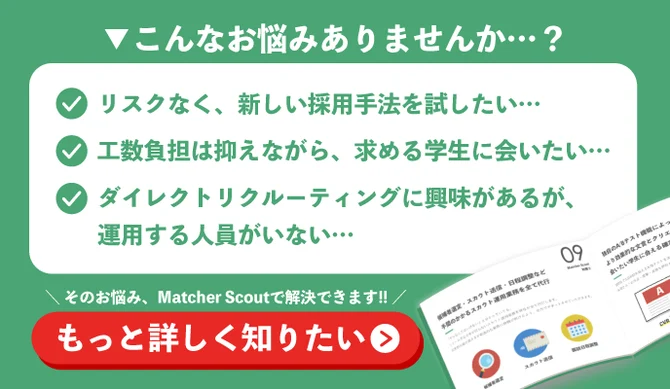
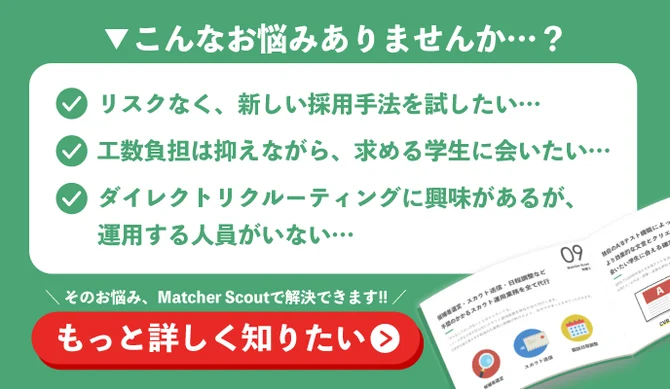




_Crop%20Image.jpg)