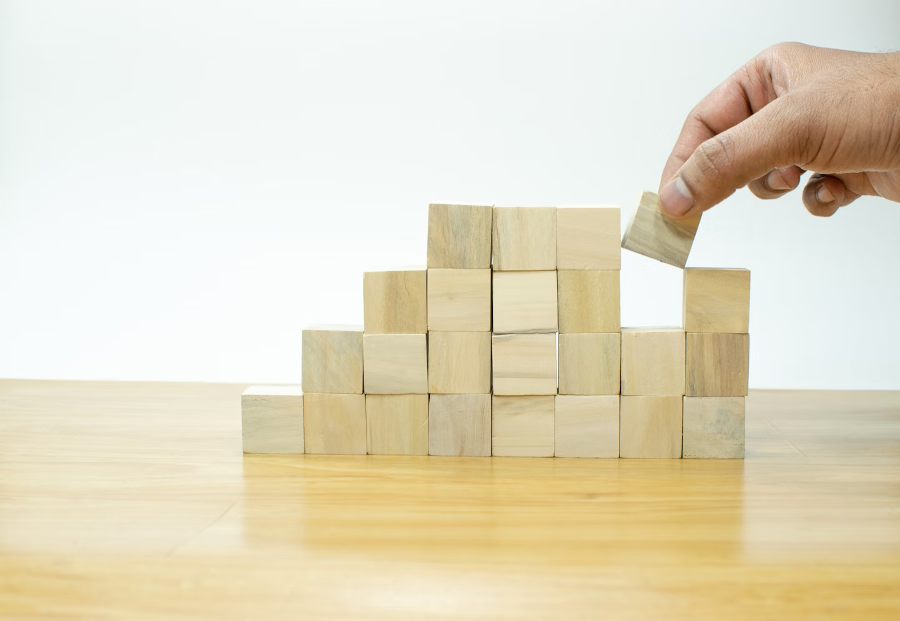新卒社員の離職率についてお悩みを抱えている採用担当者様は多いでしょう。
この記事では、そんな採用担当者様に向けて、新卒の1年以内・3年以内の離職率と、勤務年数別の退職理由について解説していきます。新卒社員がすぐに退職しなかった理由や、離職率を低下させる方法についても解説しています!
新卒の平均離職率と計算方法|1年以内・3年以内
離職率とは 、「ある時点で働いていた人のうち、一定期間後に退職した人の割合」のことをいいます。通常、事業年度を基準にして、期首から期末の1年間(4/1〜翌年3/31)で離職率を算出している企業が多いです。主に企業の働きやすさを示す指標として注目されています。
まずは、新卒の1年以内の平均離職率、3年以内の平均離職率について解説していきます。
新卒の1年以内の平均離職率
厚生労働省によると、令和6年3月に卒業した大学生の1年以内の平均離職率は10.1%でした。つまり、新卒で入社した学生の10人に1人は1年以内に退職しているということです。
前年の令和5年3月の大卒者の1年以内離職率は11.0%、令和4年3月の大卒者の1年以内離職率は12.1%ですので、ここ数年で離職率は下降傾向にあるといえるでしょう。
【参考】厚生労働省『新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況』
新卒の3年以内の平均離職率
また、令和4年3月に卒業した大学生の3年以内の平均離職率は33.8%で、前年より1.1ポイント減少しました。新卒の3年以内の平均離職率はここ数年30%代を保っており、大きな変化は見られません。新卒の3年以内離職率は3割で変動が少ないと考えて良いでしょう。
◎事業所規模別|大企業ほど新卒の3年以内の平均離職率は低い
続いて、事業所規模別の新卒3年以内の平均離職率について解説していきます。大手企業や中小企業など、事業所の規模によって離職率も大きく変化します。
▼事業所規模別の新卒の3年以内の平均離職率
| 事業所規模 | 5人未満 | 5~29人 | 30~99人 | 100~499人 | 500~999人 | 1,000人以上 |
| 離職率(前年との差) | 57.5%(-1.6%) | 52.0%(-0.7%) | 41.9%(-0.5%) | 33.9%(-1.3%) | 31.5%(-1.4%) | 27.0%(-1.2%) |
以上の表より、3年以内の平均離職率が最も高いのは事業所規模が5人未満の会社で、57.5%でした。平均離職率が最も低いのは1,000人以上の会社で、27.0%です。
事業所規模が大きくなるにつれて、平均離職率が低下していることがわかります。
◎産業別|宿泊業・飲食サービス業が新卒の3年以内の平均離職率が最も高い
ここでは、産業別の新卒の3年以内の平均離職率が高い5つの産業について解説します。新卒社員の離職率に悩んでいる採用担当者様は、自社が属している産業が平均離職率が高い5つに入っているのか確認してみてください。
▼産業別の新卒の3年以内の平均離職率
- 宿泊業、飲食サービス業:55.4%
- 生活関連サービス業、娯楽業:54.7%
- 教育、学習支援業:44.2%
- 医療、福祉:40.8%
- 小売業:40.4%
以上のように、宿泊業と飲食サービス業が最も平均離職率が高いという結果になりました。
平均離職率が高い上位5つの産業は、すべてサービス業をはじめとする第3次産業です。第3次産業は就業前後のミスマッチが起こりやすいということが分かります。
【参考】厚生労働省『新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します』
離職率の計算方法
離職率の計算方法について、法的に定められた絶対的なものはありませんが、ここでは厚生労働省が定めている離職率(常用労働者数に対する離職者数の割合)の計算方法を紹介します。
離職率 = 調査対象期間内の離職した人の数 ÷ 起算日の従業員数 × 100
例えば、従業員が200名いる会社(事業年度(4/1〜翌年3/31)の場合で考えてみましょう。この企業で事業年度内に30名退職すると仮定すると離職率は15%(30 ÷ 200 × 100 = 15)となります。
これは、必ずしも事業年度内である必要はなく、200名いる従業員のうち5年間で50人離職すると、5年間の離職率は25%(50 ÷200 × 100)となります。
※常用労働者・・・期間を定めずに雇われている、または1ヶ月以上の期間を定めて雇われている者のこと(正社員だけでなく、契約社員なども含む)
※離職者・・・一定期間内における退職者または解雇された者。
【参考】厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況ー主な用語の定義ー」
自社にマッチした人材を採用するならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「採用してもすぐに離職してしまう」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
【勤務年数別】新卒の退職理由
厚生労働省による、はじめて勤務した会社をやめた理由について聞いた調査によると、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」が28.5%と最も高く、「人間関係がよくなかった」が26.4%、「賃金の条件がよくなかった」が21.8%となりました。
▼はじめて勤務した会社をやめた理由の上位3つ
- 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった:28.5%
- 人間関係がよくなかった:26.4%
- 賃金の条件がよくなかった:21.8%
ここからは、同調査から、勤務年数別に新卒社員の退職理由について解説していきます。
【3か月以内】「人間関係がよくなかった」が半数越え
▼新卒社員が3か月以内に退職した理由
- 人間関係がよくなかった:52.3%
- 仕事が自分に合わない:42.1%
- 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった:40.8%
- 賃金の条件がよくなかった:22.4%
- 雇用期間の満了・雇止め:18.3%
新卒社員が3か月以内に退職した理由として最も多かったのは「人間関係がよくなかった」が52.3%でした。3か月以内に離職する新卒社員の半数は、人間関係が原因で離職していることが分かります。
【1年以内】「人間関係がよくなかった」4割
▼新卒社員が6か月~1年以内に退職した理由
- 人間関係がよくなかった:37.4%
- 仕事が自分に合わない:34.6%
- 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった:32.4%
- 賃金の条件がよくなかった:15.2%
- 雇用期間の満了・雇止め:15.2%
新卒社員が6か月~1年以内に退職した理由として最も多かったのは、3か月以内の離職と同様に「人間関係がよくなかった」で、37.4%でした。
離職理由の上位5つにばらつきがでてきたものの、3か月以内に離職する新卒社員と1年以内に離職する新卒社員で理由はあまり変わらないことがわかります。
【3年以内】「労働条件」「賃金」がそれぞれ3割
▼新卒社員が2年~3年以内に退職した理由
- 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった:30.3%
- 賃金の条件がよくなかった:30.0%
- 人間関係がよくなかった:23.1%
- 仕事が自分に合わない:18.8%
- 雇用期間の満了・雇止め:17.9%
新卒社員が2年~3年以内に退職した理由として最も多かったのは、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」で30.3%で、次に多いのは「賃金の条件がよくなかった」で30.0%でした。
1年以内の退職理由から変化して3年以内の退職理由は、人間関係や仕事内容のミスマッチから、労働条件や賃金のミスマッチが退職理由の中心となっています。
【5年以内】ライフステージの変化による退職理由が増加
▼新卒社員が3年~5年以内に退職した理由
- 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった:23.6%
- 賃金の条件がよくなかった:22.2%
- 人間関係がよくなかった:19.4%
- 結婚・子育てのため:18.1%
- 仕事が自分に合わない:17.8%
新卒社員が3年~5年以内に離職した理由として最も多かったのは、3年以内の退職理由と同様に「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」で23.6%でした。
3年以内の退職理由と5年以内の退職理由で大きくは変わりませんが、5年以内の退職理由では、「結婚・子育てのため」が18.1%と4番目に多い退職理由でした。5年近く働くと社員のライフステージも変化し、生活に合わせて退職を選ぶ社員も増えるようです。
【10年以内】役職や社内での立場の変化が退職理由にランクイン
▼新卒社員が5年~10年以内に退職した理由
- 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった:25.0%
- 結婚・子育てのため:23.6%
- 賃金の条件がよくなかった:23.3%
- ノルマや責任が重すぎた:21.1%
- 会社に将来性がない:18.9%
新卒社員が5年〜10年以内に離職した理由として最も多かったのは、「結婚・子育てのため」で23.6%でした。
10年以内の退職理由は5年以内の退職理由とは大きく変化し、結婚や子育てといった自身のライフステージの変化に伴った退職だけでなく、「ノルマや責任が重すぎた」や「会社に将来性がない」といった、役職や社内での立場が変化することで分かることを理由に退職を選ぶ社員が増加しました。
このように、勤務年数別に退職理由は大きく異なります。自社の社員が新卒入社後何年で退職していることが多いのかを把握し、退職理由をもとに改善していく必要があります。
新卒社員が3年以内に離職しなかった理由ランキング
今まで、新卒が早期離職した理由についてみてきました。では、今度は逆に、新卒で早期離職をしなかった理由は何でしょうか。離職をさせない条件を把握し、自社の離職率改善につなげていきましょう。
【参考】THE ADECCO GROUP「新卒入社後3年以内に離職しなかった若手社員を対象にした調査」
上の調査は、入社後4年目の新卒を対象に、「入社3年目で離職しなかった理由」を聞いたものです。
以下で上位5項目を見ていきます。
1位:有給が取りやすいから
早期離職しなかった理由の第1位は、有給の取りやすさでした。
実際、マイナビの調査によると新卒で行きたくない会社として「休日・休暇がとれない(少ない)会社」が22.2%で上位に入っていました。
▼学生が行きたくない会社
- ノルマのきつそうな会社:38.2%
- 大学・男女差別のありそうな会社:31.0%
- 暗い雰囲気の会社:24.1%
- 休日・休暇のとれない(少ない)会社:22.2%
休暇が取れない状況が続くと、ストレスがたまり、ワークライフバランスが実現しにくくなってしまいます。社内に、新人が休暇を取りづらいと感じさせる空気感がないかどうか確認してみましょう。
【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査』
2位:次の仕事が見つからなさそうだから
第2位に挙がったのは、転職先が見つからないためでした。しかし、人手不足で売り手市場が続く現在、以前に比べて転職がしやすくなっているのもまた事実です。
実際に、5年前と比べて転職就業者数(離職経験のある就業者数)は19万人も増加しています。自社よりも待遇がよく、働きやすい転職先が見つかれば離職してしまう可能性があるため、自社に不満を抱えている新人はいないかどうか常に目を配りましょう。
3位:同期や同僚との関係が良いから
第3位に挙がったのは、同期や同僚との関係の良さでした。給与や福利厚生といった、労働条件以外では、職場の人間関係を改善していくことが早期離職を踏みとどまらせるのに有効といえそうです。
株式会社マイナビが実施した調査によると、新入社員が仕事をする上で抱えている不安について、「上司とうまくやっていけるか」が44.2%で2位、「先輩・同僚とうまくやっていけるか」が38.4%で3位という結果になりました。
▼新入社員が仕事をする上で抱えている不安
- 仕事についていけるか:64.8%
- 上司とうまくやっていけるか:44.2%
- 先輩・同僚とうまくやっていけるか:38.4%
- 自分が成長できるか:30.1%
- 生活環境や習慣の変化に対応できるか:27.1%
新入社員が周囲と上手く馴染めているか、孤立していないかなどに気を配りつつ、人間関係に不安を抱いていないかヒアリングする機会を設けましょう。
【参考】株式会社マイナビ『「新入社員意識調査2025」の分析結果を発表』
4位:上司との関係が良いから
第4位に挙がったのは、上司との関係の良さでした。第3位の理由と同様に、やはり人間関係の良さが離職率低減には重要です。では、どのような上司が新入社員にとって理想なのでしょうか。
上記と同様の調査によると、上司に期待することのトップは「相手の意見や考え方に耳を傾けること」で49.7%で、続いて「一人ひとりに対して丁寧に指導すること」が47.9%という結果になりました。
▼上司に期待すること
- 相手の意見や考え方に耳を傾けること:49.7%
- 一人ひとりに対して丁寧に指導すること:47.9%
- 好き嫌いで判断しないこと:30.6%
- よいこと・よい仕事をほめること:30.5%
- 職場の人間関係に気を配ること:26.6%
仕事中には新入社員はもちろん、ほかの社員に気を配り、丁寧に接することが求められています。
5位:福利厚生・手当が充実しているから
第5位に挙がったのは、福利厚生・手当の充実でした。新入社員だけではなく、就活生のうちにも福利厚生への関心は広がっています。
実際、26卒を対象とした調査によると、就職先企業を選ぶ際に重視する点として、文系・理系ともに1位が「給与・待遇が良い」で、「福利厚生が充実している」も上位に入る結果となりました。
▼就職先企業を選ぶ際に重視する点
- 給与・待遇が良い:文系 48.0% / 理系 46.7%
- 将来性がある:文系 39.2% / 理系 42.0%
- 休日・休暇が多い:文系 34.2% / 理系 23.5%
- 福利厚生が充実している:文系 30.6% / 理系 31.8%
- 大企業である:文系 24.7% / 理系 30.7%
給与や休日、福利厚生といった、働き方や金銭面を重視している学生が多いことがわかります。
【参考】株式会社キャリタス『キャリタス就活 学生モニター2026 調査結果(2025 年 1 月発行)』
日本の平均離職率
ここからは、新卒・中途を合わせた日本全体の労働者の離職率について解説していきます。
厚生労働省の調査によると、2024年の日本全体の労働者の離職率は14.2%でした。2023年の離職率が15.4%だったため、1.2ポイント減少したことが分かります。
では、事業所規模別、産業別で見ると離職率はどの値になるのでしょうか。
事業所規模別|平均離職率
ここでは、事業所規模別の平均離職率について解説します。
▼事業所規模別の平均離職率
| 事業所規模 | 5~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300~999人 | 1,000人以上 |
| 離職率(前年との差) | 16.0% | 13.6% | 16.6% | 14.7% | 13.2% |
以上の表より、平均離職率が最も高いのは事業所規模が100人〜299人の会社で、16.6%でした。平均離職率が最も低いのは1,000人以上の会社で、13.2%です。
最も事業所規模が大きい1,000人以上が最も離職率が低いですが、全体の平均離職率は事業所規模であまり大きな変化はないといえるでしょう。
産業別|宿泊業・飲食サービス業が平均離職率が最も高い
ここでは、産業別に、平均離職率が高い5つの産業について解説します。
▼産業別の平均離職率の高い上位5つ
- 宿泊業、飲食サービス業:25.1%
- サービス業:20.3%
- 生活関連サービス業、娯楽業:19.0%
- 卸売業、小売業:15.1%
- 医療・福祉:13.8%
以上のように、産業別の平均離職率は「宿泊業、飲食サービス業」が最も高く、25.1%となりました。日本全体の平均離職率も、新卒の3年以内の平均離職率と同様に、サービス業をはじめとした第三次産業が離職率が高いことがわかります。
離職率が上昇することで生じる問題
離職率の上昇に伴ってさまざまな問題が発生します。特に、大きな影響として次の3つが挙げられます。
▼離職率の上昇に伴って生じる問題
- 人手不足による機会損失
- 採用・育成コストの発生
- 既存社員の負担増大
- 企業イメージが低下する
①人手不足による機会損失
企業の経営資源には「ヒト・モノ・カネ」の3つが重要で、この中で「ヒト」はモノ・カネを動かすことから最も重要であると考えられています。
離職者が増えることでモノ・カネの流れが悪くなり、本来得られた利益を逃す可能性が高いです。このように、離職率の上昇は企業の長期的な成長を阻害する要因となってしまいます。
②採用・育成コストの発生
離職率が上昇すれば、新たな人材を採用して育成する必要が生じるでしょう。採用方法・育成方法にもよりますが、1人の人材を採用して3ヶ月間育成する際に生じるおおよそのコストは一人当たり約188万円となります。
このように、上昇した離職者の穴を埋めるためには、多額のコストが生じることにも注意しましょう。
③在籍社員の負担増大
3つ目の問題が「社員1人にかかる負担が増えること」です。離職率が高いと、本来携わるはずだった人数よりも少ない人員で業務を行う必要があり、社員1人1人の負担が増加します。
そうなると、社員の業務に対する不満が高まり、離職が連鎖して起こる可能性もあります。
④企業イメージが低下する
企業の離職率が高い状態が続くと、「この会社は働きにくい環境なのではないか」という印象をもたれやすくなり、新卒学生からの印象が悪くなる可能性があります。離職率が高いことが、母集団形成の妨げになることも考えられます。
離職率の高さは単なる数字ではなく、新卒採用にもかかわる重要な指標です。企業として早めに改善へ向けて動くことが大切です。
離職率を下げて新卒を定着させるための5つの方法
従業員の離職率を抑えるにはどのような施策があるのでしょうか。ここでは、5つの対策方法について紹介します。
▼離職率を下げて新卒を定着させるための5つの方法
- 新入社員の研修体制を拡充する
- 自動化で生産性を上げ、労働時間を減らす
- 人員の配置を流動的に行えるようにする
- 給与・待遇を競合他社と変わらない水準まで引き上げる
- コミュニケーションしやすい環境を作る
①新入社員の研修体制を拡充する
まず1つ目が、社員の教育制度を拡充することです。特に新入社員の教育は手厚く行いましょう。座学だけでなく、自社が社会に与える影響・意義などを研修にて伝えることで、新入社員の会社に対する思いを強くすることができます。面接を突破した優秀な社員に長く働いてもらうためにも、新入社員の教育は手厚く行いましょう。
②自動化で生産性を上げ、労働時間を減らす
2つ目が「自動化で生産性を上げ、労働時間を減らすこと」です。DXという言葉に代表されるように「自動化」は、労働生産性を上げるために重要な要素となっています。今一度社内の業務を見返し「機械に代替できる業務はないか」を確認するようにしましょう。
③人員の配置を流動的に行えるようにする
3つ目が「人員の配置を流動的に行えるようにする」ことです。
具体的には、以下のことが行えます。
- 希望する部署を定期的にヒアリングし、空きがあれば希望部署に異動をしてもらう
- 上司と部下の関係性が悪い場合に、どちらかを他の部署/チームに移す仕組みを整える
「人間関係の悪化による退職」を減らすためにも、配置を流動的にできる仕組みを作ることは重要です。
④給与・待遇を競合他社と変わらない水準まで引き上げる
4つ目が「給与・待遇を競合他社と変わらない水準まで引き上げる」ことです。給与・待遇面の不満は競合他社との比較によって生じることが多いです。そのような事態を防ぐために、給与・待遇面はできるだけ競合他社と変わらない水準まで引き上げましょう。
⑤コミュニケーションしやすい環境をつくる
5つ目は「新人が周囲とコミュニケーションしやすい環境をつくる」ことです。ALLDIFFERENT社が新卒に対して実施した調査によると、入社後ぶつかると予想される壁の第1位は「仕事の難易度」でした。また、仕事の難易度の壁に対して会社側に求めるサポートとして、「先輩社員との人間関係を築く機会」との回答が最多でした。このことから、新卒社員は入社後自分が担当する仕事につまずいたときは、先輩からの積極的な支援・手助けを求めていることがわかります。
新人が業務を進める上で悩んだ際、先輩社員や上司に気軽に相談できる環境をつくることで、新人の不安を解消し、早期離職を防ぐことにつながります。コミュニケーションの行き違いから、無駄なすれ違いを生んでしまわないよう注意しましょう。
【参考】ALL DIFFERENT「【考察】内定辞退や早期離職を防ぐために企業が取り組めることとは」
離職率が低下した企業事例3選
続いては実際に「離職率が改善した企業」を、その方法とともに紹介していきます。「離職率を下げたいけど、具体的にどうやってやったら良いのか分からない・・・」という方は必見の内容です。
サイボウズ株式会社
サイボウズ株式会社は、離職率を28%から4%に減らすことに成功しました。このポイントとして「人事制度」を、社員みずから設計するようになったことが挙げられます。
人事担当者以外の社員が人事制度を変更し、自身にマッチした人事制度を選べるようになりました。結果として「在宅勤務制度」や成果や生産性を重視する「ウルトラワーク制度」など、さまざまな人事制度が作り出されました。
それにより社員の働きやすさも大きく向上しています。また「人事制度をみずから作成すること」により、社員1人1人の主体性が向上した、というメリットもあったとのことです。
【参考】離職率28%、採用難、売上低迷。ボロボロから挑んだサイボウズのハイブリッドワーク10年史
株式会社鳥貴族ホールディングス
株式会社鳥貴族は、さまざまな取り組みを通じて、離職率を低く抑えています。具体的には「店舗に配属されて間もない新卒の社員に、入社後1ヶ月程で本社の社員が直接話を聞きに行く」といった取り組みを行っています。
直属の上司にはいいづらい要望・不満を本社の社員が吸い上げることで、新入社員の労働環境が改善し、早期離職が減少しました。
また飲食業界の一般的なイメージとは異なり、無断での残業・休日出勤も禁止されています。加えて、休日を増やしたことで、完全週休2日に近い年間休日111日を実現しました。
働く社員に寄り添った仕組みづくりを複数行うことで、鳥貴族の離職率は低くなっています。
【参考】【定着率の裏に理念あり】離職率が業界平均を大きく下回る鳥貴族の秘密 | リクナビNEXTジャーナル
株式会社レオパレス21
株式会社レオパレス21は、新入社員の離職率を15%から9%弱まで改善することに成功しました。この数値は、業界平均以下です。
離職率を下げるために同社は以下の2つの対策を行いました。
- 研修制度の導入
- 評価制度の見直し
研修制度では、
- 管理職向けのコンテンツ
- 営業力を強化させるためのコンテンツ
- 組織マネジメント
などさまざまなものを実施しています。その結果、社員の能力向上だけでなく、会社に対するロイヤリティも向上しました。
また評価制度の見直しでは、時間の長さではなく、限られた時間で成果を出す社員を評価する制度に変更したことで、労働環境の改善を実現しました。
この研修・評価制度を行った結果、社員1人あたりの月間労働時間を約6時間短縮させ、34%だった有給取得率を70%にまで伸ばすことに成功しています。社員が働きやすい環境になったことが、レオパレス21の離職率低下につながったのです。
【参考】3年間で離職率が劇的に改善! レオパレス21はなぜ変われたか? | リクナビNEXTジャーナル
ミスマッチを防ぐ新卒採用を行うならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
まとめ
いかがでしたか?
この記事のポイントは以下の通りです。
- 新卒3年以内の平均離職率は約3割
- 特にサービス業や教育・医療・福祉業、従業員数の少ない企業は離職率が高い傾向にある
- 離職の理由は「待遇や労働時間などの労働条件」「業務内容やキャリア形成」「人間関係」
- 離職を下げるには研修体制や評価制度・待遇の見直しや、自動化による業務効率化などの工夫を行うのがおすすめ
「自社の離職率が高い・・・」とお悩みの方は、まず自社の離職率が平均より高いのか、離職が起きている原因はどこにあるのかを明確にして、対応策を練りましょう。




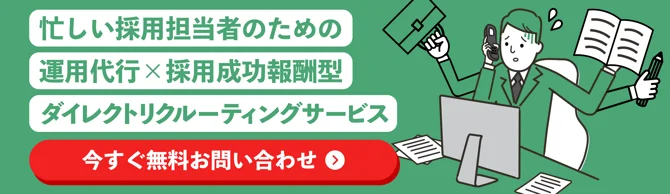
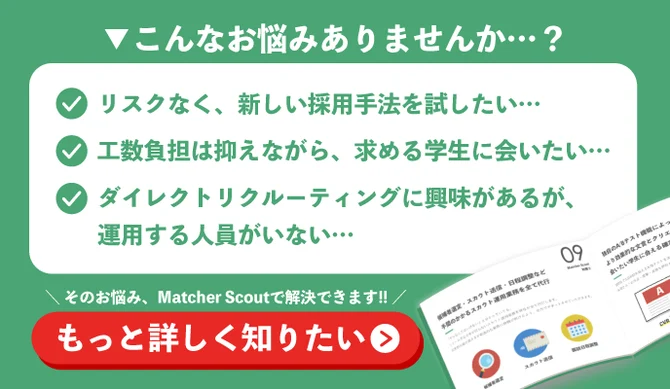
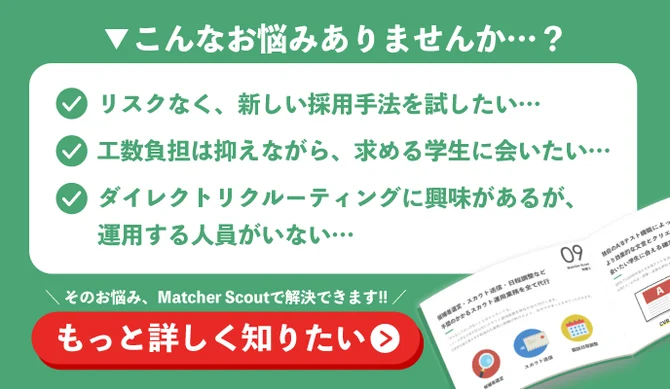




_Crop%20Image.jpg)