新卒採用において「適性検査を行うべきか」または「どの適性検査ツールを使用すべきか」について悩んだことのある採用担当者様も多いのではないでしょうか。
本記事では
- 適性検査ツールの比較ポイント
- 新卒採用で使える適性検査ツール26選徹底比較
- 新卒採用で適性検査を行う理由や実施の際に気を付けるべき点
これらの3つを中心に、適性検査ツールを比較していきます。
適性検査とは
適性検査とは、知的能力や性格の傾向などを把握するために実施するテストのことです。
新卒採用活動における適性検査では、自社で業務を遂行する上で必要となる最低限の知力やコミュニケーション能力、ストレス耐性などを持っているのかを調べるために行います。
書類選考や面接だけでは評価しにくいポイントを適性検査を行うことで数値化することで、候補者が自社に適した人材かどうかを見極めることが可能です。
実際、就職みらい研究所の調査によると、2025年卒採用で適性検査・筆記試験を実施した割合は86.9%でした。9割近くの企業が適性検査を採用活動に導入しており、適性検査の導入が一般化していることが分かります。
【参考】株式会社インディードリクルートパートナーズ『就職白書2025』
適性検査でわかること
適性検査では、学力や知識を測定する「能力適性検査」と、性格や特性を測定する「性格適性検査」の二つに分けることができます。それぞれの検査の特徴と、測定できる内容は以下の通りです。
❚ 能力適性検査の特徴
業務を行う上で必要な知識や思考力などを候補者が有しているのかを見極めるテストがあり、以下の2つの分野から問題が出題されることが多いです。
- 語彙力や読解力を測る言語分野
- 計算力や推論力を測る非言語分野
他にも場合によっては、英語や構造的把握力の問題が出されることもあります。学力や知識を測る適性検査を行う場合、合格の最低ラインを設定する企業が多いです。
高い知力を持った優秀な人材を見極めるためではなく、あくまでも業務遂行に必要な理解力などが候補者に備わっているのかを判断するために使用されています。
▼能力適性検査で測定できる力
| 測測定できる力 | 特徴 | 必要となる場面 |
| 言語理解力 | 説明を正しく読み取る力 | 文書作成業務やクライアントとのやり取り |
| 数的処理力 | 計算やデータ分析などの処理能力 | 経理・分析業務 |
| 情報処理力 | 情報を素早く理解・処理する力 | マルチタスクの業務 |
| 論理的思考力 | 筋道を立てて考える力 | 課題解決や企画立案業務 |
| 一般常識 | 社会人として必要な知識や常識 | 働くうえで必須 |
❚ 性格適性検査の特徴
候補者のパーソナリティやストレス耐性、価値観などを見極めるテストがあります。性格や特性を適性検査によって数値化することで、自社の環境にフィットする人材かどうかを評価することが可能です。
一方で、適性検査の結果のみで候補者の性格や特徴を断定することは難しいです。エントリーシートや面接の内容と照らし合わせながら、候補者について知るための一つの材料として使用することができます。
▼性格適性検査で測定できる力
| 測定できる力 | 特徴 |
| コミュニケーション能力 | 他者と円滑にやり取りができるか |
| 協調性 | チームで協力して働くことができるか |
| ストレス耐性 | プレッシャーのなかでも安定して働くことができるか |
| 積極性・主体性 | 自らチャレンジできるか |
| 責任感 | 最後までやり遂げようとする姿勢があるか |
| 慎重性 | 計画を立てて行動できるか |
| 組織適応力 | チームや社風に馴染めるか |
適性検査の活用方法
適性検査は新卒採用の選考時、様々な場面で活用することができます。
▼適性検査の活用方法
- 母集団形成:適性検査の検査結果をフィードバックすることを訴求する
- 1次選考時の足切り・スクリーニング:能力適性検査で最低ラインをつけて足切りをする
- 面接での参考資料:面接官による評価の偏りを防ぐ
- 内々定出しの判断材料:自社社員との特性や性格を比較して、総合的なマッチ度を判断する
- 配属参考資料:性格特性や志向を踏まえて、育成・配属に活用する
- 入社後のキャリア面談:面談時のフィードバック材料として活用する
適性検査の料金相場
適性検査の料金相場は、1回あたり数百円から7,000円程度と幅広いです。また、基本的な検査費用だけでなく、追加料金がかかる場合もあります。
▼追加でかかる可能性のある料金
- 初期費用
- システム使用料
- 試験用紙費用
- オプション費用
自社にとって必要なサービスが含まれているか、契約する際にしっかり確認することが必要です。
新卒における適性検査実施方法
適性検査を受検する形式や、テストの回答方式などはツールによって異なります。ここでは主な受検形式と回答方式をご紹介します。
受検形式
適性検査には主に「紙受検」「Web受検」「テストセンター受検」3つの受検形式があります。以下は各形式のメリットとデメリットを示した表です。
それぞれの受検形式の特徴について解説していきます。
◎紙受検
紙受検では、基本的にマークシートを用いながら適性検査を行います。候補者が面接会場など一つの場所に集まり受検するため、身代わり受検などの不正行為が起きにくいです。
一方で、場所と時間が制限されることで候補者の負担になること、監視することが会社側の負担になるデメリットもあります。採点についてはツールの提供元が行う場合と、自社で行う場合があります。
◎Web受検
Web受検では、候補者がそれぞれのパソコンを使用してWeb上で適性検査を行います。
どこからでも受検することができるため、時間と場所の拘束がなく、また結果集計をシステムに任せることができるため工数を削減できます。
一方で、受検時に監督する者がいないため、身代わり受検などの不正行為が起きやすいです。
◎テストセンター受検
テストセンター受検では、適性検査を提供する会社が会場を用意し、紙もしくはパソコンを使って適性検査を行います。
紙受検形式と異なり、結果の集計などを運用元の会社に任せることができるため業務工数の削減が可能ですが、その分費用も高くなることが多いです。学生は、テストセンターに出向いて受検する必要があるため、場所と時間が拘束されます。
回答方式
テストの回答方式としては「ノーマティブ方式」と「イプサティブ方式」の2つがあります。以下でそれぞれの方式について詳しくご紹介します。
◎ノーマティブ方式
一つの問題に対して「はい/いいえ」もしくは「3〜5段階中の最も当てはまる項目」で回答するのがノーマティブ方式です。
ノーマティブ方式には以下のような特徴があります。
- シンプルな回答方式のため受検者が答えやすい
- 回答を偽りやすい
◎イプサティブ方式
「以下の項目の中で自分に最も当てはまるものと当てはまらないものを選択してください」というように複数の質問項目に対して順位付けを行い、回答するのがイプサティブ方式です。
イプサティブ方式には以下のような特徴があります。
- 回答に本音が現れやすい
- 複雑な解答方式のため受験者が答えにくい
❚ 新卒採用で自社にマッチした人材を採用するならMatcher Scout
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
【ニーズ別】おすすめの適性検査のタイプと選び方
ここでは、採用担当者様のニーズ別におすすめの適性検査のタイプと選び方、そのタイプがおすすめの企業について解説していきます。
ここで紹介した適性検査は次の見出しの比較表などで詳しく紹介しますので、そちらも参考にしてみてください。
▼ニーズ別のおすすめの適性検査のタイプと選び方
- 実績のある適性検査を導入したい
- コストを抑えて適性検査を実施したい
- 学生の性格を重視して採用したい
- 学生の適性検査の事前対策を防ぎたい
- 診断結果の信頼性が高い適性検査を導入したい
- スピーディーに結果が欲しい
1.実績のある適性検査を導入したい
「実績のある適性検査を導入したい」と考えている採用担当者様におすすめなのは、定番の適性検査です。定番の適性検査は、以前から広く使われている実績があるため、安心してサービスを利用することができます。
▼定番の適性検査の利用がおすすめの企業
- 信頼性の高い適性検査を利用したい
- 人気の高い適性検査を利用したい
▼定番の適性検査5選
- SPI3|シェアナンバー1のサービス
- 玉手箱Ⅲ|「知的能力」と「パーソナリティ」の両面から測定
- CUBIC適性検査|ミスマッチを防げる適性検査
- tanθ|活躍人材の見極めやチームビルディングに
- GAB|新卒総合職採用に特化
2.採用単価を抑えたい
「採用単価を抑えたい」と考えている採用担当者様におすすめなのは、コストを抑えて診断できる適性検査です。適性検査のなかには、一人あたり0円〜800円と高いコストパフォーマンスを誇るものもあります。
適性検査は相場が幅広いため、必要なサービスと料金を比較して導入を検討しましょう。
▼コストを抑えた適性検査の利用がおすすめの企業
- 採用コストを抑えたい
- 別の採用フローにコストを割きたい
- コストパフォーマンスの高い適性検査を利用したい
▼コストを抑えた適性検査3選
- 不適性検査スカウター|1人あたり0円~800円の高いコストパフォーマンス
- ミキワメ|コストを抑えて社風とマッチした人材を見極められる
- TAPOC|「学習適性」と「就業適性」を測ることができる
3.学生の性格を重視して採用したい
「学生の性格を重視して採用したい」と考えている採用担当者様におすすめなのは、パーソナリティの理解に強みのある適性検査です。
パーソナリティ理解に強みのある適性検査には、独自の心理テストを実施していたり、AIを用いて自社社員と比較して結果を出したりと、独自の検査方法をとっている適性検査が多いです。特に理解したい性格や特性に沿った適性検査を選びましょう。
▼パーソナリティ理解に強みのある適性検査の利用がおすすめの企業
- 採用ミスマッチが多い
- 効率的に自社にマッチした学生を集めたい
- 採用人数に対する応募者数が多いため、適性検査で相性の良い応募者だけを残したい
- 自社の社員や部署との相性を重視したい
▼パーソナリティ理解に強みのある適性検査8選
- Compass|人事担当者の“本音”を反映した適性検査
- CIY|企業と受験者の比較によってミスマッチを防げる
- DPI/DIST|対人関係処理能力やストレス耐性が検査可能
- 内田クレぺリン|独自の心理テストで性格や行動特性を測る
- SCOA|「知」「情」「意」から多面的に受験者を評価
- V-CAT|ストレス環境下でも力を発揮できるか専門家が結果を分析
- アッテル診断|既存社員のデータ×AIで採用ミスマッチを防ぐ
- ミツカリ|詳細な性格と価値観の検査結果から社員・部署との相性を確認
4.学生の適性検査の事前対策を防ぎたい
「学生の適性検査の事前対策を防ぎたい」と考えている採用担当者様におすすめなのは、試験内容が特徴的な適性検査です。
例えば独自の検査を実施する適性検査や思考力を測る適性検査など、学生が事前に対策を取りにくい適性検査を導入するとよいでしょう。
▼試験内容が特徴的な適性検査の利用がおすすめの企業
- 検査対策をされることを防ぎたい
- 受験者の本当の性格を測定したい
- 様々な角度から受験者の本質を理解したい
- 学力だけでは図れない能力を測定したい
▼試験内容が特徴的な適性検査6選
- eF-1G|測定項目数が業界最多の194項目
- HCi-ab|基礎能力検査で3分野から出題
- コンピテンシー適性検査Another 8|コンピテンシー(成果を創出する能力)を測る
- GPS-Busines|問題解決に必要な3つの思考力を見極める
- TAL|独自の検査「図形アイコン配置式」から受験者本来の特性を抽出
- Talent Analytics(3Eテスト)|学力に依存しない知的能力を測ることが可能
5.診断結果の信頼性が高い適性検査を導入したい
「診断結果の信頼性の高い適性検査を導入したい」と考えている採用担当者様におすすめなのは、採用結果に定評のある適性検査です。
例えばAIによるデータ補正により、信頼性の高い調査結果を得られる適性検査や、診断結果を確認しやすいシートを提供している適性検査などがあります。
▼採点結果に定評のある適性検査の利用がおすすめの企業
- 偏りをなくした信頼性の高い結果が欲しい
- 視覚的に見やすいフィードシートが欲しい
▼採点結果に定評のある適性検査2選
- GROW360|AIのデータ補正による高い信頼性
- PETⅡ|受験者を多面的に判断したわかりやすいフィードバックシート
6.スピーディーに結果が欲しい
「スピーディーに結果が欲しい」と考えている採用担当者様におすすめなのは、短時間で検査・採点ができる適性検査です。応募者を素早く見極めたい場合におすすめです。15分で検査が完了する適性検査などがあります。
▼スピーディーに結果がわかる適性検査の利用がおすすめの企業
- 短時間で検査結果を知りたい
- 受験者への素早いフィードバックで歩留まりを改善したい
▼スピーディーに結果がわかる適性検査2選
- HCi-AS|10分で検査が完了・スピーディーなフィードバック
- TAP|スピーディーな採点
適性検査ツールを比較する時のポイント
26種類の適性検査ツールを紹介する前に、適性検査を選ぶ際にチェックしておきたい比較ポイントについて以下の3つを解説します。
- ツールの強み
- 費用
- その他サポートの有無
①ツールの強み
適性検査はそれぞれ、検査対象や検査方法、強みとしている領域が異なります。
例えば、学力・知識を測るツールの中でも、一般常識問題を中心とするものから、事務処理能力を図る事務適性など特定のジャンルの問題を中心とするものまで様々です。自社で必要な検査対象に強みのあるサービスを選びましょう。
②費用
適性検査ツールの利用にかかる費用や料金体系は、それぞれ異なります。また、1つのツールでも、選ぶサービスや追加オプションなどによって費用は変動します。自社にあった無理のない費用、料金体系を選ぶことがおすすめです。
例えば説明会で参加者全員に適性検査を受験させるなどの場合は、年間利用や月額制を選ぶなど利用方法や受験する人数に応じて選んでみてもいいかもしれません。
③その他サポートの有無
適性検査ツールの中には、検査だけでなく検査結果に関するアドバイスをくれるなど適性検査以外のサポートを付けてくれるサービスもあります。例えば、専門コンサルタントが付き検査結果の解説や、採用活動の支援を行ってくれるなどです。
「適性検査を最大限に活用した採用活動を行いたい」という企業は、どのようなサポートがあるか見ておいてもいいかもしれません。
【比較表】新卒採用におすすめの適性検査
ここからは、新卒採用におすすめの適性検査26種類を以下の6つに分類し、「強み」「費用」「サポートの有無」から比較していきます。
- 定番の適性検査
- コストを抑えた適性検査
- パーソナリティ―理解に強みのある適性検査
- 試験内容が特徴的な適性検査
- 採点結果に定評のある適性検査
- スピーディーに結果がわかる適性検査
それぞれの詳しい特徴についてはこの後記載していますので、気になった企業については合わせて参考にしてみてください。
【定番】新卒採用の適性検査5選を比較
ここからは定番の適性検査5つをご紹介していきます。
1.SPI3|シェアナンバー1のサービス
 SPI3は、年間13,500社、203万人が受験している、適性検査サービス導入社数No.1のサービスです。
SPI3は、年間13,500社、203万人が受験している、適性検査サービス導入社数No.1のサービスです。
面接の質問例や応募者と接するときの注意点まで記載されており、わかりやすく実践的な報告書を見ることができます。
また、採用適性検査で最も歴史があり、裏付けとなるデータが豊富です。
○テスト内容
- 性格検査 :環境や状況によって変わりにくい様々な行動のベースとなる性格特性を測定
- 基礎能力検査 : コミュニケーションや思考力、新しい知識・技術の習得などのベースとなる能力を測定
○所要時間
- WEB受験: 能力検査35分、性格検査30分 計65分
- 紙受験:能力検査70分、性格検査40分 計110分
○受検形式
Web受検・紙受検・テストセンター受検・インハウス受検(企業内で行うWeb受検)
○費用
初期費用は0円
大卒採用の場合:1人あたり 5,500円(税抜)
※料金はテストの種類・実施方法により異なる
【参考】SPI3 公式HP
2.玉手箱Ⅲ|「知的能力」と「パーソナリティ」の両面から測定
 玉手箱Ⅲは、「知的能力」と「パーソナリティ」の両面から測定する総合適性診断システムです。新卒採用で使われることが多い適性検査で、中途採用ではあまり使用されません。
玉手箱Ⅲは、「知的能力」と「パーソナリティ」の両面から測定する総合適性診断システムです。新卒採用で使われることが多い適性検査で、中途採用ではあまり使用されません。
IMAGES検査6尺度のフォーマット、もしくは、入社時に見ておくべき「ヴァイタリティ」「チームワーク」などの9特性のフォーマットで報告されます。
受験人数制限がないため、大手企業の新卒採用に向いています。
○テスト内容
- 知的能力 :計数、言語、英語
- パーソナリティ(OPQ検査)
○所要時間
約49分
○受検形式
Web受検
○費用
- 利用料 120万円/年、受検料 1,000円
- 利用料 250万円/年、受検料 500円
【参考】日本エス・エイチ・エル 公式HP
3.CUBIC適性検査|ミスマッチを防げる適性検査
 CUBIC適性検査は、ミスマッチを防ぐことに特化した適性検査です。「動機付けポイント」の分析によって面接で入社意欲を高めるポイントと質問例を知ることができます。
CUBIC適性検査は、ミスマッチを防ぐことに特化した適性検査です。「動機付けポイント」の分析によって面接で入社意欲を高めるポイントと質問例を知ることができます。
受験者を4つのタイプに分類し、コミュニケーションの取り方や相性の良い社員を把握することが可能です。それによって、離職予備軍を特定&フォローアップができます。
○テスト内容
- 個人特性分析:性格や興味、行動性など個人の特性を測定
- 能力検査:5科目32種類から科目、難易度、時間によって選択が可能
○所要時間
約20分
○受検形式
Web受検
○費用
基本料金 2,500円〜/人 3名まで無料受検可能
【参考】CUBIC適性検査 公式HP
4.tanθ|活躍人材の見極めやチームビルディングに
 tanθは、活躍人材の見極めやチームビルディングに活用が可能な適性検査です。結果は5つの思考タイプに分類され、直感的に受験者の特性を理解することが可能です。
tanθは、活躍人材の見極めやチームビルディングに活用が可能な適性検査です。結果は5つの思考タイプに分類され、直感的に受験者の特性を理解することが可能です。
適性検査は約15分で受検完了し、受検者の負担を軽減できます。また、A4・1枚ですべての情報が確認できる面接官用のシンプルなアウトプットになっています。
○テスト内容
- 適性検査 :性格・欲求・思考タイプ
- 能力検査:言語・非言語・英語
○所要時間
- 適性検査 約15分
- 能力検査3科目(言語・非言語・英語) 各15分
○受検形式
Web受検
○費用
要問い合わせ
【参考】tanθ 公式HP
5.GAB|新卒総合職採用に特化
 GABは、新卒総合職採用を目的に開発された適性検査です。英語での受験、個人結果報告書の出力に対応しています。入社時に確認しておきたい「バイタリティ」や「チームワーク」などの9特性、将来のマネジメント適性、「営業」「研究開発」などの7つの職務適性について予測することが可能です。
GABは、新卒総合職採用を目的に開発された適性検査です。英語での受験、個人結果報告書の出力に対応しています。入社時に確認しておきたい「バイタリティ」や「チームワーク」などの9特性、将来のマネジメント適性、「営業」「研究開発」などの7つの職務適性について予測することが可能です。
○テスト内容
知的能力:言語・計数
パーソナリティ:OPQ検査
○所要時間
WEBテスト 80分
マークシート 90分
○受検形式
Web
○費用
WEBテスト
- 年間利用料 1,200,000〜2,500,000円
- 受験料 500〜1,000円
マークシート
- 問題冊子 600円
- 採点処理 3,500円
【参考】日本エス・エイチ・エル 公式HP
【コストを抑える】新卒採用の適性検査3選を比較
ここからはコストを抑えた適性検査3つをご紹介していきます。
1.不適性検査スカウター|1人あたり0円~800円の高いコストパフォーマンス
 不適性検査スカウターは、業界唯一の不適正検査を提供している適性検査です。
不適性検査スカウターは、業界唯一の不適正検査を提供している適性検査です。
初期費用は0円と利用しやすい価格帯で、能力検査は無料になります。検査結果の納品の早さも特徴です。およそ8か国語の受検に対応しています。
○テスト内容
能力検査(基礎学力)
適性検査
- 潜在的な資質
- 問題行動やトラブルの原因になる性質
- 不満やストレス
○所要時間
能力検査30分
資質・精神分析・定着検査 10〜15分
○受検形式
Web検定・紙検定
○費用
能力検査 無料
資質検査 864円/名
精神分析 540円/名
定着検査 540円/名
【参考】不適性検査スカウター 公式HP
2.ミキワメ|コストを抑えて社風とマッチした人材を見極められる
 ミキワメは、無料で社員に受験してもらうことで自社の社風を分析し、採用基準を策定することが可能な適性検査です。候補者が活躍する可能性を「S~E」の14段階で表示し、結果が出ます。
ミキワメは、無料で社員に受験してもらうことで自社の社風を分析し、採用基準を策定することが可能な適性検査です。候補者が活躍する可能性を「S~E」の14段階で表示し、結果が出ます。
また、専属のコンサルタントが組織分析や採用基準の策定、面接での活用などを支援するサポートもあります。
○テスト内容
- 性格検査:性格やストレス耐性など
- 能力検査:言語・文章構成力など
○所要時間
- 性格検査10分
- 能力検査20分
○受検形式
Web受検
○費用
- 1人あたり500円
- システム利用料 3万円/月 ※社内受検し放題
【参考】ミキワメ 公式HP
3.TAPOC|「学習適性」と「就業適性」を測ることができる
 TAPOCは職種を遂行するうえで欠かせない事務処理能力を測定する適性検査です。
TAPOCは職種を遂行するうえで欠かせない事務処理能力を測定する適性検査です。
新卒から中途、教育など幅広い場面で使われています。実務をどれだけ早く正確に習得できるかという「学習適性」だけでなく、実務を能率的に継続できるかという「就業適性」も予測が可能です。およそ8か国語の受検に対応しています。
部数によって値段が異なり、部数が多いほど安価な値段で受験することが可能なため、大手企業に特に適した適性検査であると言えます。
○テスト内容
能力検査:言語知識・計算能力・記憶力・処理速度
○所要時間
40分
○受検形式
Web受験・マークシート受験
○費用
自社採点方式
- 1-50部 450円/部
- 51-100部 400円/部
- 101-200部 350円/部
- 201-500部 300円/部
- 501- 250円/部
Web採点方式、1000円/名
【参考】TAPOC 公式HP
【パーソナリティ理解に強み】新卒採用の適性検査8選を比較
つづいて、パーソナリティ理解に強みのある適性検査を8つをご紹介していきます。
1.Compass|人事担当者の“本音”を反映した適性検査
 Compassは、1,800社を超える企業の人事担当者の“本音”を評価項目に反映した適性検査です。求める人物像をパーソナリティ因子の配点に反映し、オリジナルの評価基準を設定できます。英語・中国語での受検にも対応しています。
Compassは、1,800社を超える企業の人事担当者の“本音”を評価項目に反映した適性検査です。求める人物像をパーソナリティ因子の配点に反映し、オリジナルの評価基準を設定できます。英語・中国語での受検にも対応しています。
○テスト内容
- 性格検査:ストレス耐性や対人コミュニケーション、抑うつ傾向などを検査
- 基礎能力(オプション)
○所要時間
約20分
○受検形式
Web受検、紙受検
○費用
- 適性検査 2,200円/人
- 基礎能力検査 1科目275円/人
※半額プランあり(年間利用100人超)
【参考】Compass 公式HP
2.CIY|企業と受験者の比較によってミスマッチを防げる
10名以下のチームで検査結果と業績の相関が0.792という高い精度を誇り、離職率が2.6倍改善されました。診断結果は「面接アドバイスシート」付きのほか、面接質問が追加料金なしで自動生成されます。
また、診断結果はリアルタイムで閲覧できるだけでなく、企業の診断結果と受験者の診断結果を簡単に比較することが可能なため、ミスマッチを防ぐことができます。
○テスト内容
能力や強み、性格などを検査 企業が必要とする特性と候補者の特性のマッチ度が分かる
○所要時間
約25分
○受検形式
WEBテスト
○費用
- 診断人数に応じた月額制(1名あたり¥0〜¥796)
- 初期費用不要
- 最初の3名+月1名は無料で適性検査を実施
【参考】CIY適性検査 公式HP
3.DPI/DIST|対人関係処理能力やストレス耐性が検査可能
 DPI/DISTは、態度能力(対人関係処理能力、意欲)やストレス耐性を診断できる適性検査です。多くの企業で働く人を調査したデータから標準化したため、精度が高いことが特徴です。
DPI/DISTは、態度能力(対人関係処理能力、意欲)やストレス耐性を診断できる適性検査です。多くの企業で働く人を調査したデータから標準化したため、精度が高いことが特徴です。
DPIとDISTは、Web総合診断サービスI-Datsと呼ばれるサービスのひとつで、職場適応性DPI、ストレス耐性DISTを両方受験することで、受験者の性格や能力についてより正確に判断することが可能になります。
また、基礎知的能力DBITを受験することでさらに診断の精度を高めることもできます。
○テスト内容
パーソナリティ(態度能力)、ストレス耐性の検査
○所要時間
60分
○受検形式
紙受験
○費用
- 標準プラン:3,850円/名
- 大量受験者向けプラン:2,750円/名 ※別途導入料で550,000円(税込)が必要
- 英語版・標準プラン:4,400円/名 ※受験は英語、管理画面は日本語
【参考】DPI・DIST 公式HP
4.内田クレぺリン|独自の心理テストで性格や行動特性を測る
 内田クレペリンは、簡単な一桁の足し算を行い、その結果から能力や性格、行動特性を測る心理検査です。企業だけでなく官公庁や学校の教育指導などでも利用されている検査で、独自の検査方法のため受験者のコントロールを防ぐことができます。
内田クレペリンは、簡単な一桁の足し算を行い、その結果から能力や性格、行動特性を測る心理検査です。企業だけでなく官公庁や学校の教育指導などでも利用されている検査で、独自の検査方法のため受験者のコントロールを防ぐことができます。
対策ができない検査のため、受験者の性格や能力を精度の高い検査で測ることが可能です。
○テスト内容
処理能力の程度、発動性、可変性
○所要時間
思考力:50分
○受検形式
Web受験・紙受験
○費用
個別診断的判定 2,420円
個別診断的判定(曲線類診断的判定のみ) 770円
数量的評価(PF判定)
- 名簿+集計一覧 18,249円(30名まで一律)※31名以上は1名につき608円
- 個票+集計一覧 31,449円(30名まで一律)※31名以上は1名につき1,048円
【参考】内田クレペリン 公式HP
5.SCOA|「知」「情」「意」から多面的に受験者を評価
 SCOAは、「知」「情」「意」の3つの視点から多面的に受験者を評価できる適性検査です。知的能力や気質、後天的な性格や意欲についても測定が可能です。
SCOAは、「知」「情」「意」の3つの視点から多面的に受験者を評価できる適性検査です。知的能力や気質、後天的な性格や意欲についても測定が可能です。
ストレス傾向や仕事、業務への取り組み方がわかるだけでなく、仕事への対処の「スピード」「確実性」を判断できます。
○テスト内容
基礎能力、パーソナリティ、事務能力
○所要時間
基礎能力テスト:60分
パーソナリティテスト:35分
事務能力テスト:50分
○受検形式
テストセンター受験・マークシート受験
○費用
1科目 2,000円/名
2科目 3,000円/名
3科目 5,000円/名
【参考】SCOA 公式HP
6.V-CAT|ストレス環境下でも力を発揮できるか専門家が結果を分析
 V-CATは60年以上にわたり、累計1500万人を超える臨床データをもとに専門家が独自解析する適性検査です。
V-CATは60年以上にわたり、累計1500万人を超える臨床データをもとに専門家が独自解析する適性検査です。
受検者の作為が反映されにくい検査で、受験者の性格や能力をより正確に知ることができます。また、採用選考の合否判定だけでなく、入社後の指導育成にも活用することができます。
○テスト内容
適性検査:「持ち味」と「メンタルヘルス」を把握する検査
○所要時間
約50分
○受検形式
紙受検
○費用
要問い合わせ ※無料トライアルが可能
【参考】V-CAT 公式HP
7.アッテル診断|既存社員のデータ×AIで採用ミスマッチを防ぐ
 アッテル診断は、既存社員のデータとAIを用いた適性検査です。データとAIを活用することで人材情報の定量化を実現しました。独自のAIで、3〜6倍の精度の入社後評価・早期退職を予測することができます。
アッテル診断は、既存社員のデータとAIを用いた適性検査です。データとAIを活用することで人材情報の定量化を実現しました。独自のAIで、3〜6倍の精度の入社後評価・早期退職を予測することができます。
また、ハイパフォーマー、ローパフォーマーの違いをワンクリックで確認することが可能です。
○テスト内容
性格検査:資質や価値観、ストレス耐性などを検査
○所要時間
約10〜15分
○受検形式
Web受検 インハウス受検(企業内で行うWeb受検)
○費用
スモールプラン・スタンダードプラン・コンサルティングプラン:要お問い合わせ
【参考】アッテル診断 公式HP
8.ミツカリ||詳細な性格と価値観の検査結果から社員・部署との相性を確認
 ミツカリは、採用だけでなく、配置、マネジメントにも活用できる適性検査です。
ミツカリは、採用だけでなく、配置、マネジメントにも活用できる適性検査です。
28種類の性格や価値観が7段階で可視化されます。個人の性格や部署との相性を、AIを用いた客観的な分析で確認することが可能です。
日本の外国人労働者の80%以上をカバーする8ヶ国語に対応しています。
○テスト内容
会社や部署ごとの社風を分析 候補者の性格や価値観を可視化
○所要時間
約10分
○受検形式
Web受検 ・インハウス受検
○費用
初期費用無料
月額料金 2,000円
受験者 2,000円/名 ※社員受験料は月額料金に含まれているため追加料金なし
【参考】ミツカリ 公式HP
【事前対策を防ぐ】新卒採用の適性検査6選を比較
つづいて、試験内容が特徴的な適性検査を6つをご紹介していきます。
1.eF-1G|測定項目数が業界最多の194項目
 eF-1Gは、測定項目数は業界最多の194項目の適性検査です。測定領域が広く診断精度が高いことも特徴です。導入実績500社以上にも及び、なかには内定辞退率2割低減の事例もあります。課題感や利用目的に応じてカスタマイズが可能です。
eF-1Gは、測定項目数は業界最多の194項目の適性検査です。測定領域が広く診断精度が高いことも特徴です。導入実績500社以上にも及び、なかには内定辞退率2割低減の事例もあります。課題感や利用目的に応じてカスタマイズが可能です。
○テスト内容
- 性格診断
- 能力テスト
○所要時間
- 性格診断 20~40分
- 能力テスト 最大 約30分
○受検形式
Web受検
○費用
企業アカウント利用料 年間基本料金:117,600円
受験料
- 性格診断+能力テスト 3,000円/件
- 性格診断のみ 2,000円/件
- 能力テストのみ 1,000円/件
【参考】eF-1G 公式HP
2.HCi-ab|基礎能力検査で3分野から出題
 HCi-abは、基礎能力検査として「言語」「数理」「時事社会」の3分野から出題している適性検査です。受験者一覧で成績上位からや上位何名を次選考へなど基準を設定しやすい点が特徴です。また、「常識度」と「思考度」の独自項目によって、柔軟な思考傾向の診断が可能です。
HCi-abは、基礎能力検査として「言語」「数理」「時事社会」の3分野から出題している適性検査です。受験者一覧で成績上位からや上位何名を次選考へなど基準を設定しやすい点が特徴です。また、「常識度」と「思考度」の独自項目によって、柔軟な思考傾向の診断が可能です。
○テスト内容
能力検査:言語・数理・時事分野を診断 ※言語分野は英語と国語の選択制
○所要時間
約45分
○受検形式
紙受検
○費用
最初の1名 2,000円 2名目以降 一律1,000円/名
【参考】HCi-ab 公式HP
3.コンピテンシー適性検査Another 8|コンピテンシー(成果を創出する能力)を測る
 コンピテンシー適性検査Another 8は、人材の持つコンピテンシー(成果を創出するための能力)を測定する適性検査です。大手企業を中心に2,000社以上の企業での導入実績があります。コンピテンシー面接で確認すべきポイントが示されたアウトプットにより、面接での客観的なヒアリングが可能です。
コンピテンシー適性検査Another 8は、人材の持つコンピテンシー(成果を創出するための能力)を測定する適性検査です。大手企業を中心に2,000社以上の企業での導入実績があります。コンピテンシー面接で確認すべきポイントが示されたアウトプットにより、面接での客観的なヒアリングが可能です。
ヒューマネージが提供する適性アセスメントツールは、新卒採用向け適性検査では業界シェア第3位でという実績もあり、信頼性が高い点も特徴です。
○テスト内容
コンピテンシーを定量的に測定
○所要時間
約15分
○受検形式
紙受検 Web受検 テストセンター受検
○費用
要問い合わせ
4.GPS-Busines|問題解決に必要な3つの思考力を見極める
 GPS-Businesは、「批判的思考力」「想像的思考力」「協働的思考力」の3つに分け、問題解決に必要な思考力を見極める適性検査です。
GPS-Businesは、「批判的思考力」「想像的思考力」「協働的思考力」の3つに分け、問題解決に必要な思考力を見極める適性検査です。
独自性の高い問題で能力をスコア化します。回答を偽りづらいパーソナリティ設問のため、事前対策を防いで受験者の性格や能力を正確に判断することができます。
また、結果を活用した候補者・内定者へのフォローアップができます。
○テスト内容
- 性格検査:思考力(「批判的思考力」「想像的思考力」「協働的思考力」の3つに細分化し出題)」
- パーソナリティ:レジリエンス・リーダーシップ・コラボレーション
- 基礎能力:言語処理・数理処理
○所要時間
- 思考力:45分
- パーソナリティ:10分
- 基礎能力:25分
○受検形式
Web検定
○費用
1人あたり4,500円
【参考】GPS-Busines 公式HP
5.TAL|独自の検査「図形アイコン配置式」から受験者本来の特性を抽出
 TALは、個性を多面的に測定できる適性検査です。36問の質問がされる検査と、図形アイコンを使った特徴的な検査の2種類を実施しています。対策がしにくい図形アイコン形式の検査より、受験者本来の特性を抽出できます。
TALは、個性を多面的に測定できる適性検査です。36問の質問がされる検査と、図形アイコンを使った特徴的な検査の2種類を実施しています。対策がしにくい図形アイコン形式の検査より、受験者本来の特性を抽出できます。
また、約20分という短時間での受験が可能なため、受験者側も利用しやすい検査です。
○テスト内容
性格検査:36問の質問検査・図形アイコン配置式
○所要時間
20分
○受検形式
紙
○費用
2800円/名
【参考】TAL 公式HP
6.Talent Analytics(3Eテスト)|学力に依存しない知的能力を測ることが可能
 3Eテストは、学力に依存しない知的能力が測れるため、優秀な人材を取りこぼさない点が特徴の適性検査です。
3Eテストは、学力に依存しない知的能力が測れるため、優秀な人材を取りこぼさない点が特徴の適性検査です。
試験時間が最大35分程と短く、初期費用も0円のため企業側だけでなく受検者の負担も少ない試験です。今の時代に求められる人材の発見、見極めができ、適材適所・キャリアプランの形成、目標設定など、入社後の活躍支援にも活用が可能になります。
○テスト内容
知的能力
性格検査:コミュニケーション力、ストレス耐性
○所要時間
約35分
○受検形式
Web検・ 紙検定
○費用
Web検定(日本語版):
- Webパックプラン 7万円〜/年(20件〜)
- Web従量プラン 基本料金 15,000円/月 採点料 3,200円/件
紙検定(日本語版) :マークシート 7万円〜/2年(20部〜)
【参考】Talent Analytics(3Eテスト) 公式HP
【信頼性の高い】新卒採用の適性検査2選を比較
つづいて、採点結果に定評のある適性検査2つをご紹介していきます。
1.GROW360|AIのデータ補正による高い信頼性
 GROW360は、360度評価に、AIを活用した評価補正を掛け合わせ、信頼性の高い他者評価を実現した適性検査です。
GROW360は、360度評価に、AIを活用した評価補正を掛け合わせ、信頼性の高い他者評価を実現した適性検査です。
IATと呼ばれる潜在的な傾向チェックにより、隠れたパーソナリティやバイアスを可視化することが可能です。すぐに活用可能な学生個人へのフィードバックレポートや面接官向けのシートも提供しています。
○テスト内容
性格検査:ハードスキル(職務遂行能力)・ソフトスキル(行動特性)・気質
○所要時間
- 候補者 ・気質診断:15~20分
- コンピテンシー自己評価:20分 評価者
- コンピテンシー他者評価:20分(1名あたり)
○受検形式
Web受検
○費用
- AIデータ管理料 10万円/年
- 受検料 4,000円/人(*1)
- 受検サポート費 10万円〜(*2) (*1) 人数によりディスカウントあり (*2) 受検人数および受検内容により変動
【参考】GROW360 公式HP
2.PETⅡ|受験者を多面的に判断したわかりやすいフィードバックシート
 PETⅡは受験者を多面的視点から判断できる適性検査です。テスト結果より15の人材タイプにカテゴリー分けをし、わかりやすいフィードバックシートにまとめて提供します。
PETⅡは受験者を多面的視点から判断できる適性検査です。テスト結果より15の人材タイプにカテゴリー分けをし、わかりやすいフィードバックシートにまとめて提供します。
速やかなフィードバックによって、マッチ度の高い人材へ早いアプローチが可能になります。
○テスト内容
性格検査:組織管理者適性診断、メンタル診断、組織文化適合度診断
○所要時間
約35分
○受検形式
Web検定 紙検定
○費用
各1,500円/名
【参考】PETⅡ 公式HP
【スピーディー】新卒採用の適性検査2選を比較
つづいてスピーディーに結果がわかる適性検査2つをご紹介していきます。
1.HCi-AS|10分で検査が完了・スピーディーなフィードバック
 HCi-ASはスピーディーな検査時間、フィードバックが特徴の適性検査です。ストレス耐性の詳細がわかり、注意が必要な場合は記述文で補足されます。8か国語対応で外国人の受験も可能です。
HCi-ASはスピーディーな検査時間、フィードバックが特徴の適性検査です。ストレス耐性の詳細がわかり、注意が必要な場合は記述文で補足されます。8か国語対応で外国人の受験も可能です。
○テスト内容
性格検査:目標追求力、対人力、主体性。メンタルヘルス
○所要時間
約10分
○受検形式
紙受検・Web受験
○費用
導入時に50,000円の基本料金が必要
1名〜30名まで 4,000円31名〜100名まで 3,500円
100名超 3,000円
【参考】HCi-AS 公式HP
2.TAP|スピーディーな採点
 TAPは、使い勝手のよさとスピーディーな採点が特徴の適性検査です。不調和傾向も測定が可能です。オプションが豊富なため、自社の欲しい機能だけを自由に選ぶことができます。
TAPは、使い勝手のよさとスピーディーな採点が特徴の適性検査です。不調和傾向も測定が可能です。オプションが豊富なため、自社の欲しい機能だけを自由に選ぶことができます。
○テスト内容
能力問題、性格検査
オプション内容
- 英語
- 事務適性
- 情報処理
- オリジナル(自社で問題作成)
○所要時間
総合タイプ(能力問題+性格検査) 60分
性格タイプ 15分
短縮タイプ(総合タイプの半分の時間で能力問題と性格検査の実施) 30分
○受検形式
マークシート
WEB
○費用
※ユーザー登録料(初年度のみ発生) 33,000円
Web受検版
- 総合タイプ・性格タイプ 1,320円/名
- オプション検査 660円/名
マークシート受検版
- 総合・性格・短縮タイプ 1,485円
- オプション検査 770円
採点月間利用料 11,000円
【参考】TAP 公式HP
新卒採用で適性検査を行う目的
新卒採用で適性検査を行う目的は以下の4つです。
▼新卒採用で適性検査を行う目的
- 候補者を客観的な視点で見極めるため
- 基礎学力や能力を把握するため
- 企業と学生のミスマッチを防ぐため
- 候補者を集客するため
候補者を客観的な視点で見極めるため
適性検査を行うことで、候補者の学力や性格などを数値として定量的に表すことができ、候補者の見極めに役立ちます。
数値として表れることで、候補者に対する主観的な印象を取り除いた状態で客観的に候補者を判断することが可能です。そのため、面接の前に足切りとして適性検査を利用する企業も多いです。
また、他の選考要素であるエントリーシートや、面接の結果と比較しながら候補者を評価することで、候補者が自社にマッチしているのかをより正確に判断することができます。
基礎学力や能力を把握するため
適性検査では、能力検査と性格検査の二つを実施するものが多いです。能力検査は、国語を中心とした言語分野と、数学を中心とした非言語分野の2種類を測定します。
性格検査だけでなく能力検査も実施することで、最低限の学力や仕事をするための能力が備わっているかを把握することができます。能力検査をすることで、以下のような能力が備わっているか判断することができます。
▼能力検査で判断できる能力
- 論理的に考えることができるか
- 効率的に物事を解決できるか
- 課題解決力があるか
企業と学生のミスマッチを防ぐため
適性検査で能力・性格ともに検査することで、企業とマッチしているかどうかを客観的に判断することができます。ミスマッチによる退職は、会社にとって大きな損失にも繋がるため避けておきたいですよね。
そこで適性検査を実施することで、面接だけでは判断できなかった適性まで把握することができます。
候補者を集客するため
就職活動を行う上で、避けて通れない適性検査に対する学生の関心度は高いです。そのため、集客時に「適性検査結果を元にフィードバック面談を行う」という訴求を行うことで、より多くの学生の獲得を狙えます。
以下は母集団形成時の集客にフィードバック付き適性検査を行う際の例です。
▼母集団形成時の集客にフィードバック付き適性検査を行う場合の例
◎会社説明会の場合
→午前中に適性検査を行い、会社説明会後にフィードバック面談を設ける
◎1週間短期インターンシップの場合
→初日に適性検査を行い、最終日に検査結果を含めた全体的なフィードバック面談を行う
◎座談会の場合
→適性検査で同じ性格傾向だった社員と会える座談会を行う
新卒採用における適性検査の注意点
ここでは新卒採用で適性検査を実施する前に知っておきたい気を付けるポイントについてご紹介します。
▼新卒採用における適性検査の注意点
- 検査結果は参考程度にとどめる
- 自社のニーズに合った適性検査ツールを利用する
- 集客の際は適性検査フィードバックに頼りすぎない
- 同じ業界の利用実績があるか確認する
検査結果は参考程度にとどめる
前述したように、適性検査は候補者を理解するための一つの指標として扱うようにしましょう。
人の能力や性格などは流動的なため、適性検査の結果は不確実性を伴います。適性検査の結果を信じるあまりに候補者を見極める姿勢が欠如してしまうと、自社が求める人材かどうかを見抜けない可能性があります。
適性検査の結果と面接時の印象を比較しながら、候補者が自社とマッチしているのかを確かめていくと良いです。
自社のニーズに合った適性検査ツールを利用する
適性検査はツールによって調べられる内容が異なります。特に候補者の見極めのために適性検査を利用する場合は、自社の採用要件を見られるような検査項目があるのかを事前に確認しておきましょう。
また、それぞれのツールに強みや特徴があります。料金体系や価格なども参考にしながら、自社のニーズに合った適性検査ツールを見つけましょう。
集客の際は適性検査フィードバックに頼りすぎない
従来よりも多くの学生の集客に成功したとしても、その中に自社とマッチする人材がいなければ意味がないですよね。
候補者を集客するために適性検査を利用する場合、「適性検査のフィードバックを行う」ことばかりに頼りながら学生を集めることは避けた方が良いです。
適性検査フィードバックでターゲティングできる学生層は広いため、業界や志望職種などを限定するなど工夫を行いましょう。
同じ業界の利用実績があるか確認する
適性検査ツールの利用実績に同じ業界、もしくは募集職種があるか確認しておくことをおすすめします。確認しておくことで、失敗のリスクを減らすことができるでしょう。
適性検査の中でも、IT業界の採用に優れているもの、事務職採用に優れているものがあります。
MatcherScoutはリスクなく自社に合う人材を採用できます
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
さいごに
いかがでしたか。
適性検査での定量的な評価と併せて、書類選考や面接を行うことで、より候補者について理解できるようになります。ミスマッチを防ぎ、入社後に活躍できる人材を採用するためにも、自社に合った適性検査を選びましょう。




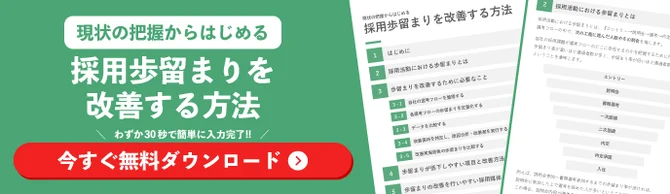


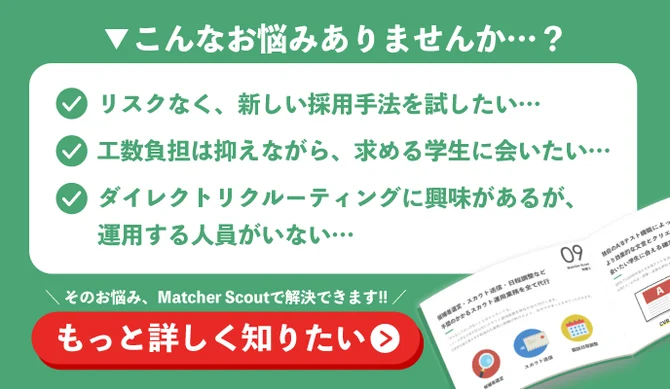



_Crop%20Image.jpg)

