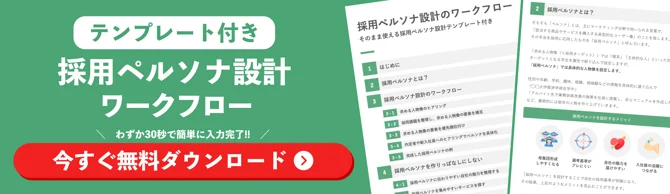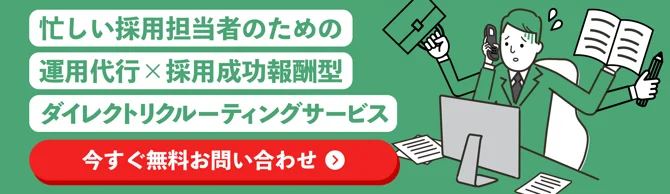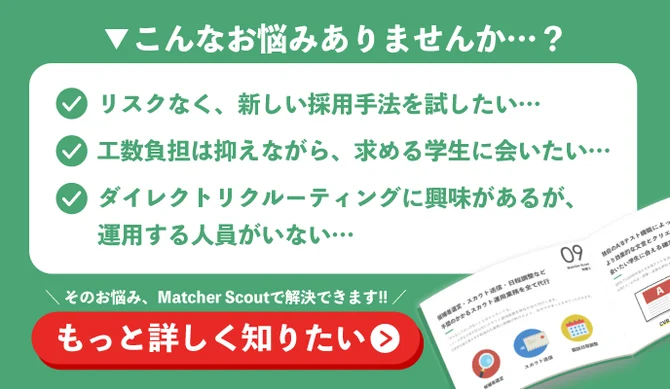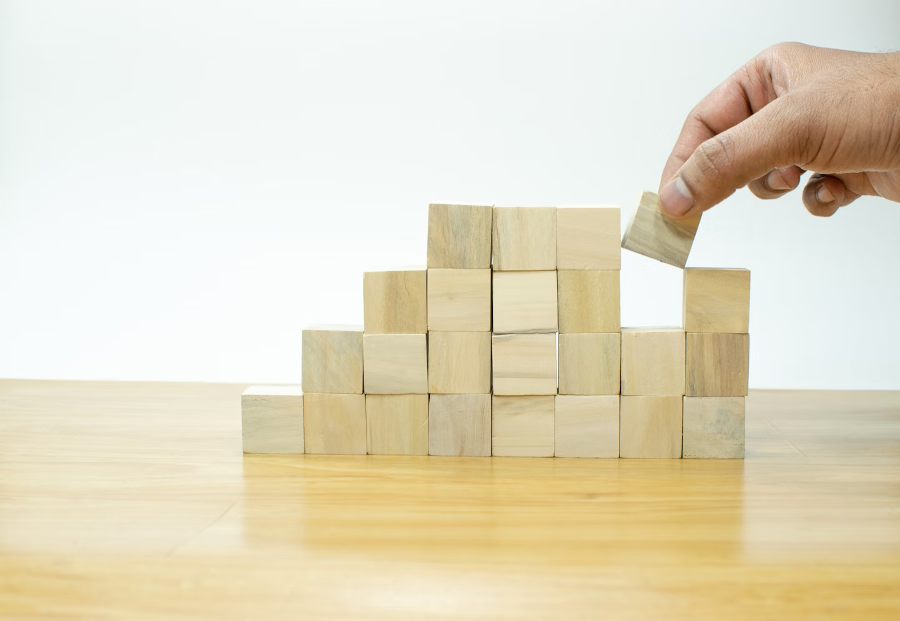採用市場は、企業による優秀な人材の獲得競争が激化していて、採用戦略に力を入れている企業も増えています。
しかし、採用は各企業それぞれ目標が異なるため、普遍的な成功状態がありません。
「選考フローに適性検査を取り入れたが、応募者と事業との親和性がわかりづらい」
「入社後どの部署に配属するかは、本人の希望を尊重したいから、部署の人員構成に偏りが出るのは仕方がない。」
このような悩みを抱える人事の方も多いのではないでしょうか。
本記事では人材ポートフォリオを取り入れるメリット、作り方からその活用方法まで丁寧に解説します。
人材ポートフォリオとは
人材ポートフォリオとは、経営戦略に基づいて配置された企業内の人的資源の構成内容をさし、様々な経験やスキルをもった社員を適切に配置し、効率的に業績向上を図ることを目指す人材マネジメント手法の1つです。
人材ポートフォリオは
- 人的な資源を可視化する
- 人材配置
- 採用計画
- 人材育成
- 評価
など、人事の要を担います。
具体的には社内のどのような部署・ポジションに、どのようなスキルや特徴を持った人材が何人いるのかが可視化されたものです。人材ポートフォリオを活用することで、採用をはじめとした人事戦略に役立てることができるでしょう。
人材ポートフォリオはなぜ必要か?
人材ポートフォリオの作成は、人や時間的コストがかかるタスクです。そのため「今は必要ない」、「作成する人員を割いている場合ではない」と優先順位を下げて考える人事担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、これからの企業経営では必ず必要になる分析です。その理由を下記にて紹介していきます。
▼人材ポートフォリオが必要な理由
- 人材版伊藤レポートへの注目
- 人的資本の情報開示が義務化
- 働き方の変化への対応
人材版伊藤レポートへの注目
「人材版伊藤レポート」とは、収益性を上げるための必要な組織体制について特化した報告書のことです。
そもそも「伊藤レポート」とは、2014年に伊藤邦雄一橋大学教授(当時)が座長とした経済産業省の報告書のことで、経済産業省が日本企業の収益性の停滞を危惧し、どうすれば改善できるか方向性を日本企業に示す目的で作成されました。
2022年5月に第二弾の「人材版伊藤レポート2.0」が公表され、その中で人材戦略に求められる要素として「動的人材ポートフォリオ、個人・組織の活性化」が挙げられています。ここから、変化の激しいこれからの時代において人材戦略を高度化する必要があり、そのために人材ポートフォリオの活用が必要不可欠だということができるでしょう。
人的資本の情報開示が義務化
世界的に人的情報開示を開示する動きが高まっていることも、人材ポートフォリオが必要とされるようになった理由の1つでしょう。
2018年に国際標準化機構(ISO)によって人的資本情報開示のガイドラインである『ISO30414』が出版されたことによって、米国で人的資本情報開示が義務化する流れが生まれました。情報の開示が義務化された際、人的資本を正しく把握するために、人材ポートフォリオが用いられるようになりました。
働き方の変化への対応
今の50-60代の方が就活生だった時代は、男性が主な働き手でした。会社のために時間と体力を費やして、どれだけ「会社」に貢献できるかが社会人の在り方だったと思います。
しかし現在は労働力人口の減少で、人材は売り手市場、さらに女性が働くことも一般的となり、多様な働き方・雇用形態が求められるようになりました。そのため、全ての人が働きやすい環境を整えること、柔軟な働き方を担保することが重要となってきています。また、少ない労力でこれまでと同じような成果をあげるためには、人材ポートフォリオを用いてそれぞれの人材を適切な場所に配置する必要があることがわかるでしょう。
労働市場が売り手なことから、転職を考える方も増加していて、労働人生を会社へ尽くすようないわゆる「終身雇用」の考え方も薄れてきています。これらのことから、企業が採用活動を行う際に「どのような人材」を求めているかを人材ポートフォリオを使って明確にしていく必要があるのです。
人材ポートフォリオのメリット5選
人、資金、時間を費やしてポートフォリオを作成するため、相応のメリットがないとやってられないと思う方もいらっしゃると思います。なぜ取り組む企業が一定数あるのか、自社が作成する目的確認のためにも参考にしてください。
▼人材ポートフォリオのメリット5選
- 適切な人材配置ができる
- 人材・人件費の過不足を把握できる
- 社員・事業のパフォーマンスが向上する
- 社員に合わせたキャリアパスを実現できる
- 人件費削減につながる
1.適切な人材配置ができる
社員それぞれのスキルや特徴を把握することができるので、それぞれの特徴を活かした部署やポジションに配置することができます。
社員それぞれが自分の強みを活かせる業務に携われることで、業務の生産性が上がるだけではなく、社員のモチベーションアップにも繋がり、業務内容のミスマッチによる早期退職なども防ぐことができるでしょう。
2.人材の過不足を把握できる
人材ポートフォリオの導入によって、現状の組織構成を可視化することができます。これによって、どの部署に人材が不足しているか、反対に配置しすぎているのかを理解することができます。これによって自社の人材に対しての課題を把握することができ、次に着手するべき行動が明確になるでしょう。
3.社員・事業のパフォーマンスが向上する
現状事業が問題なく遂行している部署・プロジェクトでも、配属された社員は「正直自分の興味や得意と合わない」と感じているかもしれません。配属の最適化は社員のパフォーマンスを向上させる効果が期待されます。
誰にでも得意な作業、苦手な分野はあります。同じ部署の全員が同じ得意不得意とも限りません。さらに、経験を積むごとに能力は変化していくので、現状を定期的に把握して常に配置をアップデートしていくことが理想的です。
地道で大変な取り組みですが、人材配置の最適化は、会社や事業の効率的な成長につなげるだけでなく、中長期的な人材育成に効果があります。
企業が長く事業を続けていくためにも、社員のスキルアップ、キャリアアップを考えていきましょう。
4.社員に合わせたキャリアパスを実現できる
目指すキャリア(選んでいく仕事、働き方)を実現するためには、キャリアに必要な経験を積むことが必要です。キャリア観の多様化によって、マネジメント力を身に着けたい人、専門性を高めたい人など、さまざまです。画一的なキャリアパスでは全ての社員にとって理想的なキャリアプランを描くことができないでしょう。
やりたい仕事だけ選べるほど会社の人事に余裕はないにしても、ある程度本人の能力に見合った配属をしていくことが、会社・社員両者にとって大切になります。
各社員が目指す目標、現状の得意不得意を正確に把握し、その社員に合ったキャリアパスを描くことが人材ポートフォリオで可能です。各社員が求めるキャリアを考慮して配属をすることで、社員が他社でも通用するほどキャリアアップしても、自社内で働き続ける方がメリットになるため、優秀な人材の社内定着にもつながります。
5.人件費削減につながる
人材ポートフォリオは人材の過不足を的確にマネジメントできます。
人材ポートフォリオの作成によって、自社に多くいる人材、足りない人材を把握でき、過不足しているプロジェクトや部署に対して、採用や配置など適切な対応をとることが可能です。また、無期雇用の社員と雇用期間が限られている派遣スタッフの役割を明確にすることで、人材を最大限に活用することができ、結果的に人件費削減にもつながります。
人材ポートフォリオの作成から活用までの流れ
いよいよ、人材ポートフォリオを作成していきます。
何から手を付ければいいか分からない方も、一旦こちらの作り方を参考にしていただいて、自社独自のポートフォリオを作成していってください。
▼人材ポートフォリオの作成から活用までの流れ
- STEP1:目的の設定
- STEP2:人材タイプの分類
- STEP3:社内人材のタイプ振り分け
- STEP4:タイプの偏りをみて、理想と現状のギャップを明確化
- STEP5:ギャップを埋めるうち手の考案
STEP1:目的の設定
会社の中長期な経営目標に沿って、人材ポートフォリオを作成して何を達成したいか、明確にしましょう。目的を決めることで、作成後、活用後に振り返りを行った際、その目的を達成できたか確認ができます。
達成の有無によって次回以降の採用活動をどのように行っていくか、再計画するのにもつかえるので、現時点での活用目的を立てることをオススメします。
STEP2:人材タイプの分類
ポートフォリオにおいて最も重要なポイントともいえるのが、人材タイプの分類です。
設定した目的をもとに、自社の現在から将来にかけて必要な人材のタイプを考えていきます。タイプの定義は、縦軸と横軸の四象限で示すことが一般的です。
◎分類方法の事例紹介
タイプの分け方は、さまざまな方法がありますが、ここでは具体例をご紹介します。自社の目標や、事業の特性にあわせて設定していきましょう。
仕事の性質を分ける一般的な方法として、「個人と組織」「創造と運用」で分けていく例を紹介します。
片方には業務を行う人数「個人(個人で行う)↔組織(組織・チームで行う)」
もう片方には業務のタイプ「創造(新規企画や商品設計)↔運用(運用中事業の管理・改善)」を設定すると、縦軸と横軸のタイプ掛け合わせにより、4つの分類ができます。
・組織✕運用 :オペレーション人材
日々上司から与えられた日常業務をこなして、会社の運営の一端を担っている人材です。
アルバイトや派遣社員を含めると、日本企業に最も多い人材です。アルバイトを想像していただくと分かり易いように、業務内容が決まっていて、教育制度も整っているので、人員補充も比較的容易でしょう。
・組織✕創造 :マネジメント人材
現状の自分や自分がいる組織の立ち位置を理解し、自分が何をすべきか自ら考え、提案や意思決定を行える人材です。将来の経営幹部候補と表現されることもあります。
慣用句に「鉄は熱いうちに打て」とありますが、マネジメント人材の育成は実は早いうちから行われる場合が多いです。
20代の間に子会社やプロジェクトのマネジメント経験を積ませて、実績を積んだ社員からより高いポジションを与えていくような制度を作成することで、マネジメント人材のさらなる強化が見込まれます。
・個人✕運用 :エキスパート人材
特定の分野の専門家として組織の運営に関わる人材です。
オペレーション人材が経験を積んで、特定の分野の専門性をもつことでエキスパート人材になることが多いでしょう。
1つの分野の業務をきわめてベテラン社員になった方が、特定のプロジェクトで、後輩育成や安定した組織運営に貢献する様子が分かり易いかと思います。
多くのオペレーション人材が経験を積んでエキスパート人材になることから、新卒採用を通して人材育成をすることで社内のエキスパート人材を増やしていく方法が一般的です。
・個人✕創造 :オフィサー人材
組織の改革、新規プロジェクトなど、新たな方向へ経営戦略を立てる際に、個人の創造性によって貢献する人材です。クリエイティブ人材とも表現されることがあります。
個人の能力次第で、与えられる環境、業務内容、処遇なども変わってくるので、一定水準以上の能力を発揮できる方は、特定の企業に属さず、業務委託という形で働くこともあるでしょう。
オフィサー人材は企業の即戦力でもあるので、中途採用で人員を獲得し、社内環境に刺激をあたえる存在となることが期待されます。
STEP3:社内人材のタイプ振り分け
分類方法が決定したら、内部の現状分析に移ります。
「職能、得意不得意」や「性格、部署の適性」は定性的で、判断する人が変わると評価も変わることがあり、分類が難しいです。そのため人間の感情や関係を取り除いて判断する方法が必要になります。
客観的かつ数値的に判断できるツールとして、適性検査による分類が一般的です。
適性検査のような客観的な分類は信頼性も高く、働き手の納得感も得られるので、新卒採用だけでなく、社内人材の分析にも適性検査を活用することをオススメします。
新卒採用で用いられることが多い適性検査ですが、各テストに特徴があり、自社の目的に沿った選び方が大切です。
一方で部署の適性は、個人の要因だけでなく、組織の雰囲気や人間関係も関わってきます。
どんなに適性のある業務だったとしても、関係の悪い人と一緒に働くと、その社員のパフォーマンスも下がってしまいます。
そこで活用されるのが360度評価制度というものです。360度評価というのは、複数の立場の異なる関係者が1人の従業員の判断を行う評価方法のことをいいます。一般的な評価方法は主に上司が判断しますが、360度評価は上司だけでなく同僚や部下も評価をする側に回るので、多面的に評価が可能です。
STEP4:タイプの偏りをみて、理想と現状のギャップを明確化
社内の現状把握ができたら、過不足の確認をします。
これから力を入れていくプロジェクトや、一旦縮小させていこうとする事業など序盤で整理した今後の経営戦略から、本来必要な人数構成を割り振って、懸念点があるか確認をしましょう。考えやすくするために理想的な人材ポートフォリオを作成してみると良いです。人員配分に偏りがある、特定の職種の高齢化、若手育成環境など普段何気なく意識されている問題が顕在化して見えると思います。
この時点で問題がはっきりわからなかったり、経営戦略に必要な人材が不明確な場合は、手順を振り返ったり、経営層と話し合いましょう。
焦って曖昧な決定をせず、時間がかかっても基盤を固めることが、最終的な採用活動の成功につながります。
STEP5:ギャップを埋めるうち手の考案
現状の人数構成で過不足があった場合、理想的な人材ポートフォリオへ近づけるために調整できる施策を考えます。具体的には、採用、育成、配置転換、解雇などです。
解雇
対応:会社の方針と社員の働く価値観が合わない、求めているパフォーマンスにとどいておらず、今後も改善の見込みがない場合に会社を辞めてもらう(早期退職の推奨、役職定年制度など)
解雇の場合は退職を促すことが一般的で、人事担当者が一方的に解雇させることは日本の法律では難しいです。さらに、一度の解雇が社員の会社に対する印象を変えてしまう場合があるので、慎重に行う必要があります。
採用
対応:外部から人材を補充する(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣契約採用等)
一度採用した社員は社員の意思が変わらない限り、定年退職までその会社で働くことができます。
だからこそ、採用のタイミングが非常に重要です。これから共に働く仲間を集める採用活動で、お互いに入社して(してくれて)よかったと思える人材になるように、採用する人を丁寧に見極めていきましょう。
育成
対応:現状から理想的な人材へ成長してもらうために社員を鍛える(研修、人事評価など)
育成や配置転換は、現状最適ではない人材を、最適に近づけるための手段です。
育成は主に新入社員に行う場合が多いですが、ジョブチェンジを社内で行う場合は、複数年勤務の社員にも該当します。社員のありたい姿、なりたい将来像と企業が必要とする人材像が重なるときに育成の効果が高いです。
配置転換
対応:各社員が最高のパフォーマンスを発揮できるように適した環境へ移動(部署移動、出向、転勤など)
「適材適所」という言葉がまさにその通りで、その社員にとって最適な環境へ配置することで、社員のパフォーマンスの効果を最大化する施策です。
育成よりも時間や費用的なコストが小さく、自分の将来像が不明瞭な社員に対しても部署を入れ替えることで社員のパフォーマンスに効果が得られます。人材が過剰なときは、解雇ではなく、配置転換によって調整していきましょう。
人材ポートフォリオの活用方法
▼人材ポートフォリオの活用方法
- パフォーマンスマネジメントを行う
- 動的な人材ポートフォリオとして活用する
- 社員の優劣をはかる道具ではない
- 中小企業だからこそ利用する
1.パフォーマンスマネジメントを行う
パフォーマンスマネジメントとは、社員の能力やモチベーションを引き出し、社員のパフォーマンスを高めるためのマネジメント手法です。ただ人材ポートフォリオによって人材戦略を打ち出し、配置転換や育成を行っただけでは、「なぜ移動になったのだろう」など、社員が不信感を感じてしまったり、能力を発揮しきれなかったりするおそれがあるでしょう。
また配置転換して終わり、ではなく、定期的に社員と面談やフィードバックを行う機会を設け、社員が配置転換後にしっかりと高いパフォーマンスを発揮してもらえるようにサポートしていくことで、中長期的に成果が期待できるでしょう。
2.動的な人材ポートフォリオとして運用する
動的ポートフォリオについて、「人材版伊藤レポート2.0」では以下のように述べられています。
「経営戦略の実現には、必要な人材の質と量を充足させ、中長期的に維持する
ことが必要となる。このためには、現時点の人材やスキルを前提とするのではなく、経営戦略の実現という将来的な目標からバックキャストする形で、必要となる人材の要
件を定義し、人材の採用・配置・育成を戦略的に進める必要がある。」
人材ポートフォリオはただつくるだけではなく、動的に、中長期的に維持していく必要があると述べられています。
中長期的に維持していくために、その時の経営戦略や取り巻く環境に合わせて、考え直し続けていく必要があるでしょう。
【出典】経済産業省「「人材版伊藤レポート2.0」を取りまとめました」
3.社員の優劣をはかる道具ではない
勘違いされがちですが、人材ポートフォリオは社内人材の評価に用いるものではありません。組織にいる様々な強み・弱みを持った人材の能力を最大限発揮することを目指して利用するべきものです。本来の目的以外で特定の社員への優遇や、ペナルティを課すことにつながると、社内の不安や不信感につながる可能性があるので、配慮しましょう。
4. 中小企業だからこそ利用する
大企業に比べて人数がそこまで多くない中小企業では、人事マネジメントは人事の裁量に任せている場合が少なくありません。
「これまで上手くいっていたから」、「現在人事業務に割く人材、時間の余裕がないから先送りに」など人事や役員のかたの解釈でないがしろにするのは危険です。仮に「優秀な人材」を新たに主要事業へ補充しようと考えるとき、何が優秀なのか考える必要があります。
「優秀」だけでも以下の3つのように様々な定義ができます。
- 人とのコミュニケーションが優れている
- 現状を客観的に分析してロジックを建てた課題の打開策を考えられる
- 実務経験(インターンなど)がある
また、他の企業も同様に優秀な人材を求めています。
有名大手企業、福利厚生の充実した大企業と比べると、資金、人的資源が少ない中小企業の場合は、人材獲得が不利です。だからこそ、ピンポイントで必要な人材を絞って採用していくことが中小企業には大切です。
人材ポートフォリオを作成・導入する時の注意点
人材ポートフォリオを設計・運用する時の注意点を3つ解説します。
▼人材ポートフォリオを作成・導入する時の注意点
- 時間、予算がかかることを考慮する
- 社員の優劣をはかる道具ではない
- 従業員の意思や要望も反映する(社員からの不満)
1.時間・コストがかかることを考慮する
人材ポートフォリオを作成・運用するためには、ある程度コストがかかります。人材ポートフォリオの設計に加えて、人材ポートフォリオを活用する際には、社員の理解も必要です。
運用するためには、人事が中心となって企業全体で時間をかけて取り組むのが基本です。
すぐに効果が出るとは限らず、時間と費用を確保した上で長期的に取り組まなければなりません。従業員への負荷や予算などのリソースを考慮した上で、人材ポートフォリオの作成に着手すると良いでしょう。
2.すべての雇用形態の社員を対象にする
ポートフォリオ分析を正社員のみに行うことは、あまりおすすめしません。企業経営に関わる人材全員を把握する必要があるので、派遣社員、パートアルバイトも含めて分析しましょう。
実際、オペレーション人材の多くはパートアルバイトの方々が担っています。ポートフォリオ作成に、時間がかかると記載したのは、このような大量の分析を行う場合があるためです。
3.従業員の意思や要望も反映する(社員からの不満)
社員の適材適所を考える際に、社員本人の意思も可能な限り考慮しましょう。
企業側の都合だけで作成してしまうと、その後社員が離職して新たに欠員が出てしまう可能性があります。社員個人のキャリアを理解して、その成長を後押しできるような姿勢を見せていくことで、優秀人材が社内に残って組織運営に携わってくれるでしょう。
【事例】人材ポートフォリオを取り入れている企業
ここまで、人材ポートフォリオの作り方や活用方法をご紹介しました。ここでは、実際に人材ポートフォリオを取り入れている企業の事例をご紹介します。
TIS株式会社
TISインテックグループでは、「人材」を最も重要な資本と捉え、ビジネス革新や市場創造に繋がる社員1人1人の新たな挑戦を支援するために積極的な人材投資を進めています。事業の成長を継続的に支える人材を確保するため、事業領域ごとに求められる経験やスキル要件、レベルごとの必要人数を可視化した人材ポートフォリオを策定し、計画的な人材の確保に取り組んでおり、人材ポートフォリオ計画に沿って、「人材開発」「人材配置」「人材獲得」の3つの戦略を連動させ、人材の拡充を進めています。
また、新たなビジネスモデルへの対応と複線的なキャリア支援を目的とし、「キャリアフレーム」を導入し、事業の中長期的な目標達成に必要な人材要件、そのレベルや人数をキャリアフレームを用いて定義し、現状とのギャップを把握したうえで拡充に向けた採用、育成、配置を推進しており、それを活用することで中長期のキャリアを描くことができるでしょう。
【参考】株式会社TIS『人材戦略』
東京海上グループ
 東京海上グループでは、「中期経営計画2023〜成長への変革と挑戦〜」において、長期ビジョンを達成すべく、「経営を支える基盤(人事戦略)」を掲げています。東京海上グループの人事戦略は「グループ一体経営を支える”人材”」と「グループ一体経営を支える”企業文化”」によって構成しており、「グループ一体経営を支える”人材”」を実現するために行うとされているのが戦略整合的な人材ポートフォリオの構築です。
東京海上グループでは、「中期経営計画2023〜成長への変革と挑戦〜」において、長期ビジョンを達成すべく、「経営を支える基盤(人事戦略)」を掲げています。東京海上グループの人事戦略は「グループ一体経営を支える”人材”」と「グループ一体経営を支える”企業文化”」によって構成しており、「グループ一体経営を支える”人材”」を実現するために行うとされているのが戦略整合的な人材ポートフォリオの構築です。
「戦略整合的な人材ポートフォリオの構築」に関しては「人材育成と再配置」や「人材採用」を行っており、具体的には入社年次・年齢によらない育成・配置や、重点分野への優先的な人材配置などを行っています。
【参考】東京海上ホールディングス株式会社『Human Capital Report2023』
必要な人材にスカウトを送れるMatcherScoutとは
「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
おわりに
あまりなじみのない言葉だった人材ポートフォリオについて、理解は進んだでしょうか。
何事も、やってみなければわからないと言うので、内容をみて必要かも!と思ったら行動に移すことが大事かもしれません。
ぜひ1度だけでなく、何度も読み返していただいて理解を深めながら、作成してみてください。