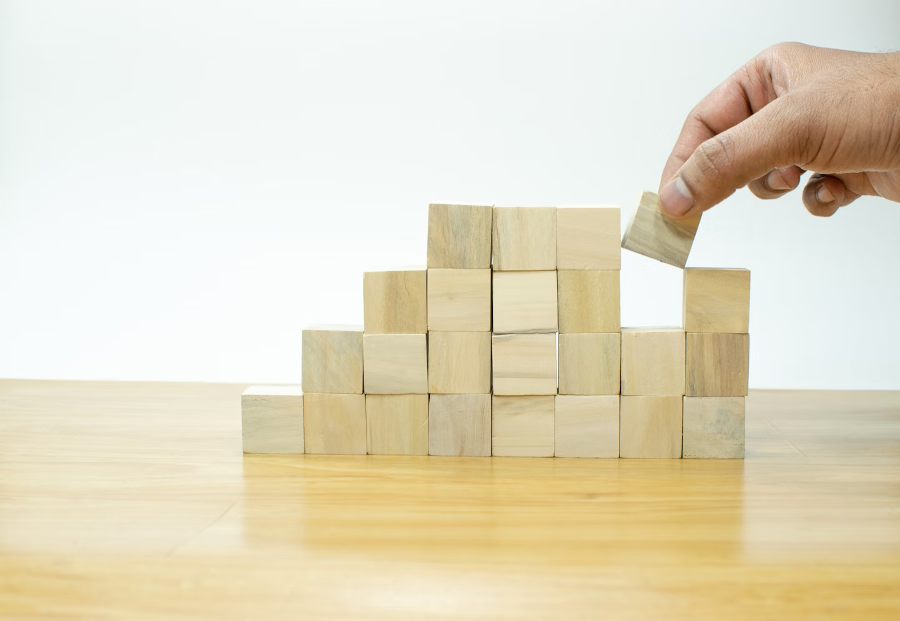自社が抱える採用課題を採用ブランディングで解決しよう、と思っている採用担当者の方もいらっしゃるかと思います。
しかし、採用ブランディングは長期的で継続した取り組みが必要になるため、成功方法や注意点を事前に知っておくことが必要です。本記事では、採用ブランディングとは何かというところから、企業の成功事例、方法について解説していきます。
採用ブランディングとは?
採用ブランディングとは、自社の理念に共感してもらいファンを獲得することで、自社をブランド化し、採用活動に役立てることです。
企業が持つ魅力や価値を整理し、採用説明会・インターンシップ・Webサイトなどあらゆる「場」で一貫したコンセプト・情報を発信することで、求職者の共感を得ます。
採用ブランディングをうまく活用することで、求職者の「ファン化」を促し、自社とマッチする人材を採用できる可能性が上がります。
採用ブランディングの実施の有無による採用担当者と人事部の選考負担は、以下の図のように変化します。採用ブランディングを実施した場合、エントリー時点で会社の理念に対して共感・理解した学生が応募するため、企業とマッチした人材が集まりやすいです。
そのため、採用ブランディングを実施することで採用担当者と人事部の選考負担を小さくした採用活動を行うことが可能です。
採用ブランディングと採用広報の違い
採用広報とは、自社の求める人材からエントリーをしてもらうために、学生に対して企業に関する情報を発信していくことです。採用広報が情報発信活動を指すのに対して、採用ブランディングは企業のイメージづくりやファン獲得のための活動を指します。
採用広報はあくまで応募につなげるための広報活動ですが、そこから一歩進んで企業のブランド化を行うのが採用ブランディングです。
採用ブランディングの目的
採用ブランディングの最大の目的は、自社の企業戦略にマッチした人材の採用です。採用ブランディングを通じて求める人材像を明確にすることで、採用のミスマッチを未然に防ぎ、長期的な人材の定着を図ります。
採用ブランディングが注目されている背景
ではなぜ近年、採用ブランディングが注目されているのでしょうか。
採用ブランディングが注目されている背景として、以下の3つがあげられます。
▼採用ブランディングが注目されている背景
- 自社とマッチする学生に会うのが難しくなっている
- デジタル化により、学生と出会う手段が増えている
- 口コミを重視する学生が多い
①自社とマッチする学生に会うのが難しくなっている
まず第一の理由としてあげられるのが、自社にマッチする学生に出会うのが難しくなっていることです。理由としては、「少子高齢化による学生数の減少」があげられます。
2026年卒を対象にしたワークス大卒求人倍率調査によると、大卒の有効求人倍率は1.66倍でした。これはつまり大卒就職希望者1人につき1.66件の求人があるということです。
前年の2025年卒の有効求人倍率1.75倍より0.09ポイント低下しましたが、依然として高い倍率となっています。
求人倍率が高いということは、優秀な人材の競争率が高くなり、自社の求める人材の採用が難しくなることが考えられます。
そこで、自社をブランド化して求職者に自社理解・応募を促す採用ブランディングは、自社にマッチした人材を惹きつけるために重要な手法なのです。
【参考】株式会社インディードリクルートパートナーズ『第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)』
自社にマッチした学生に会いやすい!Matcher Scoutとは?
求人倍率が高まる中で、自社にマッチした学生に効率よくアプローチしたい方におすすめなのが、新卒向けダイレクトリクルーティングサービスMatcher Scoutです。
OB訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社担当者がスカウトを代理送信します。
【Matcher Scoutの特徴】
- 運用に際する事務作業を代行する
- 独自のA/Bテスト機能で、会いたい学生に会える確率を向上できる
- 自社にマッチした優秀な学生にアプローチが可能
- 採用成功まで料金は一切かからないため、リスクなく導入できる
まずはお気軽に、お問い合わせまたは資料請求をお願いいたします。詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】運用負荷は一番少ない。「効率的」に「会いたい学生」に会えるツール
②デジタル化により、学生と出会う手段が増えている
採用ブランディングが必要となっている背景としてあげられる2つ目の理由が、学生と接触する方法が多様化していることです。
これまでの採用は、ナビ媒体を通じて行われることが代表的でした。しかしデジタル化が進んだ影響などもあり、近年ではさまざまな媒体が採用活動で用いられるようになってきています。
例えば、学生と出会う・やり取りをする手段としては下記のようなものがあげられます。
▼学生と出会い、やり取りをする手段
- オフライン、オンラインの合同説明会
- 大学が開催する企業説明会、就職セミナー
- 就活生が参加するオンラインコミュニティ
- 企業のリクルーティングサイト
- 就活特化型の口コミサイト
- X(Twitter)やInstagramなどのSNS
- OB、OG訪問 ・夏季、冬季インターンシップ
- ダイレクトリクルーティング等の逆求人サイト
- ナビ媒体
- 就活系NPO法人
上記のように、就活生と接点を持つ機会・媒体が増えています。複数の採用媒体を使って学生にアプローチするからこそ、自社の魅力を一貫した言葉で伝える採用ブランディングが重要なのです。
③口コミを重視する学生が多い
就活生の特徴として、口コミを重視する人が多いことも採用ブランディングが重要となっている理由としてあげられます。
実際、就職活動全体を通して最も活用した就活サイトは、文系では「マイナビ」が39%でトップ、2位が「ONE CAREER」で23%、3位が「就活会議」で15%でした。
理系では「ONE CAREER」が34%でトップ、「マイナビ」が2位で28%、3位が「就活会議」で17%という結果になりました。
▼文理別|就職活動全体を通して最も活用した就活サイト
| 文系 | 理系 | ||||
| 1位 | マイナビ | 39% | 1位 | ONE CAREER | 34% |
| 2位 | ONE CAREER | 23% | 2位 | マイナビ | 28% |
| 3位 | 就活会議 | 15% | 3位 | 就活会議 | 17% |
| 4位 | OpenWork | 7% | 4位 | OpenWork | 6% |
| 5位 | リクナビ | 4% | 5位 | LabBase | 5% |
【参考】HR総研・ポート株式会社『2026年新卒学生の就職活動動向調査(6月)』
この表のなかで、ONE CARRER、就活会議、OpenWorkは就活・企業口コミサイトです。就活・企業口コミサイトが上位にランクインしていることからも分かるように、就活生は口コミによって選考を受けるか決めることが多いです。
口コミを見て選考をやめたということにならないよう、採用ブランディングを通した企業のイメージづくりは非常に重要になっています。
採用ブランディングのメリット・デメリット
ここからは、採用ブランディングを実施するメリット・デメリットについて解説していきます。
採用ブランディングのメリット
続いて採用ブランディングのメリットを紹介します。
▼採用ブランディングのメリット
- 応募者数の増加が見込める
- 自社にフィットした学生を集めやすくなる
- 採用コストを抑制できる
- 入社後の社員教育がスムーズになる
- 既存社員のエンゲージメントが向上する
一つずつ見ていきましょう。
①応募者数の増加が見込める
採用ブランディングを成功させ、企業認知を上げることで、説明会・インターンシップの応募者数の増加が見込めるでしょう。
②自社にフィットした学生を集めやすくなる
採用ブランディングでは、自社の強みとその強みを伝えたい対象を明確にした上で情報発信を行います。そのため、自社の強みや今後伸ばしていきたい点を分析する過程で自社が採用したい人物像が明確になります。
その上で企業自らが発信したメッセージに共感する学生が集まりやすくなるため、自社にフィットした学生からの応募が増え、採用活動がスムーズになるでしょう。
自社にフィットした学生を採用することで、早期退職を防ぐことにもつながります。
③採用コストを抑制できる
自社のブランドを確立できれば、企業の理念やビジョンに共感するターゲットからの応募が増えやすくなります。内定辞退や早期退職のリスクが下がるため、採用にかかるコストを抑えられる点もメリットのひとつです。
④入社後の社員教育がスムーズになる
採用ブランディングを行うと採用の質が高くなり、企業理念や事業内容に深く共感・理解している意欲的な学生が入ってくる可能性が高くなります。
そのため、新入社員のモチベーションに左右されずに社員教育を行いやすくなるでしょう。
⑤既存社員のエンゲージメントが向上する
採用ブランディングには社員の協力が欠かせません。社員が自ら企業理念や事業を見直し、学生に発信したいメッセージやイメージをすり合わせます。
日々の業務で自社の魅力や強みを考える機会はなかなかないので、「自社にはこんな魅力があったのか!」と社員が再認識するきっかけになるでしょう。
採用ブランディングのデメリット
採用ブランディングを成功させるためには、いくつか注意しなければならない点もあります。
▼採用ブランディングのデメリット
- 採用ブランディングには、経営層や他部署の協力が必要
- 長期的に継続して行う必要がある
① 採用ブランディングには、経営層や他部署の協力が必要
今ある自社の強みや魅力を整理して伝えるのであれば、人事担当者だけでも可能でしょう。
しかし採用ブランディングは、企業理念の浸透や事業内容の競合他社との差別化等を通して、「この会社で働きたい」と思ってくれる人を1人でも多く増やすことが目的です。
これらのことを達成するには、経営層や他部署の協力を得て全社的に取り組むことが必要です。現場社員や経営層とのすり合わせを行うことで、適切なターゲットにアプローチができるためです。
企業全体で採用ブランディングに関する共通の認識を持つことで、一貫したブランドイメージの構築が可能になるでしょう。
② 長期的に継続して行う必要がある
採用ブランディングは一朝一夕で行えるものではありません。いいね数や閲覧数などを元に、常に学生のニーズを掴みながら発信することが求められます。
採用ブランディングは採用力を高める手段であるため、行う際には課題に対しての打ち手の必要性・緊急性を社内リソースや採用状況と検討する必要があります。
【課題別】採用ブランディングの成功事例8選
採用ブランディングによって課題を解決した企業事例を、課題別にご紹介します。事例と同じ悩みを抱えている採用担当者は、採用ブランディングの導入を検討してみてください。
▼課題別の採用ブランディングの成功事例6選
- 企業イメージと仕事の現実にギャップがある|日鉄鉱業株式会社
- 業界が不人気なイメージがある|株式会社エー・ピーホールディングス
- 業界内で埋もれてしまう|三幸製菓株式会社
- 自社の採用要件に合った学生が集まらない|株式会社一休
- 理系学生を採用したい|金属技研株式会社
- 就活市場からみた自社の印象がわからない|株式会社サイバーエージェント
- 業界に関心がない優秀な学生を採用したい|株式会社三井住友銀行
- 入社後のミスマッチを減らしたい|株式会社メルカリ
課題①企業イメージと仕事の現実にギャップがある|日鉄鉱業株式会社
日鉄鉱業株式会社では、本社は丸の内のおしゃれなビルである一方、高知県の鉱山で暮らす場合があるため、入口のイメージと仕事の現実にギャップがあることが課題でした。
施策:「山」をメインとした採用コンセプト
 そこで、日鉄鉱業で働くことは、山と暮らしていくことであるという印象を与えたかったため「大きな人になろう」という採用コンセプトに共感できる学生をターゲットとしました。
そこで、日鉄鉱業で働くことは、山と暮らしていくことであるという印象を与えたかったため「大きな人になろう」という採用コンセプトに共感できる学生をターゲットとしました。
「大きな人になろう」は、山と暮らすことが、大きな意味で懐の深い生き方であることから生まれたコンセプトです。パンフレットで山の写真を題材にしたり、入社後の成長を山登りに例えたキャリアステップを紹介することで、日鉄鉱業=山という印象付けに成功しました。
このように、働く環境をありのままに伝えられる採用コンセプトを設定することで、ミスマッチを減らした採用につなげることができました。
【参考】日鉄鉱業株式会社
課題②業界内で埋もれてしまう|三幸製菓株式会社
「雪の宿」に代表される米菓メーカー三幸製菓株式会社では、競合企業と知名度の差が約4倍近くありました。さらに採用にかけられる予算も低く、製菓業界内で埋もれてしまうことが課題でした。
施策:採用方式を時間と場所を変えて改善
従来にはない採用方式で話題性を高めたことで採用課題を改善しました。
具体的には、時間と場所を変える「出前全員面接会」や「カフェテリア採用」、採用内容そのものにインパクトがある「日本一短いES」や「35の質問」を取り入れることで、学生の注目を集めました。
「出前全員面接」とは、「5人集めてもらえたら全国どこでも行きます」をテーマとする面接方法です。あらかじめ会場の候補をいくつかあげ、5人以上の学生が選択した会場で面接を行います。
「カフェテリア採用」では、17のコースから自身にあった選考コースを選んで応募できます。中でも話題となったのが「日本一短いES」です。
他にも、適正を調べられる「35の質問」などを取り入れることで、意外な視点から学生を見ることでミスマッチも少なくなりました。実際の質問では、「おせんべい好き?」「新潟来れる?」などシンプルな質問を行うことで学生の本音を見ていきます。
このように、競合企業が行っていない採用方式を取ることで、学生からの注目を集めると同時に自社で活躍できる人材の発掘に繋がっています。
【参考】「新卒採用エントリーを300名から13,000名に増やした」地方のお菓子メーカーの採用戦略とは |HR NOTE
課題③自社の採用要件に合った学生が集まらない
株式会社一休では、応募は多数あるにもかかわらず自社にマッチする学生が少ないことが課題でした。同社が展開する一休.comは応募者からラグジュアリーなイメージを持たれており、ベンチャー企業である同社の実態との間にギャップが生まれていたのです。
施策:取材記事やイベントでカルチャーを伝える
経済メディアサイトNewsPicksで、20代の若手社員やCEOなどのインタビュー記事を掲載し、そのCEOと直接会えるワークショップを開催しました。
ワークショップを通じて同社の業務内容を実際に体験してもらい、CEOと直接話す機会を創出することで、参加者にカルチャーを伝えることに成功しました。
このように、イベントで実際にカルチャーを理解してもらう施策を取ったことで、自社にマッチした学生を採用することにつながっています。
【参考】「欲しい人材を獲得」を叶えた採用ブランディングの秘訣とは
課題④理系学生を採用したい
金属技研株式会社では、好奇心旺盛な物理・理工・化学科専攻の学生を採用したいという課題がありました。
施策:インパクトのあるパンフレット
好奇心旺盛な理系学生の興味をひくため、「難問をクリアせよ」という挑戦的なキャッチフレーズのパンフレットを作成しました。5〜10メートル先でも目につくようなデザインにし、理系学生を対象にした合同説明会にて、パンフレットを設置しました。
これまで企業が取り組んだ難題を就活生に問いかける仕様のパンフレットを作成したことで、学生が企業への関心を高めること、実際に働くイメージがつくような資料になっています。
【参考】採用ブランディング事例 採用パンフレット|会社案内 パンフレット専科
課題⑤業界イメージと実際の仕事にギャップがある|エイベックス株式会社
エイベックス株式会社は、業界イメージと実際の仕事にギャップがあり、ミスマッチに繋がりやすいという課題がありました。
施策:シンプルで分かりやすい採用メッセージの設定
そこで、多様な事業を行うエイベックス株式会社は、「モテる人・うごく人・つよい人」というシンプルな採用メッセージを打ち出しました。
「モテる人」は一緒に働きたいと思われるような求心力のある人、「うごく人」は自発的に動くことができる人、「つよい人」は芯をもって貫き通すつよさがある人です。
エンタメ業界は楽しそうというイメージを持たれやすいですが、実際の仕事では地道な作業も多く、ユーザーとして得ていた「楽しさ」と実際の仕事では乖離があります。そこで、3つ目の「つよい人」を掲げたことによって、楽しいだけでなく大変な仕事でもやり通すことができる人材を集めることができました。
このように、自社の求める人材の特徴を具体的に伝えることで、イメージとのギャップを解消し、ミスマッチを防ぐことに成功しました。
【参考】エイベックス株式会社
課題⑥就活市場からみた自社の印象がわからない|株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントでは、すでに選考を受けている学生からの意見だと偏りが生じると同時に、ファクトがなかったため就活市場から見た自社の印象が分からないという課題がありました。
施策:リサーチによる数値結果と具体的な声から採用コンセプトを考案
そこで、リサーチ会社に調査を依頼し、学生が自社に抱く印象や意見、競合他社への印象を踏まえた採用コンセプトを立案しました。
また、調査で得た結果をもとに内定者や選考中の学生へヒアリングも同時に行い、広報の一環である大規模イベントの開催につなげています。
調査結果やヒアリングをもとに採用コンセプトを変更したことで、その後のエントリー数が約2倍にまで増加しました。
このように、就活市場からどう見えているのか実際に調査を行い、客観的なデータを集めたことでより学生に刺さる採用コンセプトの作成に繋がり、エントリーを増やすことができました。
【参考】株式会社RECCOO『サイバーエージェントの新卒採用戦略に迫る|成功を支えるリサーチの重要性』
課題⑦業界に関心がない優秀な学生を採用したい|株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友銀行は、就職活動の早期化によって銀行業界を見る前に就活を終えてしまう優秀層と接点が持てないという課題がありました。
施策:採用活動を3か月早期化
そこで、2022年卒以降、採用活動の開始を大学3年6月から大学2年の3月に早めることにしました。3か月早期化することで、これまで銀行業界が採用活動を始めるまえに就活を終えていた優秀な学生層にアプローチすることを狙いとしています。
同時に、志望業界を絞り始める前にメガバンクへの偏見を払しょくすることも狙いとして掲げていました。
株式会社三井住友銀行は早期から「古いメガバンク」というイメージを払拭するために、夏インターンシップに力を入れます。
ターゲットを絞らずにさまざまな学生に向けたプログラムを設計した結果、夏インターンシップの総エントリー数は1万を超え、イメージの変容も促すことができました。
このように、採用活動の早期化によって早い段階で学生のイメージの変容を促すことができ、当初は銀行に関心のなかった学生も関心を持ってもらえるようになりました。
【参考】株式会社RECCOO『従来のメガバンクのイメージを払拭し、夏前に1万超のエントリー獲得』
課題⑧入社後のミスマッチを減らしたい|株式会社メルカリ
株式会社メルカリは、自社のプロダクトや企業自体が認知されるなかで発信する内容や文脈を自らコントロールできる媒体が欲しいという思いがあり、それによって採用におけるミスマッチを減らしたいと考えていました。
施策:自社のコンテンツプラットフォーム「メルカン」の立ち上げ
そこで株式会社メルカリは、自社のオウンドメディアであり、コンテンツプラットフォームと呼んでいる「メルカン」を立ち上げました。
メルカンでは社内インタビューなどを発信しており、実際に学生がさまざまな面からメルカリの理解が深まるという効果がありました。メルカンによって、学生は会社について十分に理解している状態で面接に臨めるため、共通の土台があるうえで話を進めることができています。
メルカンによって、採用や認知拡大だけでなく、社内のコミュニケーションなど、幅広い効果を生み出しました。
このように、自社のオウンドメディアの運営によって学生の自社への理解を増やし、入社後のミスマッチを減らすほか、入社後も自社に対してさらなる理解を促すことが可能となりました。
【参考】株式会社メルカリ『メルカリの「人への投資=People Branding」が生み出した想定外な反響』
◎採用ブランディングに成功する企業の特徴
以上の成功事例をもとに、採用ブランディングに成功する企業の特徴として以下が挙げられます。
▼採用ブランディングに成功する企業の特徴
- 自社についてありのままに伝える
- 入社後のイメージを持たせる
- 競合との差別化を図っている
- 伝え方を工夫している
1〜3は求職者と自社とのミスマッチを防ぎ、自社への関心を持ってもらうために重要です。自社の伝えたい特徴を明確にし、それをありのままに伝えることでミスマッチを防ぐことができます。
しかし、採用ブランディングを成功させるために最も重要なのは、「4.伝え方を工夫している」ことです。どれだけ魅力的な企業でも、伝え方を工夫していないと競合に埋もれてしまったり、ターゲットに適切に届かない場合があります。
そこで、次の見出し「採用ブランディングの5つの進め方」とその次の見出し「採用ブランディングを成功させるための「伝え方」」で、ターゲットに届く採用ブランディングのやり方を詳しく解説していきます。
採用ブランディングの方法・進め方
ここからは、採用ブランディングを実施する5つの方法について解説していきます。
手順①自社分析の実施
まずは自社分析を行います。自社分析の目的は、自社の理解をすることで就職活動中の学生へのアピールポイントを把握することです。
自社分析を行う際には以下の5つのポイントを押さえると良いでしょう。
▼自社分析の5つの項目
- 競合と比較して優位な点は何か
- 自社の今後のビジョンは何か
- 自社が抱えている課題は何か
- 社員(経営層・マネージャー・若手社員)のリアルな声は何か
- 自社に不足している人材はどんな特徴があるのか
❚ 競合と比較して優位な点は何か
まずは採用市場における自社の立ち位置を把握することが重要です。具体的には、競合と比較して以下の点を調べるとよいでしょう。
▼競合優位性を把握するために自社・競合で比較するべきこと
- 事業内容・技術力
- 働き方
- 成長機会
- 社風・雰囲気
以上の情報を、競合企業の採用サイトやOpenWorkなどのクチコミサイトをもとに集めていきましょう。
また、自社の分析を行う際は3C分析やSWOT分析などのフレームワークにそって行うこともおすすめです。
競合他社と比較したうえで、自社のアピールできる強みを理解することが大切です。
❚ 自社の今後のビジョンは何か
既に企業理念やミッションとして掲げている会社も多いと思いますが、自社が「これからどんなことを行っていきたいのか?」という想いを改めて言語化してみると良いでしょう。
具体的には、自社が出しているIR情報の確認や、ミッション・ビジョン・バリューの再確認を行いましょう。
❚ 自社が抱えている課題は何か
「現在解決したい課題」を明確にし、解決に向けてどんな取り組みをしているのかを整理しましょう。
例えば、採用面での課題として以下が挙げられることがあります。
▼採用で企業が抱えることが多い課題
- 母集団形成がうまくいかない
- 内定辞退が多い
- 早期離職が多い
実際に課題を見つけるためには、採用フローごとの人数や途中離脱の割合を計算して数値を分析すること、退職者や内定辞退者へのヒアリングを行いましょう。
❚ 社員(経営層・マネージャー・若手社員)のリアルな声は何か
様々な立場・役職の社員からリアルな声を聞き、自社を多角的に評価することでより深く理解することができます。
1人の人物にフォーカスして把握するのではなく、複数人インタビューすることでその企業の色が浮かび上がります。自社のあらゆる面を見ることで、企業についての社風や志向性の理解を深められるでしょう。
質問相手の社員の属性ごとにおすすめの質問を以下の画像にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
❚ 自社に不足している人材はどんな特徴があるのか
自社がどのような人材を求めているのかを知るためには、既存の人材を把握しておく必要があります。
自社の業務を以下の4象限にわけ、どのような人材が必要なのかを整理することができます。
▼自社の特徴を分析する4象限
- 「個人で実施する業務」or「組織の業務」
- 「ルーティーン(定型)」or「クリエイティブ(創造)」
4象限にわけて整理した情報をもとに、自社の人材を以下のように分類することができます。
▼人材分類例
- 組織×運用=オペレーション人材
- 個人×運用=専門職
- 組織×創造=経営幹部候補
- 個人×創造=経営参謀
自社の状況に合わせて人材を分類し、不足している人材を特定しましょう。
手順②採用コンセプトの設計
以上の自社分析を元に採用コンセプトを設計します。採用ペルソナ(求める人物像)を設定した上で、その人物に刺さるようなメッセージを検討しましょう。
詳しく解説していきます。
▮採用ペルソナの設定
企業の最終的な目標は自社が求める人材の獲得です。そのため「どんな人材を採用したいのか」を言語化しておく必要性があります。採用ペルソナを明確にし、全社的な共通認識を持っておくようにしましょう。
採用ペルソナの決定の際には以下の手順に沿って設定することをおすすめします。
▼採用ペルソナの立て方
- 採用する目的を明確にする
- 必要な人材要件を洗い出す
- 設定したペルソナを他部署とすり合わせてブラッシュアップを行う
- 採用市場に応じて、募集と選考を実施する
その他、採用ペルソナを設定する際の注意点はこちらの記事を参考にしてみてください。
【参考】【テンプレート付き】採用ペルソナの作り方とは?活用方法も解説
▮採用メッセージの検討
採用メッセージを決める際のポイントは「言葉にして伝えるべきこと」をきちんと把握することです。企業のことを知っている人であれば既に知っているようなことや、他社との差別化が難しいありきたりなメッセージにならないように注意してください。
<採用メッセージ例>
Eat Well, Live Well. (味の素株式会社)
より速く、よりシンプルに、もっと近くに。世の中の「不」を解消する(リクルートホールディングス)
やってみなはれ(サントリーホールディングス株式会社)
きみは、おもちゃが好きか?(タカラトミー株式会社)
採用メッセージや、よりコンパクトな採用キャッチコピーを考案したい場合は以下の記事を参考にしてみてください。
【参考】【事例15選】採用キャッチコピーの作り方|魅力的な言葉選びのコツ
手順③発信方法を選定する
採用コンセプトを作成したあとは、発信方法を選定します。発信媒体によって特徴が異なるため、自社の採用方法にマッチした発信媒体を選定することが重要です。
採用ブランディングを求職者に発信するための媒体として、例えば以下が挙げられます。
代表的なものとしては採用ホームページやSNSでの発信があげられますが、採用ブランディングに有効な手段はホームページやSNSだけではありません。
例えばインターンシップでは、自社の業務内容を理解してもらうために有効ですし、対面式のイベントでは自社のビジョンや理念を、熱量を持って伝えることが可能です。
その他にも業界特化型の説明会を開催することで、自社と他社の違いを分かりやすく伝えることができます。さらにグループディスカッションのイベントを開催することで、自社に興味がない学生にも接触もできるでしょう。
また最近では、文字だけでは伝わらない魅力を動画で伝える採用動画も主流になりつつあります。
手順④クリエイティブ制作
採用コミュニケーションの設計ができたら実際にクリエイティブを作りましょう。採用ブランディングにおいて、採用HPは長期的な運用が必要になるので、特に発信媒体の中でも必ず力を入れましょう。
クリエイティブ制作にあたって重要なのは、一貫性を持たせることです。採用サイトやSNSなど複数の媒体を利用する場合は特に、メッセージやデザインを統一しましょう。一貫性を持たせることで、企業への信頼感が生まれ、採用ブランディングの強化につながります。
発信するコンテンツ例として例えば以下が挙げられます。
▼発信するコンテンツ例
- 社員インタビュー
- 1日の仕事紹介
- 社員のキャリアパス
- カルチャー紹介
採用サイトなどで発信すべきコンテンツの詳しい内容については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
【参考】参考事例23選|採用サイトに必要なコンテンツとは?ポイントも解説
手順⑤仮説検証を繰り返す
採用ブランディングのための施策からどのような効果が生み出されているかを次回の採用ブランディング施策へ生かせるようにまとめておきましょう。施策の効果は「口コミ」「問い合わせ」「アンケート」などを通して、把握することができます。
採用市場は常に変化します。そのため、常にPDCAサイクルを心がけることで、採用市場やターゲットニーズにあった最適なブランディングへとブラッシュアップされていきます。
採用ブランディングを成功させるための「伝え方」
採用ブランディングにおいて重要なことは「伝えるべき情報」を見極めること、そして「情報の伝え方」です。
現代社会においてSNSが普及することで、より情報の幅が広がり、増えていることで、本来伝えたい相手にも伝えられていない可能性がとても高いです。
しかし企業の規模や知名度に関係なく、採用ブランディングによって採用活動を成功させている事例は、もちろんあります。
ここではまず、どのように採用ブランディングをすれば、情報が伝わるのかを解説していきます。
▼採用ブランディングを成功させるための「伝え方」
- 「伝えるべき情報」を慎重に選ぶ
- 「伝えるべき情報」の伝え方に気を付ける
- 信ぴょう性が高いメディアを利用する
- 原体験などを盛り込んでリアリティを高める
①「伝えるべき情報」を慎重に選ぶ
採用活動においての「伝えるべき情報」は、「理念、存在意義、独自性、ビジョン、志」など、その企業にしか語れない本質的なメッセージです。注意するべき点として「何をしているのか」より「何のために事業を行っているか」を伝えましょう。
「何のために事業を行っているのか」を明確にすることで他社との違いが明確にわかるからです。
▼株式会社Plan・Do・Seeの例
- 「何をしているのか」→ホテル/レストランの展開。ウエディングの提供
- 「何のために事業を行っているのか」→日本のおもてなしを世界中の人々へ
このように「何をしているのか」ではなく「何のために事業を行っているのか」を伝えるこ
とで、伝えられた人にもインパクトや良い印象を与えることができます。
②「伝えるべき情報」の伝え方
「伝えるべき情報」の伝え方として2つのポイントがあります。
▼「伝えるべき情報」の伝え方
- 信ぴょう性が高いメディアを利用する
- 原体験などを盛り込んでリアリティを高める
これらのポイントについて詳細を紹介します。
⑴信憑性の高いメディアを利用する
株式会社キャリタスの調査によると、就職活動に関する情報の入手先として、「就職情報サイト」が最も高く、次に各企業のホームページ(採用サイト)、大学内のガイダンス、キャリアセンターと続く結果となりました。
▼就職活動に関する情報の入手先
| 文系 | 理系 | ||||
| 1位 | 就職情報サイト | 91.0% | 1位 | 就職情報サイト | 85.4% |
| 2位 | 各企業のホームページ(採用サイト) | 64.7% | 2位 | 各企業のホームページ(採用サイト) | 67.3% |
| 3位 | 大学内のガイダンス、キャリアセンター | 41.0% | 3位 | 友人 | 36.6% |
| 4位 | 就職情報会社主催の就職イベント | 33.1% | 4位 | 大学内のガイダンス、キャリアセンター | 36.0% |
| 5位 | 友人 | 29.4% | 5位 | 就職情報会社主催の就職イベント | 31.5% |
【参考】株式会社キャリタス『1 月 1 日時点の就職意識調査』
⑵原体験などを盛り込んでリアリティを高める
情報が豊かであり増えているからこそ、原体験やリアリティを感じられるようなエピソードが重要視されます。
そのため、採用サイトやパンフレットには、現場社員の声を載せるなど、原体験のエピソードをしっかり盛り込むと良いでしょう。
同時に、オフラインのイベントもとても重要です。リアルであるからこそ熱量が伝わりやすく、求職者の信頼を獲得できるチャンスです。
採用ブランディングのコンサルティング会社3選
「採用ブランディングが重要なのは分かったけど、社内にノウハウがないので着手しづらい・・・」 とお悩みの方はいませんか。
ここではそんな悩みを抱えた方に対して、「採用ブランディングをお願いできるコンサルティング会社」を紹介します。
株式会社パラドックス
株式会社パラドックスは、企業の強みを生かした採用ブランディングを行い、その企業の価値観にマッチする求職者との出会い作りを創出する会社です。
クライアント企業の人事担当者はもちろん、現場社員や経営者、学生や顧客にもヒアリングを行った上で採用コンセプトを開発してくれます。
【参考】採用ブランディング | 株式会社パラドックス/PARADOX Corp
むすび株式会社
むすび株式会社が提供する採用ブランディングは「理念共感採用を実現する」ことをコンセプトとしています。
企業の価値観や理念を土台にコミュニケーション・コンセプトを設計し、求職者が採用フローを通して自社の”ファン”となるようなフローの実行を支援してくれます。
博報堂コンサルティング
株式会社博報堂コンサルティングの採用ブランディングは、独自のブランディングノウハウと生活者視点を活用し、採用市場におけるプレゼンスを強化します。
社員に対して入社前後のギャップをヒアリングしたり、求職者の就活意識や競合分析まで行ってくれることが特徴です。
【工数0で学生と接点が持てる】Matcher scoutとは?
採用活動を成功させるためには、採用ブランディングが重要であることを理解していただけたかと思います。
しかし、「そもそも採用ブランディングを行う工数をかけられない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方は多いのではないでしょうか。そんな方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました
おわりに
いかがでしたか?
今回は企業の採用力を高める『採用ブランディング』についてお伝えしました。就職活動を行う学生のニーズを的確に捉えて、長期的に継続して行うことで現在の自社が抱える採用課題を解決できるかもしれません。
ぜひ、現在の採用状況と課題を捉えながら導入を検討してみてください。




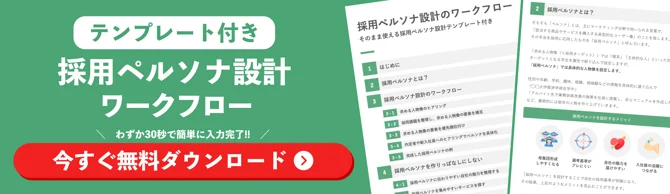

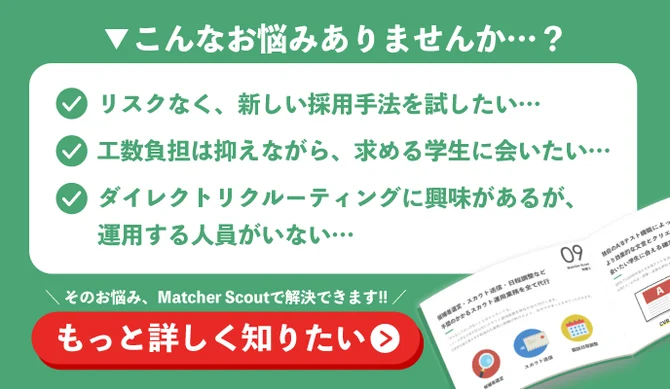




_Crop%20Image.jpg)