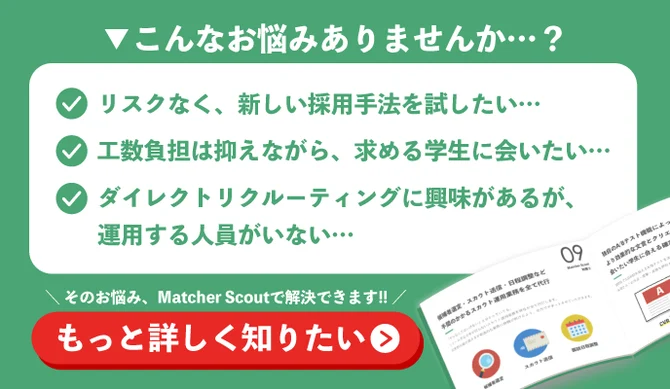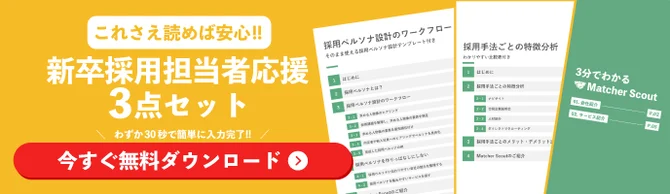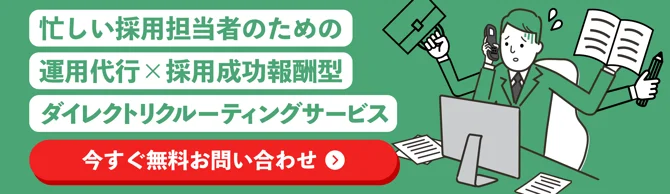そこで本記事では、オンライン研修を実施するメリット・デメリットから、実施方法まで徹底解説していきます。
オンラインでの採用活動に関連する情報は、下記の記事もご参照ください。
【参考】【106選】短時間/小・大人数でできるアイスブレイクネタ一覧|新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout
【参考】Web面接のメリット・デメリットは?対面実施とどっちが良いか解説|新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout
オンライン研修とは?
オンライン研修とは、Zoomなどのweb会議システムを活用し、PCを通して受講できる研修です。
現在、コロナ禍や働き方改革を経て研修のオンライン化が進んでいます。
株式会社マイナビが実施した調査によると、内定者研修の実施形態は以下のようになりました。
▼内定者研修の実施形態
- 集合研修(66.0%)
- オンライン研修(20.3%)
- 対面とWEBを用意し、学生が選択(2.1%)
- 遠方の学生のみオンライン研修(1.7%)
集合研修を導入している企業が多い一方で、5社に1社は、全面的・部分的にオンライン研修を導入していることがわかります。
さらにIT技術の発達により、今後オンライン研修が増加すると考えられます。
【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2026年卒 企業新卒内定状況調査』
Web研修との違い
Web研修は基本的にはオンライン研修と同義の意味で用いられ、ウェビナーやオンライン研修のことをさす場合が多いです。パソコンやタブレット、スマートフォンを用いてインターネット上で研修を行います。
集合研修との違い
集合研修とは複数の社員が集まり、対面で指導を受ける形式の研修のことです。
集合研修を実施することで、社員教育はもちろん、共同作業を通じたコミュニケーション・一体感の強化が期待できます。下図でオンライン研修と比べた際の強み・弱みをまとめましたので参考にしてください。
自社にマッチした人材を集めたいならMatcher Scout
「自社にマッチしている人材がなかなか集まらない」とお悩みの採用担当者の方はいませんか?そんな採用担当者の方におすすめしたいのがMatcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの企業にとって労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由により、自社にマッチした人材を確保することができ、採用活動を効率的に進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で解説しているので、ぜひご覧ください。
【導入事例】10名以上の入社数を安定的に獲得!質を落とさずに数を増やし、採用要件にマッチした学生にリーチできました|新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout
オンライン研修の種類
オンライン研修と一言にいっても様々な種類があります。ここではオンライン研修の主な種類について4つ紹介します。
▼オンライン研修の種類
- 双方向型・リアルタイム型(ライブ配信)
- アーカイブ型
- オンデマンド型(eラーニング)
- ハイブリット型(複合型)
①双方向型・リアルタイム型(ライブ配信)
双方向型・リアルタイム型は、講師による講義を生中継し、リアルタイムで行われる研修です。受講者は、時間が決まっているものの、直接会社や研修場所に足を運ばずに受けることができます。
Web会議システムの機能を活用して、グループワークやディスカッション、さらにリアルタイムでの質問ができることで双方向のコミュニケーションを円滑に取ることが可能です。
<特徴>
- グループワークができる
- チャット・発話により、その場で質問ができる
<向いている場合>
- グループワークが伴う研修内容を実施したい場合
- 受講者の理解度をリアルタイムで確認したい場合
②アーカイブ型
アーカイブ型は、ライブ配信で行われた研修内容を録画・保存し、後日視聴者が好きなタイミングでアーカイブを見られるようにする研修です。
やむを得ない事情でライブ配信に参加できない受講者がいたとしても、アーカイブを残しておくことによって、研修においていかれないような環境をつくることができます。
<特徴>
- 時間に縛られずに済む
- やむを得ない事情により、ライブ配信に参加できなかった受講者への配慮が可能
<向いている場合>
- 双方向型・リアルタイム型の研修のみ実施している場合
- 任意参加の研修がある場合
③オンデマンド型(eラーニング)
オンデマンド型は事前に録画した動画や配信されている教材を活用して個人的に受講できる研修です。先ほどのアーカイブ型はライブ配信した研修をそのまま配信することに対して、オンデマンド型は研修動画や資料を複数用意し、事前に編集しておいたものが多いです。
株式会社キャリタスの調査によると、内定後の課題や研修の形態として学生が希望していたものは以下の通りでした。
▼学生が希望している内定後の課題や研修の形態
- eラーニング:54.8%
- オンラインでの集合研修(Zoomなど):31.7%
- 対面での集合研修:30.2%
上記のことから、オンデマンド配信(eラーニング)は多くの学生のニーズに応えるために導入してみるのも良いかもしれません。
<特徴>
- 均一な教育を担保できる
- 学習の進捗状況が管理できる
<向いている場合>
- インプットが中心の研修の場合
- 研修内容の専門性が高く、繰り返し学習する必要がある場合
【参考】株式会社キャリタス『調査データで⾒る「入社に向けた内定者フォロー」-2025年卒調査-』
④ハイブリット型(複合型)
ハイブリット型はこれまで紹介したライブ型やアーカイブ型、オンデマンド型を組み合わせて実施される研修です。これに加えて、集合研修も実施することで対面とオンラインの双方のメリットを活かすことができます。
<特徴>
- 学習の定着度や理解度に合わせて柔軟なカリキュラムが組める
- 様々なコンテンツがあるので受講者の研修へのモチベーション維持につながりやすい
<向いている場合>
- 研修費用に余裕がある場合
- 研修内容のインプットとアウトプットの両方を実施したい場合
オンライン研修を実施するメリット
ここではオンライン研修を実施するメリットについて解説します。オンライン研修を実施するメリットは以下の5つです。
▼オンライン研修を実施するメリット
- 遠方の内定者・社員でも参加することが可能である
- 交通費や会場費を削減できる
- 研修内容を録画しておくことができる
- 研修管理の工数を削減できる
- 研修の質を均一化できる
それぞれ1つずつ解説します。
①遠方の内定者・社員でも参加することが可能である
対面で1箇所に集まる集合研修とは異なり、インターネットに繋げるだけで研修に参加できるため地方に現在住んでいる内定者や社員でも参加することが可能です。
開催場所を考える必要がなくなるため、急なスケジュール変更や参加人数の増減にも柔軟に対応できるようになります。
②交通費や会場費を削減できる
オンライン研修の受講者の多くは自宅で受けていることが多いです。そのため、内定者や社員の交通費を削減することができます。
内定者や社員の出張費だけではなく、会場費用、会場の設営費用、遠方受講者の費用などを削減することも可能です。
③研修内容の録画が容易である
オンライン研修ではWeb会議システムを使います。そして、多くのWeb会議システムには録画機能がついていることから、研修内容を簡単に録画することができます。
さらに、動画資料を活用したオンデマンド型の研修を実施することで、受講者は時間に縛られずに研修を受けることができるため、受講者のストレス軽減にもつながるでしょう。
④研修管理の工数を削減できる
集合研修では内定者や社員の出欠席を手作業で確認する場合が多いですが、オンライン研修を実施することでその手間を少なくすることができます。
例えば、現在どの程度学習を進めているのか一括管理することで、いち早く情報を手に入れられるようになり、内定者や社員の学習意欲を促すことができます。
⑤研修の質を均一化できる
オンライン上では多くの内定者や社員が参加できるため、研修をまとめて実施でき、研修の質を均質化することができます。
また、内定者や社員は同⼀教材で学べるため、勤務地や時間、講師による差が生まれにくいこともメリットです。
オンライン研修を実施するデメリット
ここまではオンライン研修を実施するメリットについて解説しました。
しかし、オンライン研修の実施にもデメリットはあります。オンライン研修を実施するデメリットは以下の5つです。
▼オンライン研修を実施するデメリット
- 受講者側のインターネット環境によって質が変わる
- トラブルが発生しやすい
- 受講状況がわからない
- 実習などの研修に適さない
- グループワークで参加者が発言しにくい
それぞれ1つずつ解説していきます。
①受講者側のインターネット環境によって質が変わる
参加者側のインターネット環境によって、講師の話を十分に聞き取れなかったり、画面の文字が読み取れなかったりと均一な教育を担保できない可能性があります。
そのため、オンライン研修を実施するのであれば、必ずネットワーク環境がしっかりと準備できているのか確認することが必要です。
②トラブルが発生しやすい
オンライン研修では常に通信環境や機器のトラブルのリスクがつきまといます。特に双方向型・リアルタイム型でトラブルが発生した場合は研修の進行に多大な影響を及ぼします。
通信環境や機器のトラブルが起きるリスクを極力減らすためにも、「安定した通信環境であるか」「機器が故障していないか」を確認しておくと良いでしょう。
また、ITリテラシーに関する知識を持っておくと、トラブルが発生した際に迅速に対応できるでしょう。
③受講状況がわからない
オンライン研修では、参加者の受講状況や集中度がわかりにくいことがデメリットとして挙げられます。
オンライン研修ではカメラがあることで受講者の態度は見えるものの、画面内しか見えないため、どのような態度で受講しているかわからないことがあります。
オンデマンド型の研修においては、動画を流すだけで研修内容が全く頭に入っていない受講生もいるかもしれません。
④実習などの研修に適さない
オンラインでできる研修にも限度があります。例えば、技術取得のための研修や実務に必要な手法や接客などを含む項目はオンライン研修には適さないでしょう。
このような場合は、知識のインプットはオンライン研修で行い、アウトプットは対面で行うという方法をとると良いでしょう。このように、対面とオンラインを組み合わせて研修を進めていくのがオススメです。
⑤グループワークで参加者が発言しにくい
集合研修に比べて、グループワーク、ディスカッションでは発言がしにくいことがデメリットとして挙げられます。
極力全員が発言をしっかりできるように、グループを少人数にすることや、全員がワーク、ディスカッションできるようなテーマ、お題を出すように意識しましょう。
【ステップ別】オンライン研修のやり方
ここからは実際にオンライン研修を導入する手順について3ステップに分けて説明します。
▼オンライン研修のやり方
STEP1:事前準備
STEP2:研修の実施
STEP3:研修後の改善
STEP1:事前準備
オンライン研修を実施するにあたって、まずは事前準備を行いましょう。
◎STEP1-1:研修の目的を明確化する
オンライン研修の企画をする前に、オンライン研修の目的を明確化させる必要があります。オンライン研修を通して内定者や社員に伝えたいことや身につけてほしいスキルを明確にすることで、それを軸とした運営を行うことができるでしょう。
例えば、内定者研修において、「社会人基礎力の向上」を目的とした場合は、ビジネスマナー講習や業務理解といった研修内容が中心となります。一方で「入社後の不安解消」を目的とした場合、同期・先輩との交流会が中心となるでしょう。
このように、研修の目的によって実施する内容が大きく異なってくるため、事前に研修の目的を明確にしておきましょう。
◎STEP1-2:必要なツールを準備する
続いて、オンライン研修を実施するための環境を整えましょう。オンライン研修でオンライン研修実施に向けて用意するべきものは以下の通りです。
▼オンライン研修で用意するべきもの
- インターネット環境
- WEB会議システム
- パソコン
- WEBカメラ
- スピーカー
- マイク
- イヤホン
研修前には以上の機器・システムの動作確認をしておきましょう。加えて、Web会議システムの検討も必要です。以下は代表的なWeb会議ツールです。
▼代表的なWeb会議ツール
- Zoom
- Google Meet
- Teams
- Webex
この中でも、Zoomは大規模な人数がミーティングに参加できることに加え、無料プランで手軽に録画が行えるため、特にアーカイブ型研修において非常に役立つでしょう。また、研修前にオンラインツールの操作方法を確認しておくと良いでしょう。
◎STEP1-3:研修内容を企画する
オンライン研修を円滑に進めるためには研修内容の企画も大切です。例えば、研修スライドの作成や研修のリハーサルを行っておくことで、研修の流れを事前に把握しておくことができ、スムーズな進行ができるでしょう。
企画をする際には、「オンライン研修の目的」を軸に、「内定者・新入社員が求めるコンテンツ」を企画する必要があります。
内定者研修、新人研修において企業に設けてほしい企画内容、満足している企画内容は以下のようになりました。
▼内定者研修において企業に設けてほしい内容ランキング
- 基本的なビジネスマナー(69.1%)
- 仕事に必要な知識・資格の学習(42.7%)
- コミュニケーションスキルなど社会人基礎力の向上(47.2%)
▼新人研修においてカリキュラムに満足している点
- 同期との仲が深められた(65.2%)
- 研修が実際の仕事に役立つカリキュラムだった(43.5%)
- カリキュラムが様々で退屈しなかった(34.9%)
- 先輩社員の手厚いフォローがあった(34.9%)
【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2025年卒内定者意識調査』
【参考】株式会社Synergy Career『【調査報告】新人研修カリキュラムは「OJT」が満足度80.4%と最も高い | 同期との仲が深められたの声も多数』
◎STEP1-4:参加者に連絡を行う
研修の日程が決まり次第、研修内容や実施日などを共有しましょう。参加者にオンライン研修に参加できる場所(自宅・オフィス)を確保しておくように合わせて伝えることも必要です。
また、研修資料を事前に共有することで講習の時間を削減し、ディスカッションや質疑応答といったアウトプットに時間を割くことができます。
STEP2:研修の実施
いよいよ研修を実施しましょう。ここでは、2つの例をもとにどのように研修を進めていくのかみていきます。
▼オンライン研修のプログラム例
- オンライン研修プログラム例①:電話応対ロールプレイ
- オンライン研修プログラム例②:プレゼン大会
【オンライン研修プログラム例①】電話応対ロールプレイ
複数グループに分けることで、1つのグループの人数も少なくすることができます。それにより、電話対応のロールプレイなどを実施することが可能です。
グループディスカッションやグループワークだけではなく、実践的な研修も少人数にし、講師(社員など)とコミュニケーションが円滑に取れることで双方向のコミュニケーションを実現することができます。
企業側も画面録画などの機能を使い受講者のロールプレイを録画できることで、一人一人に改めてフィードバックをすることも可能です。
オンライン研修と聞くと、講師(社員など)と受講者のコミュニケーションが取りにくいと思われがちですが、グループ分けを行うことで少人数で対応できるため、より近い距離で接することもできます。
【オンライン研修プログラム例②】プレゼン大会
録画機能や投票機能を使ってプレゼン大会なども実施できます。
録画機能は、人数が多い研修で活用できる便利な機能です。また、投票機能を用いることで簡単に優秀者を決めることができることができます。
プレゼン大会の流れは以下の通りです。
▼プレゼン大会の流れ
- グループごとに分かれてプレゼンをし、録画しておく
- 全体で全員分のプレゼンを共有する
- 投票機能を用いて投票する
STEP3:研修後の改善
オンライン研修を実施した後は、研修の振り返りを行いましょう。
オンライン研修を行ったあとは参加者にアンケートの記入を求めましょう。アンケートから意見を抽出し、研修の良かった点と悪かった点の洗い出しを行います。次回以降の研修において、良い点は継続して実践し、悪い点は改善することが重要です。
このサイクルを繰り返すことでオンライン研修の質を継続的に高めていくことができるでしょう。
オンライン研修サービスを提供する企業3選
「オンライン研修を実施したいが、資料作成の工数負担に不安がある」という方もいるかもしれません。
しかし、オンライン研修は外注が可能です。
ここからはオンライン研修サービスを提供している企業を3つご紹介します。
▼オンライン研修サービスを提供している企業
- 株式会社グロービス
- 株式会社グロースX
- Mogic株式会社(LearnO)
①株式会社グロービス
グロービスグロービス経営大学院では他校に先駆け、2014年からオンラインMBAプログラムをスタートしています。そのオンラインMBAプログラムを法人向けに再設計したものが、企業内研修(オンライン)のカリキュラムです。
<グロービスの特徴>
- オンライン専用のコンテンツ設計
- オンラインに合わせた講師のファシリテーション力
- WEB会議システムの機能を最大限活用したアウトプット中心の研修スタイル
- 個人学習〜ディスカッション~振り返りまで、全工程をオンラインで提供
【参考】株式会社グロービス『プログラムラインナップ - グロービス (GLOBIS) の集合研修(講師派遣型)』
②株式会社グロースX
株式会社グロースXは、業績に繋がるマーケティング人材育成を目標に掲げたWebマーケティングスクールです。
専門家が監修する体系的で実践的なマーケティング・AIの人材育成カリキュラムを提供しています。
<グロースXの特徴>
- 効率的かつ生産性高く学習できる独自のグループラーニングシステム
- マーケティングや営業、AI/DX等の様々なコンテンツテーマを提供
- 受講者の学習の進捗や課題を可視化できる
【参考】株式会社グロースX
③Mogic株式会社(LearnO)
Mogic株式会社が提供しているサービスである「LearnO(ラーノ)」は、3,800社、月間60万人以上が利用するeラーニングシステムです。
スマートフォン/タブレット/パソコンでの受講が可能で、社員教育、人材育成、学校教育、研修に利用できます。
<LearnOの特徴>
- 50名まで月額4,900円という業界最安値レベルの利用料金
- 1ヶ月単位での利用が可能
- 受講生ごとに学習履歴やテスト結果を閲覧できる
オンライン研修を成功させるためのコツ
オンライン研修を成功させるコツは以下の6つです。
▼オンライン研修を成功させるコツ
- 研修の目的と実施手段を合わせる
- 事前準備を徹底しておく
- 1時間区切りでタイムスケジュールを組む
- ファシリテーターをつける
- 研修資料を事前に配布する
- 双方向性の研修で効果をあげる
それぞれ1つずつ解説していきます。
①研修の目的と実施手段を合わせる
1つ目は研修の目的と実施手段を合わせることです。
例えば、「内定者・新入社員と先輩社員の交流」を目的とした研修内容の場合に、オンデマンド型のオンライン研修の形をとってしまうと、受講者に不満が生じてしまうかもしれません。
この場合は、双方向型・リアルタイム型のオンライン研修を実施することが良いでしょう。これにより、内定者・新入社員がそれぞれ抱えている悩みを直接、研修の場で話すことができるため、有意義な時間になると考えられます。
②事前準備を徹底しておく
2つ目は事前準備を徹底しておくことです。
オンライン研修の前に徹底した事前準備をしておくことで、研修をスムーズに進めることができます。その際、以下のような事前準備を行っておくと良いでしょう。
▼オンライン研修前の事前準備
- インターネット環境・各デバイスの動作確認
- Web会議システムの利用方法
- トラブル対応マニュアルの作成
- 研修リハーサルの実施
なお、詳しくは【ステップ別】オンライン研修のやり方にて解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
③1時間区切りでタイムスケジュールを組む
3つ目は1時間区切りでタイムスケジュールを組むことです。そもそも時間を意識しなければならない理由は、人間の集中力はおおよそ15分〜90分であり、集中力に限界があるためです。
受講者が長時間モニターを見ることや、ずっとヘッドフォンをすることでの目と耳への負担などを考慮しなければ研修の質が低下します。
そのため、細かな休憩やストレッチする時間などを設けることが必要です。長時間の研修の場合は、極力コンパクトにしましょう。
④ファシリテーターをつける
4つ目はファシリテーターやオペレーターをつけることです。ファシリテーターをつけることでスムーズに研修が進められます。それに従い、受講者の集中力を持続させることができます。
オペレーターとは、進行補助役です。特にWeb会議システムの操作に慣れている進行補助役がいることで、機材トラブルなどに素早く対応することが可能です。オペレーターがいるだけで、受講者や講師が安心して研修に取り組むことができます。
⑤研修資料を事前に配布する
5つ目は研修資料を事前に配布しておくことです。
事前に研修終了を配布することで進行を円滑に進めることができます。
進行が円滑に進められるため、ディスカッションやグループワーク、質疑応答の時間を長く取ることができます。
一方的な講義時間を最小限にとどめ、受講者との双方向のコミュニケーションを取る時間を増やすことで、受講者の満足度を上げることができます。
⑥双方向性の研修で効果をあげる
6つ目は双方向性の研修です。ただ講義の内容を聞くだけでは、受講者のモチベーションは低下してしまうでしょう。
そのため、例えばライブ配信型であれば、クイズやミニテストを実施したり、オンデマンド型であればレポートやアンケートを実施したりすることでより受講者が理解しやすくなります。
オンライン研修を実施する際の注意点
オンライン研修を成功させるコツを紹介しましたが、ここではオンライン研修を実施するにあたっての注意点を紹介します。オンライン研修を実施する際の注意点は以下の3つです。
▼オンライン研修を実施する際の注意点
- カメラを常時オンにしておく
- トラブルが発生した際の対応方法を考えておく
- 対面研修も実施する
それぞれ1つずつ解説していきます。
①カメラを常時オンにしておく
カメラを常時オンにしておくことで、受講者がしっかりと研修を受けているか監視するのと同時に、受講者の反応を見ることができます。
仮にカメラオフの場合、一方的なコミュニケーションとなってしまい、受講者の緊張感が薄れてしまいます。そうした事態を防ぎ、受講者にある程度の緊張感を持たせるためにも、カメラを常時オンにしておくことが大切です。
また、受講者の反応を見ることができるため、発表者側のストレスの緩和にもつながるでしょう。
②トラブルが発生した際の対応方法を考えておく
オンライン研修の事前準備をどれだけ丁寧に行っても、本番で通信トラブルや機材トラブルが発生してしまうおそれがあります。そうなった時に迅速な対応ができるようにあらかじめマニュアルを作っておくと良いでしょう。
トラブルが起きたとしても滞りなく進行できるようであれば、オンライン研修は実りのある時間となるでしょう。
③対面研修も実施する
オンライン研修はワークショップの実施には不向きです。そのため、オンライン研修で完結するのではなく、対面研修も実施することが望ましいでしょう。
複合型の研修のように、業界知識やビジネスマナーはオンライン研修で実施し、ロールプレイングや大きなイベントを行う際は対面研修で実施することで、受講者のモチベーション維持につながるでしょう。
【内定辞退・早期離職対策】定着率を高めるオンライン研修の進め方のポイント
ここからは定着率を高められるようなオンライン研修の進め方について解説します。定着率を高めるオンライン研修の進め方のポイントは以下の3つです。
▼定着率を高めるオンライン研修の進め方のポイント
- アイスブレイクの時間を確保する
- 個別にフォローできる環境を設ける
- 先輩社員との交流会を実施する
①アイスブレイクの時間を確保する
アイスブレイクによって話しやすい環境をつくることでより交流が活発になり、有意義な研修の時間となるでしょう。
オンライン研修は空気感の醸成が難しく、対面と比較して研修の雰囲気が重く感じられがちです。
このオンライン研修特有の雰囲気の重さを打破するために、まずはアイスブレイクの時間を設け、受講者同士や講師と会話しやすい雰囲気を築きましょう。
②個別にフォローできる環境を設ける
個別にフォローできる環境があると、受講者は自身の悩みや不安を相談しやすくなります。
双方向型・リアルタイム型のオンライン研修では、複数人での受講が一般的であり、個別に相談できる環境・時間があまりないことがあります。したがって、研修のなかで(もしくは研修とは別で)個別にフォローできる時間を設けることが必要です。
では具体的にどんなフォローをすると良いのでしょうか。株式会社キャリタスの2025年卒を対象とした調査によると、以下のような学生の企業への要望・意見がありました。
▼学生から企業への要望・意見
- 「年次が近い先輩社員と実際の業務について話す機会があると、より不安感が払拭されると感じた」
- 「内定者同⼠で交流できたのが内定式しかなかったので、もっと同期と話す機会があれば嬉しい」
- 「eラーニングの形態を取っていて、1人で⾏うことに孤独を感じたため、中間地点で一度近況報告会などを設けて欲しい」
【参考】株式会社キャリタス『調査データで⾒る「入社に向けた内定者フォロー」-2025年卒調査-』
このことから、学生は企業に対して研修だけでなく、同期・先輩との交流がしたいという声が多いことがわかります。
確かに研修はスキルや知識を学ぶ場所でもありますが、同期や社員とのコミュニケーションが取れる貴重な場所でもあります。
そのため、フォロー方法としては内定者懇親会や同期交流会、先輩社員との1on1面談といった場を設けることが良いでしょう。
③先輩社員との交流会を実施する
先輩社員との交流会を実施することも学生や新入社員の定着率を高める要因になるでしょう。学生から企業への要望・意見の中にあったように、学生・新入社員が先輩社員と話すことで不安感が払拭されることもあります。
先輩社員とのお悩み相談の中では、仕事のイメージや苦労話、先輩からの励ましがあると、学生や新入社員が内定辞退・早期離職するのを防ぐことにつながるかもしれません。
したがって、先輩社員と交流する時間をつくることが間接的に定着率を高めることにつながります。
オンライン研修の導入事例
実際にオンライン研修を導入している企業について以下の3つの企業を紹介します。
▼オンライン研修の導入事例
- 株式会社ドコモCS 長野支店
- パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
- 株式会社アシックス
株式会社ドコモCS 長野支店
株式会社ドコモCS長野支店では、2020年度からオンラインで新入社員教育を行っています。オンライン研修を導入した当初は「実践の場がほしい」「同期の間の横のつながりがとりづらい」といった声がありました。
そのため、実践力を養うために新入社員以外も含めた実践的なオンライン研修を実施しました。具体的には研修の始まりに今日やるべきことを意識づけする時間を設けたり、研修とは別にコミュニケーションの時間を確保したりするといった取り組みです。
その結果、実践につなげられる研修になったとともに、同期との関係構築につなげることができました。
【参考】株式会社パーソル総合研究所『株式会社ドコモCS 長野支店様 |導入事例 - パーソル総合研究所』
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社は2020年度に新人社員研修を大きくリニューアルし、全ての研修をオンラインに移行しました。
全ての研修をオンライン化した課題として、受講者とのコミュニケーションが取りづらいことや研修の質の低下が挙げられたと言います。
そこで、研修の見直しを行い、オンラインで習得が難しい研修内容の場合はグループワークの時間を長くとることで、受講者同士がコミュニケーションをとって課題に向き合える環境を作りました。
その結果、グループの雰囲気や議論が活性化し、現在でも実りのある研修になっています。
【参考】株式会社パーソル総合研究所『パナソニック システムソリューションズ ジャパン様 |導入事例 - パーソル総合研究所』
株式会社アシックス
株式会社アシックスは、「自社で働くイメージを伴った仕事理解」の促進が難しい状態に直面していました。
そこで、独自のビジネスゲーム『仕事理解グループワークMOVE』をオンラインで導入したことで、学生や内定者は対面開催以上に活発な議論を行ったそうです。
加えて、アシックスでは昔からグローバルな拠点間のテレビ会議が行われているため、内定者研修をオンライン研修にすることで実際の仕事の雰囲気を確かめる機会につながりました。
【参考】株式会社プロジェクトデザイン『【事例インタビュー】内定者や学生に対して「自社で働くイメージを伴った仕事理解」を促進するビジネスゲーム(アシックス) | 株式会社プロジェクトデザイン』
学生とのミスマッチを防ぎたいなら、Matcher Scout
「学生とのミスマッチが生じてしまい、内定辞退がでてしまう」とお悩みの採用担当者の方におすすめしたいのがMatcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの企業にとって労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由により、自社にマッチした人材を確保することができ、採用活動を効率的に進めることができます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で解説しているので、ぜひご覧ください。
【導入事例】4名の学生さんとの出会い。スカウトを通じて弊社の魅力が伝わり、マッチ度の高い学生さんとのご縁が生まれました。|新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout
まとめ
いかがでしたか?この記事では、オンライン研修についてメリット・デメリットや導入方法、成功させるコツについて解説しました。
オンライン研修が成功し、少しでも内定者・新入社員の定着率向上につながれば幸いです。



.png)