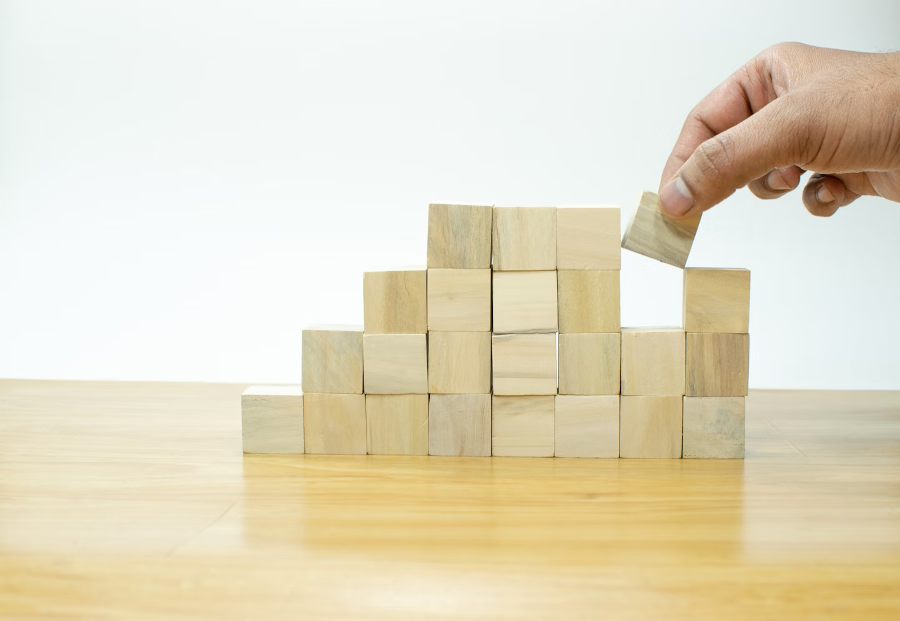「思ったように応募が来ない…」
「母集団形成で課題がある」
「採用できても辞退され、入社までつながらない…」
以上のような課題を抱えている中小企業の採用担当者様は多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では中小企業の新卒採用で成功するための採用戦略とやり方について解説していきます。中小企業の新卒採用が苦戦する理由や成功事例も紹介していますので、ぜひポイントを抑えて自社の新卒採用を成功させましょう!
中小企業における新卒採用の現状
中小企業の新卒採用の現状として、以下の2点を解説していきます。
▼中小企業における新卒採用の現状
- 中小企業の大卒求人倍率が前年度より上昇し、採用は難化
- 中小企業志向の学生は4割で前年より微増
中小企業の大卒求人倍率が前年度より上昇し、採用は難化
リクルートワークス研究所の調査によると、26卒全体の大卒求人倍率と、中小企業・大手企業それぞれの大卒求人倍率は以下のようになりました。
▼26卒の大卒求人倍率
| 大卒求人倍率(前年度比) | |
| 全体 | 1.66倍(-0.09) |
| 中小企業(300人未満) | 8.98倍(+2.48) |
| 大手企業(5,000人以上) | 0.34倍(±0) |
26卒の全体の大卒求人倍率は1.66倍と、25卒の1.75倍より0.09ポイント低下しました。これは新卒学生1人あたり、1.66件の募集・求人があることを表しています。
中小企業の大卒求人倍率を見ると、8.98倍と、昨年度より2.48ポイント上昇したという結果になりました。これは新卒学生1人あたり8.98件の募集・求人があるということで、前年度より採用しにくくなっていることが分かります。
【参考】株式会社インディードリクルートパートナーズ『第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)』
中小企業志向の学生は4割で前年から微増
マイナビの26卒を対象にした調査によると、「やりがいのある仕事であれば中堅・中小企業でもよい」「中堅・中小企業がよい」と回答した中小企業志向の学生は43.0%で、前年比0.1ポイント増加となりました。
また、「絶対に大手企業がよい」「自分のやりたい仕事ができるのであれば大手企業がよい」と回答した大手企業志向の学生は51.8%で、中小企業志向の学生より8.8ポイント高い結果となりました。
同調査によると、26卒では中小企業を含めて多くの企業が初任給引き上げをしているという結果が出ています。給与待遇の改善が中小企業の志向が微増したひとつの要因であると考えられるでしょう。
つまり、大手企業の方が根強く人気であるものの、働く環境の整備や採用戦略によって、中小企業を志望する学生もいると考えられます。諦めずに自社の魅力を伝えられる採用戦略を立てていくことが大切です。
【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査』
中小企業が新卒採用で苦戦する理由
中小企業が新卒採用で苦戦しやすい理由として、以下の6つが考えられます。
▼中小企業が新卒採用で苦戦する理由
- 採用にコストをかけられない
- 採用にかけられる人手が足りない
- 知名度が足りない
- 自社の魅力を訴求できていない
- 採用ノウハウがない
- 内定辞退者が多い
1つずつ詳しく見ていきましょう。
①採用にコストをかけられない
中小企業は採用にかけられる予算が少ないことがあげられます。マイナビの調査によると、24卒の非上場企業の採用費平均総額は233.1万円、採用費中の広告費平均は123.7万円でした。
中小企業の採用費総額平均は上場企業より約680万円少なく、広告費平均は約480万円少ないという結果になりました。
| 採用費総額平均(万円) | 採用費中の広告費平均(万円) | |
| 全体 | 287.0 | 161.7 |
| 上場企業 | 917.6 | 606.7 |
| 非上場企業 | 233.1 | 123.7 |
| 上場企業と非上場企業の差 | 684.5 | 483 |
【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2024年卒 企業新卒内定状況調査』
中小企業は大企業と比べて採用数が少ないこともあり、採用活動に投じられるコストが限られることが、このような金額の開きに繋がっているといえるでしょう。
予算が少ないことで、どのようなことが起こるのでしょうか。
▼かけられる予算が少ないことで起こること
- 就活生へ認知を広げる機会が減ってしまう
- 使用できる採用サービスが限られる可能性がある
「就活生へ認知を広げる機会が減ってしまう」という点に関しては、就活サイトへの掲載やイベント開催・出演の機会が少なくなることが原因です。
イベントの開催については、就職活動のオンライン化に伴い自社だけでの機会を作りやすくなりました。しかし、イベントの開催はできても集客するためには、露出・宣伝が必要となります。予算が少ないと、十分な数の参加者を集めるのに苦労することもあるでしょう。
また「使用できる採用サービスが限られる可能性」もあります。昨今さまざまなツールが発展していますが、使用するにはコストがかかります。
使いたいツールが新卒採用を効率的に進めていく上で効果的だとしても、予算の都合で使用できなかったり、使用が限定される可能性もあるかもしれません。
中小企業はコストを投じられない分、戦略を練って新卒採用を行っていく必要があります。
❚ 低コストで新卒採用を成功させるならMatcher Scout
「費用を抑えて母集団形成を行いたい」「入社につながらなかった場合のリスクが心配」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。
Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービスです。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、費用面でのリスクを心配せずに、効率的な採用活動を進めることができます。ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
②採用にかけられる人手が足りない
大企業と比べて社員数の少ない中小企業は、採用活動に専念できる人員も限られてきます。一方で、新卒採用の成功のためには対応の迅速さが重要です。また、内定後のフォローの手厚さによって辞退者の数は大きく変わります。
したがって、採用に関わる人員が少ないことは、これらの対応が疎かになってしまうことに繋がりかねません。
以上の点を踏まえ、採用業務の中で自社でやることと外部委託をすることを明確にして効率的に採用を行うことが大切になります。
③知名度が足りない
基本的に新卒採用を行うためには自社に応募してもらうことが必要です。しかし、中小企業は知名度が低いため、就活サイトでもほかの会社に埋もれてしまうことが多いです。
そのような状況では、応募数を増やすことは難しいため、母集団の形成の難易度は高いと言えます。
したがって、中小企業における新卒採用では、いわゆる「待ちの採用」だけでは自社に合う人材に出会えない可能性がでてきます。ターゲットを絞ることや、ダイレクトリクルーティングなど「攻めの採用」への転換が必要不可欠です。
④自社の魅力を訴求できていない
学生は採用活動において、数十社数百社単位の企業と接点を持つことが多いです。仮に自社が学生から認知を得たとしても、「待遇・事業内容・事業の安定性・社風・知名度」などで比較検討先の企業と比べて劣っていると判断されれば、自社のエントリー数を増やすことはできません。
「事業内容は面白そうだけど、上場してないなら入社したくないな・・・」
「毎年業績は伸びているけど、ノルマがきつそうで自分にはマッチしなさそうだな・・・」
といった理由で学生から敬遠されることは、珍しくありません。そのような事態を防ぐためにも、新卒採用においては、自社の魅力付けを工夫することが重要です。
⑤採用のノウハウが少ない
採用ノウハウの蓄積も重要です。「アプローチを行った学生の数、総エントリー数、各選考過程における合格者の割合、効果の高いスカウトメール」等、採用活動の実績は、次年度以降の採用活動で欠かせないデータです。
しっかり実績を蓄積しておくことで、
「昨年は動き出しが遅かったから、少し早く採用活動を開始しよう」
「昨年の採用活動で、一番効果の高かったスカウトメールのタイトルを今年も使おう」
といった工夫ができるようになります。
来年以降の採用活動を成功させるためにも、採用ノウハウの蓄積は、何らかの形で行っておきましょう。
⑥内定辞退者が多い
内定を通知しても、採用活動は終わりません。内々定者に内定を承諾してもらい、入社するまで採用活動は続きます。
この記事をご覧になっている方の中にも「学生の内定辞退が多い・・・」と困っている方は少なくないでしょう。
実際、就職みらい研究所の調査によると、25卒の学生の内定辞退率は63.8%でした。半数以上の学生が内定を辞退していることが分かります。
【参考】就職みらい研究所『就職プロセス調査(2025年卒)「2025年3月度(卒業時点)内定状況」』
また23卒・24卒を対象にした調査によると、内定辞退をした理由として、「他企業の内定が決まった・他企業の方が魅力的だったから」が32.5%と最も高く、「自分の理想と違っていた、企業のことを知っていくうちに社風などが自分とは会わないと感じたから」が27.4%と次いで多い結果となりました。
▼企業の選考や内定を辞退した理由
- 他企業の内定決まった・他企業の方が魅力的だったから:32.5%
- 自分の理想と違っていた、企業のことを知っていくうちに社風などが自分とは合わないと感じたから:27.4%
- 勤務条件が自分の希望と合わないと分かったから:13.9%
- 志望業界・職種が変わったから:9.3%
- 企業のことをよく知ることがないまま採用が進んでいったから:5.9%
【参考】株式会社インタツアー『内定承諾・辞退の決定要因調査』
このように、他企業を魅力的に感じて辞退する学生と、社風や条件が合わないために辞退する学生に大きく分けることができます。
このような内定辞退を防ぐためにも、自社の強みは何かを改めて明らかにすることや、自社の魅力を適切に訴求できているかを見直すことが大切です。
先ほどの調査結果より、大手企業を志望している学生は多く、中小企業を志望している学生は約4割にとどまっています。そのため、大手企業からの内定を学生が得た場合、大手企業に流れてしまうことはある程度仕方がないことでしょう。
しかし、内定辞退のなかには防げる内定辞退もあります。内定を通知しただけで安心せず、その後の内定者フォローも手厚く行い、継続して自社の魅力を訴求することが大切です。
【悩み別一覧表】中小企業が成功するために取るべき新卒採用戦略
では、新卒採用で成功するために何をすればよいのでしょうか。ここでは、中小企業の新卒採用担当者様が抱えやすいお悩みと、解決できる新卒採用戦略についてご紹介します。
| お悩み一覧 | 取るべき新卒採用戦略 |
| 「説明会に人が集まらない」 | ・情報発信の内容を見直す ・利用する採用媒体を見直す ・企業ブランディングを行う ・学生との接点を見直す |
| 「説明会後の選考につながらない」 | ・情報発信の内容を見直す ・求める人物像を明確にする |
| 「条件・魅力が大手に見劣りしてしまう」 | ・企業ブランディングを行う ・情報発信の内容を見直す ・求める人物像を明確にする |
| 「人手不足で十分なフォローができない」 | ・WEB選考を導入する ・採用ノウハウを蓄積する ・利用する採用媒体を見直す |
| 「選考中の途中辞退率が高い」 | ・学生とのコミュニケーション量を増やす ・WEB選考を導入する |
| 「内定辞退率が高い」 | ・学生とのコミュニケーション量を増やす ・手厚い内定者フォローで内定辞退を防ぐ |
| 「採用後にミスマッチが発生してしまう」 | ・求める人物像を明確にする ・採用ノウハウを蓄積する |
| 「採用目標が達成できない」 | ・利用する採用媒体を見直す ・採用スケジュールを見直す ・採用ノウハウを蓄積する |
続いての見出しで、中小企業が取るべき新卒採用戦略について解説していきます。
募集開始~母集団形成|中小企業が取るべき新卒採用戦略7選
まずここでは「採用募集の開始〜母集団形成まで」に、中小企業の採用で行うべきことを解説していきます。
▼募集開始から母集団形成までで取るべき新卒採用戦略
- 選考スケジュールを見直す
- 求める人物像を明確にする
- 情報発信の内容を見直す
- 企業ブランディングを行う
- 学生との接点を見直す
- WEB選考を導入する
- 利用する採用媒体を見直す
1つずつ詳しく見ていきましょう。
1.選考スケジュールを見直す
「採用目標が達成できない」というお悩みを抱えている方は、選考スケジュールの見直しがおすすめです。
まず中小企業の採用においては「就活生のスケジュールを把握し、適切な時期に選考を行う」ことが重要です。
「毎年大学3年生の3月から選考を始めているので、今年も同じ開始時期にしよう」という形で何となく募集を始めてしまうと、知名度のある大企業に埋もれ、学生の認知度が向上しません。
▼選考スケジュールを見直す際に確認したいこと
- 他社の採用スケジュールを確認する
- 就活生の就活スケジュールを知る
この2点を注視しておき、その結果に基づいて採用計画を立てることが重要です。以下で詳しく見ていきましょう。
❚ 他社の採用スケジュールを確認する
経団連は、原則として以下のスケジュールで採用活動を進めることを定めています。
しかし、これよりも早い段階で採用活動・内定出しを行う企業も多くあります。というのも上記の経団連の就活スケジュールで選考を行う企業には、大企業・有名企業が多く、そのような企業と同じ時期に選考を行っても、学生の募集を増やすのは困難だからです。
そこで、中小企業が採用を成功させるための採用スケジュールのコツは、以下の2つがあげられます。
▼中小企業が採用を成功させるための採用スケジュールの立て方
- 大企業、有名企業が選考を始める前に選考を開始する
- 大学4年生の8月以降も継続して採用活を行う
例えば、経団連の採用スケジュールよりも早い時期から選考を始めたい場合の採用スケジュールは以下があげられます。
自社が大手企業に埋もれない採用を行うために、改めて自社の採用スケジュールを見直すことが大切です。
❚ 就活生の就活スケジュールを知る
母集団形成で成果を出すためには、学生が就職活動をしているタイミングで適切にアプローチする必要があります。以下は、26卒の学生が就職活動を開始したと思う時期についての調査です。
大学3年生の4月が30.8%と最も多く、前年調査の26.0%を上回りました。また、2年生の時点で就職活動を始めた学生も12.1%と、前年調査の7.6%を上回りました。
さらに、就職活動を始めた時期について、大学3年生の6月以降ポイントが下がり、活動開始の早期化が読み取れます。
この結果から、多くの就活生は大学3年生になる4月から就職活動を行っています。25卒と比較して早期化が進んでいるため、27卒、28卒の学生は大学2年生から始める等、さらに早い時期から活動を開始することが考えられます。
【参考】株式会社キャリタス『11 月後半時点の就職意識調査』
2.求める人物像を明確にする
「説明会後の選考につながらない」
「条件・魅力が大手に見劣りしてしまう」
「採用後にミスマッチが発生してしまう」
といったお悩みを抱えている方は、求める人物像を明確化することがおすすめです。
中小企業は大手企業のように知名度が高いわけではないため、「とりあえず優秀な学生を採用したい」という方針ではなかなか採用活動を順調に進めることができません。また、就職活動の軸や志向、価値観は学生個人によって大きく異なります。
そのため、自社に合う学生はどんな人物像なのかをしっかりと考えたうえで採用活動を行うか否かで成果は大きく変わります。
したがって、採用を担当する人事部の社員は勿論、現場の社員の意見もくみ取りながら具体的な求める人物像を明確に策定することが、採用活動を進めるうえでは大切になります。
3.情報発信の内容を見直す
「説明会に人が集まらない」
「説明会後の選考につながらない」
「条件・魅力が大手に見劣りしてしまう」
といったお悩みを抱えている方は、情報発信の内容を見直すことがおすすめです。
中小企業の採用においては「自社のナビサイト・企業ホームページの内容を定期的に見直す」ようにしましょう。
ナビサイトやホームページは、自社の業務や待遇などを掲載して学生に伝えるだけでなく、ホームページを見た学生の志望度を高める「採用ブランディング」の効果を持つこともあります。
学生が企業研究を行ううえで知りたい情報は、以下のようになりました。
▼学生が企業研究を行ううえで知りたい情報
- 実際の仕事内容(85.1%)
- 給与水準・平均年収(56.2%)
- 社風(54.3%)
- 福利厚生制度(50.1%)
- 求める人物像(47.1%)
- 残業・休日出勤の実態(46.6%)
- 他社と比べた強み・弱み(44.4%)
ナビサイトや企業ホームページなどで情報を発信する際は、学生が知りたいと思う情報を理解したうえで、学生の興味を惹くコンテンツを作成できるようにしましょう。
【参考】株式会社キャリタス『3 月 1 日時点の就職活動調査』
「ナビ媒体に掲載している自社の採用サイトを、これまで一度も変更したことがない」という場合は、適切な採用ブランディングを実現できていない可能性があります。
それにより、多くの学生に自社の採用サイトを見てもらっているのに、エントリーまでは至らないという問題が発生することもあるでしょう。
このような問題を防ぐためにも、採用に関するサイトは定期的に更新し、学生から興味を持ってもらうようにするのがおすすめです。
▼採用サイトの運営のおすすめの方法
- 採用サイトには、常に最新情報をアップしておく
- 長年改修されていないサイトは、悪い印象を持たれる可能性があるので見直す
- 採用サイトに動画を掲載するなど、分かりやすいサイト作りを意識する
4.企業ブランディングを行う
「説明会に人が集まらない」
「条件・魅力が大手に見劣りしてしまう」
といったお悩みを抱えている方は、企業ブランディングを行うことがおすすめです。
先述の通り、学生の就職観や企業を選択するポイントは人によってそれぞれです。時間はかかりますが、学生のニーズに合わせて自社の魅力を伝えることが新卒採用の成功に繋がります。
そうはいっても、学生のニーズを正しく把握することは難しいです。実際にはどのようなことをすればいいのでしょうか?具体的には、以下を行って学生のニーズを把握しましょう。
▼企業ブランディングのやり方
- 入社して間もない若手社員に就活当時魅力に感じたポイントをヒアリングする
- 自社の説明会に来た学生にアンケートを実施する
- 選考辞退者に対して辞退の理由を聞くアンケートを実施する
このようなことを通じて把握した学生のニーズ、自社の魅力、そしてそのギャップをその後の採用フローの設計に活かすことが新卒採用を成功させる近道になります。
5.学生との接点を見直す
「説明会に人が集まらない」といったお悩みを抱えている方は、学生との接点を見直すことがおすすめです。
十分な母集団の形成を行うためには、学生との接触方法を定期的に見直すことが重要です。
例えば求人広告やナビサイトのみで募集を行っていて、学生からの募集が集まらない場合は、ダイレクトリクルーティングやSNS採用を導入してみるなど、定期的な見直しを行うようにしましょう。
学生が新たな企業を探す手段として最も多いのが「就職情報サイト」、次いで「合同企業説明会」や「学内企業説明会」、その次に多いのが「逆求人サービス」でした。
求人広告やナビサイトのみで募集を行っても企業説明会・合同説明会のブースに人が集まらない場合は、逆求人サービスを利用し、企業側から学生にアプローチする必要があると言えるでしょう。
先程も触れましたが、母集団形成に悩む中小企業の場合は、ダイレクトリクルーティング等「企業側からアプローチをかける採用手法」がおすすめです。
【参考】株式会社キャリタス『3 月 1 日時点の就職活動調査』
6.WEB選考を導入する
「人手不足で十分なフォローができない」
「選考中の途中辞退率が高い」
といったお悩みを抱えている方は、WEB選考を導入することがおすすめです。
母集団形成を行う際は「どれだけ多くの学生にアプローチできるか」が重要です。アプローチできる学生の数は、採用エリアを広げれば広げるほど増加します。
母集団形成に悩んでいる場合は「関東圏の学生のみを対象とする」というような形のエリア制限は行わない方がよいでしょう。
しかしオフィスが東京など都市圏にある場合、地方の学生は選考を受けるのに、時間とコストがかかります。そこでおすすめなのがWEB選考の実施です。
WEBを用いて選考を行えば、地方学生が気軽に面接や説明会に参加できるため、採用エリアを広げることができるでしょう。
またWEBで選考を行えば、下記のようなメリットを受けることができます。
▼WEB選考を導入するメリット
- 学生に対する交通費や旅費などを支払う必要がなくなる
- 人事部の負担軽減に繋がる
アプローチする学生の数を広げ、採用コストを抑えるためにも、WEB選考を積極的に導入しましょう。
7.利用する採用媒体を見直す
「説明会に人が集まらない」
「人手不足で十分なフォローができない」
「採用目標が達成できない」
といったお悩みを抱えている方は、利用する採用媒体を見直すことがおすすめです。
利用する採用媒体を見直すことも、新卒採用を成功させるために重要です。そこで、以下の3つのお悩みに分けて、おすすめのサービス・採用手法を紹介していきます。
▼悩み別|おすすめのサービス・採用手法
- 優秀層を採用したい企業向け
- 予算に余裕がない企業向け
- 社内の人員が足りない企業向け
❚ 優秀層を採用したい
まず予算に余裕がある場合に、おすすめの採用サービス・媒体を下記の表でまとめました。
| サービス名 | 特徴・メリット |
| 採用コンサルティング | ・採用戦略の立案やナビ媒体の運用方法、選考方法など、選考全般に関するアドバイスを行う。
・料金例 ※料金は選考の煩雑さなどによって変わるため、導入時は見積もりを取ることをおすすめします |
| 採用代行 | ・採用業務の一部を代行してもらえるサービス。代行料金・人件費がかかるため、高額になることが多い。 ・料金例 新卒採用 代行 5万円~70万円 ※依頼する業務の範囲等で、費用は変動するため、導入時は見積もりを取ることをおすすめします |
❚ 予算に余裕がない企業向け
中小企業の採用担当者の中には「採用に関する予算が足りずに困っている・・・」という方もいるでしょう。
そんな採用担当者の方に向けて、予算をかけずにできる採用手法・サービスを紹介します。
| サービス名 | 特徴・メリット |
| SNS採用 | ・初期費用が0円で始められる。企業ブランディングにも効果的。ただし発信に工数がかかり、効果がでるまでにも時間がかかる可能性がある |
| 中小企業特化型ナビ媒体サイト | ・大手ナビサイトに比べて、安く始めることができる。 ・ただし学生の登録数が少ないことが多く、母集団形成には不向きである可能性あり |
| 成果報酬型のサービス
(人材紹介・ダイレクトリクルーティング等) |
・「内定承諾時にはじめて費用が発生する」等成果報酬型のサービスであれば、初期費用・運用手数料などを0円で始めることができる。 |
❚ 社内の人員が足りない企業向け
中小企業は、採用にかけられる人数が少ないため、人手不足に陥りやすいです。そんな企業におすすめの採用手法・サービスを紹介しました。
| サービス名 | 特徴・メリット |
| 採用コンサルティング・採用代行 | ・採用業務の一部を外注できるため、社内のリソースが足りない時におすすめ。 |
| 採用ホームページの改修 | ・自社の採用ページを「学生が募集したくなるようなページ」に変更すれば、継続的に学生の応募が見込めるようになる。
・効果が高ければ、ページの更新が必要なく、工数がかからない |
社内の人員が足りない場合は、採用業務の工数を削減できるようなサービス・媒体を用いることが重要です。
選考~内定出し・入社前|中小企業が取るべき新卒採用戦略3選
次に選考〜内定出し・入社までにやるべきことを紹介していきます。
選考に進んでいる学生は、ある程度自社に興味を持っているので「自社の魅力付けを行い、志望度を高める」ことが重要です。
具体的には、以下の3点を行うと良いでしょう。
1つずつ紹介していきます。
1.学生とのコミュニケーション量を増やす
「選考中の途中辞退率が高い」
「内定辞退率が高い」
といったお悩みを抱えている方は、学生とのコミュニケーション量を増やすことがおすすめです。
学生とのコミュニケーション量を増やすことで、以下の3つの効果が期待できます。
▼学生とのコミュニケーション量を増やすことで期待できる効果
- 入社後のイメージ形成
- 学生との良好な関係性構築
- 志望度の向上
以下では、学生とのコミュニケーションの増やし方を選考前、選考中、合格通知時の3つにわけて解説しました。
【選考前】座談会・個別面談を実施する
選考が始まる前から、適宜座談会・個別面談を実施するのがおすすめです。面接以外の座談会・個別面談で、社員の雰囲気や社風を伝える場を設けることで、自社への志望度を高められる可能性があります。
学生も「ホームページやナビサイトだけでは、社風が伝わってこない・・・」と不安に思っている人が多いはずです。選考の途中で直接対話する機会を作ることは、学生の不安を取り除くことにも繋がります。
| 座談会の特徴 | ・社員同士が話している雰囲気から、学生が社風を感じ取ることができる ・「どんな社員が働いているのか」のイメージがしやすくなる |
| 個人面談の特徴 | ・人事に聞きづらいような質問ができ、学生の不安や疑問を取り除ける |
【選考中】キャリア相談にのり学生の将来像を共に考える
「学生の将来歩みたいキャリア」や「そのキャリアを歩むためには、どんな企業に入社するとよいのか」などをキャリア相談により明確にすることで、より具体的に将来像を描きやすくなります。
キャリア相談を行う際は「学生の将来像実現のために、自社が何をできるのか」も加えて説明するとよいでしょう。
例えば「10年後は子供を産んで家族を持ちたいけど、仕事と育児が両立できる会社選びが分からない・・・」と悩んでいる学生がいたとします。
その際はキャリア相談を行い、「自社であれば育児と仕事の両立ができます」ということを、社員の事例を見せながら紹介すれば、学生の不安を取り除くことができるでしょう。
学生は社会人経験がないため、3年後5年後10年後といった長期的なキャリアを描くことは非常に困難です。キャリア相談は、そんな学生の不足点を補う最適なサポートといえるでしょう。
キャリア相談を行うことで、以下の2つのメリットがあります。
▼キャリア相談を行うメリット
- 自社でのキャリアイメージが沸きやすくなり、志望度を高めることができる
- 学生との接触回数が増えるため、学生と良好な関係を築きやすくなる
【合格連絡時】面接のフィードバックを丁寧に行う
学生に対して、合格連絡を行う場合は「面接のフィードバックを丁寧に行う」ことが重要です。面接時の評価を言葉にして学生に伝えることで「どこを評価してもらえるのか(自身が会社で活かせる強み)」が明確になります。
自分の評価されているポイントが分かれば「自分がこの会社に入ったら、このような形で貢献できる」というような、入社後の活躍イメージが沸きやすくなるでしょう。
また「面接のフィードバックをしてくれる会社」という口コミが広がることで、面接を受けたい!と思う学生の数が増える可能性があります。
2.手厚い内定者フォローで内定辞退を防ぐ
「内定辞退率が高い」といったお悩みを抱えている方は、手厚い内定者フォローを実施することがおすすめです。
内定を出したらそこで終わりではありません。出した内定を承諾されてはじめて、就職活動が終わります。先程も紹介しましたが、現在の就職活動において、6割以上の会社で内定辞退が発生しています。そのため「内定辞退をゼロにする」というのは、困難でしょう。
しかし中には、適切にコミュニケーションを取っていれば、防げた内定辞退もあったはずです。採用人数を充足させるためにも、内定者フォローは手厚く行う必要があります。
では、どのような内定者フォローが効果的なのでしょうか。25卒を対象にした調査によると、入社予定企業から受けたフォローで入社意欲が高まったものとして、「内定者懇親会(対面)」が65.3%と最も高い結果となりました。
▼入社意欲が高まったフォロー内容
- 内定者懇親会(対面):65.3%
- 社員を交えた懇親会(対面):59.8%
- 内定式(オンライン含む):47.2%
- 社内や施設などの見学会(オンライン含む):43.2%
- 社員を交えた懇親会(オンライン):38.4%
以上の結果のように、実際に働く場所に行くことや、社員と交流をすることで入社意欲が高まる傾向があります。
特に、対面での内定者フォローは入社意欲を高めやすいです。遠方の内定者が多くない場合は、対面でのフォローを多く実施するとよいでしょう。
【参考】株式会社キャリタス『調査データで見る「入社に向けた内定者フォロー」―2025年卒調査―』
3.採用ノウハウの蓄積
「採用後にミスマッチが発生してしまう」といったお悩みを抱えている方は、採用ノウハウを蓄積することがおすすめです。
中小企業の採用においては、採用ノウハウを蓄積し、次年度以降の就職活動に活かすことも重要です。採用活動は企業が存続する限り、永続的に行われます。以下のようなデータを毎年蓄積していくことで、より効率的で効果の高い採用活動が実現できるようになるでしょう。
▼採用ノウハウとして残しておくべきデータ
- 何人の学生にアプローチし、その中で何割が選考に進んだのか
- 内定辞退の原因は、どんな理由が一番多かったか
- 内定者のうち、求人広告が何割でダイレクトリクルーティングが何割だったのか
中小企業ならではの強みを活かそう!
「中小企業は大企業に比べて採用活動で苦戦する」と言われますが、実は必ずしもそうとは限りません。むしろ、中小企業だからできることがあるのです。中小企業ならではの強みとして、以下の2点があげられます。
❚ 採用人数が少ないため、学生1人1人を細かくサポートできる
中小企業では、大企業のように大量採用を行うことが少ない分、学生一人ひとりと丁寧に向き合うことができます。
面接や面談の場で、学生の性格や強みや希望をしっかり把握し、その人に合ったポジションや育成方法を考えることで、学生の満足度の高いサポートができるでしょう。
❚ 社員数が少ないため、自社の社風がより的確に伝わりやすい
社員数が少ない中小企業では、組織全体の雰囲気や人間関係が見えやすく、会社のリアルな社風を感じ取りやすいというメリットがあります。
説明会や面接で経営者や現場社員と直接話す機会も多く、「どんな人が働いているのか」「どんな考え方の会社なのか」を肌で感じることができます。自分の価値観と会社の雰囲気が合うかどうかを判断しやすく、ミスマッチを防げる点も大きな強みです
中小企業の採用における成功事例
最後に、中小企業の中で採用に成功した事例を紹介します。「他社の事例を知って、自社の採用に活かしたい」という方におすすめの内容です。
▼中小企業の採用における成功事例
- 株式会社WORK SMILE LABO
- アサヤ株式会社
- 株式会社インティメート・マージャー
- 株式会社プラン・ドゥ
事例①株式会社WORK SMILE LABO
株式会社WORK SMILE LABOは、経営危機により相次ぐ従業員の退職に直面していました。そこで実施したのが、事業の根本的な見直しと経営理念の明確化です。
採用面では、新しい経営理念に共感し、ともに業務遂行ができる人材をメインに採用活動を行いました。その結果、経営理念に共感する人材を採用でき、23卒で新卒4名の採用を達成しました。
▼株式会社WORK SMILE LABOが行った新卒採用戦略
- 経営理念やビジョンに共感し、ともに会社をつくっていく意欲のある人材を採用
- 会社説明会では待遇や条件、職種について紹介せず、経営理念・ビジョンの共有に絞っている
- 入社後には個々のキャリアビジョンを社内研修等で上司や同僚と共有することで、新卒社員のやりがいの向上と定着につながった
【参考】厚生労働省『地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集』
事例②アサヤ株式会社
アサヤ株式会社は、細やかな採用活動や入社後のケアに手が回らず、採用者が定着しないという課題に直面していました。
そこで、専任の採用担当者を配置し、採用手法の抜本的見直しや、面接前のカジュアル面談の実施、入社後の面談などを行った結果、1年間で12名の採用に成功しました。
▼アサヤ株式会社が行った新卒採用戦略
- ハローワークや採用コンサルティングを活用し、直接求職者にアプローチ
- 本選考前に応募者が各自の状況や希望等を率直に言える場として、カジュアル面談を実施
- 「アサヤ人的資本経営宣言」など、人材に関する考え方を伝えるコンテンツを掲載
- SNSで業務内容や従業員紹介の記事を連載
- 「ナナメ面談」と称し、入社後も採用担当や他部署の上司と定期的に面談を実施している
【参考】厚生労働省『地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集』
ここからは、弊社のダイレクトリクルーティングサービス「MacherScout」を利用して、採用を行った企業事例になります。
事例③株式会社インティメート・マージャー
株式会社インティメート・マージャーは、ビックデータを取り扱うデータ専門のコンサルティング会社です。
21卒から新卒採用を開始した同社は、以下の3つを課題として抱えていました。
▼抱えていた新卒採用課題
- 学生に興味を持ってもらい、母集団を形成すること
- 新卒採用のノウハウがなく、すべてが0からのスタートであったこと
- 採用担当者が1名のため、採用業務に工数がかけられないこと
特に「データ活用コンサルティング」という、学生には馴染みがない仕事を伝え、興味を持ってもらうことを課題として感じていたようです。
同社に魅力を感じていただいたMatcher Scoutの特徴は以下の2点です。
▼魅力を感じていただいたMatcher Scoutの特徴
- スカウト送信、日程調整などの業務を代行する点
- 完全成功報酬制で、リスクなく運用を開始できる点
最終的には、同社の最終選考を受けた19名のうち、10名がMacherScout経由という成果を得ることに成功します。
この事例から見ても、学生の馴染みがない業界・業務の場合は、ダイレクトリクルーティングが有効であるということがわかるでしょう。
【参考】最終選考に進んだ半数がMatcher Scout経由でした。
事例④株式会社プラン・ドゥ
株式会社プラン・ドゥは、不動産経営・不動産管理から収益不動産の売買等を行っている会社です。同社は会社の理念と価値観に共感しやすいとされる新卒を、10年以上前から採用しています。そんな同社は、新卒採用において、以下の2つの課題を抱えていました。
▼抱えていた新卒採用課題
- 自社にマッチする学生を集めること
- アプローチする学生の数を増やすこと (母集団形成)
そんな中で同社には、弊社が提供するMacherScoutを導入して頂きます。MacherScoutには大きく下記の3つのメリットを感じて頂きました。
▼Matcher Scoutを利用して感じたメリット
- Macherに登録する学生は、主体的な学生が多いこと
- 十分な数の学生にアプローチできること
- 運用負担をかけずに集客ができること
弊社サービスを導入して頂いた結果、最終的には21卒と22卒の両方で1名ずつMacherScout経由の内定承諾を出すことに成功しました。
【参考】ターゲットを絞りながらも、十分な母集団を確保。サービス利用開始から21卒、22卒で安定して内定承諾を獲得
中小企業の採用課題解決にはダイレクトリクルーティングがおすすめ
中小企業の採用課題の解決には、ダイレクトリクルーティングがおすすめです。
ダイレクトリクルーティングとは
ダイレクトリクルーティングとは、採用要件に合致した学生に直接アプローチできる採用手法です。
従来の採用手法は、求人サイトへの掲載・人材会社への依頼が主であり、応募や紹介があるまでは待つことしかできない『待ちの採用』でした。ダイレクトリクルーティングは、企業が自ら会いたい学生にアプローチできる『攻めの採用』と言えます。
ダイレクトリクルーティングは、自社にあった形で運用することができれば、人事の負担を削減しつつ自社にマッチする学生に直接アプローチをすることができ、採用活動にプラスの効果をもたらします。
「ダイレクトリクルーティングって他の採用手法と何が違うの?詳しく知りたい!」「ダイレクトリクルーティングにかかる費用が気になる」という方は、下記の記事を併せてご覧ください。
【参考】ダイレクトリクルーティングとは?導入率や各採用手法との特徴比較
中小企業がダイレクトリクルーティングを使うメリット
中小企業が新卒採用でダイレクトリクルーティングを使うメリットは、主に以下の2つです。
▼中小企業がダイレクトリクルーティングを使うメリット
- 自社にフィットする学生にアプローチできるため、企業の認知度がなくても学生の応募を獲得することが可能
- 採用コストを抑えることが可能
❚ 自社にフィットする学生にアプローチできるため、企業の認知度がなくても学生の応募を獲得することが可能
ダイレクトリクルーティングは、企業が会いたいと思った学生に自らアプローチをする手法です。そのため、認知度が低くても企業からのアプローチを通じて学生に自社の存在を知ってもらうことができます。
学生の思考をしっかりと理解し、正しく魅力づけできれば応募獲得につながります。
❚ 採用コストを抑えることが可能
ダイレクトリクルーティングには初期費用型や成功報酬型などがありますが、成功報酬型を用いることで採用コストを比較的抑えることができる手法と言われています。
ダイレクトリクルーティングの選考報酬型プランを利用することで、採用できなかった場合のリスクを負わずに採用活動を行うことができます。
一方、新卒採用ナビ媒体では、初期費用として広告掲載料が発生します。採用人数に関わらず一定額がかかるため、採用予定人数が少ない または ナビ媒体経由での応募が見込めない場合はあまり良い方法ではないかもしれません。
また、人材紹介会社の相場は1人あたり80~120万円です。人材紹介会社の担当者が採用要件に合わせて学生の選定を行なってくれるため、工数は削減できますが、その分金額はあがります。
ダイレクトリクルーティングは、どんな場合でも効果を発揮する万能薬ではありませんが、自社の課題に合わせて運用することができれば大きな効果を発揮することを期待できます。
特にコストもリソースも限られている中小企業の採用では、自社にフィットする学生にいかに効率的に会うことができるかということが鍵になります。
求める人物像を明確に決め、採用課題を特定した上で自社に合った形でダイレクトリクルーティングを効果的に運用しましょう。
コストを抑えて求める人材にアプローチできるMatcher Scoutを使って、採用活動を成功させよう!
Matcher Scoutは、「自社の求めている学生に、手間を掛けずに、リスク無く採用したい」というニーズにお応えする、新卒向けダイレクトリクルーティングサービスです。
Matcher Scoutでは、ダイレクトリクルーティングサービスのデメリットを最大限無くし、効率的かつ効果的な運用ができる仕組みとなっています。弊社のサービスには5つの特徴があります。
Matcher Scout をおすすめする理由
- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行
- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層
- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い
- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる
- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意
以上の理由より、費用面でのリスクを心配せずに、効率的な採用活動を進めることができます。ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!
詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout
さいごに
中小企業は大手企業と比べると、知名度や採用コストの面で不利になってしまう部分がどうしてもあります。
このような課題を乗り越え、新卒採用を成功させるためにも本記事を参考に自社の採用活動を改めて見直してみてはいかがでしょうか?




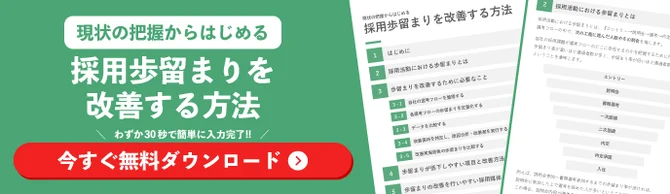






_Crop%20Image.jpg)